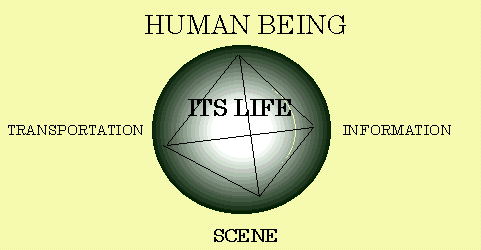モバイルメディア・ITS
出典:日本工業新聞 1998年7月~10月
第1回 モバイルマルチメディアの一翼
~7000万台のフロンティアへ~
東芝を中心とするカーナビ向けCSデジタル放送「モバイルブロードキャスティング」の会社設立と2001年の実用化が発表された。すでに携帯電話回線によるカーナビ向けの情報サービスもはじまっている。交通情報も含めたラジオやカーテレビを除いて、長い間「情報の孤島」であった車の中に向けての情報メディアは、オーバーに言えば日本の自動車約7,000万台をターゲットにした、まだ誰も見通していない未踏峰の市場である。これが注目に値しないわけがない。
すでに5省庁(建設、運輸、通産、郵政、警察)共同の国家プロジェクトとして、移動体向け情報サービスの基礎となるプロジェクトが進行していることをご存じであろうか。
ITS(高度道路交通システム)。狭義には、人と車と道路の一体的な交通システムの構築を目指して、1995年から全世界で統一名称となった、各種システムの総称である。カーナビの高度化、高速道路自動料金収受システム、安全運転の支援などが、道路交通の円滑化を目指して取り組まれている。
しかしこのような道路交通サービスとしてのITSは、あくまでも官庁の政策目標に過ぎない、と、当の担当官が公言している。モバイルマルチメディアの一端として情報産業を担う市場を創出することが、官庁側からも期待されているのである。すでに300社以上の大手企業が参画する推進協議会(VERTIS)も運営されており、まだ見ぬ市場の姿を描こうと、広義のITSすなわち「自動車に電波を飛ばしてできることすべて」に関わるあらゆる業界の企業がITS関連ビジネスを視野に入れつつある。
番組や広告を流す放送メディアは、この広義のITSの、間違いなく中心的な存在である。本稿では生活者視点からの「ITSメディア」、すなわち「自動車で移動する生活者が放送メディアに何を欲しているか」というアプローチから、CSデジタル放送や地上波データ放送などの可能性について分析を試みたい。
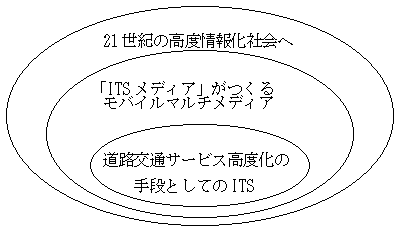
第2回 ITSメディアの進化シナリオ
~プッシュ型メディアへの潜在的ニーズは?~
ITSビジネスはすでに具体的なスケジュールの途上にある。当面のビジネスシナリオはどのようになっているのか。
すでに我々の目に見えているITSの受信端末はカーナビである。このカーナビに様々な機能を付加しようという動きは周知のとおりである。それは住所検索、音声案内といったカーナビ自体の機能から、VICSによる渋滞表示、それをもとにした迂回最短ルート表示などが、すでにカーナビ付加機能としてスタートしている。
交通情報の次の次元の情報 ~沿道情報、地域情報、買い物情報、‥~をカーナビ画面に提供するサービスが昨年から急激に立ち上がりつつある。
すでにトヨタは携帯電話回線での会員制情報サービス・MONET(モネ)をスタートさせた。ソニーなど7社は、カーナビ向けのインターネットサイト・モバイルリンクを立ち上げた。そして放送メディアでも、東芝を中心とするモバイルブロードキャスティング(MSB)がすでに法人設立され、2001年からカーナビ組み込みの専用端末でサービスを開始する。日産、ホンダ、テレビ朝日なども、自動車向けの情報サービスをスタートさせる予定である。渋滞情報だけではない、自動車をとりまくあらゆる情報がカーナビ画面で車の中に届けられるスタイルの基本型が作られつつある。そしてそれらは、放送・通信の壁を超えて動きつつある。
これらカーナビ・インターフェースのメディア事業者はいずれも、自動車の中の生活者のニーズにあったコンテンツの提供がビジネス発展のキーになるという認識を持ちつつ、キラーコンテンツを模索中である。
ここに放送メディアとしての大きなチャレンジがある。すでにインターネットの世界では、検索エージェント機能によるプッシュ型メディアがいくつも現れている。車の中で高度な情報検索ができない以上、プッシュ型メディアに対する生活者の潜在的ニーズを今こそ精査しなければならない。
次回は、すでにフレームが見えた放送メディア、MSBの可能性について検討する。
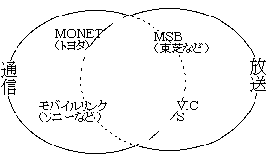
第3回 モバイルCSの立ち上がり(1) ~MSBは何を見せるか~
‥MSBの動きと現状、東芝ほか企業の意図するところ
自動車に送られてくる情報、それは久しくラジオとテレビでしかなかった。
ラジオはアイフリー(目の自由の利く)メディアとして、運転手に対して交通情報、ニュース、天気予報など、また音楽やパーソナリティーの会話など、様々な情報をリアルタイムで送ってきた。しかしAMにせよFMにせよ、それぞれの番組編成の中で、欲しい情報を欲しいときに得る、ということは長らく実現しなかった。
1620KHzの交通情報も受信地域は限定されたままである。カーテレビも、家で見たかったテレビの情報をリアルタイムで追う役割を担うに留まっており、車の中のための情報ではなかった。
放送のデジタル化、それに伴う放送各局の動きの中で、いま注目を浴びているのがモバイルブロードキャスティング(MSB)2001年サービス開始、の報である。東芝をはじめ、トヨタ、富士通、日本テレビ、FM東京などが出資して、全くのフロンティア、モバイルCS放送がたちあがることになった。周波数はSバンド(約2.6GHz)を用い、MPEG4方式で送られてきた256kbpsの画像データを、15フレーム/秒で、30チャンネル以上送信する予定になっている。システム仕様は低コスト化を目指して独自の方式を採用し、受信機はカーナビに組み込みで2~3万円程度に抑えられる。アンテナも万年筆程度のコンパクトさになるという。基本利用料金が月額100円程度が想定されている。とぎれない放送を提供するために、まずは主要高速道路向けとして15,000箇所にギャップフィラー(再発信アンテナ)を設置することが考えられている。
サービスを受ける側にとって問題になるのは、256kbpsで15フレーム/秒という、テレビ電話のような画像で何を見ることができるのか、ということである。現在は「ROMなしカーナビ」「天気現況」その他運転にとって必要な情報を想定しているが、コンテンツ探しはこれからである。512kbpsで16フレーム/秒程度にし、テレビのコンテンツを活用する、という検討も行っているという。
次回は、MSBが他のメディアとの競合、提供する情報の可能性、について考える。
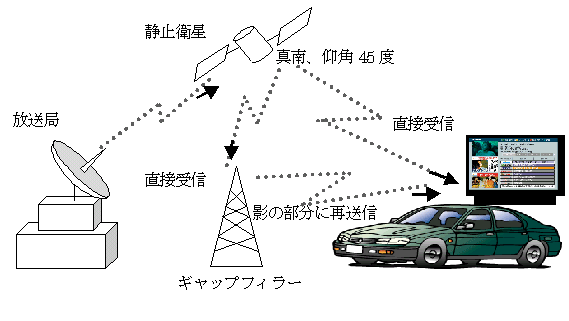
第4回 モバイルCSの立ち上がり(2)~モバイルCSには何が望まれるか~
‥エージェント機能が「ITSメディア」へのカギ
新しい車向け放送サービスとして注目を浴びているモバイルCSデジタル放送「モバイル放送株式会社」。 2001年のサービス開始に向けて出資したのは、東芝をはじめ、トヨタ、富士通、日本テレビ、FM東京などである。現在4億円の会社だが、サービス開始に向けて400億円程度まで増資するという。
投資元の各社共通に認識する課題は、搭乗者に受けるコンテンツづくり、すなわちCS放送という枠組み固有の情報にどう価値を見出してもらうか、である。MONETやモバイルリンクなどの携帯電話回線によるサービス、あるいはもともとあったカーラジオやカーテレビと違った何が提供できるのか。
車の中で小さい画面を見て高度な検索操作を行うには、運転手に限らず、自ずと限界がある。一方カーテレビ、カーラジオになかった「欲しい情報だけ、いま欲しい」機能を充実させなければ、フロンティアマーケットを得ることはできない。
カギは、エージェント機能をCS放送でどうだすか、にある。すでにインターネットで欠かせない存在になっている検索エンジン。これがさらに進化していくと、自動的に自分の欲しい情報だけをデータベースから収集し、提供してくれる機能をコンピュータが持つことになる。運転の安全性を損なわずに、今予定されている仕様のモバイルCSが'視聴率'の高い「ITSメディア」になっていくためには、検索時の注意力や手間を省けるエージェント機能を強化していくことこそ必要である。
最大の出資元となっている東芝の狙いの一つは「モバイルCS対応という付加価値のついた同社製カーナビ」の販売促進であるが、MSB固有の将来的なニーズを創出するためには、受信機側にエージェント機能を持たせるためのメモリ機能の強化などが必要になるだろう。順次拡大されていくチャンネル数も、多様なエージェント機能を持った情報提供メニューの拡大に資することになるだろう。
次回は、「ITSメディア」としての地上波データ放送の取り組みと展望について考える。
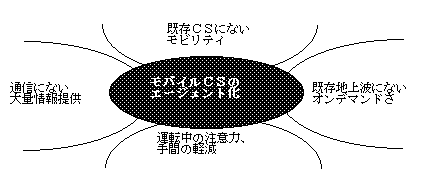
第5回 地上波データ放送の試み ~地方放送局の生き残りを賭けて~
地域情報、その最大の活用先は車の中
自動車で受け取れる映像情報には、受け手側に自ずと限界が生じる。運転手は安全性の問題があり、同乗者もまた細かい振動の中で映像を見続けることは乗り心地を損ないかねない。そこでラジオを中心とする音声情報とともに、自動車向け放送として大きくクローズアップされてきているのが、地上波の文字データ放送である。
放送電波のすき間に文字、静止画、データ等の情報を載せて送るサービスの総称であるデータ放送。受信機に双方向性を持たせることで、顧客データを使ったインタラクティブマーケティングが可能となり、一方で地上波同様の広範囲・ローコストのサービスができる。そして文字情報という音声に変換しうるコンテンツが中心であることから、車向けのローカルメディアとして非常に有望である。
発展への大きなヒントになるのが、北海道テレビ放送の行っているデータ放送「CLARK on ADAMS」である。テレビ朝日が運営する「ADAMS」からの全国情報に加えて、地域密着型のコンテンツを配信して高い評価を受けている。とくに道内を50地域に分けたきめ細かい天気予報が、農家や観光業者から非常に好評だ。道内地方新聞一七社からのニュース配信、催し物情報やショッピング、チケットの情報なども発信されている。そしていま、自動車向けサービスも具体的に検討中であるという。
テレビだけではない。FM東京による「見えるラジオ」は、タクシーの'一行ニュース'で昨今急激に認知が高まったと言えるだろう。県単位、地方単位で地域情報を提供できるFM多重波にも、大きな可能性が秘められている。
そして最後に紹介することになったが、すでに1996年からサービスの始まっている、渋滞情報をカーナビに送信するVICS(道路交通情報提供システム)もまた、NHK FMの電波を使って、政府が整備したビーコンアンテナを中心に発信している、実質無料のデータ放送である。
5 月に中間発表された放送のデジタル化。多チャンネル化によってローカル局不利と言われるデジタル化こそ、こうしたデータ放送が地域密着メディア、そしてITSメディアとして生き残っていく、大きな手がかりである。
次回は、車向けメディアの競合の可能性、とりわけ「放送化」する通信サービスの状況について述べる。
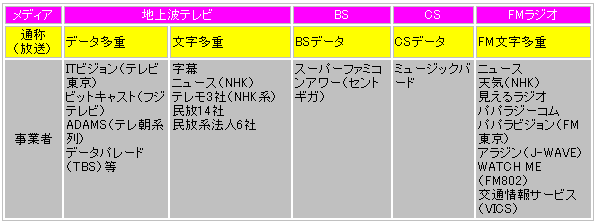
第6回 車向けメディアの競合の可能性
とりわけ「放送化」する通信サービスの状況
モバイルCS放送、モバイル地上波データ放送など、車向けの新しい放送メディアが姿を現そうとしている。これまでのカーラジオやカーテレビにない個性を打ち出せるという点では、「ITS(高度道路交通システム)メディア」は、放送だけに留まらない。
いま、通信の方がむしろ放送的なサービスを成功させつつある。むしろ双方向性を本来的に持っているという点で、ITSメディアとして各種放送サービスより先行している。
電話回線を利用した情報提供として、トヨタ自動車が立ち上げた「MONET(モネ)」は、携帯電話回線を使って沿道のレストラン情報などをカーナビ画面で得ることができる。追って、ホンダがこれと同様の仕様での情報サービス「インターナビ」をスタートさせ、日産はオペレーターが電話で回答するサービス「コンパスリンク」をスタートさせる。
これらはいずれも会員制の情報サービスが中心である。すでに世界に広くあるコンテンツ、インターネットのホームページを受信するシステムをカーナビ向けに開発したのが、ソニーが中心になって開発した「モバイルリンク」(http://mobilelink.or.jp/)である。小さな画面、クリックのみでの操作など、カーナビインターフェースに配慮されたホームページを、専用カーナビで受信することができる。
こうした'放送的な通信'情報サービスによる「ITSメディア」の問題点は、回線料金がかさむことと、携帯電話の通信速度である。モバイルCS放送の項で指摘したように、ITSメディアの理想形がエージェント機能ならば、これらの「ITSメディア」は、放送のように、より頻繁かつ大量に情報を送る必要が生じる。通信速度の技術開発予測を踏まえて、電話料金定額制のフィージビリティを検討していく必要がある。
次回は、「ITSメディア」が、カーナビインターフェースに留まらずさらなる広がりを見せていることについて考察する。
【図表】 MONETの写真(左)と、モバイルリンクのサイト画面(右)
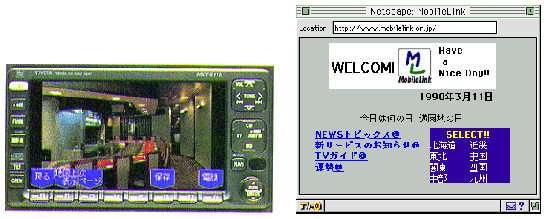
第7回 カーナビインターフェースにとどまらない「ITSメディア」
「ITSメディア」は、カーナビインターフェースだけに限定されたものではない。自動車で移動する人々に情報が何を促すのか、という視点で捉えなければ、「ITSメディア」の本当の競合地図は見えてこない。
例えばNTTドコモの「インフォネクスト」のようなポケベル向け情報サービスが、すでに電話会社によって行われている。1行メッセージで流れてくる文字情報は、見た目には「見えるラジオ」などの文字データ放送とほとんど変わらない。
またノート型パソコンも、「モバイルコンピューティング」という言葉の示すとおり、運転中の運転手でさえなければ、本来的に車の中で使える機能を持っている。すでにノートパソコンの一部にはGPS機能を接続し、カーナビとして使えるものすらある。
携帯電話は、交通安全のために使用を控えることがうたわれていながら、いまもってカーユーザーの4割近くが「運転中に頻繁に使うメディア」として挙げている。その携帯電話から、JAF(日本自動車連盟)のロードサービスをはじめ、地域の天気予報、渋滞状況、あるいは株価情報や競馬情報などの短縮ダイヤルが用意されている。これもまた立派な「ITSメディア」である。
あるいはインターネットのサイトとして「ITSメディア」の潜在的可能性を秘めたものもある。リクルートが作ったサイト「ご近所さんを探せ」(http://www.gokinjo.net/)では、デジタル地図上にプロットされた投稿者から、意気投合できる人を探すことができる。
放送、通信の世界で広く競合する「ITSメディア」は、全てが順調に市場を獲得することはないと考えるべきだろう。自動車移動という、フロンティアとはいえほんのわずかな時間の中で、お金を払ってまで人々は何を知りたいのか、参考となる前例はほとんどない。
車の中で情報を得て、自動車にどのような行動をとらせるのか、それによって誰が得をするのかが、ビジネスとして確固たる地位を獲得するための重要な視点となる。
この観点から、次回は「ITSメディア」が広告媒体としてクローズアップされる条件として、にわかに現実味を帯びてくる車内電子決済の可能性について考える。
【図表1】 ドコモの短縮ダイヤル一覧 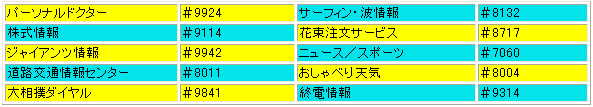
【図表2】ご近所さんを探せ、のサイト 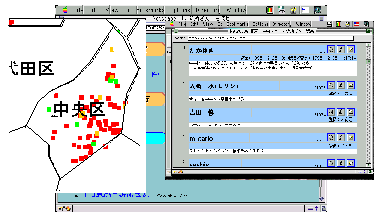
第8回 ITSメディアは車内注文・決済のツールへ
ETCの普及展開が突破口
ITSメディアにとっての重要な突破口は、こうした情報サービスの内容が、搭乗者に行動の必要を迫ること、すなわちモノやサービスを買おうとする行動に直接駆り立てる、広告宣伝的性格を持った情報である。
少なくともクルマに乗って出かける買い物は、本来的に大量、高価値の買い物であり、購買に向けて行動を開始した客である。商品の現場に近づいた人ほど商品広告に大きな影響を受ける。広告情報が購買に至る理論はここでは省略するが、自動車で購買のために行動することの特殊性は、広告理論では深く検討されてこなかった。
広告・販促としてのITSメディアの実現に向けて、大きな追い風となるのが、ETC(自動料金収受システム)の導入である。2000年スタート、2003年には高速道路の半分以上の料金所にETC対応のゲートを設置、約400万台をETC対応にしたい、という政策目標を掲げている。言い換えれば、400万人に車載機を買ってもらうマーケティングを、政府が中心になって進めなければならないということである。
ICカードによる決済機能とアンテナに反応するセンサーを持ったこの車載器のシステムは、サービスエリアなどでの買い物の決済が当初から想定されている。一方、いくつかのサービスエリアでは、ファミリーレストランやガソリンスタンドなど、すでに大規模流通業が参入している。そしてこれらの流通業は、すでに独自のシステムで商品情報をデジタル情報で管理している。これらの流通業は、自動車による購買行動を促す情報を、本来的に持っているのである。
これら流通業と提携することで、商品の販売戦略の一つとして、車内オンラインショッピングが大きな位置づけになってくる可能性が高い。
まだETCの実体すら見えていない現在、車内オンラインショッピングの実現を疑う見解もあろう。
次回は、車内オンラインショッピングが流通業にもたらす大きなメリットと、その情報ツールとしてのITSメディアの効用を検証する。
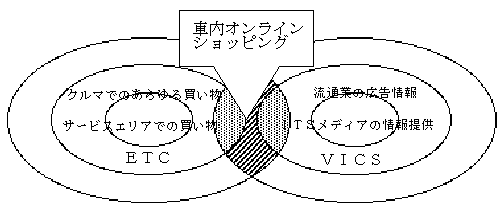
第9回 小売業が変わる、車内オンラインショッピング
ドライブスルーを実現するITSメディア
2000年スタート、2003年には利用者50%の普及を目指すETC(自動料金収受システム)。ここに導入される料金決済システムは、サービスエリア等での買い物も可能になる。ETCすら姿の見えない今年の段階でこう言い切ることは難しいかもしれないが、このシステムを展開し、広く流通業と提携することで、車内で買い物の注文を行い、決済を行うことが可能になる。
オンラインショッピングにビジネスとしての可能性はあるのか。いま、アメリカで流行っている「スーパー買い物代行業」に大きなヒントがある。
例えばピーポッド社は、大規模スーパーの商品データベースを借り、その日の商品リストを会員のパソコンに提供、会員はピーポッド社に買い物を注文すると、ピーポッド社が雇ったパートタイマーがスーパーの店頭で買い物を代行、宅配するというものである。スーパー自身が品物をピックアップしないので、消費者の立場から一番いいものを手に入れられるというのが、好評の原因である。
これらは会員制サービスだが、会員のコスト負担の最も大きな部分は、宅配コストである。そこで、注文した品物をスーパーまで取りに来ることで、会員のコスト負担は大きく減るという。
ここに買い物情報提供メディアとしての、ITS(高度道路交通システム)メディア新しい可能性がある。リアルタイムで割引サービスの情報を広域で提供し、GPSの現在位置から周辺沿道に限定して取り出すことは、規格の標準化さえ整えば技術的に難しいことではない。流す電波については、放送のデジタル化の動きとローカル局の動向も相まって、様々な可能性が考えられる。
流通業としてのメリットは、販売促進だけではない。この「取りに来る」すなわちドライブスルーが拡大すれば、店舗面積、あるいは駐車場のスペース削減にも資することになる。もちろん、これらは決済システムの普及、あるいはカーナビシステムの発展と普及を待つ必要があるが、ETCの普及スケジュールの中で是非視野に入れておく必要があろう。
次回は、こうしたシナリオの前提となる、決済システム、カーナビなどの普及シナリオに目配せしておく。
【図表】 ピーポッド社の概念図 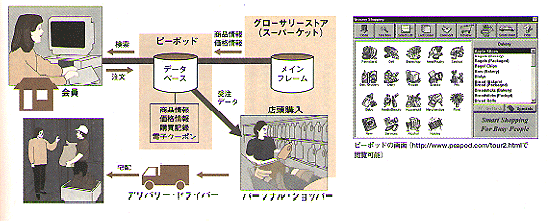
第10回 ICカードの展開から考えるITSビジネスへの広がり
ETCインフラ整備とのスケジュール調整を
車内オンラインショッピングを考えるうえで、そのキーになるICカードの機能について簡単に見ておきたい。
ICカードと一言で言っても様々な種類があるが、主なものは、8ビットのCPUと16KB程度のメモリを内蔵した、クレジットカード同様の大きさのカードである。端末にカードを挿入して使う接触型、カードにアンテナの内蔵された非接触型とあるが、これもすでに併装する技術があり、さらに光磁気コードや従来のカード同様の磁気コードも盛り込むことも可能だという。現在では1枚の製造費が3000円~5000円程度である。
97年では日本には2,000万枚程度普及し、実用化されているもののほとんどは石油会社のカードであるが、2000年には別表の項目に用途が広がり、7億枚以上普及すると言われている。とくに2002年までには既存のクレジットカードは全部このICカードに切り替わることになる予定であり、規格の標準化と盛り込むべき機能が検討されている。
課題は、用途としてどの程度マルチユースを実現するかということと、セキュリティに関わる責任問題を法律でどう解決するかいうことである。
とくに、マルチユースのオンラインショッピングツールとして機能させるためには、個々の事業主体が互いの情報を機密にする必要があるが、この機能はまだICカードには盛り込めていないという。逆に考えれば、データベース管理者が一者しかいないことを前提とした現在のICカードの仕様は、道路交通も含めた行政サービスのカードとしてスタートし、順次民間サービスに拡大させていく方が、普及シナリオとしてなじむ。この点で、交通政策・ETC(自動料金収受システム)から展開する車内オンラインショッピングは、他の「官民取り合わせ」よりも普及促進に大きな可能性がある。
現在建設省を中心に、ETCの仕様について検討中だが、ICカードの将来的なサービス展開を考慮することをむしろ中心に置いて、ITS対応インフラ整備計画や実施時期についての慎重な検討も必要となろう。
次回は最有力のITSメディア端末である、カーナビの普及シナリオについて考える。
【図表1】 世界と日本のICカード市場予測
【図表2】 2000年時点での世界のICカード用途別市場予測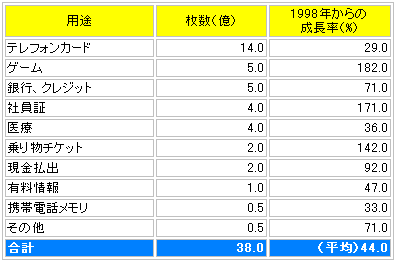
第11回 カーナビの普及シナリオを考える 遊びの要素でブレークへ
ITSメディアが新しい消費マーケットを獲得していく上で、最も有力な受信端末であるカーナビの普及シナリオは欠かせない。
ここまでのカーナビ累積販売台数は300万台を超え、VICS対応のものも50万台を超えた。しかし日本の自動車は約7700万台、乗用車だけでも約5,000万台、普及率はわずかでしかない。ITSメディア端末・カーナビの普及率はどう推移していくのか。
乗用車(軽自動車含む)のカーナビ普及率をここ5年で見ると着実に伸びており、98年もここまでは成長率の大きな低下は見られない。この伸び率で計算すると2005年には少なく見ても30%を超えることになる。
さらに、情報機器の普及というものは、ある臨界点を超えたところで比較的に伸びることが多い。携帯電話(PHS含む)の普及率は10%弱を境に急激に伸びた。カーナビもまた、遠からずうちに、ブレークと呼べる伸び率が必ず出現してくると考えるべきである。
現在、カーナビ商品のラインナップは、基本機能のみの低価格商品(10万円程度)から、DVD-ROMを採用した最新式の商品(30万円程度)まで様々である。しかし、経路誘導を中心とした「便利な定型サービス」はいずれ飽和状態となり、新しい魅力がカーナビに求められることになる。
ブレークの突破口は何か。便利さの次に求められる魅力は、ずばり「遊び」である。
サラリーマンの連絡ツールとして世に出たポケベルは、若者の遊び道具としてブレークした。デジタルカメラの市場は、プリクラで火がついた。レンズ付きフィルムは、若者の「モバイル記録メディア」として新しい広がりを見せた。カーナビがITSメディアのインターフェースとして定着するには、遊びの要素を持ったコンテンツ開発が是非必要である。カーナビインターフェースに限らず、情報提供サービス各社のコメントとして、この「遊び」の要素がキーになる旨のコメントは散見するが、具体像はまだ見えてこない。
この「遊び」とは具体的に何か、その萌芽はどこにあるのか、について、次回以降検討していく。
【図表】 乗用車のカーナビ普及率と予測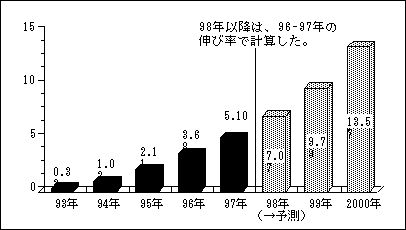
(出所)各種資料をもとに電通作成
第12回 遊べるカーナビ」の普及シナリオ 遊び=不定形情報が突破口
コミュニケーション・プラットフォームの要素は不可欠
すでにMONET、コンパスリンクなどで進められているカーナビ向け情報提供サービスだが、現在のサービスは、センターから発信される地域のレストラン情報、駐車場ガイド、交差点などの映像など、言い換えれば「万人に便利な定型情報」に留まっている。
情報化社会をめぐる議論として、情報受信者を増やしていくためには、発信される情報量もまた多くならなくてはならない。限られた情報発信者がこれを担うことは難しい。次々とヒット商品となるプレイステーションのゲームソフトは、決してプレイステーションの限られたスタッフが作っているわけではない。
解決策は、情報発信者を増やすことである。そしてITSメディアの場合、移動する人々のニーズを最も正確に理解しているのは、他ならぬ移動する人々である。
世の中移動している人全員にとって魅力的なコンテンツというものは、そうたくさんはない。移動中に急ぎ知りたい情報、しかもお金を払ってくれる情報とは、ずばり「便利な人にはとても便利な、不定形情報」である。そしてITSメディアに乗る不定形情報の中心を担うのは、自動車同士、自動車と自動車に乗っていない人との情報交換である。
以前紹介した「ご近所さんを探せ」(http/www.gokinjo.net/)、あるいは「じゃマール」をはじめとする'投稿・出会い'系の雑誌に、ヒントが隠されている。「じゃマール」の場合、広告情報を雑誌に掲載するスタイルをとっているリクルートの各種雑誌と異なり、掲載される人自身からは、広告出稿料金としてのお金をとっていない。人と知り合いたい、人づてに情報を知りたい、という行動に対して、人はただで発信し、お金を払って情報を得、その「場」は拡大しつつある。
こうした不定形の情報は本来的にテキストデータに馴染みやすい。ここにITSメディアならではの「沿道穴場情報」が結びつくことよって、情報プラットフォーム事業としてのITSメディアの可能性が見えてくる。このプラットフォームの構造に企業が参入するきっかけが見つかれば、ビジネスが大きくなる可能性はますます広がる。
これがITSメディアのサービスとして、具体的にどのようなイメージが考えられるか、次回以降で述べる。
【図表】 魅力あるカーナビの情報提供メニュー(数字は1998年3月電通調査)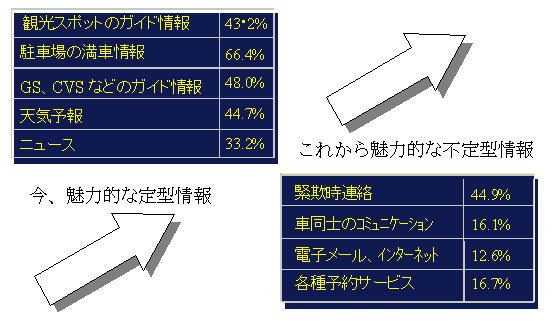
第13回 サービスイメージの試み(1)
不定形情報で車は動く カーナビ投稿情報/双方向式渋滞情報
ITSメディアは、多数の情報発信者による、不定形情報のコミュニケーションプラットフォームが突破口となることを述べてきた。ではサービスとしてどのようなイメージが考えられるか。
MONETやコンパスリンクなどによる定型情報はいずれパブリックなものになる。次の付加価値は、あまり人の知らない穴場情報、口コミ情報、'今この時'の情報である。
通りがかった店について「ここの丼物は駄目だ」「あのガススタンドはおしぼりを出す」「そのコンビニはトイレOKだ」といった音声や文字の情報が、エージェント機能によって選び出され次々重なって出てくることは、技術的にそう難しいことではないはずだ。ストック情報のオンラインフォーラムとフロー情報のリアルタイムチャットのメディアとしてカーナビが機能していくことが、一つの例として考えられる。
大企業による確かな情報と、投稿ベースの怪しげな情報が併存していてもいいのではないか。アクセスする側が主体的に選べばいいだけであって、それらがバラバラに存在できる仕組みは、地域情報発信のプロジェクトともリンクして、案外に早く実現する可能性がある。
定型情報を超える価値を不定形情報が生み出すアイデアは、ITSの本丸、渋滞緩和策でも展開できるのではないか。分岐点や交差点ごとに、個々の車が行きたい方向の集計と、方向別の交通容量がリアルタイムに表示される双方向性渋滞情報も、技術的には難しくない。車からの発信情報は「右か左か直進」、せいぜい数バイトに過ぎず、集計も容易だ。運転手に判断させる適切な交通流が、「癒しの情報」以上の効果を生むかもしれない。
車同士の双方向通信は、3,500万台まで普及した携帯電話によって現実のものとなった。上記のようなシステムづくりによって、さらに'深い'情報を得ることが、ドライブ行動の相乗・誘発効果を高めることになる。
次回は情報消費空間としての運転席のイメージを広げる。今週ソウルで開催されているITS世界会議については後日言及したい。
【図表】 カーナビ投稿情報 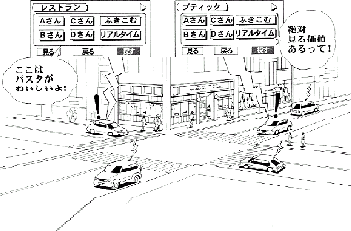
第14回 サービスイメージの試み(2)
仕事のできる車/遊べるドライブレコーダー 情報消費空間としてのリ・デザインを
高付加価値の不定形情報を受発信する自動車の中は、情報消費空間としてリ・デザインせざるを得なくなる。
素朴に考えたとき、自動車はなぜ発明以来「応接間3点セット」のごとく椅子が配置されてきたのか。それは自動車が情報と隔絶されたリラクゼーションの空間だったからである。ライター代わりのDC電源がそれを端的に示している。しかし次の100年、いや、次の10年の自動車は、間違いなくAC電源を使って大量の情報を処理する空間になる。
日産が、社長のアイデアをもとに「エグゼクティブが仕事のできる自動車」を作った。この延長上に、今すぐできるリ・デザインとして「外回りの営業さんが仕事のできる自動車」を考えることができる。
もちろん、ウェアラブルに向かうモバイルコンピューティングに机や棚は必要なのか、装着して安全なのか、など論点は多々ある。しかしいくら情報化が進んでも、紙メディアの携帯性、一覧性はおそらく不滅だと言われている。ならばやはり情報空間に「平面」は欠かせないのである。
ITSメディアに立ち返ってこの発想をすると、サービスの一つとして「遊べるドライブレコーダー」が考えられる。「ドライブレコーダー」自体は、フライトレコーダー同様、走行誘導が実現した車の事故証明機器として、いつかは装着義務が敷かれていく。しかしその前に、付加価値のある商品としての普及シナリオが考えられるのである。
運転中は、写真も撮れなければ、見知らぬ道の走行記録も残せなければ、初めて来た道を画像で覚えておくこともままならない。ドライブの潜在的ニーズを満たす商品として、「ドライブレコーダー」は装着義務に先駆けてブレイクする可能性を持っている。
ホンダのインターナビシステムでは、パソコン上で作ったルートをカーナビにインプットできるが、これをCCDカメラ、計測センサーなどを持った自動車にインプットして、多機能を遊ぼうということである。
日産が試作車で発表し、トヨタが'3つの条件'として示している「ITS時代の自動車が備えるべきデザイン」は、これから細密に検討されていくだろう。
次回は、主婦、子供にとってのITSメディア、運転席以外のITSメディアの可能性を考える。
【図表】 仕事のできる車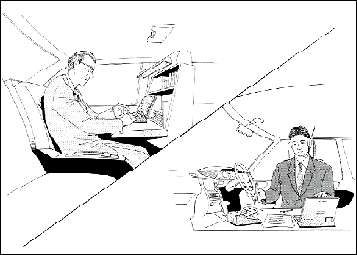
(出所)電通ITSプロジェクトチーム
第15回 同乗者のためのITSメディア
子ども、女性の特性からサービスの芽を
本稿はこれまで一貫して、運転席で享受するITSメディアの世界について述べてきた。そしてITS一般の議論でも、ほとんどが、車が受ける恩恵イコール運転手が受ける恩恵、であった。
多くの同乗者は移動のために乗っているのであり、基本的には手持ちぶさたである。車内での退屈しのぎは、優先順位は高くないかも知れないが、精神的、交通心理的には不可欠な要素である。
今あるカーテレビの本来のニーズは、画面が汚くてもいいから、決して見逃したくない番組を移動しながら見る、ということにある。とくに土日に親の都合で移動させられる子どもにとっては、カーテレビの有無、ゲームの有無は、自動車移動そのもののインセンティブをも左右する。ここに、テレビ番組に連動させてゲーム要素を盛り込んだ双方向サービスを持ち込むことは、家族行動からニーズを掘り起こす可能性がある。
子どもは一般に自動車の後部座席に乗ることが好きでないようだ。窓の位置も高く、前は見えず、シートベルトに縛り付けられることを嫌うという。ならば、後部座席で見せるべき映像は、エンターテイメントでなくとも、単純にカメラ映像で前方の車窓を見せるだけで、子どもにとっては十分魅力的な商品になる。チャイルドシートとの連動でゲーム仕立ても可能だろう。未来のITS普及を担う子どもたちの生活行動と情報へのニーズを深く分析してくことも必要となろう。
大人、とくに同乗者の女性は、あらゆるケースで寄り道の「主導権」を持つことになる。すでに行われているカーナビ情報サービスの発展形として、すでに紹介したリアルタイムチャットやフォーラムの仕組みに加えて、地域からの細やかな情報発信をより魅力的にしていく必要がある。現在「道の駅」から発信される地上波放送はないが、コミュニティFM、あるいはローカル地上波ラジオ局などが、こうした地域情報のコンテンツを担うのに有力な役割を果たすことになろう。
次回は最終回、ITS全体の描くビジョンから、ITSマーケットの展望についてあらためて整理してみる。
【図表】 子供のための後部座席映像サービス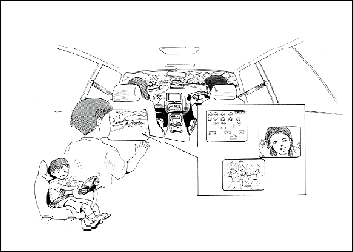
(出所)電通ITSプロジェクトチーム
第16回 モバイルマルチメディアの一翼
~7,000万台のフロンティアへ~
10月12日から5日間、ソウルで開催されたITS世界会議には、全世界から約5,000人が集まり、交通工学、経済学の面から有意義な議論が行われた。日本からは世界に先行するカーナビ情報サービスの紹介とともに、ITS対応の道路整備を積極的に進める「スマートウェイ/知能道路2001」の発表が注目を浴びた。
一方、会議の中で、法整備の必要性、利用者との合意形成の必要性、規格標準化によるグローバルマーケットの出現などが指摘されていたが、これらに該当する専門家は発表者の中にいなかった。世界の先端的研究者ですら、ITSの関わる世界の広さにようやく気づき始めた状態と言ってもいい。
~有用な情報の本質とは何か~
交通政策としてのITSは渋滞を緩和することが目的であって、ひまつぶしとしてITSメディアを考えること自体が健全でないという意見もあろう。しかし、交通情報とはそれ自体が渋滞を緩和するのではなく、一次的には運転手の精神的な救いとなり、運転手の行動を促すものに過ぎない。交通心理面から「人間にとって真に有用な情報の本質とは何か」を慎重に検討していく必要がある。
~幅広いニーズをつかめ~
電通では現在、「ITSライフビジョン研究」を進めている。生活者の行動と心理を中心に据え、図のような概念を掲げて、マーケットの全体像を描こうとしている。しかしそれも一つの道しるべに過ぎず、未来は誰にもわからない。
ITS世界会議の展示会場では、30社以上のブースで「未来商品」が展示されており、運転シミュレーターの体験ブースでは行列ができていた。本稿で紹介してきたものも含め、ITS関連商品のビジネススキームは、これから本格的に検討されていく。
「日本の市場は今後20年で50兆円」という数字だけが一人歩きしているITS。体験型商品市場だからこそ、日常生活に潜むニーズを丁寧に掘り起こした商品とサービス、普及のためのコミュニケーション活動こそが、グローバルマーケットを先導していくだろう。
言及しきれない議論を多く残しつつ、みなさんの議論の導入として、本稿を終えたい。
【図表】 「ITSライフ」の議論のフィールド