通信ビッグバンと市場大編成
出典:日本工業新聞 「シンクタンクの目」 1997年8月
本年6月に成立した電気通信関連三法案は、懸案だった日本電信電話(NTT)の再編を促し、わが国通信市場に対しビッグバン到来をもたらす契機となり得よう。来たる本格的マルチメディア・ネットワーク時代の市場大再編を俯瞰し、同時に海外のメガキャリアの動きを踏まえ、通信ビッグバンを担うプレイヤーのとるべき企業戦略とその企業像を提示したい。
なお、本稿はDDIや日本テレコムあるいはTTNetといった電気通信事業者の現場担当者(役員・部長クラス)の意見・コメントを直接の面談(今年8月以降)を通じて反映させているものである。
ポイント
| ★ | 先般国会で成立した電気通信関連三法案は、 日本電信電話(NTT)の再編を促し、従来の郵政省下の「管理競争」から、より「自由競争」に近い環境へと創造発展的変遷を遂げるためのビッグバン着火の契機となるものであろう。 |
| ★ | この通信ビッグバンを契機に、進行中の第二次情報通信改革の過程において、わが国がとるべき選択の如何が、にわかに脚光を浴びるアジア地域でわが国が通信ハブ(拠点)になることができるかどうかの鍵を握る。現在、行政改革会議(会長:橋本首相)で検討中の省庁再編案において示唆されている通り、マルチメディア・ネットワーク時代に相応しい行政の在り方(郵政省と通産省等の関係機能の統合化)や、マルチメディア法の整備が期待される。 |
| ★ | 再編後のNTTは、海外のメガキャリア(巨大通信会社)からの遅れを一刻も早く取り戻し、アジア経済圏はもとより世界の「スーパーキャリア」に飛躍すべきである。将来の本格的マルチメディア時代にあって、その誕生が予想される少数の「メディア・インテグレイター」になるための布石が課題である。 |
| ★ | 国内市場では、電力系やCATV(ケーブルテレビ)系など、あるいは必要とあらば外資とも組み、NTTに真に対抗できる強固な大同団結の結集を目指すべきである。 |
| ★ | 新電電においては、明確な地域市場戦略とブランド戦略のもと、他社との戦略的提携を巧みに取り入れた「スマートキャリア」へと脱皮できるところのみが、大同団結勢力のコア(核)となることができよう。 |
●今やリーディング産業となった「情報通信」
1980年代では理系学生の就職人気企業に、総合電機が上位を占めていた。ところが昨今、文系学生においても、新電電を含む通信会社や通信系メーカー、システムインテグレイターといった、マルチメディア・ネットワーク時代を牽引する情報通信企業に人気が集中している。
それを裏付けるように、情報通信産業のわが国産業全体に占める割合が、単一産業でトップの電力業に迫る勢いを見せ、初めて10%を超えた(1997年版「通信白書」)。
通信やコンピュータ等の情報通信分野が、かつての基幹産業(鉄鋼・自動車・電気)に代わる新たなリーディング産業として、経済成長や雇用創出に大きく寄与するに至っている。ここに来て、産業の構造シフトが確実に進んでいることが実感される。
そして本年わが国は、とりわけ電気通信分野において大きな転機を迎えた。
1982年の第二次臨調の基本答申以来、長年の懸案だった日本電信電話(NTT)の経営形態問題が、同社の純粋持ち株会社方式による再編を定めた改正NTT法などを含む通信関連三法案が6月13日の国会で成立したことにより、一応の解決をみたこととなる。
●通信ビッグバン、始動!
かねてから通信問題等を追っている日本総研当クラスターでは、本法案のもつ意味を次のように捉えている。
| ◇ | NTTは分離・分割後も持ち株会社を戦略企画部門と位置づけて「オールNTT」の枠内で一体型サービスを維持できる。その意味で、経営形態としては分離・分割というよりも「再編」と呼ぶ方が相応しい。 |
| ◇ | そもそも事の始まりであった公正競争を確保すべきはずの、地域市場におけるNTTの「事実上の独占」の解決にはなっていない。問題は、新電電等との相互接続問題である。 |
| ◇ | NTTの国際進出が純粋民間会社として可能となり、遅まきながら世界のメガキャリア(巨大通信会社)間の大競争に参入できるようになった。 |
| ◇ | NTTや国際電信電話(KDD)の足枷が部分的に解けることが呼び水となり、 NTT等への対抗策として新電電の合従連衡の模索に拍車がかかった。 |
このように今回の法案には課題が少なくない。反面これは、わが国電気通信・情報通信市場が、従来の郵政省下の「管理競争」から、より「自由競争」に近い環境へと創造発展的変遷を遂げるためのビッグバン着火の契機となるものと解したい【図表1】。
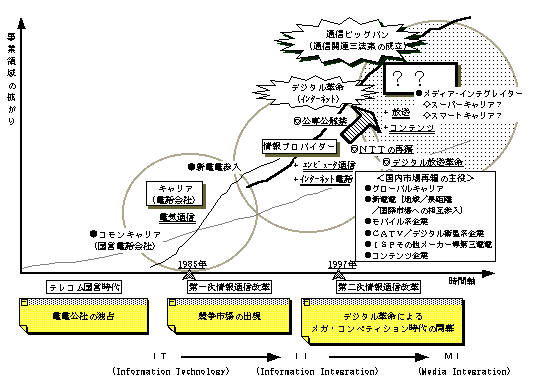
通信業界大再編(ビッグバン)の具体的な枠組みは、目下のところ、次の三極に収斂するかのように見える【図表2】。
●第一グループ:
| ★ | NTTグループは、純粋持株会社のもと、長距離会社、地域会社2社(東日本と西日本)として99年度に再編される。 |
| ★ | 国際通信へは、長距離会社が97年内に進出する見込みである。設立時に技術支援を行い関係がよいとされる国際デジタル通信(IDC)との提携等の可能性をも選択肢に入れながらの、本市場への本格参入となる。 |
●第二グループ:
| ★ | 新電電としては真っ先に、日本テレコムと日本国際通信(ITJ)が、本年10月に合併し、長距離通信と国際通信分野で事業の一体化を図る。 |
| ★ | 一方、市内市場には日本テレコムが4月、大都市JR沿線からの無線による進出を図るべく実験(CATV網を含む光ファイバー活用のダイレクトアクセス)を行っており、NTTに依存しない通信のエンド・トゥ・エンド化を積極的に目指している。 |
●第三グループ:
| ★ | 今月、先の第二グループとの対抗上、長距離系で最強の営業力をもつ第二電電(DDI)と国際系トップのKDDが業務提携を発表。企業文化等の違いから、この両社の歩み寄りはまだ先であろうと見ていた関係者を驚かせた。 KDDは、自社の日本列島周回光ケーブル一部をトヨタ系テレウェイに売却するなど業務提携を予定。 |
| ★ | 同様の出来事は今春すでにあった。移動体分野において、京セラ系セルラー会社とトヨタ系IDOが、市場で圧倒的なシェアを誇るNTTドコモと対抗するため、携帯電話で同一仕様を利用するなど提携を表明したことである。 |
| ★ | またKDDは、専用線ベースでNTTの半分近くの回線インフラを相互接続する電力系地域新電電九社との提携を行うなど、来年4月の国内市場への進出に備える。 |
| ★ | 一方DDIは、全国で無線主体のダイレクトアクセスを行うなど市内への独自進出(テレウェイも首都高速等を利用した無線実験を本年5月に実施)、総合通信サービスへの布石を怠らない。このように本グループにおいては、KDDとDDIを中心に、グループ各社の資本参加や合併を視野に入れた交渉の一層の本格化が必至の様相を示してきた。 |
上記グループの動静を占う上で、トヨタ系通信会社の三社(IDO、テレウェイ、IDC)の動きは、キャスティングボートの役割として見逃せない。
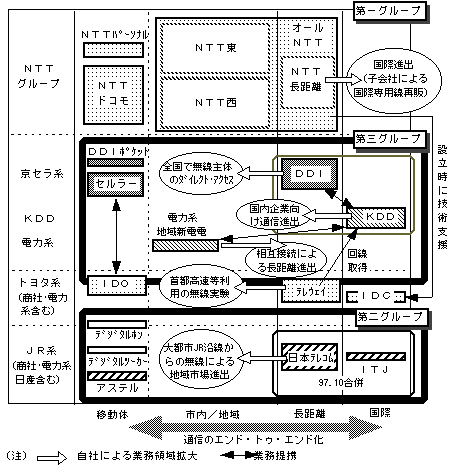
(出所)日本総合研究所 戦略ネットワークマネジメント・クラスター
●マルチメディア・ネットワーク時代の環境整備が急務
この三極を形成するグループが主役の通信ビッグバンを契機として、政府政策部門ならびに企業戦略部門が、今後どのようなカードを選択するかが、わが国のアジア経済地域での通信ハブ(拠点)確立の行方の鍵を握る。
現在、行政改革会議(会長:橋本首相)で検討中の省庁再編案においても示唆されている通り、マルチメディア・ネットワーク時代に相応しい行政の在り方(郵政省と通産省等の関係機能の統合化)に期待が寄せられる。
直近の「一府一二省二庁」再編原案では、郵政省の電気通信・放送行政や通産省が所管を自認する電子商取引等のマルチメディア情報行政は、新設の「交通・通信省」に統合されるように見える。また、今回の原案に「情報」を司る省が表向きにも表明されていないことには、冒頭の通り、情報通信がわが国のリーディング産業になったことを考えると、何ともお寒い限りである。
筆者は本欄(96年2月20日)で、「情報産業省」なるものを提言したが、昨今の産業再編の流れを注視するにつけ、少なくとも原案の「交通・通 信省」というのは、どうも問題の焦点がずれているように思えてならない。なぜならば、情報通信は公共的インフラを連想させる「交通」と一緒に扱うよりも、今やサービス産業の色彩を強めているからである。
さらに言えば、通信ビッグバンを推し進める際に不可欠な、公正競争を確保するための、例えば、郵政省の規制部門を英国のオフテルや米国のFCCのように独立化(公正取引委員会に組み入れるなど)させる仕組みは、一体どこにあるのだろうか。大変気になるところである。
加えて、米国で約60年ぶりに改正された、1996年2月の「電気通信改革法」や、本年制定のドイツ「新マルチメディア法」に準ずる法制度の整備がわが国でも必要となる。
郵政省はマルチメディア・ネットワーク時代に備え、他国と同様に「サイバー法」なるものの制定に熱心であり結構なことである。ただ留意すべきは、こうした取り組みが、単に所轄監督省庁の権限維持・強化のための政争の道具になるものではなく、真に時代の潮流を捉え、世界に誇れる内容になることを期待したい。
●再編後のNTTと「スーパーキャリア」
政省とNTTとの「合意」(96年12月)のもと、わが国通信市場の再編に向け動きだした。これが妥協の産物であることは、筆者らだけでなく関係者の意見を等しくするところであろう。しかしながら、今から85年当時(郵政省のさす「第一次情報通信改革」)に溯り、「ボタンのかけ違い」(NTT経営形態問題と国際系を含む新電電の認可数など)を正すことはできない。
「バブル経済」後、わが国金融セクターのポジションはシンガポール等の他国に対して相対的に低下、今や抜本的な規制緩和等による構造的な改革無しには、現実のグローバルな大競争に対して到底たちゆくものではない。ここに来て本格的な備えをするには遅すぎるぐらいである。
海外を見ると、次の三極が形成されつつある。
●英BTと米MCIの最も野心的連合「コンサート」
●ドイツテレコム、フランステレコム、米スプリントの「グローバルワン」
●盟主AT&Tのもと緩やかな連合体である「ワールドパートナーズ」
わが国経営者の中には、このグループのもつ意味を疑う者もいるが、早晩世界のキャリアが3、4のメガキャリア(あるいは後述のメディア・インテグレイター)の影響下に入ることの可能性は否定できない。
では、NTTはどうか。半導体(MPU)・コンピュータ分野の「デファクト標準」では、欧米に先を行かれている。トヨタやソニーの事業分野に比べ、一層グローバルな性格をもつ通信分野において、再編後のNTTには単に経営規模だけに留まらず、人材力と世界トップ水準の研究開発成果を武器に、グローバル企業へとテイクオフできるかが注目される。
そのモデルの一つ(スーパーキャリア)は、スピード経営と国際戦略の巧みさにおいて、頭一つ分以上他をリードしている現在の攻撃的な英BTであろう。同社は米AT&Tと汎欧州通信会社のユニソースを通じて提携関係にあった、中核のテレフォニカ(スペイン最大の通信会社)を自陣に組み入れ、北米と南米をカバーする汎米州市場に先鞭を付けた。新生NTTには、海外のメガキャリアからの遅れを一刻も早く取り戻し、アジア経済圏はもとより世界の「スーパーキャリア」に飛躍すべく、正にこの「攻めの経営」が問われている。
●メディア・インテグレイター」が世界市場を制覇
現在進行中の第二次情報通信改革において、主要通信企業は、電気通信事業法の業務区分(市内・長距離・国際、一種・二種等)の制約を超え、通信のエンド・トゥ・エンド化(総合化)を志向している。
やや時期尚早の感はあるが、これを経て来たる第三次情報通信改革とも呼ぶべき市場・産業の潮流を簡単に展望したい。
第一に、第三次情報通信改革は、グローバルなマルチメディア・ネットワーク市場における、メガキャリア間の激烈な大競争を経て到来するものとなろう。
第二に、その市場環境は、通信やコンピュータ分野に加え、放送・コンテンツを制する「メディア・インテグレイター」を志向するグローバル企業を中心に、ローカルには中堅的な複数の企業群から形成されるものとなろう。
「メディア・インテグレーション(統合化)」の観点から、現在の通信キャリアの辿る方向を概観すると、およそ次のような段階を想定できよう。
| プラットフォーム事業 | 既に保有の回線設備等インフラを基本とする、現行通信ビジネスを言い換えたもの。 |
| 情報プロバイダー事業 | コンピュータやソフト分野の企業との合併・提携に加え、自らがインターネット接続サービス、エレクトロニックコマース事業など、音声やデータではなく「情報」を仲介・提供し付加価値の高いサービス的要素を強めたもの。 |
| コンテンツ事業 | マルチメディア・ネットワーク市場への本格進出を果たし、コンテンツ、デジタル衛星放送、CATV等の関連事業を手掛けることで通信と放送の一括提供を行うもの。 |
この方向に向けた、海外での若干の兆しを、三つの類型にして示そう【図表3】。
第一は、 BT-MCI 連合の動きに見られる「スーパーキャリア」的なもの。これは、世界通信市場の競争環境が整う2000年頃において、全体市場の1%をとるだけで百億ドルの増収を見込める(BTバランス会長)とする、国際市場を視野に入れたグローバル戦略が極めて明確なアプローチ(BT-MCI型)である。加えて、本連合は自国のCATV事業への関心も高く(BT傘下のCATV子会社による双方向TV実験など)、近い将来により本格的なマルチメディア事業に乗り出す可能性が高い。
第二は、自ら企業を三分割し通信の総合デパートを標榜するAT&Tが、BTと同様にグローバル市場への布石に余念がないことに加え、最近、英ケーブル&ワイヤレス(C&W)が自国回帰を宣言したように、あるいはAT&Tも自国地域市場への参入に意欲的であるように(SBCとの合併交渉)、同時に国内地域市場への足場を築くアプローチ(AT&T型)である。もちろん、両社とも国内CATV市場への新規参入を通じたメディアの統合化の試みを強化している。実際昨年、C&Wが傘下の長距離会社マーキュリーを通じて英CATV四社を合併、衛星放送のBスカイB等との熾烈な競争を繰り広げている。
第三は、まずは自国内の地域市場にしっかりと根ざし、同じ地域電話会社やCATV会社との提携・合併を通じた規模の拡大(メディア統合化)にも意欲的であり、同時に長距離市場への参入機会も抜け目なく窺っている。 ナイネックスがパソコン通信最大手のAOL子会社と提携、また、独立系のGTE等がインターネット接続会社を昨年買収した総合通信化の動き、あるいは米国の電力・天然ガス会社による地域通信や衛星放送・インターネット接続事業への新規進出などもこの類型に入れられよう。
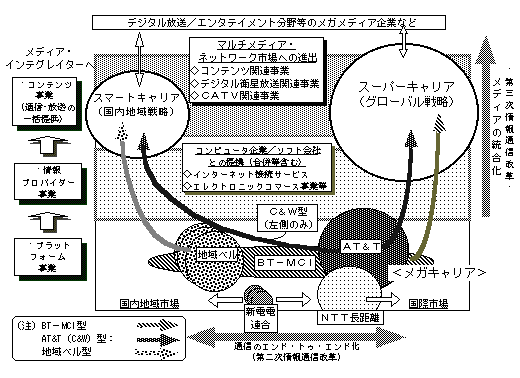
(出所)日本総合研究所 戦略ネットワークマネジメント・クラスター
特に第三の、国内地域戦略を明確にし、エンドユーザーを囲い込み、一人の顧客に対しよりきめ細かなサービスを提供することが、新たに顧客数を増加させる従来の方法よりも、顧客から多くの利用・購買行動を引き出すこととなり(ワン・トゥー・ワン・マーケティング)、ひいては収益増大に結び付けることができよう。必ずしも「規模」のみに捕われない、この事業スタイルを追求する通信会社を「スマートキャリア」と呼びたい。
グローバル戦略を明確にする「スーパーキャリア」にせよ、国内地域戦略に特化する「スマートキャリア」にせよ、メディアの統合化が、将来のキャリアの目指す方向のキーワードになるに違いない。
●NTTに真に対抗できる強固な大同団結の結集を!
汎米州市場におけるBT-MCI 連合の資本関係を伴った強力な布陣(コンサート)が、AT&Tの緩やかなワールド・パートナーズを慌てさせたことは前述の通りである。また、「通信の総合化(エンド・トゥ・エンド化)」の段階において、同サービスの収益の拠り所となる最終顧客への接点を、直接確保しておくこと(地域市場への進出)も極めて重要である。
わが国において、規模の面で圧倒的に強力なNTTに対抗できる勢力を本当に創りえるだろうか。この試みには、世界のどの国のケースも直接参考にできるものはない。今回のNTTの再編案では、米国のAT&Tと地域ベル会社のように資本関係で独立した競争を行うことはできない。まだ英国の当時の複占体制(BTとマーキュリーの二社)とその後のCATV会社や外資勢力を招き入れた多元的な競争環境の方が、わが国の今後の展開には参考になる。
鍵は大括りな競争勢力を一つないし二つ結集できるかどうかであろう。新電電各社が個別に展開する「箱庭競争」ではどうにもならない。
それには、現行新電電に加え、KDDや電力系地域新電電、さらに商社・外資系CATV統括会社(MSO)等との提携による通信ネットワークの規模の確保や、新たな有望市場であるマルチメディア・ネットワーク市場への積極的な進出が必要であろう。また、海外に進出するには一兆円程度の事業規模が必要と言われる。そのためにも合併による選択肢は回避できない。必要であれば、海外キャリアとの戦略的提携も当然視野に入ってくる。
問題はどこが主役(あるいはパトロン)になれるかである。海外の放送・エンタテイメント分野では、大資本力とグランドデザインのもと、メガメディア企業が市場を牽引する例は少なくない。わが国において、自前の回線を自グループに保有し、豊富な資金を持ち合わせている、それが可能なパワーはどこか。そこがキャスティングボートのみならず、大同団結の吸引力となるに違いない。
●新電電の目指すべき「スマートキャリア」とは
その対抗勢力がNTTと、国内市場で真に有効な競争を行えるようにするには次の点が期待される。
| ・ | 「ネットワークの経済」を機能させるため、前述の通り、先の多元的なプレイヤーの結集を通じて、一定の経営規模(ネットワーク規模)を実現させる。 |
| ・ | 利益の源泉である「個客」に直接サービスを行うため、最新技術(無線など)と、従来の長距離系新電電や電力系地域新電電、あるいはCATV会社等の結集勢力の相互接続(NTT網に拠らない)とその相互利用により、明確かつ徹底的な地域戦略のもと、地域市場への進出を本格化させる。 |
| ・ | これまでの不毛な「料金競争」から脱却し、顔の見える事業展開により「付加価値サービス競争」を行えるよう、「ブランド戦略」を導入・強化する。 |
特にNTTに拠らないネットワークとは、エリア面積では限定的であるものの、経済活動の集積地域である大都市部を中心に投資すべきものである。ネットワークの二重投資は、市場全体から見れば得策ではない。したがって、長距離系三社が来春予定している、NTTとの市内交換機(GC)接続(全国1,700箇所)により、一層基幹通信回線に近い箇所での接続を推し進め、NTTへのアクセスチャージの低減が図れる。
また、無線による個客へのダイレクトアクセスは、NTTの独占的地域市場に風穴を開ける可能性があり、非常に注目される。米国等の最先端無線技術の活用により、今や400から500メートルの範囲でテレビ画像と同等の動画像をも送信できる。この手段を通じ、長距離系新電電の中には、鉄道網(山手線など)や道路網(首都高速など)等を利用した無線インフラの拡充により、地域市場の加入者を獲得することができる。米AT&Tは本年2月、地域ベル会社の地域網を迂回(バイパス)する無線技術を発表し、すでに実用化に取り組んでいる。
日進月歩の技術革新は、これまでの固定観念を覆す。わが国「地域」6,000万人市場の熾烈な争奪戦(初の本格的な地域市場競争)はもう目の前にある。
また、「スマートキャリア」の企業像とその企業戦略を明確にすることが不可欠である。先の結集勢力をリードできるスマートキャリアには、コア・コンピテンスの確立がポイントとなる。
それは具体的には、当面のものとして、同業他社あるいは外資企業等との間で戦略的提携交渉をタイムリーにまとめあげられる力、また個客に対しては効果的な広告宣伝をうまく活用し自社(あるいは自社グループ)ブランドの浸透・確立を的確に行える能力である。加えて将来的には、本稿で何度も強調してきた通り、メディアの統合化の道筋を明示でき、かつ着実に実行できる能力である。
最後に、わが国通信市場にも、本格的な有効競争が行われるようになり、価格面とサービスの質の両面 で、消費者への適切なサービスの還元が実現し、同時にわが国マルチメディア・ネットワーク産業の発展につながることを期待したい。

