初めて直面する「ネット革命」の進行を、どのように捉えればよいか?
出典:就職ジャーナル 1998年7月
【基本講座】経済変革および社会変革となる「ネット革命」
1969年の米国防総省のアルパネット(インターネットの前身)開始以来、WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)等の開発を経て、現在、情報検索等の利便性を大幅に向上させた「ネットスケープ・ナビゲータ」等のブラウザソフトを私達は手にするに至っている。これら先駆的なネットワーク技術が一部専門家のものに留まらず、私達の個人生活にも大きな変革をもたらした。自宅やオフィスに居ながらにして最新情報を入手し、オンラインショッピングもできるようになった。この新種のネットワークの急速な普及により、人類が初めて経験する「ネット革命」は、一国の経済のみならず私達の社会活動や生活にまで多大な影響を及ぼし始めた。
●急増するインターネットユーザ-
イーサネット(インターネットの中核技術)開発で知られる技術評論家ボブ・メットカーフ氏が「情報量増大に耐え切れず、1996年にインターネットは崩壊する」とし関係者を驚かせた。しかし、全米科学財団が次世代インターネット網の開発に着手、数年後に毎秒22億ビットという膨大な容量のネットができあがる。今や「メットカーフ予言」は陳腐化している。
1996年末の企業ユーザ-を含む、「ネット革命層」とも呼ぶべきインターネット・アクティブ・ユーザ-の数400万人(「日経マルチメディア」誌調べ)は、堅実に見て(過去5年間のパソコン通信の伸びと同等と見て)、今年末で645万人、そして2003年には2,100万人程度と推定される(筆者予測)。ブームとなっている携帯電話(約3,200万。16歳以上の国民約30%に普及)に比肩する勢いがあり、一大社会現象と呼ぶに相応しい大勢力が出現することになる。
●ネット革命がビジネスの仕組みを抜本的に変える
「ドッグイヤー(犬齢:1年の変化が従来の7年にも相当)」とも呼ぶべき時間尺度の中、ネット革命層は単なる消費者に留まらず今後のビジネスの新興パワーとなるものである。私達はまさに革命前夜からその真っ只中に、現在身を置いているわけだ。ここでビジネスの仕組みに関わる主な動きを見てみよう。
個人の立場からは、自宅に居ながらにして通常並みの仕事が行える、SOHO と呼ばれる勤務形態が出現した。ネットとの親和性を高めた携帯電話やハンディーパソコン等とを組合わせた昨今のモバイル技術進歩は、これを一層普及させるだろう。
また、企業組織の新規形態の例として、製造部門を自社の中に持たず他社資源を活用し、初期投資やリスクを大幅に回避したファブレス経営や、ネット上で必要な経営資源(人・設備・技術等)を結集させ、あたかも実際の企業として具備すべき機能をネット上で発揮するバーチャル・コーポレーション が注目される。
以上は米国の例だが、ここで国内企業の業態の変革例を挙げる。公共料金の支払いはもとより通販の収納代行サービスも定着しつつある、大手コンビニ等による銀行業務進出の可能性だ。電子決済技術をネット上で駆使し、金融機関の独占してきた決済や送金業務の一部代替により、預金を持たない決済機関が登場する。そうなると、電子マネーを充填したICカードをレジに差し込めばオンラインで電子マネーを送れ、支払いは瞬時に完了。現金の確認・輸送・管理コストも大幅低減できる。店頭で休眠中の現金をすぐさま運用できる。こうした数々の目新しい場面は、今後、既存の基本ビジネスフレームを様変わりさせるに十分なはずだ。
●ネット革命の裏舞台で暗躍するネット犯罪
華やかなネットビジネスの導入例や、ドラスティックなサービス利便性の向上が私達の生活にもたらされる反面、ネット犯罪がより深刻な問題となろう(図表参照)。
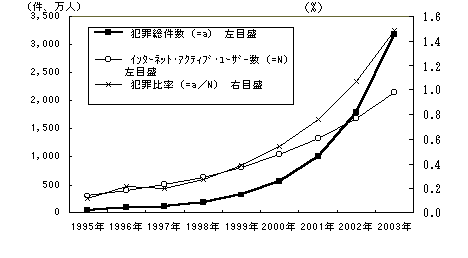
(出所)日本総合研究所 ネットワーク事業戦略クラスター
具体的なネット犯罪の中でも、最も厄介な「なりすまし」犯罪の事例を示す(表参照)。例えば、「契約した覚えのない商品のクレジットカード請求事件」は、ネットで商品を購入したところ、買った覚えのない商品代金30万円をクレジット会社から請求され銀行口座から引き落とされてしまったというもの。これはいつの間にか暗証番号を第三者に読み取られ不正操作が行われたケースだ。
【表】 なりすまし犯罪の事例
| インターネットプロバイダ会員のID盗用(時期不明) | 不明 | 約6万円 |
| 契約した覚えのない商品のクレジットカード請求(時期不明) | 不明 | 30万円 |
| パソコン通信を利用したパソコン部品売名下の詐欺事件(1996年11月検挙) | 1996年11月検挙 | 約210万円 |
| 口座屋事件(1996年11月逮捕) | 1996年11月逮捕 | 不明 |
| 音響楽器販売詐欺事件(1996年11月逮捕) | 1996年11月逮捕 | 約1,100万円 |
| パソコン機器販売詐欺事件(1997年3月逮捕) | 1997年3月逮捕 | 約240万円 |
(出所) 警察庁「情報セキュリティビジョン策定委員会報告書」、警察庁露木康浩「コンピュータ犯罪等の現状と法制度上の課題」(ジュリスト1997.8)、国民生活センターニュース「インターネットの消費者トラブル」(1998.3.4)等を基に日本総合研究所作成
このほか青少年問題など社会的に大きな影響を及ぼしつつある「コンテンツ問題」がわが国でもにわかに注目され出した。特に1996年2月に米国でCDA(通信品位法) が成立した後、海外にも大きな波紋を投げかけている、ネット上のわいせつ画像等の扱いに関するものである。
例えば、今年2月12日、警察庁はインターネットのポルノ画像提供、販売への法規制である風俗営業適正化法改正案を発表し物議をかもした。
ネット犯罪への対策には、これまでの①公開鍵暗号方式やSET等の暗号・プロトコルに関する「技術的対応」、②ネットワーク犯罪防止法等の「法制度的対応」、③消費者に対しID・パスワード等の扱い方法を徹底する「啓蒙・教育」に加え、④電子認証(本人確認等)や電子公証(内容証明等)のための実施機関設置や、損保会社によるネット保険(情報価値の査定・補償)適用等「ネット商取引のインフラ整備」が挙げられる。このような幾層もの対策を講じることで、ネット革命は確実に市民権を得ていくこととなろう。
●ネット革命時代のビジネスパーソン
本格的ネット革命を迎えるに当たり、私達の周りには以上のような予兆がある。このなか特に今後のビジネスパーソンとしては、これを如何に捉えればよいか?紙面の都合により詳細は示せないが、シリコンバレー等地域でのネットビジネスのうねりが、そのビジネスの流儀(情報収集・分析の仕方、ビジネスモデルの作り方、コミュニケーション術、パートナーシップの在り方等)を世界に伝播し、デファクト標準 になりつつある。この新たな流儀を今後しっかりと注視しておきたい。
用語集
●SOHO(ソーホー)
自宅等をオフィスにしている、購買層の知識が豊富な個人や中小事業者の勤務者を対象にした、コンピュータ・ビジネス用家庭市場のことで「スモールオフィス・ホームオフィス」の略。仕事ではパソコンとインターネット等を駆使、電子メールで注文や発注先からの作業指示を受ける。コンピュータソフト業、コンサルタント、不動産業、旅行代理業、生命保険の代理店など、大企業と契約した上で都心にオフィスを構えなくても顧客の身近な存在として活躍できる業種に適している。
●バーチャル・コーポレーション
米国のW・ダビドー氏らの共著「バーチャル・コーポレーション」で有名になった仮想企業の概念。これは専門の知識・スキルを持った個人・グループがネットワークを駆使して必要に応じ有機的に連携し合うことで、顧客ニーズや環境変化に柔軟に対応できるようにするもので、企業の内部資源や機能を有効に活用できる。米国シリコンバレー等で普及しつつある新規の企業形態である。
●通信品位法
子供の目に触れる形でわいせつ画像等をネット上に流すと罰金と禁固刑が科される、あるいは画像を流した本人だけでなくインターネット接続会社などのプロバイダーにも罰則が適用されるとする、「1996年米電気通信法」の付帯法案のこと。言論の自由やプロバイダーの責任を巡り、全米四カ所の連邦地裁で、政府を相手取り違憲訴訟が起きた。「規制は違憲」との連邦地裁初判決に対し、米司法省は同年7月、最高裁に上告するに至り係争中。
●デファクト標準
最近ではマイクロソフト開発の基本ソフト「ウィンドウズ」等の、特にネットワークの世界でその傾向が顕著な、市場シェア等の実勢として業界標準とみなされるようになった技術的な規格。加えて本文では、市場席捲を目論んだ企業等の経営戦略的な手法として、成功企業モデルやその企業人行動原理・パターンが、ネットビジネス上の示唆すべきものになると捉えた。

