欧米の優位に立てないハード志向の日本の通信技術
出典:週刊エコノミスト 1997年11月4日号
ハーバード大学のM・ポーター教授のモデルでは、国家の競争力は「生産要素条件」「関連サポート業界」「需要条件」及び「国内での競争」の軸で表される。わが国は、ハイテク分野のなかでも半導体メモリーや家電機器等のハード分野には圧倒的な強さを誇ってきた。しかし、今日のネットワーク時代にあってわが国の情報通信産業の競争力は、米ITアナリストのモシュラ氏によると「情報家電業界」と「統合した機器市場」において強さを発揮しているものの、米欧に比べ決して有利な立場にない【図表1】。
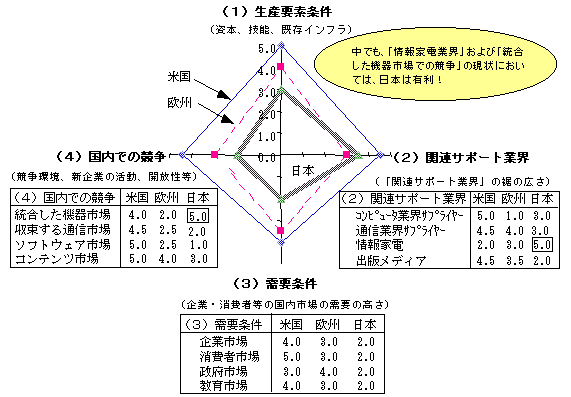
(出所)D.C.Moschella「Waves of Power」から日本総合研究所作成
将来の「マルチメディア・ネットワーク産業」は、①通信機器メーカー等が含まれる装置産業的な「プラットフォーム市場」、②従来の電機通信サービス分野を中心とする「テレコム市場」、③SI企業等がオープン技術を武器にシステム構築等の事業を展開する「インテグレーション市場」、④情報配信等をインターネットを活用し行う「ディストリビューション市場」で構成されている。
こうした4つの市場で構成されるといっても、「プラットフォーム市場」での主要事業者は、これまでのウィンドウズOSと米インテル社製MPU等の関連機器(PC等)を提供する「Wintel」陣営から、同OSと米シスコ社製ルーター等を供給する「Wisco」陣営へとシフトし、通信市場では急速にネットワーク機器が注目を集めている。また、昨今のネットワーク技術確信は、無線や非電話網によるアクセス回線代替を通じた地域市場参入や、モバイル市場の急成長など「テレコム市場」の活性化を促進。さらに、インターネット革命によるコンピュータ型通信へのシフトにより、放送・コンテンツ系サービスを含むマルチメディア・ネットワーク産業への進展として、「インテグレーションン市場」と、「ディストリビューション市場」において、高度かつ多様なサービスの展開が予想される。
これまでのハイテク(半導体等)の特徴であった「軽薄短小」から、ウィンドウズCE搭載の携帯端末(シャープのカラーモバイル等)など最新のインターネット家電では「親密高小」が強みとなっている。すなわち、ユーザーに「親」しく(フレンドリー)、伝送速度が「密」であること、「高」いインテリジェンス、そして「小」型であることが要求される。いずれにせよ、マルチメディア・ネットワーク市場におけるわが国企業の技術的な強みは、NTTの世界トップ水準にある光ファイバー等の基盤技術に加え、ハード中心のメーカー系基幹部品技術(半導体や液晶、電池など)と消費者ニーズを的確かつ迅速に捉えられる企画総合力にあると言えよう。
マルチメディア・ネットワーク市場を、情報の取り扱い」と「サービスの性格」に分けて表したのが図表2である。右上斜め線を基準に右下領域に第一種事業者からの参入を、左上領域には第二種事業者に加えコンピュータメーカー、SI事業者やコンテンツ関連事業者からの参入の現状を示す。図をもとに、わが国を含め世界がしのぎを削る技術を見てみよう。
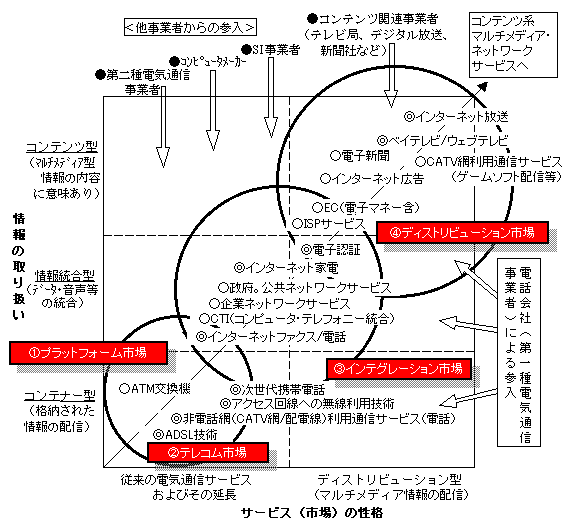
(注)太枠の市場名などは関西大学高橋洋文教授の資料を参照。◎印は本稿で取り上げた技術(市場)
(出所)日本総合研究所 戦略ネットワークマネジメント・クラスター作成
これだけの先端技術
潜在力の大きな地域市場の競争促進技術として、米国で開発されたADSL(非対称形デジタル加入者線伝送)が特に海外では注目される。電話回線と同じペア線を使いメガビット級の高速伝送を光ファイバーに比べ安価に実現する。今年になり初めてイスラエルのOrckit社がISDNリンクを介したADSL通信を一般公開し注目を集めた。
米AT&Tと同様、日本テレコム等が本格的な実験を試みている無線による顧客へのダイレクトアクセス技術は、米国等の最先端無線技術の活用により、今や400~500メートルの範囲でテレビ画像と同等の動画像を送信でき、鉄道網等利用の無線インフラ拡充により、地域市場に風穴を開ける可能性がある。
非電話網(配電線)活用したものとして、加ノーザンテレコム社が英電力・ガス会社の配電線を使い、現行デジタル回線の10倍の速度でデータ通信を実現する新技術がある。これにより電力会社が地域通信に参入し、競争が激化する可能性がある。一方CATVは、ISDNに比べ毎秒10メガビットの高速通信を可能とし、空きチャンネルの利用により、加入者電話回線料が不要になることから、CATV電話のほかインターネットの足回り回線インフラとしても注目される。
携帯技術による次世代モバイル市場の切り札として、新携帯電話方式に関する開発競争が激しくなっている。NTTドコモが開発したISDNと同等の品質と毎秒2メガビットの高速データ通信を実現するW-CDMA(広帯域符号分割多重アクセス)方式を、同社はこれが世界標準となるよう他の独自方式(米CDMAと欧州GSM)と競いながら、各国の通信事業者やメーカーに提案・情報公開を行っている。
新たな市場を創出するためのインターネット技術には、多岐の応用が考えられ、現在、通信事業者が大いに関心を示す分野である。イスラエルAreNet社が今年8月に発表した「E-mail@I-fax」モジュールによる電子メール/ファックスシステム技術は、ユーザーに電子メールアプリケーションからのファックス送信を可能とし、従来回線のファックスのコストを大幅に節約する。
また、インターネット市場を十分機能させるための「電子認証局」は、米国のベリサイン社とサイバートラスト社のわが国への上陸(1994年以降)により脚光を浴びた。電子商取引には事実上の標準である米系クレジット会社提唱の通信手順SET対応の証明書発行等を行うが、わが国銀行カードに関するネット取引の手順がなく商慣行に馴染まないとの指摘がある。一方、日立・富士通・NECの3社が今年9月に設立した「日の丸電子認証会社」は、共同開発の手順SECEにより、わが国銀行業界の支援を取付けSET陣営に対しその採用を働き掛けるなど世界標準を狙う。
欧州通信製品メーカーComOne社は米企業と提携し、テレビ/インターネット機器「SurfTV」の開発を最近発表した。ウェブブラウザ付きテレビを通じてインターネットのナビゲーション、ボイス/電子メールメッセージ、スクリーン上でのファックスの送受信など多くの通信機能を備えており、新規市場創出の例となろう。
わが国の「インターネット放送」の例として、IIJ社のインターネットを使ったビデオ等の動画像をパソコン向けに低コストで一括送信(放送)するサービスがある。キー技術は、回線混雑を解消、端末数の制限なく配信し、途中でコンテンツを複製する「IPマルチキャスト」である。
以上のようにマルチメディア・ネットワーク市場においては、ターゲット市場が明確であり、開発スピードが速くそれに適したベンチャー型の経営を採用する企業に勢いがある。本分野でのわが国のハイテクが部品・ハード機器のみに依然あるとすれば、その強みを活かしたR&Dに加え、グローバル市場を視野に入れたデファクト戦略、マーケティング戦略とネットワーク時代の技術戦略の建直しが必須である。

