特例政令を踏まえたコンピュータ調達への対応
出典:地方自治コンピュータ「特集/コンピュータ調達」 1997年8月
はじめに
特定地方公共団体におけるコンピュータ等の物品・役務等の調達を対象とする「特例政令」とは、平成8年1月1日発効の「政府調達に関する協定」(以下「協定」)を実施するために、国内法令整備の一環として日本国政府が制定した、地方自治法施行令(以下「施行令」)の特例等必要な事項を定める「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」をさすものであり、先の「協定」と同時に発効されたものである。
昨今の情報通信技術の日進月歩の進展、経済活動が急速にボーダレス化しているなか、これまでの保護・育成の閉鎖的な慣行・制度から、WTO(世界貿易機関)等の国際的ルールのもと契約社会への順応・転換が迫られるなど、より競争的でオープンな慣行・制度へ移行しつつある。これは政府レベルのコンピュータ等物品や役務等の調達においても期待されるところ大である。
1. 本稿の検討目的並びに範囲
本稿では、「特例政令」についての中央政府(自治省)から見た見解、あるいは地方公共団体(県・市・町)における取り組み事例についての本誌の記述を受け、最新の国内外の先進的な取り組み事例を参考にし、かつ情報通信技術の活用を前提とした、今後の地方公共団体におけるコンピュータ調達の在り方について整理してみたい。
また検討の範囲は、「特例政令」対象の都道府県及び政令指定都市において、ハードウェア機器、ソフトウェア製品及び関連サービス(コンサルタントサービス、システムの分析・設計・保守サービス、データ入力サービス等)に区分可能な「コンピュータシステム」が、「政府調達協定」及び「特例政令」で通知された内容に加え、地方自治法との比較の中で今後如何に調達されるべきか、あるいはその課題は何か等を整理することである。
2. 政府調達協定と特例政令の相違点
本節では、地方自治法ないし「施行令」も踏まえ、「協定」及び「特例政令」各々に基づいた調達の相違点を明かにすることにより、今後の特定地方公共団体における調達の在り方を探る一助としたい【図表1】。
2.1 基本的な取り組み姿勢
まず、「協定」はWTOで協議・決定された国際法に該当するのに対し、「特例政令」は「協定」の中で「地方政府の機関」として附属書に明示されているものの、国内法による規定となる点が異なる。なお、双方ともに平成8年1月1日をもって発効されたものであり、「特例政令」の中では、特に明示されているものではないが、「協定」でうたわれている内国民待遇及び無差別待遇というGATTの基本精神を受け継いでいる。
一方地方自治法は、50年前の昭和22年に制定されたものであり、グローバル時代のモノやサービスの扱いを前提とした、今回の「協定」「特例政令」とはその時代背景を大きく異にするものである。
2.2 適用範囲
次に、調達の適用対象となる機関や、主な調達対象と適用金額に関して整理する。
「特例政令」における適用対象機関は、全ての地方公共団体を対象とするものではなく、前述の通り、 47都道府県及び政令指定12都市の合計59団体となる。
国際社会の中で、例えば、東京都はいうまでもなく、大阪府や神奈川県などの経済規模はGD P (国内総生産)換算でみて、EU諸国の幾つかの国のそれを上回る規模となっており、地方行政府の国際経済社会に占める位置づけは、より一層大きなものとなっている。その意味で、「特例政令」が海外の企業等に対し入札の機会を与える内容となったことは合点のいくところである。
「協定」と「特例政令」を比較すると、主な調達対象とその適用金額は、前者が産品で13万SDR(特別引出権)、後者が物品等で2,800万円(20万SDR相当)といった違いがある。特定地方公共団体の方が、適用基準額が高めに設定されている。
2.3 事前招請の段階
本項では、競争入札参加者の資格公示や競争入札時の情報提供などについての比較を行う。
「施行令」では、競争入札に対する公告あるいは通知についての記述はあるものの、地元企業に受注させ地場産業の育成・活性化を図ろうということも念頭にあるためか、これまで建設工事契約の「制限付一般競争」の参加資格として、建設共同企業体方式により代表構成員と市内企業構成員とを組み合わせる方式が広く採用されてきている 。
一方、「特例政令」の規定が適用される調達契約(「特定調達契約」と呼ばれる)では、契約締結見込みの年度毎に公示する旨決まっていることに加え、事業所の所在地に関する資格を規定できないこととなっている。これは、「協定」が国内供給者と他の締約国との間の差別を許していないのと同等の精神が貫かれているように思われる。
本契約が、特定地方公共団体のみならず、地元企業に与える影響を考えると大きなものがあるはずである。
次に競争入札時の情報提供等においては、「施行令」が本件について規定していないのに対し、「特例政令」では「協定」と同様に、入札者が競争入札時に情報入手等の機会を平等に得られるような記述となっている。これにより、多様な企業からのより公平な調達のための事前招聘が可能になることが期待される。
2.4 仕様作成の段階
本項では、先の競争入札時の情報提供等の後、入札説明書を応札者に対し提示し、地方公共団体の調達担当者が仕様書を作成する際の特筆事項を示す。
地方自治法ないし「施行令」には、「入札説明書」に関する規定はないが、「特例政令」では「規則で定める事項について説明する文書」とした規定がある。
「協定」には、商標や供給者等を特定してはならない旨の記述があること、また、特定業者に有利になったり特定業者の排除ができなくなったなど、これまで以上に厳しい内容となったことに対し、「特例政令」ではこれには言及していない。
2.5 入札手続きの段階
地方自治法は、代表的な入札方式について次のように定義している。
●「一般競争入札」(同法第234条)
◇定義: 契約に関する公告をし、一定の資格を有する不特定多数の者をして入札の方法によって競争させ、最も有利な条件を提供した者との間に契約を締結する契約方式
●「指名競争入札」(施行令第167条)
◇定義: 資力信用その他について適当である特定多数の競争参加者を選んで入札の方法によって競争させ、最も有利な条件を提供した者との間に契約を締結する契約方式
◇適用3条件:
・当該契約の性質又は目的が一般競争入札に適しない場合
・参加者が一般競争入札に付する必要がないほど少数の場合
・一般競争入札に付することが不利と認められる場合
●「随意契約」(施行令第167条の二)
◇定義: 競争の方法によることなく、任意に特定の者を選んで契約を締結する契約方式
◇適用7条件:
・緊急の必要により競争入札に付することができない場合
・競争入札に付することが不利と認められる場合
・時価に比して著しく有利な価格で契約を締結できる場合
・競争入札に付し入札者がいない場合など
一方、「協定」での入札の手続きは、上記入札手続きとほぼ対応したかたちで、以下のように分類されている。
●「公開入札」: 関心を有する全ての供給者向けのもの
●「選択入札」: 機関召集された供給者に対するもの
●「限定入札」: 機関が供給者と個別に折衝するもの
「特例政令」では、自治法と同様に「一般競争入札」「指名競争入札」及び「随意契約」という表現が用いられているが、同政令の定める例外的な事項を除き、原則「随意契約」は行えないこととなっている。
特定地方公共団体において「特例政令」の適用対象となる「コンピュータシステム」(定義は前述の通り)の調達では、政府調達と同様に、まず「芸術品その他これに類するもの」では通常ありえず、また、既に調達を行った物品等の「交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等」でもない限り、随意契約による調達を実施することができなくなった。この規定は、「施行令」第167条の二(上記適用7条件)における規定よりも厳しいものであると言えよう。
しかしながら、コンピュータシステムの場合、「特許権等の排他的権利若しくは特殊な技術に係る」もの、例えば、特許権を保有するようになったソフトウェアが含まれるため、「特例政令」の本規定については、適切な判断が期待されるところである。
2.6 契約及び評価の段階
さて競争入札による契約締結の際、「施行令」では、競争入札の場合、予定価格の制限の範囲をもって申込みをした者を契約の相手方とすることになっており、「特例政令」でも基本的にこの考えが踏襲されているようである。
次に、各応札者のプロポーザル(提案書)を評価する段階で、政府調達では「総合評価方式」が適用できるのに対し、地方自治法及び「特例政令」ともに「最低価格方式」を適用することが決まっている。これは、いかに特定地方公共団体であっても、同法の適用対象となるからである。
ところで、37年前の昭和35年、大阪市に電子計算機が導入されたのが、わが国地方公共団体における最初のケースである。当時に競争入札的なプロセスで調達がなされたかどうか、あいにく筆者は知らないが、これ以来、地方行政分野においても、事務処理の効率化等のためコンピュータが導入・利用されてきた。
早急に現行地方自治法を改正することは難しい面も多々あるものと推察されるが、今日の時代環境等を鑑み、より効率的でかつ効果的な調達を地方公共団体で行うには、機能対価格で調達先を決定する際の「総合評価方式」の適用が、早い時期に、少なくとも特定地方公共団体には求められるものとなろう。もしそうなれば、旧来の最低価格方式による評価と異なり、日本企業が走りがちだった価格勝負一辺倒では落札しにくい状況となり、調達側および入札双方にとってより健全な仕組みとなり得よう。
2.7 落札の段階
最後に、落札時の段階における相違点を整理したい。
地方自治法ないし「施行令」には、何ら規定がないのに対し、「協定」ではたとえ「限定入札(随意契約)」であっても落札に関する経過等を、あるいは落札情報を公的な出版物に公開することが明示されている。この点「特例政令」では、特定地方公共団体の定めにより公示するものとなっており、政府調達と同様な取り組み姿勢が期待されていると思われる。
さらに、苦情等落札後の対応として、苦情処理機関の設置を規定していることが特筆すべき点である。
新たな政府調達苦情処理体制として、経済企画庁調整局政府調達苦情処理対策室では、CHANS(Office for Government Procurement Challenge System)と呼ぶ、弁護士や大学等からの専門委員14名で構成する苦情処理体制(本部長;内閣官房長官)が設けられている 。
この体制では、官報、インターネット等において公示がなされた後、5日以内に事務局まで、「参加希望の苦情(政府調達苦情検討委員会公示第○号 )」や住所氏名など所定の項目について連絡することにより、苦情処理手続に参加が可能となる。将来は、地方公共団体においても、こうした具体的な体制が各団体共通の機能・基盤として求められるに違いない。
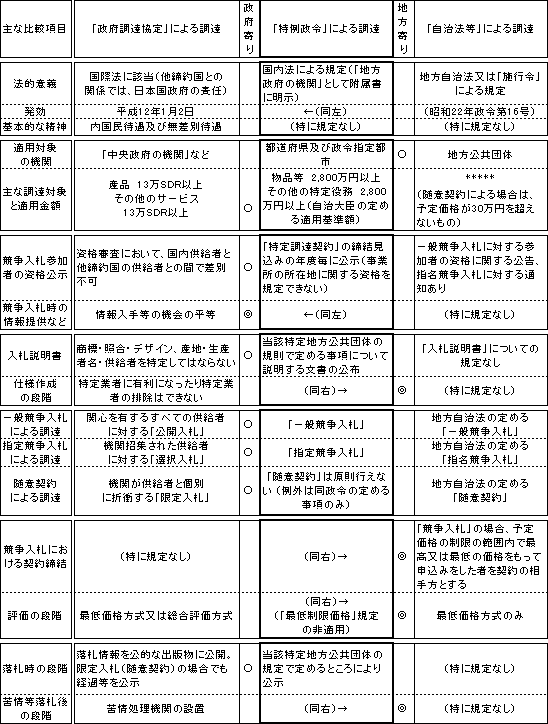
(出所)日本総合研究所
3. 調達に係る取り組み事例
3.1 諸外国の例
政府調達協定締約国であるカナダ、米国、そして非締約国ではあるが、行政改革において先進的なオーストラリアを例に、海外機関の取り組みを簡単に示す。
1)カナダ政府
自治大臣官房課長補佐として1996年10月のAPEC政府調達セミナーに出席した佐々木浩氏の報告 によると、カナダでは「協定手続きの導入に当たって、新たな事務負担に関する行政の不満は出たが民間からの不満は一掃されている。透明競争による利益は確実に負担を上回っている」とのことである。
昨今、行政サービスの効率化が声高に叫ばれるなか、調達に伴う行政コストと民間へのリターン(事業機会の獲得等)との双方の関係において、従前の方法に比べ競争条件の一層の確保並びにトータルでコストダウンが図れるのであれば、所期の精神・目的が達成されよう。
(2)米国政府及び地方政府
米国では、「現行政府調達協定の加盟に当たっては、連邦調達庁(筆者注;GSA)との接触がなく、USTR(筆者注;米国通商代表部)がNASPA(州政府調達庁全国連合)の力を借りつつ、州政府に対し個別に協定への加入を説得する必要があった」【同報告】とのことである。
スーパーコンピュータ調達が話題となった1994年7月に、政府調達問題でGSA(The Office of Federal Information Resources Management部門等)やUSTR(the Japan Desk)、ニューヨーク州の3つの郡政府を筆者らが尋ね意見交換を行った時にも、地方政府と連邦政府との間に本問題で統一的な見解が示されていたわけではなかった。ただ当時から、評価プロセスや同基準の明確化を前提とする、一般競争入札中心主義は、そのドキュメントの整備状況と過去の調達実績等から、英国と並び世界で最も浸透していたものと推察される。
また、30万米ドル以下の調達については、CBD(Commerce Business Daily)と称する電子広報システムを活用するなど、情報通信技術を用いた取り組みには先進的なものがあった 。
(3)オーストラリア政府
ニュージーランドと並んで、大胆なアウトソーシング(業務の外部委託)など、行政改革において先進的な取り組みが行われているオーストラリア政府の場合 、従来の官公庁的な文化、書類による業務システム、行政支援活動といった政府の役割を、よりビジネス志向の文化を目指し、電子商取引や戦略的なマネジメント機能を備えた役割へと目標を再設定し変革を推し進めている。
また同国では、「オーストラリアにおける政府調達マネジメントと組織についての指針」というものがあり、まず政府調達の戦略的な役割が決定され、民間企業の効率化を模した抜本的な取り組みが行われている。
物資・サービスの配置を確認した後には、政府組織におけるマネジメントの在り方を決定し、ターゲット(調達対象)と規模の決定など、一連のループが描かれており、不具合があればそのループの中で、次の調達時にはそれが解決できるような仕組みとなっている【図表2】。
【図表2】 オーストラリアにおける政府調達
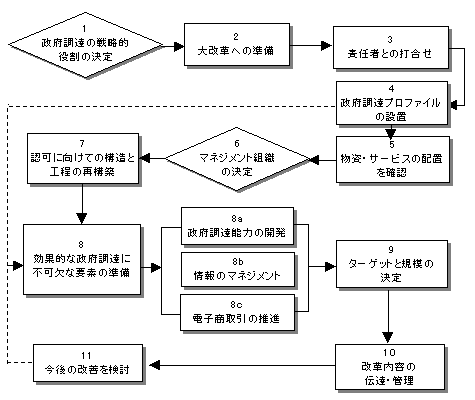
(出所)「オーストラリアにおける政府調達マネジメントと組織についての指針」から日本総合研究所作成
3.2 わが国中央省庁
郵政省では、「郵政省調達品サイバーカタログの提供」 として、国内及び国外供給者へ情報提供機会の拡大のため、インターネットにより、平成8年5月28日から政府調達情報を提供している。具体的には、調達物品(通信機器やコンピュータ等)の写真、仕様及び用途、そして調達している主なサービスが示されている(掲載品目約150)。
調達プロセスは、英文ホームページ上で視覚的にも分かりやすく掲載されており、海外企業等からも簡単に同省の調達について情報が得られるような配慮がなされている。
通商産業省機械情報産業局の「コンピュータの政府調達における外国製品等調達について」 の中で、内閣外政審議室が「日本の公共部門のコンピュータ製品及びサービスの調達に関する措置」の対象機関に対して実施した調達の結果が報告されている。
それによると1994年度の外国製品調達比率は、製品合計で29.3%であり、91年度の8.8%と比較すると、同比率は大幅に増大した。同措置に基づき、このように年々、外国製品の調達参入機会が増えている実態を考えると、次に述べる地方公共団体においても自ずと門戸をより一層開放せざるを得ないこととなろう。
3.3 地方公共団体
わが国の地方公共団体の例として、東京都と神奈川県の例を示す。なお双方は、首都圏に位置する一都三県(他に埼玉県、千葉県)の情報管理部門における「政府調達に関する研究会」のメンバーである。
(1)東京都
東京都のケース では、契約方式案において調達対象を「ハードウェア」「ソフトウェア」「その他」に分類し、かつ各々に対し「原則入札」「随意契約が可能」「入札が望ましいが特例政令の随意契約理由に該当」など都度契約方式を判断することを試みている。
また、委託先選定方法案として、従来の「業者選定委員会」において、業者数社からの「提案書」の比較検討・随意契約による契約という方式から、「仕様検討委員会」による「仕様書」を基にした「競争入札」による契約方式の導入を検討している。
(2)神奈川県
神奈川県のケース では、財務部門やシステム部門の担当者が作成した「システム開発委託等のガイドライン」により、新制度への円滑な移行を図っている。
ガイドラインの特徴として、従来まで未分離であった様々な業務を、その特質や類型毎に調達の方向性を示している。
その区分は、「システム企画・設計立案」「システム開発(上流、下流工程)」「システム運用(特殊制御、オペレータ・ハンドラー、保守・プログラム修正、データ入力等)」「機器導入(システム用、OA用)」といった具合に、調達参入機会の拡大を図るため可能な限りの分割を試みている。
また、事前招請等の情報収集活動をとりいれた手続きの例として、「簡易技術提案(ミニプロポーザル)」及び「競争入札手続き」を併用したものを、「情報収集段階」と「価格評価段階」とに分け検討している。
一方、「情報システムの調達にあたって必要な仕様書の記載内容(抄)」やその例が詳細かつ具体的に示されており大変参考になる。
この2つの地方公共団体の場合は、地方自治法の規定により、政府調達では可能な「総合評価方式」をとることができないため、如何にして「仕様書」側で工夫を施し、価格以外の総合的な要素を調達時に反映するかに取り組んでいるケースといえよう。
4. サイバーネットワーク時代の調達の在り方
わが国中央政府において、建設省が公共工事の受発注に「電子入札」の導入を計画 している。
同省によると、同受発注業務をインターネット上で処理する仕組みの技術開発(暗号化技術、電子認証システム等)を1998年度末までに終え、2年間の試行後、遅くとも2001年には実施するとのことである。
インターネットの活用は、入札に留まるものではなく、工事概要の事前公告、届け出の書類の提出、入札参加の資格審査、契約手続きなど関連情報のやり取りにも利用する方針である。これにより、国内外の多くの業者に参加機会を与え、業者間の競争を促進すること、あるいは調達に伴うコスト削減が期待されている。
米国防省で本格スタートしたCALS(コンピュータ援用の調達システム)やEDI(電子データ交換)などの電子的な仕組みを、限定のないインターネット上で行うオープンな調達により、安価で効率的な調達を行うことも遠い将来の話しではなくなってきた。
米ゼネラル・エレクトリック(GE)社は、ネット調達システム「TPN(Trading Process Network)」 を1996年に開始し、同年の部材調達金額は3億5千万ドルから、今年末には10億ドル、98年末には20億ドルに膨らむ見通しである。また、2000年までに「ネット調達」市場は、約70億ドルに拡大すると予測されており、同様のネット調達システムの活躍の場が一層増えるに違いない。
このネット調達は、サプライヤーの過去の取引実績を問わず、自由に入札できることにより、わが国の従来の系列による取引慣行に対し、抜本的な変更・変革を迫る仕組みとなることが予想される。
5. 今後の取り組みへの示唆
今日では、コンピュータを中心とする情報通信技術の恩恵により、情報収集能力の飛躍的な向上が図られており、サイバーネットワーク時代にあって、調達事例集の蓄積や、同ネットワーク上での公開による情報・ノウハウの共有化などが簡単に図られるようになり、調達事前招請段階でのネットワークの活用がより一層重要なものとなってきた。
中央省庁では、「一人一台パソコン」が標榜されるなど、積極的な情報化投資が続けられている。既存コンピュータシステムの運用を含め、年間の予算は1996年度で9,612億円、97年度予算は1兆円を超えるとされ 、今や国内最大級のユーザーとなってきた。
同様に地方公共団体での情報化投資額の規模からしても、「地方公共団体市場」の魅力度に加え、「御用達」といった民間へのアピール効果も手伝い、より一層透明な調達プロセスが不可欠となる。
ただ、政府調達の場合のように、総合評価方式の導入を前提とした際の「点数化作業」は、情報システム部門にとってはより煩雑な業務になるものと言われている。
一方、比較的小規模な「部門等」への提案営業やコンサルティング・サービス、アフターサービス等について、「適用基準額」に満たない調達に関しては、依然不透明な部分も残ることが推察される。
前述の時代環境に合わせた地方自治法の改正に加え、本分野の調達について、より公平で合理的な調達の仕組みが、今後確立されることが期待されるところである。

