なぜ少子化は止められないのか
日経プレミアシリーズ
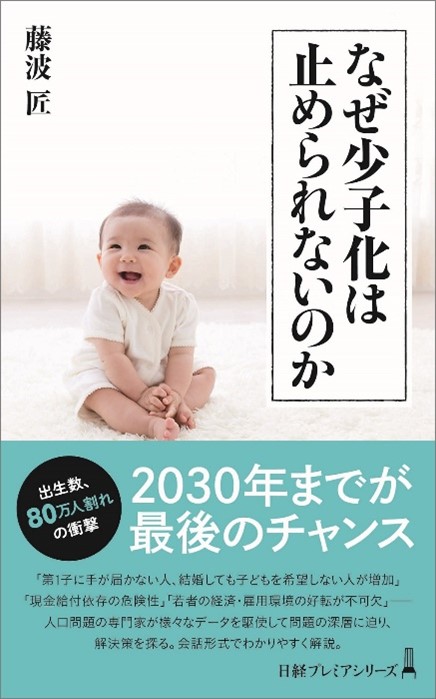
- 著者
- 藤波匠(調査部)
- 出版社名
- 日経BP 日本経済新聞出版本部
- 出版日
- 2023年5月11日
- 価格
- ¥990(税込)
なぜ少子化は止まらないのか。どのような手を打てばよいのか。若者の意識の変化や経済環境の悪化、現金給付の効果など、人口問題の専門家が様々なデータを基に分析、会話形式でわかりやすく解説します。
目次
- 第1章 加速する少子化
- わずか7年で20%以上減少した出生数
- 出産の年齢的な制約への意識
- 子ども3人は難しい理由
- 団塊ジュニア世代で非婚・晩婚が進んだ
- 手遅れとあきらめてはいけない
- 2025年には出生数70万人割れ?
- 少子化の原因は非婚・晩婚ではなくなっている
- 結婚した人の出生率が下がっている
- 若者の9割近くが結婚願望を持つ意外
- 未婚男性の5割近くが結婚相手の経済力を重視
- 2021年調査で明かされた衝撃のデータ
- 非正規雇用の女性は結婚・出産に後ろ向き
- なぜ若い世代の賃金は上がらないのか
- 少子化の本質的な問題はどこにあるのか
- 現金給付を多少増やしても少子化は改善しない
- フィンランドも実は日本並みの出生率に低下
- 経済環境が出生率を左右する現実
- 人手不足なのに賃金が上がらないカラクリ
- 非正規や高齢労働者の増加も賃金を下押し
- 人口減で経済はどこまで縮むのか
- 保育所を充実させても少子化は止まらない
- 非正規の女性は結婚・出産の意欲が低い
- 相変わらず犠牲になる女性のキャリア
- 家事・育児負担の男女差はいまだに大きい
- 東京都5000円支給策の懸念
- 日本の構造問題にメスを入れる必要性
- 「少子化対策は手遅れ」という主張の落とし穴
- 経済成長がなくて本当に豊かに暮らせるのか
- 日本企業のDXが進まない理由
- テレワークが増えない残念な状況
- コンパクトシティはあきらめたわけではない
- ハードルが高いコンパクトシティの現実
- 移民が来ても出生率が上がるとは限らない
- 「経済成長はもういらない」という老人を怒鳴りつけたい
- 税収の自然増で毎年6兆円を確保する案
- 児童手当をどこまで増やすべきか
- 多子世帯優遇は不要
- 給付付き税額控除、N分N乗税制の問題点
- 所得制限は撤廃すべきなのか
- 子ども保険創設への課題
- 給付増のための増税が少子化に拍車をかける?
- 中小企業の賃金引き上げがカギ
- 人手不足を意図的につくり変革を生む
- 非製造業で研究者が増えていない
- 実は低い日本の大学進学率
- 研究開発型の農業で輸出促進
- 鶏卵にみる技術者の権益の重要性
- なぜ女性は地方から東京に向かうのか
- いまだに「家制度」に縛られている地方の男性
- コロナ禍の中、大都市で正規採用される女性は増えていた
- 東京の企業に一本釣りされる地方の優秀な女性
- 地方にも高度人材を受け入れる雇用が必要
- 育休中にリスキリングしてはいけないのか
- 余裕を持って子育てできる体制をつくるには
- 育休をアップデートする
- 行きすぎた現金給付のリスク
- 結婚を支援するために最も重要なこと
- 大学の存在意義と学費の問題
- 子育て支援は企業の役割がいっそう重要に

