「北の国から」で読む日本社会
-日経プレミアシリーズ
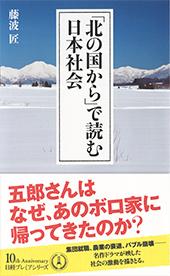
- 著者
- 藤波匠(調査部)
- 出版社名
- 日本経済新聞出版社
- 出版日
- 2017年11月9日
- 価格
- ¥850+税
五郎さんが生きた、あの時代。
フジテレビで1981年から2002年にわたって放映され、国民的な人気ドラマとなった「北の国から」。単なるヒューマンドラマにとどまらず、戦後間もないころから現代までの日本の社会のあり様とその変化を描いた秀作でもある。
ドラマがリアルタイムで描いた1980年代から2002年まではもちろんのこと、戦後の富良野で黒板五郎が成長し、東京で家族を持つまでの時代をも物語の背景として取り込み、ドラマは1 人の男の生涯を描いたものとなっている。
本書では、そうした黒板五郎を中心としたドラマの登場人物たちの人間模様を取り上げ、その背景にある社会の変化―東京への人口移動、大量消費社会の台頭、農業の衰退、バブル崩壊、交通事情の変化、恋愛の変遷、受験戦争、ゴミ問題などに注目し、改めて戦後日本のあり様を見直す。[関連記事]KyodoWeeklyNo.3,2018年1月15日号(PDF220KB)![]()
目次
- 子どもを富良野に連れ帰った五郎の真意
- “もの"に対する純の意識の変化
- 螢の複雑な想い
- 現代の暮らしが形作られた1980年ごろ
- 東京に多くの若者が流入した1960年代
- 富良野からも失われた五郎の理想
- あえてボロ家に帰ったわけ
- 「お前ら敗けて逃げるんじゃ」
- 1961年、農業が変わった
- 農業の機械化と離農のすすめ
- 廃屋の数だけ物語がある
- 農家にとって厳しい富良野、麓郷の大地
- 北海道では離農が農地集約を促した
- 8割以上の農家が離農
- 補助金による市場のゆがみ
- 赤い牛乳が意味するもの
- 集約と経営の合理化で利を得たのはごく一部
- 農業だけでは食えない厳しい自然
- 五郎の親兄弟はもういない
- 炭鉱で死んだ兄たち
- 国内石炭産業の盛衰
- 東京に出たのが自然だった時代背景
- 「金の卵」たちはどこに行ったのか
- 東京で職を転々とした五郎と純
- 1970年以降、若者は地方へ
- 金なしでも何とかするのが男の仕事
- 金銭トラブルに巻き込まれる五郎
- ラーメン店での名シーン
- 1万円札2枚が意味するもの
- 日本人の金銭感覚
- 誠意とは何か
- 失ったものと引き換えに得たもの
- バブル景気に救われた東京での純
- バブル崩壊とともに地方に流れた若者たち
- 富良野で経済的な安定を得た純
- バブルの牙に周回遅れで襲われる
- ツケは最果ての地にも
- バブルにもてあそばれた農民たち
- ぶれない五郎の生き様
- なぜ五郎は令子の葬儀に遅れて来たのか
- 飛行機か、鉄道か
- 十和田2号が運んでいたもの
- 姿を消した夜行列車
- 次々と廃線になる北海道の鉄路
- 合理性の追求が大切なものを見失わせる
- 何を残し、だれが残すのか
- 大人向けドラマとしての『北の国から』
- 積極的に取り上げた人の性
- わかってはいるがどうにもならない
- 螢のまぶしい後ろ姿とれいのウエディングドレス
- 妊娠女性の決断と中絶
- 身近になる不倫と離婚
- 性を商品化する社会
- だれにでもある言いたくない過去
- 一億総批評家社会の怖さ
- 優等生タイプの純と体育会系の螢
- 純の塾通いは社会の変化を受けたもの
- ユニークな凉子先生の教育方針
- 子ども自身の学び取る力を重視する教育
- 若年者の自殺
- 凉子先生は五郎にとっても師
- 五郎の生への執着
- ゴミを出さない五郎の暮らし
- ゴミ戦争に見舞われた五郎が暮らした東京
- 五郎に感化される純
- 先進的な富良野のゴミ処理
- ゴミ収集の仕事にやりがいを見出す純
- ゴミと宝の境い目
- 石の家や拾ってきた家は文明への風刺か
- 豊かさの本質

