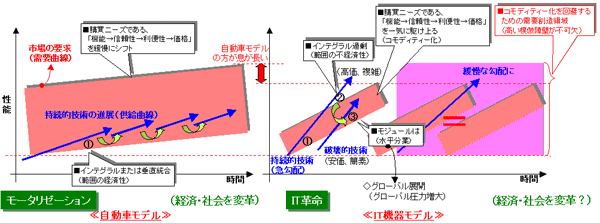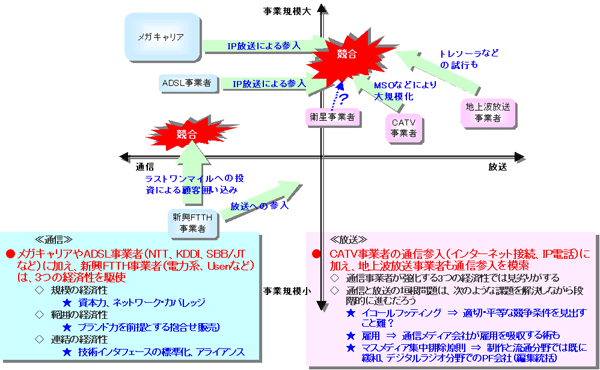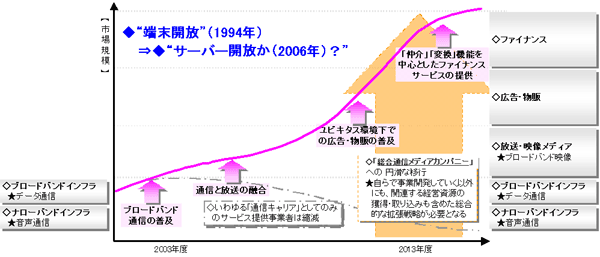「光ブロードバンドの進展がもたらす産業・社会へのインパク
ト」 |
 | |
|
| ||
| <講演のポイント> ・光ファイバーは、2000年の ITバブル以降も着々と整備が進んできており、社会や産業のインフラとしてますます重要な意味合いを持ってきている。光ファイバーは一般に 最高100メガの回線速度を持っており、技術的にはテレビの生中継と同じ画像をインターネットで送ることができる。また、光ファイバーの素 材は無尽蔵にあり、電気的ノイズにも強く、人類が手にした最後の通信手段だと言われている。 ・光ファイバーの普及には敷設コスト の回収がネックであり、競争原理だけに委ねると、整備が都市部に集中してしまう。光ファイバーの整備には地方への配慮が欠かせない。 ・光ファイバーの超高速大容量の特性を生かして、IP電話とインターネット、動画配信の3つを合わせた「トリプルプレー」と言われる サービスが普及するようになる。 ・その結果、放送と通信の融合、放送と携帯電話との連携、固定電話網と携帯電話との統合など、情 報通信業界の事業環境は全く新しい局面に入る。 ・ITや情報通信関連の産業だけが頑張っても、日本経済は回復しない。産業界が良い 製品を作り、画期的なサービスを考え出しても、財布の中身が豊かでないと、物は売れないわけで、消費の拡大が期待できる経済政策が重要に なる。 ・ITを活用することで、マネジメントの仕方、ノウハウ、さらには、マネジメントの状況を「見える化する」(可視化する)こ とが、今後の企業経営のポイントになる。 | ||
|
| ||
| ただ今、ご紹介いただきました、新保でございます。本日は 、「光ブロードバンドの親展がもたらす産業・社会へのインパクト」と題してお話させていただきます。 | ||
| 1.次世代ネットワークの現状と今後の方向 ◇光ファイバーの将来性 最初に、次世代ネットワークの現状と今後の方向についてお話いたします。 情報通信分野のインフラとして光ファイバーが話題になっています。光ファイバーは、2000年のITバブル崩壊以降も着々 と整備が進んでおり、社会や産業のインフラとしてますます重要な意味合いを持ってきています。通信事業者をはじめ、その利用者にとって、 通信コストの削減や新たなビジネスチャンスをもたらす大きなきっかけになり得るでしょう。 光ファイバーは、一般には最高100メガの回線速度を持っています。これは、新聞朝刊で20日分ぐらいの膨大な情報を1秒 間で伝達することができる能力です。BSデジタル放送やハイビジョンといった高画質のテレビ放送を送信するには、28Mbps、つまり1秒間 に28メガという速度が必要ですが、これも可能となります。技術的には、テレビの生中継と同じ様な動画をインターネットで見ることができ ます。著作権などの問題を除けば、光ファイバーを使って放送も通信もできる時代になっているのです。 光ファイバーの材料は、土の中にあるため、地球環境にやさしく、ほぼ無尽蔵に入手できます。また 、光ファイバーは、電気的なノイズにも強く、総合的にみると、人類が手にした最後の通信手段ではないかと言われております。 ただ、普及に関しては、敷設コストの回収を考慮しなければなりません。ですから、競争原理に委ね てしまうと、どうしても都市部だけに集中してしまい、地方は置いていかれてしまうということがあります。 現在、NTT東西会社は、全国広くあまねく同一料金でサービスを行う「ユニバーサルサービス」の義務を課せられています 。 これと同様に光ファイバーについても、地方への配慮をしなければなりません。日立製作所庄山社長や慶応大学の国領教授 らが構成員をつとめる評価専門調査会から今年出された、政府のe-Japan戦略に関する報告書の中に、光ファイバーとユニバーサルサービスの 問題が示されています。光ファイバーは、日本全国共通のインフラにする必要があると思います。 また、道路や橋と同じようにインフラを整備すれば、次は、それを活用する段階になります。それを使って、いかに付加価 値をつけるか、生産性を上げるかという経済性のステージに入ります。今年5月末の政府のIT戦略会議で、慶応大学の村井教授が小泉首相に「わ が国のITインフラは、間違いなく世界最先端である。問題は、マーケットである。マーケットが、いかにこれから活気を呈して行くかが重要で ある。」ということをおっしゃっていました。私も今後はそこがポイントであると考えております。 ◇デジタル家電と景気 次に、ITの応用形であるデジタル家電、ネット家電、あるいは、情報家電と呼ばれているものについてお話します。 現在の景気を浮揚させるには、こういった先進的な技術が生まれたときに、それに応じたマーケット をいかにつくり出していけるかどうかにかかっています。 その話をしていくのにあたって、技術の供給とそれを受け止める市場の変化・需要面について申し上 げたいと思います。 1950年代後半、特に、1964年の東京オリンピックを契機として、白黒テレビ・電気洗濯機・電気冷蔵庫という3種の神器が 爆発的に普及しました。仮に1956年をスタートとしますと、世帯普及率が100%近くになるのに、10年くらいしかかかっておりません。VTR やルームエアコンなども、それに近い伸びを示しています。これらの製品は、戦後の景気浮揚の大きなドライバー(推進力)になったと考えら れます。 それでは、新3種の神器といわれるデジカメ・DVD・薄型テレビといったデジタル家電はどうかといいますと、市場に投入 されてから急激に売り上げを伸ばし、わずか数年後の昨年の夏ぐらいから失速気味になっています。 新技術・新製品の普及と景気の波との関係を振り返ってみると、やはり供給側の努力だけではダメだ ということです。いかにいい物を作っても、その需要につながる財布の中身と財布の紐の固さと言いますか、消費者側のマインドを刺激するよ うな経済政策とセットでなければうまく普及していきません。 また、もう一つ見落としてはならないのは、需要と供給の関係です。 戦後の景気を引っ張ってきた自動車と最近のIT製品を比較してみますと、IT系は短期間にかつ急激に売上高が上昇しますが 、自動車の方は、立ち上がりは緩やかでしたが息長く普及してきています。 自動車というのは、供給側が新車や新技術を提供するのに応じて、需要側も拡大し続けています。い わば、需要のレンジの中に、供給曲線がうまくはまっているというような格好になり、需給がしっかりとマッチしています。その相互作用によ り産業が大きくなっており、海外マーケットにおいても成功しています。 それに対して、IT製品は、技術開発が早く、企業間競争がより激しいものですから、供給側が、消費者の期待を上回るスピ ードで技術的に先へ行ってしまいます。そのため、余計な機能がついたりして、とかく先走りする傾向があります。必ずしも単純な比較はでき ませんが、例えば自動車産業を見習い、次の需要を引き出すような手を打たなければいけません。【資料1】 | ||
|
【資料1】コモディティー化回避のための需要創造 | ||
|
| ||
| (出所) | 日本総合研究所作成 | |
|
◇固定電話網のIP化 では次に、固定電話のIP化(インターネット・プロトコル)のお話をいたします。 昨年の6月に、イギリスのブリティッシュテレコム(BT)という会社が、電話網のIP化を宣言しました。電話会社がIP化をす るということは、今まで使っていた一つ10億円程度かかる交換機を、ルーターとかスイッチとか呼ばれる十数万円~数十万円ぐらいの簡素な機 械に置き換えることです。そうしたデジタルのネットワークに作り替えると、単に音声だけではなく、インターネットも映像も、同じネットワ ークに乗せることができ、コストも非常に安くなります。 ブリティッシュテレコムと同様に、KDDIも明確にIP化を打ち出しました。彼らは電話網のフルIP化を2008年3月までに終了 する計画です。NTTグループも、昨年11月に発表した経営計画の中で、2010年ぐらいまでに固定電話の約半数をIP化するとしています。ソフト バンクグループは、最初からIPで通信網を構築しています。 ◇トリプルプレー IP化が進む中で通信事業者が取り組んでいるのが、光ファイバーの超高速大容量の特性を活かしたトリプルプレーです。ト リプルプレーというのは、固定系のIP電話、インターネット、映像(動画)配信の3つを合わせたサービスをいいます。 トリプルプレーは、2年ぐらい前から、アメリカでも言われ、ヨーロッパのIT後進国といわれていたイタリアでも既にその 前から行われています。日本でも、IP化が進んできましたのでKDDIやNTTグループをはじめ、ソフトバンクグループ、ケイ・オプティコム、ス カイパーフェクトTVなどで動画コンテンツを配信できるようになっています。しかし、現在はまだ、著作権などいろいろ未解決の問題があり、 地上波コンテンツの再送信は一部の方式しか認められていません。他の方式は、ハリウッドや映像所有者と交渉して映画やスポーツなどを配信 しています。 それでは、映像を通信網で送るサービスは今どういった状況であるかといいますと、まだ低調な滑り 出しといったところです。これを視聴するためには、一般のテレビ放送と違って、ブロードバンド放送を扱うプロバイダーと契約しなければな りません。この点が今のところ普及率がうまく上がらない理由ではないでしょうか。 ただし、今までのテレビの視聴スタイルを確実に変え得るものであり、この映像配信事業は、大きな ポテンシャルを持っています。
| ||
| 2.新局面を迎えた情報通信産業
◇放送と通信 巷では、通信と放送の融合ということが取り沙汰されています。放送業界と通信業界それぞれの領域をまたがるような形で 、通信会社・電力会社・鉄道会社などが新たにサービスを始めようとしています。【資料2】 | ||
|
【資料2】融合から発生する新たな競合環境 | ||
|
| ||
| (注) | 両軸のフレームなどは、『通信コンテンツ マネジメント』( 日本経済新聞社、 2004年10月)を参考にした。 | |
| (出所) | 日本総合研究所作成 | |
|
こうした、サービスの垣根を低くする技術が出てきたところにビジネスチャンスがあるだろうと思い ます。特に、端末系においてその可能性があります。ラジオと携帯電話などは、これから一緒になりますし、ラジオも「見えるラジオ」を使っ てデータ放送を行う動きが出ています。ラジオのデジタル化放送はイギリスでは、相当進んでいます。 テレビ放送の形態についても新しい動きがあり、地上波デジタル放送をにらみ、NHKなどがサーバー型放送を検討していま す。サーバーというのはコンピュータのことだとお考え下さい。放送の受信機・インターネットの通信機能などいろいろなサーバー機能を使っ て、視聴者の要望やニーズをくみ取りながら番組編成することを考えています。 ◇放送と携帯 放送側としては、地上波デジタル放送に期待しています。その活用例の一つに「モバイルデジタル放送」があります。既に デジタル放送の電波の1区分(1セグメント)を、携帯電話向けの放送に使うことが決まっています(「1セグ放送」といわれています)。 米国では、西海岸のクアルコムという会社が、13セグメントという広い周波数を使って携帯電話向けに放送を予定していま す。彼らは、通信機器メーカーでありながら、電波を買って、携帯電話向けに新しいサービスを開発しています。そして、新しい需要を喚起す ることで、その携帯電話会社に自分達の通信機器を買ってもらうという戦略を打っています。新しい通信サービス提供の仕組み(プラットフォ ーム)づくりをすることで、ハードの販売につなげるという戦略的な動きが米国に出てきているのです。 こうしたクアルコムの経営戦略は、現在のビジネスのやり方も、売手と買手の力関係の再構築と技術 の使い方によって大きく変わってくるという格好の事例と言えるでしょう。 ◇固定網と移動網の統合(FMC) FMCサービス(fixed mobile convergence)といいまして、固定電話と携帯電話を一緒に合わせたサービスがあります。オフ ィスでは内線電話として使い、それを外出先に持ち出して通話もできるといったことが、一つの携帯電話端末で可能なのです。 他にも、携帯電話から自宅のホーム・サーバーに指示して、サッカーの試合を録画し、公衆無線LANという通信の仕掛け を使って、得点シーンだけをダウンロードし、携帯電話画面でそれを見るとか、そうしたサービスが出てきており、業界の期待が大変高くなっ ています。 固定と携帯の統合により通信コストを削減したいというニーズや、それを実現する技術も既にあることから、FMCのサービスは 一層加速していくものと予想されます。 ◇情報通信業界の見通し 今後、どの産業界においても、新技術を用いて市場を拡大しようとするならば、コンピュータ産業の 基本ソフトに見られるように、何もかも独占するというやり方ではうまくいきません。それよりも、オープン化する仕組みつくり、産業の裾野 を広げることが大切です。オープン化するには、それを介在させる土台になる技術が重要になります。 そういった技術の開放について例を上げると、NTTドコモが携帯電話を使ったクレジットカードビジネスを今春打ち出しま した。NTTドコモは、クレジットカードの認証や決済などの仕組みを、KDDIなど競合他社に開放する方向で動いております。このように、携帯 電話業界が一体となって、クレジット業界と連携することで新たな市場が創出される可能性があります。 さらに、今後、光ブロードバンドやIP網を活かして携帯やWEBを使用した広告・物販・ファイナンスなどとの複合ビジネス が出現し、事業領域の拡張に向けた新たな統合・競争が起きることが予想されます。こうして、情報通信業界の今後の形態は、通信だけ、放送 だけといった枠組から離れ、総合通信メディア会社へ変貌していくものと考えられます。【資料3】 | ||
|
【資料3】融合から発生する新たな競合環境 | ||
|
| ||
| (注) | ◆「仲介」:投資銀行機能などのこと。◆「変換」:派生証券 機能などのこと。 | |
| (出所) | 日本総合研究所作成 | |
| 3.今後わが国が向かうべき先(産業政策など)
◇マクロ経済 次に、ITとマクロ経済の話をいたします。 IT製品や情報通信関連産業だけが頑張っていても、景気対策をしっかり打ってもらわなければ景気は回復しません。小泉政 権が続く間は、今のデフレ景気を打開する可能性は低く、今のような状況がまだ3~4年は続くと考えています。金利ゼロ状態が続いていますか ら、日銀の金融緩和政策もほとんど効果がない(流動性の罠にはまっている状態)と考えるべきだと思います。 具体的に景気の状況を見る、一番分かりやすいバロメーターは、総所得です。総所得が増えなければ 、景気回復になりません。いってみれば、皆さんの給料です。財布の中身が増えるという状況を作らないとダメです。 2002年から日本経済はほとんどゼロ成長です。GDP500兆円程度から大きく増えていません。一時はマイナス成長だった こともあります。同じ時期にイギリスやアメリカは、だいたい3%~4%ぐらいの堅実的な経済成長をしています。本来であれば、日本も3%ぐ らいの成長は十分望めますので、仮に、年1%の成長が2001年以降15年間続いていたとすれば、バブル時からGDPが86兆円増えます。GDPの内 、消費部門はだいたい7割を占めていますので、仮に86兆円の7割として、消費に回るのは60兆円ぐらいです。60兆円を1億人で割ると、1人当た り、赤ん坊も含めて60万円になります。家族4人だとして年間240万円の消費が増えることになります。これが情報支出にも流れて行くわけで す。 いい物を作り、画期的なサービスを提供しても、財布の中身の元になる部分が成長していないと物は 売れないわけです。その意味で消費の拡大を期待できる経済政策が重要になってきます。 ◇光ファイバー投資の経済効果と産業政策 情報通信市場における、移動体通信事業への新規参入や固定電話の減少、光化・IP化の拡大などを想定した上で、最も確率 の高い経済成長のシナリオを使って計算すると、情報通信市場の規模は、2013年には、新たなFMC市場の3.7兆円を含み合計19.6兆円程度になる と見ております。 また、光ファイバーがもたらすGDPの押し上げ効果を、産業連関表を用いて計算してみました。地上波デジタルテレビのイ ンパクトよりも、光ファイバーのもたらすGDP効果の方が、かなり大きいのではないかと見ています。さらに、その試算結果から言えることは 、これからの我が国の産業は、自由競争だけしていると、価格の叩き合いになって、マーケットが縮小しかねないということです。 したがって、競争政策だけではない、産業政策が重要であると考えております。産業政策とは、つま り、産業をどう育てていくかということです。そういった視点で、新興勢力も既存事業者も、いろいろなサービスが融合し合う中で、拡大均衡 的なマーケットを作っていかなくてはいけないと考えています。 | ||
| 4.ITインフラの活用と経営スタンス
当地松山市は「e-まちづくり」で光ファイバー整備に取り組まれていますが、インフラを整備した後は、それをいかに活 用していくかが重要になります。私は、日本全国どこへ行っても、東京でも地方でも、町が同じになっていると感じています。一方、ドイツで は、各州が、それぞれ違ったまちづくりをしています。 自分たちは、よその県とは違うんだ、違うことはいいことであるということを、子供が小学校・中学 校の時から教えることが重要であると考えています。 地域における戦略も他地域との違いをいかにつくり出すかということが大切であると思います。 また、これから、ITやIPを経営インフラとして企業の中に取り入れていく際には、単にハードを整備するのではなく内形的 なストックを充実させることが必要になります。つまり、企業の行動規範、マネジメントのノウハウ、さらには、マネジメントの状況・成果を 可視化する、最近「見える化する」といいますが、こういうことを企業や組織の中で、いかに作っていけるかということがポイントであると考 えます。 最後に、勝つためのマネジメントノウハウとして、①成功願望を描き、②アクションに移し、③考えて修正する、といった 自律的に行動できる組織を創りあげていくことが重要であると思います。ご清聴有り難うございました。 | ||
| [質疑応答]
質問1 回答 質問2 回答 | ||
コンサルティングサービス