第9回 「技術および市場の不確実性に柔軟に対応するために」
2004年6月8日 浅川秀之
(1)はじめに
企業の選択可能な研究開発戦略として「プロダクトアウト」、「マーケットイン」という2つの相対する手法がある。一般的な定義としてのプロダクトアウトとは、自社の持つ技術を起点(シーズからの発想)とし、生産者側の立場から製品やサービスを提供することを意味する。反対にマーケットインとは、消費者のニーズを把握し、消費者の視点に立った商品を提供していくことを意味する(ニーズからの発想)。
ある時期における日本の製造業企業の多くはプロダクトアウト的な発想で製品をリリースし、しかもそれで十分に利益確保が可能な状況にあった。なぜそのような状況であったかという理由について、伊藤修は『プロダクトアウト戦略』(2003年4月、ダイヤモンド社)の中において「市場の渇望をとらえ、大量生産によるコストダウンを行うことで、その渇望を充足させることができたから」としている。つまりひと昔前はまだ市場の多くに「渇望」が存在し、そこに対して製品をリリースさえすれば、後は日本企業の得意な品質向上、安定供給、コストダウンといった自社に閉じた持続的な技術の改善により十分な利益を確保することができたということである。製品をリリースする際には、自社技術を製品に仕立てることのみを考え、あとは持続的な改善によりなんとかなっていた時代である。
その後、このようなプロダクトアウト的な発想の限界が認識されるに従い、「もっと顧客の声をよく聞いた上で製品をリリースする必要がある」という意見が台頭し始めた。プロダクトアウト的な発想で失敗した多くの製造業企業は、こぞってユーザーアンケートを実施したり、営業部隊の人間を開発部門に人事異動したりと、少しでも市場のニーズを製品開発にフィードバックしようという動きが盛んになった。マーケットイン戦略の台頭である。
しかしながら、今現在はというとどちらの戦略も少し使い古された感があり、その有効性がほとんど認識できないような状況になりつつある(個別の市場においては、どちらかの戦略が有効な場合もある。ここでは全体的な傾向について述べている)。
このような状況の中、伊藤修は顧客絶対主義からの決別を謳い「真のプロダクトアウト」という概念を提唱している。まず「自社がやりたいこと(=自社にしかできないこと)」を第一に考え、次に「それをどのようにすれば顧客に喜んでもらえるか」と考えることを「真のプロダクトアウト」と定義し、自社の「強い(「得意」ではない)」独自性を起点とし、「勝てるニーズ」をターゲットとすることの重要性を述べている。(真のプロダクトアウト戦略については、同書の中に非常に分かりやすく記されている。特に近年の顧客志向偏重戦略に活路を見出せず悩んでいるような企業の担当者にとっては、一読後には元気が出てくるような非常に明快かつ力強いメッセージが込められている。)
(2)技術の不確実性、市場の不確実性
先に述べたように、現在はプロダクトアウト(技術、シーズ起点)的な戦略も、マーケットイン(市場、ニーズ起点)的な戦略もその適応が非常に難しい状況になりつつある。その根本的な要因として2つの不確実性が挙げられる。つまり「技術の不確実性」および「市場の不確実性」である。
技術の不確実性とは、例えば今現在自社で推進している研究開発対象の1つ1つがまさに不確実性を含んでいるということである。例えば、今現在かなりの割合で普及しているある特定の技術があり、一方でこれに取って代わるような(代替的な)技術を開発している企業の存在を想定する。開発が成功すれば先行企業、競合他社を席捲することが可能であるが、その成功・失敗には様々な不確実性を含んでおり、この不確実性こそがCTOや経営企画部門に属する者にとって、まさに研究開発投資の可否判断の要となる部分である。
市場の不確実性とは、市場のニーズの変化に関する不確実性のことをさす。近年では、顧客ニーズの変化周期の短期化やその予測の難しさについて、様々なメディアにおいて取り沙汰されている。研究開発を1年、製品開発を1年、生産準備や広告戦略策定を1年などと悠長なことをいっている余裕はない。顧客の要求は日々変化しており、その予測は非常に困難な状況である。
しかしながら、この技術および市場の不確実性に対して、単純に「不確実だから対応できない」と、運を天に任せて何の対策も講じないようでは競合他社に対して優位性を築くことはできない。不確実性をリスクととらえ、適切なマネジメントにより競争優位性を構築する具体的な戦略手法が必要である。
以降において、第8回において説明した「顧客の要求曲線を意識したイノベーション・マネジメント」手法をベースとし、技術および市場の不確実性に対応するための手法について考察を行う。
(3)「顧客の要求曲線を意識したイノベーション・マネジメント」の適応
顧客の要求曲線を意識したイノベーション・マネジメント手法においては2つの曲線(あるいは直線)を意識する必要がある。「顧客の要求曲線(下図表の中の太実線)」と「技術の機能・性能曲線(下図表の中の太破線)」である。第8回においては、実在の通信機器製品を例にとったケーススタディにより、「顧客の要求曲線を意識した柔軟な開発戦略」をとったか否かが明暗を分けたことを示した(詳細は第8回を参照頂きたい)。
【図表】 顧客の要求曲線に柔軟に対応 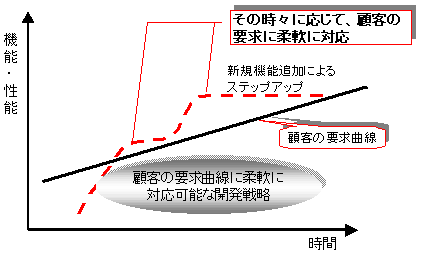
(出所) 日本総合研究所ICT経営戦略クラスター浅川[2004.05]作成
上図表の中においては顧客の要求曲線は単純に「右肩上がりの直線」で示されているが、実際には未来の要求曲線の様相を予測することは非常に難しい(市場の不確実性に起因する。下図表参照のこと)。例えば、IT関連市場の場合は、比較的要求曲線の様相は予測しやすいとされているが、その他の一般的な市場においては「顧客の現在の要求や、それに対する満足度合い」が1ヶ月後にどのように変化しているかを予測することは難しい。アンケートなどによって直接顧客のニーズを調査し、その動向予測を試みる企業も多く見受けられる。このような場合、心理学者が呼ぶところの「機能的固定の壁(注1)」などに阻まれて、単純には顧客の真の意味でのニーズを抽出できない場合が多いので注意が必要である。
(注1) 「機能的固定の壁」:通常の使い方にこだわってしまい、それ以外の機能などを顧客自身が柔軟に発想できなくなる傾向のこと。
【図表】 市場の不確実性 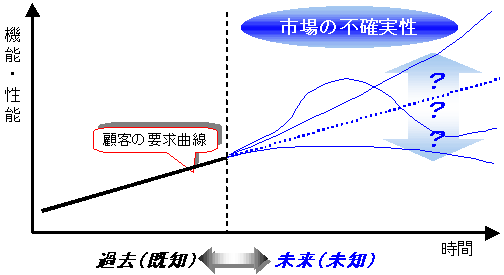
(出所) 日本総合研究所ICT経営戦略クラスター浅川[2004.05]作成
一方の機能・性能の不確実性についてもその動向予測は非常に難しい。しかしながら、IT関連技術に関しては比較的明確化が容易く、例えば半導体技術の進歩に関する「ムーアの法則」は有名である。これは、1965年にゴードン・ムーアが提唱したもので、新しく開発されるチップの能力が、18~24ヶ月毎に、それ以前の最新チップの約2倍になるというものである。このようになんらかの数学的トレンドに沿った機能・性能上昇が見込まれる場合は稀であり、通常はある技術に対してその動向を予測する、つまり「真の意味」を予測することは非常に難しいとされる(技術に関する「真の意味」についての詳細は、本コラム第3回、および浅川秀之「研究開発戦略、不確実性に動的対応」『日本工業新聞』2004年1月23日記事参照のこと)。
市場の不確実性と技術の不確実性は共にその動向予測が難しい。両者において大きく異なる点は、「市場の不確実性」は基本的には所与のものであり自社内においてコントロールすることは難しく(注2)、一方の「技術の不確実性」については、その「真の意味」を動的にマネジメントすることにより、ある程度は自社内においてコントロールすることができるということである。この両者の根本的な差異に鑑みつつ、以降において、技術および市場の不確実性に対して柔軟に対応する手法について述べる。
(注2) 一般的に「顧客の要求曲線」は所与のものであり自社においてコントロールすることが難しいとされているが、「需要創造」という観点から、自社のコンピタンスをうまく活用できるよう、顧客の需要を創造する戦略も考えられる。例えば「自動車産業」については、1907年にアメリカにおいてT型フォードが世界で最初に大量生産を前提として導入されて以来、その根本的な構造は変化しておらず(内燃エンジンという意味では現在も変わりはない)、その用途についても「人やモノを運ぶ」という原点には変わりない。しかしながら、現在も尚売上高を向上させている企業が存在するということは、なんらかの形で顧客の需要をうまく創造(「人やモノを運ぶ」という要求以外の要求を創造している)する仕組みが存在すると推測される。自動車産業の需要創造の考え方については、新保(日本総研主席研究員)から示唆を得た。
一方の機能・性能の不確実性についてもその動向予測は非常に難しい。しかしながら、IT関連技術に関しては比較的明確化が容易く、例えば半導体技術の進歩に関する「ムーアの法則」は有名である。これは、1965年にゴードン・ムーアが提唱したもので、新しく開発されるチップの能力が、18~24ヶ月毎に、それ以前の最新チップの約2倍になるというものである。このようになんらかの数学的トレンドに沿った機能・性能上昇が見込まれる場合は稀であり、通常はある技術に対してその動向を予測する、つまり「真の意味」を予測することは非常に難しいとされる(技術に関する「真の意味」についての詳細は、本コラム第3回、および浅川秀之「研究開発戦略、不確実性に動的対応」『日本工業新聞』2004年1月23日記事参照のこと)。
市場の不確実性と技術の不確実性は共にその動向予測が難しい。両者において大きく異なる点は、「市場の不確実性」は基本的には所与のものであり自社内においてコントロールすることは難しく(注2)、一方の「技術の不確実性」については、その「真の意味」を動的にマネジメントすることにより、ある程度は自社内においてコントロールすることができるということである。この両者の根本的な差異に鑑みつつ、以降において、技術および市場の不確実性に対して柔軟に対応する手法について述べる。
(4)イノベーション・マネジメントにリアル・オプション的な発想を取り込む(注)
(注) 「顧客の要求曲線を意識したイノベーション・マネジメント」手法に、リアル・オプションの考え方を適応することの有用性については、新保(日本総研主席研究員)から示唆を得た。本章における分析および考察は新保から得た示唆に基づくものである。
まず、顧客の要求曲線に関する不確実性については、様々な実例から推測してもそのトレンドが急激に下降することはほとんどないと考えられる。基本的にはどのような市場においても右肩上がりのトレンドを示す。問題となるのは、どれだけの割合で上昇するかということである。特にIT分野などにおいては、非線形的(時間の2乗に比例など)な上昇傾向を示す場合があり、「X年前には考えもつかなかったほど技術は進歩した」といった類の言葉はよく耳にする。
先にも述べたがこの顧客の要求曲線は、顧客需要創造・喚起といった積極的な戦略の実施などを除けば、基本的には生産者側のコントロール下にはないので、なんらかの形で予測する必要がある。この際に有効となるのがシナリオ・アプローチを取ることである。シナリオ・アプローチとは、対象となる市場に関連する競合他社や技術の状況は勿論のこと、必要に応じて社会状況、経済状況なども総合的に鑑みた上で、いくつかのキー・ファクター(シナリオの分岐点に大きな影響をおよぼす事象など)を抽出し、これを基に複数のストーリーを構築することである。将来発生しうるシナリオを前もって複数認識し、必要に応じて対応策を講じておくということは、今後の顧客要求の不確実な変化に対して柔軟な経営判断を下す際には非常に重要となってくる。
次に技術についての機能・性能曲線に関する不確実性については、基本的には生産者側のコントロール下にあると考えられる。また、将来の機能・性能曲線を描く(技術的な戦略を構築する)ためには、先に述べた顧客の要求の不確実性に対応可能な、なんらかの策を含ませておかなければならない。そうでなければ、新たなイノベーションをタイミングよく創造することが難しくなる。具体的には、将来の要求曲線の上昇にタイムリーに追随可能な技術的なプラットフォームを、初期の段階から作り込んでおく、といった戦略などが考えられる。下図表は、顧客の要求曲線の上昇に対して追随していくことに失敗した例と、成功した例とを列挙したものであり、「ユーザーの要求曲線を意識した柔軟な開発戦略」を取ったか否かが両製品の明暗を分けたことを示す。
【図表】 不確実性に対応することの失敗および成功 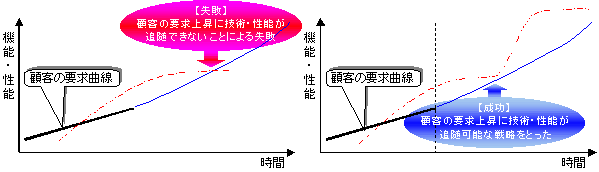
(出所) 日本総合研究所ICT経営戦略クラスター浅川[2004.05]作成
成功例(上図表中の右図)の場合、顧客の要求曲線の変化に合わせて、技術的な向上をステップ的に向上させたことを示す。このような成功例を図に示すことは容易であるが、実際にいつでもタイミングよく技術的な向上を実行できるかというと、それほど単純な話ではない。前もって柔軟性を考慮したなんらかの作り込みを意識的に盛り込んでおき、その上で各局面において今のままある程度一定に保つのか、あるいは機能・性能を向上させるのかといった判断を適宜下していく必要がある。
この一定に保つのか、向上させるのかといった判断は、まさにリアル・オプション理論に則った判断を下していることに他ならない。
ある時点において当該事業の環境に不確実性が高い場合、例えば顧客の要求曲線の上昇傾向があまりに予想し難い場合や、競合他社の出方が非常に不透明であるような場合、新たな機能・性能向上のための追加投資を見合わせる、といった判断を下す方が懸命な場合がある。この場合ある程度時間が経過し、不確実性が低下するのを待ってから、新たな投資の判断を下すことが可能となる。ただしこの際、新たな投資によりスムーズな機能・性能向上が実施可能なよう、必要最低限の投資(将来の機能・性能向上のための作り込みなど)は必要となる。
このように、機能・性能向上のための意思決定を保留するということはリアル・オプション理論でいうところの「延期オプション」に他ならない。またその後、必要と判断される場合において、機能・性能向上のための追加投資を行うということは「拡大オプション」の行使に他ならない(下図表参照)。
【図表】 ステップ型イノベーション曲線へのリアル・オプションの適応 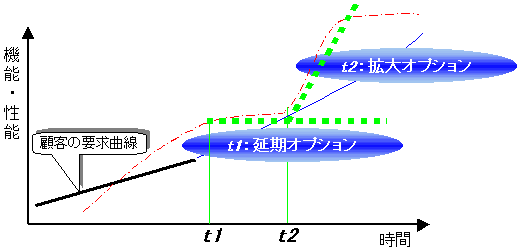
(出所) 日本総合研究所ICT経営戦略クラスター新保・浅川[2004.05]作成
つまり、「ステップ型のイノベーション曲線」を用いたマネジメント手法は、研究開発戦略における技術と市場の不確実性に対応する際に、リアル・オプションの持つ柔軟性をとりいれることの有用性を可視化したものであり、研究開発戦略において柔軟な意思決定を下す際の重要な分析手法の一つであるといえよう。一般的に拡大可能なオプションを持つプロジェクトや事業は、拡大の可能性を持たないよりも、高い価値を持っていると判断される。
初期の段階でそれなりのコストが必要とされ、このコストに見合った将来の収入が見込めないような研究開発に対する投資判断は非常に難しい。これまで一般的に用いられてきたようなDCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法などでは、将来の不確実性や戦略の柔軟性を反映することが難しいとされる。しかしながら、これまで述べてきたような技術と市場の不確実性に対してリアル・オプション理論を適応した分析手法は、より柔軟な意思決定を下すための重要な示唆を与えることになろう。

