第4回 「不確実性やリスクを指標としたアウトソーシングマネジメントについて」
2004年1月6日 浅川秀之
(1)はじめに
近年、製造業企業における研究開発のあり方が問われ、これにともない産学連携の動きが活発になっている。他方、大手製造業の生産部門が、生産を専門とする世界規模のEMS(Electronics Manufacturing Service)へ売却されるケースが増えてきている。産学連携の活発化とEMS化、一見全く関連のないように思われる2つの現象である。しかしながら、両現象は「製品開発サイクルにおけるアウトソーシングマネジメント」という視点で捉えると、製造業の研究開発戦略を考える上で共に重要な現象であることがわかる。
アウトソーシングというと、自社にとって収益性が芳しくない部門をアウトソースする、つまり「嫌なものは外にまかせる」というマイナスイメージがあり、また実際このような観点からアウトソーシングを実施している企業も見受けられる。しかしながら、アウトソースする側も、される側もそれぞれが自分の得意とする分野で、コア・コンピタンス(注)を生かすことができ、両者ともにハッピーというのが本来あるべき姿ではないだろうか。
(注) 「コア・コンピタンス」:顧客に対して、他社には提供できないような利益をもたらすことのできる、企業内部に秘められた独自のスキルや技術の集合体のこと。ゲイリー・ハメル、C.K.プラハラード『コア・コンピタンス経営―未来への競争戦略』(2001年1月、日経ビジネス人文庫)など。
そのためにも、製品開発サイクルや研究開発のリニアモデル全体の流れを把握し、不確実性やリスクをベースとしたアウトソース・インソース判断が重要となる。
(2)製品開発サイクルとは
製造業における一般的な製品開発サイクルは、「研究→開発→生産→販売」という流れに従うが、これを「リニアモデル(線形モデル)」と呼ぶ。20世紀初頭の米国の民間企業では、主に大学において研究が進んでいる「科学」を技術創造の起源とすべく、大学の講師や優秀な学生を早期の段階で自社に雇用し、自社内において科学の研究に従事させていた。これらはやがて中央研究所や基礎研究所と呼ばれ、自社内で得られた研究成果を基に応用研究、開発とフェーズがシフトしていくリニアモデルを形成するようになった(注)。
(注) リニアモデルとその起源については、西村吉雄『産学連携―「中央研究所の時代」を超えて』(2003年3月、日経BP社)から抜粋
【図表】 リニアモデル(線形モデル) 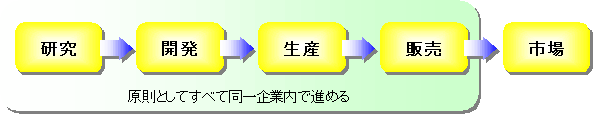
(注) 本図表のリニアモデルは研究、開発、生産、販売と4つのフェーズで示されているが、これは製品開発の流れを簡略化し、主だったフェーズのみを示したものである。従って、実際にはさらに詳細なフェーズが存在する。例えば、開発フェーズと生産フェーズの間には、生産段階へ移行するための準備が必要で、「製造仕様検討」等のさらに詳細なフェーズが存在する。
(出所) 西村吉雄『産学連携―「中央研究所の時代」を超えて』(2003年3月、日経BP社)から抜粋
しかしながら、近年では自社内において上記のような一連の研究開発シーケンス(リニアモデル)を実行することは様々な問題点を含んでいることが認識されてきている。冒頭に述べた産学連携やEMS化の動向は、これらの問題点に柔軟に対応するための手法の一つであるという捉え方ができる。
(3)研究開発フェーズにおけるアウトソーシングについて
研究開発フェーズにおけるアウトソーシングとしては、他企業へのアウトソーシングや、コンソーシアム、産学連携など様々な形式があげられる。
研究開発フェーズをアウトソーシングする理由については様々であるが、近年は技術やノウハウが複合的に集約された「複合製品」が主流であることが大きな原因のひとつであろう。何百という特許が1つの製品に集約されることも稀ではない。これは消費者のニーズが多様性を帯びてきたことにも起因している。このような複合製品をリニアモデルに従って市場にいたらしめるにあたって、その全ての技術を自社内で賄うことは非常に困難であることは想像に難くない。仮に自社内で全てを賄うよう努力したとしても、それ相応のコストと時間が膨らむことになり、消費者のニーズが短期間にかつ多様に変化するような市場においては、適切な製品開発モデルとはいえない。ある部分は自社内で賄うが、ある部分に関してはアウトソーシングによって対応する、というような研究開発モデルが必要となってくる。
研究開発における主なリスク要因(不確実性要因)としては、先にも述べたとおり「開発コスト(コスト的なリスク)」と「開発期間遅延(時間的なリスク)」の問題が上げられる。これら2点のリスクに関しては以下に示す「リターンマップ」によって認識することができる。
【図表】 リターンマップ 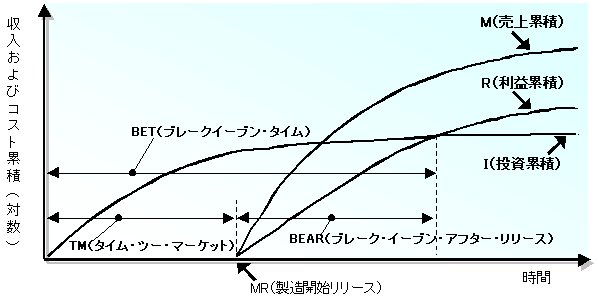
(出所) チャールズ・ハウス、レイモンド・プライス「ストラテジック・リターン・マップ」『ダイヤモンド・ハーバードビジネス』(1991年5月)から抜粋
リターンマップは米ヒューレット・パッカード社で開発された、収入およびコストを時間軸に沿って管理する手法であり、技術開発の評価法の一つとして用いられている。リターンマップをベースに、常時コスト的なリスクおよび時間的なリスクを監視し、戦略や計画からの乖離をマネジメントする。
産学連携などにより、研究開発フェーズをアウトソーシングすることは、このようなコスト的なリスクや時間的なリスクを外部に転嫁しているという捉え方ができる。
(4)生産フェーズにおけるアウトソーシングについて
生産フェーズにおけるアウトソーシングの形態として、国内にある日本のメーカーの工場をEMSへ売却するケースが増えてきている。以前は、海外にある日本メーカーの工場をEMSに売却することが多かったが、近年ではその舞台が日本国内に移ってきている。EMS企業が、中国、韓国をはじめとする有望なアジアマーケットを見据えての動向であろう。生産フェーズをEMS化するメリットとしては主に下図表に示す項目があげられる。
【図表】 EMS化するメリット
| コスト低減 | ● 規模に起因するもの ◇ 資材調達コスト、設備調達コスト、間接費用などを大規模化することにより低減。 ● 顧客の多様化に起因するもの ◇エレクトロニクス業界でEMS化が進展したのは、個々の製品需要予測が困難で変動が激しいため。これに対してEMSは複数の顧客、製品分野の仕事を同工場内に持つので、トータルな需要は安定。 ● 徹底した標準化に起因するもの ◇ 生産設備やプロセス技術、情報システムなど製造に関係するあらゆる要素をEMS企業全体で世界的に標準化し、これにより間接費用が最小化される。 ● 低賃金国での生産 ◇ グローバルなメガEMS企業だけが提供できるコストダウン手法。 |
|---|---|
| 財務体質改善 | ● 固定費の変動費化 ◇ アウトソーシングすることにより、最終的には製造コストの殆んどが変動費となる。 ● 資産効率の改善 ◇ 生産投資はEMS側企業が行うことにより、メーカーの資産効率は大幅に上昇する。EMS側は常に資産効率を徹底的に高めることに集中。 |
| Time to Marketの短縮 | ● 新製品導入センターの設置 ◇ 顧客メーカーの開発部門が集結している場所(サンノゼなど)に設置し、製品開発の早期の段階から顧客メーカーとコミュニケーションをとり、量産に入る前の問題点への対策をとる。 |
| グローバル製造体制 | ● グローバル製造体制のサポート ◇ 製品ライフサイクルのなかで製造する地域をフレキシブルに変える。EMS企業は工場間の標準化が徹底しているため、生産を移すことがメーカーの社内工場よりはるかに容易である。 |
(出所) 稲垣公夫『EMS戦略』(2001年1月、ダイヤモンド社)から抜粋
かつては「EMSの安い労働力と低い間接費を利用して少しでもコスト削減を」ということが主たる目的であったが、近年は、かつてのような狭い領域でのコストではなく、「メーカー受注から出荷までのトータルなコスト(時間短縮も含めて)を最小化すること」を目指している傾向にある。
上図表からもわかるように、生産フェーズをアウトソーシングすることにより、コスト的なリスクや時間的なリスクを外部(EMS)に転嫁しているという捉え方かできる。下図表は、EMS化によるリスクの外部転嫁の様子を示したものである。
【図表】 EMS化 によるリスクの転嫁 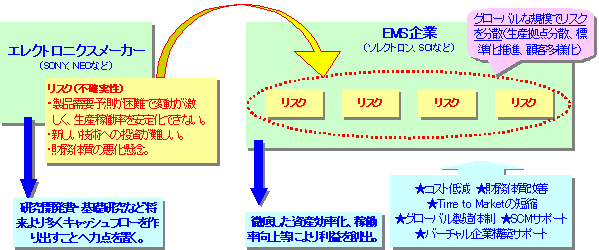
(出所) 日本総合研究所作成
(5)リスクを指標としたアウトソーシングマネジメントについて
ここまで述べてきたように、リニアモデルにおける研究開発フェーズ(特に基礎的な研究フェーズ)と生産フェーズは、一般的に不確実性に起因するリスクが他のフェーズに比べて高い(下図表参照)。もちろん、企業によっては研究開発部門が活発で、絶えずイノベーティブな製品を創出することができる能力をもっていることもあり、この場合研究開発フェーズのリスクは小さいといえる。逆に、コア・コンピタンスとして独自の生産技術を持っていたり、材料部品の調達能力が傑出している場合などは、生産フェーズのリスクが一概に高いとはいえない。
【図表】 一般的なリニアモデルにおけるリスク 
(出所) 日本総合研究所作成
上図表のように自社内における不確実性、リスクを的確に把握し、これをベースに適切なアウトソーシング戦略を考慮することが重要となる。
(6)まとめ
「研究→開発→生産→販売」というリニアモデルの中で、工程の大部分を占める研究開発や生産フェーズをアウトソーシングし、果たしてそれで製造業といえるのだろうか、製造業とは何を生業とする事業体なのだろうか、疑問に思う方も多いのではないか。しかしながら、決して「何もかもできるものは全てアウトソーシングするほうがよい」といっているわけではない。重要なのは、自社内の不確実性・リスク分布を的確に把握し、必要に応じてアウトソーシングをする、ということである。したがって、研究開発部門の中でも、自社が不得意とするような領域の一部をアウトソースし、他はコア・コンピタンスとして自社内で開発を進める、という戦略も考えられる。アウトソーシングとインソーシングの両ケースをコスト面だけで比較し、判断する場合が多い。コストという1つの指標に頼るのではなく、製品開発サイクル一連の流れの中での、不確実性・リスクを意識したアウトソース、インソースのマネジメントが重要である。
「ハイリスク、ハイリターン」という言葉があるように、一般的な競争市場においては、リターンを得るためには、ある程度リスクを覚悟しなければならない。逆に、リスクが全くないところにはリターンもない。競争市場においては当然の原理である。ここまで述べてきたように、研究開発戦略や製品開発戦略上においても、複数の計り知れない不確実性・リスクが潜在する。下図表は、シナリオツリーにおける各分岐点の数と研究開発・製品開発戦略全体の不確実性との関係を模式的に示したものである。
【図表】 シナリオツリーにおける各分岐点の数(N)と研究開発・製品開発戦略全体の不確実性との関係 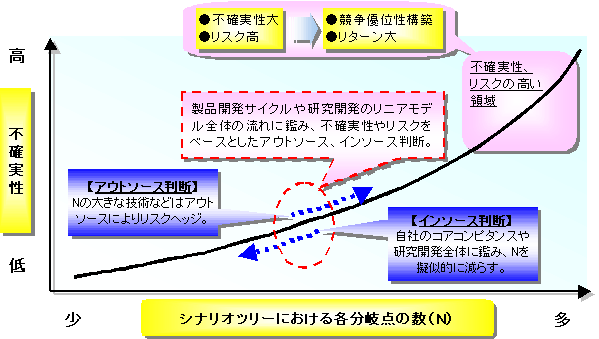
(注) シナリオツリーにおける各分岐点の数とデスバレーの深さとの関係については、第3回「新技術に意味を見出す方法」『ゼロからの研究開発戦略』参照のこと。
(出所) 日本総合研究所作成
本図表は、一般的にシナリオツリーにおける分岐点の数が多い程、全体としての不確実性は高くなる傾向を示す。本図表の右上部「不確実性、リスクの高い領域」は、アウトソーシングによりその不確実性、リスクを回避するという戦略が正攻法であることはいうまでもない。しかしながら、「不確実性、リスクが高い」と一纏めに全てをアウトソーシングするのではなく、自社内においてある程度マネジメント可能な技術であるかどうか(自社の強みやコア・コンピタンスではないかなど)を、製品開発サイクルや研究開発のリニアモデル全体の流れに鑑み判断、取捨選択することが、他社に対して競争優位性を構築する重要なポイントとなる。あまりにも自社の強みやコア・コンピタンスからかけ離れた領域でのリスクや、不確実性が全く判断できない程に未知であるような領域においてはアウトソーシングする、もしくはある程度リスクがコントロールできる状態に至るまで「待つ」というオプションを選択する方が好ましい。
シャープ株式会社常務取締役・技術本部長の太田賢司氏は「デスバレーがあるおかげで、それを乗り越えたメーカーだけが利益を得ることができるのではないか。デスバレーがなければ、誰でも実用化できてしまうため、大きな利益は生まれないだろう。まさに技術者の腕の見せどころだ。」(注)と述べている。デスバレーの深さを的確に認識し、不確実性やリスクをマネージメントできるという同社の研究開発・製品開発に対する自信の表れであろうか。
(注) 「Cover Story特集:研究開発、異域の才を得て未踏の地を狩る」『日経エレクトロニクス』(2004年1月5日)から抜粋
「EMS化で製造部門をアウトソース化、産学連携ということで研究開発をアウトソース化、残った部分を自社でなんとかする」というような消極的な戦略での事業遂行では、競争優位性は築けない。製品開発サイクルや研究開発のリニアモデル全体の流れに鑑み、例えば「価格変動が激しい部材からなる製品の生産については、部材調達も含めてEMSへ生産委託」したり、「自社において従来ほとんど手のつけられていない分野の基礎研究のみ産学連携により大学研究機関へアウトソーシング」といったように、不確実性やリスクをベースとしたアウトソース、インソース判断が重要となる。
● 参考文献
◇ ゲイリー・ハメル、C.K.プラハラード『コア・コンピタンス経営―未来への競争戦略』(2001年1月、日経ビジネス人文庫)
◇ 西村吉雄『産学連携―「中央研究所の時代」を超えて』(2003年3月、日経BP社)
◇ 稲垣公夫『EMS戦略』(2001年1月、ダイヤモンド社)
◇ チャールズ・ハウス、レイモンド・プライス「ストラテジック・リターン・マップ」『ダイヤモンド・ハーバードビジネス』(1991年5月)
◇ 「Cover Story特集:研究開発、異域の才を得て未踏の地を狩る」『日経エレクトロニクス』(2004年1月5日)

