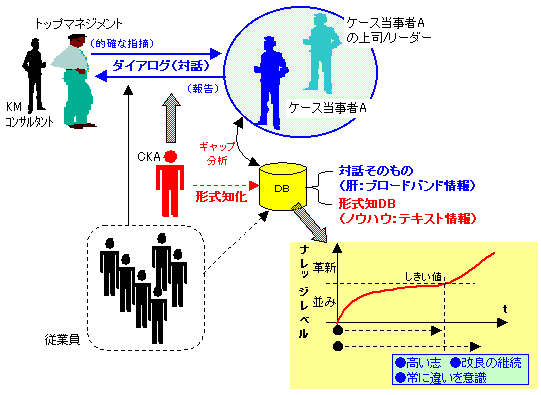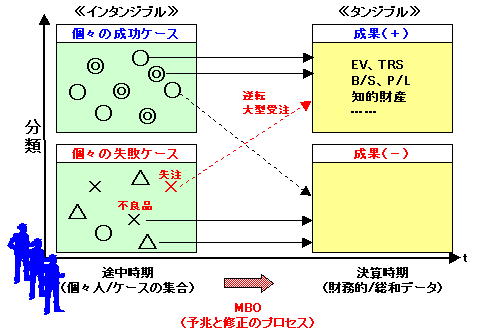なぜナレッジマネジメント(KM)がうまくいかないのか?
|
| ||
|
▼▼▼ なぜナレッジマネジメント(KM)がうまくいかないのか?① ▼▼▼ | ||
| ● | 現在のKMがうまくいかないのは、「並み」のナレッジ、即ちしきい値(ブレイクスルーの境界)未達の、当該問題のソリューションを与えうることのできないジャンクなナレッジを単にデータベース化する作業に終始しているからだ。 | |
| ◇ | あるいは、「業務遂行型」のKMを通じ、営業日報やマニュアル、報告書の類をKM-DMにインプットすることを、個々の従業員・スタッフに求め、またそのインプット無しには他の事務手続きは受理しないなどを強いても、数合わせの無用のナレッジが集積されるだけである。 | |
| ● |
イノベーションをもたらすナレッジの仕組みを実現・強化することが、生産技術頼みのコスト削減競争から脱皮することが求められる、現在の日本企業には急務である。 | |
| ◇ | 実効的なソリューションを与えうるナレッジの獲得には、トップマネジメントと事案(ケース)担当者との緊張の場を前提にしたダイアログ(対話による対峙)の仕掛けづくりが不可欠である。加えて、両者間の暗黙知的なやり取りを、社内・組織の第三者にも後日伝達できるように、形式知翻訳・分析できるCKA(Case Knowledge Analyst)の役割が必須。 | |
| ◇ | 翻訳作業を通じてKM-DBにインプットされる情報には、テキスト情報に属する従来のものと、ブロードバンド環境を利用して、ダイアログ当事者間でやり取りされるキーワードや映像を含めた対話そのものがある。 | |
| ◇ | 後者のやり取りを丸ごと記録し、かつ記録後に一定の区切りやキーワードなどのモジュール単位で編集などが自在にできるKMシステムの構築につなげられると、これまでの商品開発や生産性の向上などにも増して寄与できる武器となる。 | |
|
【図表】 ナレッジマネジメント(KM)の基本とCKA | ||
|
| ||
| (注) | 「CKA」:Case Knowledge Analyst(作者の造語)のこと。 | |
| (出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター[新保2002] | |
|
| ||
|
▼▼▼ なぜナレッジマネジメント(KM)がうまくいかないのか?② ▼▼▼ | ||
| ● |
その時には失敗と思える事象の中にも、有益なナレッジが秘められている。 | |
| ◇ | 失敗ケースを単に失敗と決め付け、その当事者を責めるのではなく、失敗を成功に導き、そして、企業バリューを結果的に上げる方向にもっていけるかがポイント。 | |
| ◇ | 企業の財務的なバリューに集約される前の途中時期における、即ちまだインタンジブルな(形になっていない)個々のケースを、担当者個々人のMBO(目標管理)基準、またはKPI((Key Performance Indicator:主要業績指標)に基づき、決算時期にはタンジブルな成果に結びつけるプロセスでの学習が重要となる。これらを通じたナレッジの蓄積は、企業競争力強化のため鍵を握る知財になるものだ。 | |
|
| ||
|
【図表】 途中段階での失敗ケースが最後まで失敗とは限らない | ||
|
| ||
| (注) | 「MBO」:Management By Objective、「EV」:Enterprise Value、「TRS」:Total Returns to Shareholdersのこと。 | |
| (出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター[新保2002] | |
|
| ||