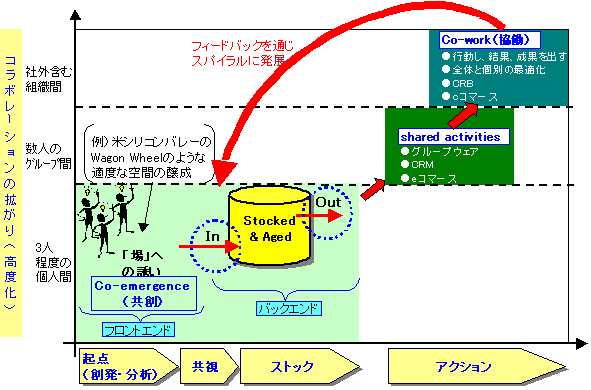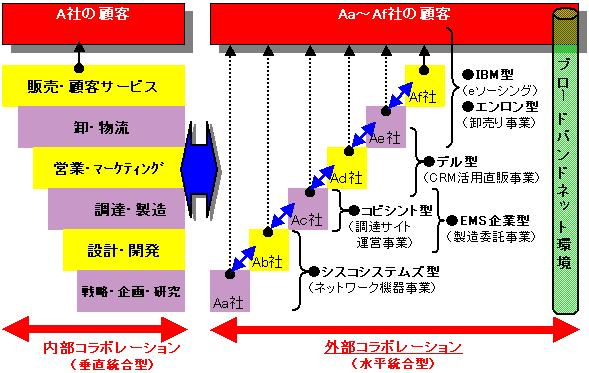企業競争力の鍵を握るコラボレーションやアライアンスにはプロセスや構造がある
|
▼▼▼ 企業競争力の鍵を握るコラボレーションやアライアンスにはプロセスや構造がある① ▼▼▼ | ||
| ● | 2001年頃から米国では、「eコマース」は軸足を「cコマース」(collaborativeなコマース)に移してきた。つまり、ITやネットだけで機械的・自動的に決定される従来の仕組みの見直しである。これは主に、B2Bコマースの場合、取引先や顧客先とのコマースがより意識されてきたことに起因する。 | |
| ● | そして、「人」のコミュニケーションがポイントとなる「コラボレーション」が一層重要になってきた。 | |
|
◇ |
コラボレーションには、cコマースのような企業外部に加え、企業内部の関係者との密接なコミュニケーションを、さらに有効にするため、プロセスの分析やプロセスの構造をよく吟味することが不可欠となってきた。 | |
| ● |
コラボレーションには、概ね「起点」→「共視」→「ストック」→「アクション」というプロセスが存在する。 | |
|
◇ |
「起点」では基本的なアイデアやコンセプトが創発される条件、即ち一定条件が備わった「場(Communities of practice)」が必要だ。米シリコンバレーにある「Wagon Wheel」(ベンチャービジネスに係わる関係者が自然と集まる地域のカフェ・レストラン)のような雰囲気の醸成がポイントとなる。 | |
|
◇ |
「共視」とは、三人寄れば文殊の知恵と呼ばれるような有効な発案や考えの整理には、それに至るプロセスや結果を同席者が相互に視認化できることが重要。イメージを描出し共有する。 | |
|
◇ |
「ストック」段階では、ナレッジマネジメントでも重要となるDBづくりがポイント。関係者が共視化プロセスを通じ得た成果を丸ごとDBに蓄積すること(Stocked)、そして、そのエッセンスとなるナレッジを自在に引き出せる仕組みが求められる。このナレッジが次第に蓄積・熟成(Aged)してくることで、生きたナレッジDBとなる。この共視及びストックの段階ではブロードバンド環境を前提としたバックエンドの仕組み(IS:情報システム)も威力を発揮しよう。 | |
|
◇ |
そして、「アクション」。いくらナレッジが蓄積されても、それをさらに高次元のコラボレーションの場で活かさなくては意味がない。 | |
|
【図表】 コラボレーションの基本構造とその拡がり | ||
|
| ||
| (注) | 「CRM」:Customer Relationship Management、「CRB」:Customer Relationship Building、「cコマース」:collaborative Commerce、「Wagon Wheel」:米シリコンバレーにあるカフェ・レストランの名前(フェアチャイルドを設立した「8人の侍」がかつて集ったことも)。 | |
| (出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター[新保2001] | ||
|
▼▼▼ 企業競争力の鍵を握るコラボレーションやアライアンスにはプロセスや構造がある② ▼▼▼ | ||
| ● | IP-VPNや広域イーサネットなどのブロードバンドネット環境が整備されてくると、「垂直統合型」としての社内でのコラボレーションをはかっている段階から、戦略・企画・研究から販売・顧客サービスに至る各機能別において、顧客企業とのコラボレーションをはかる段階でのトライ&エラーを通じ、経営全体の効率化と高度化を推し進めることができる。 | |
|
◇ |
この機能別の外部企業とのコラボレーションは、アライアンスと言換えることもできる。 | |
|
◇ |
このアライアンスは、「ICTマネジメントとは③」における「戦略パートナー型」のモデルの鍵を握るものである。 | |
|
【図表】 水平統合型アライアンス(社外での機能別コラボレーション) | ||
|
| ||
| (注) | 「EMS」:Electronics Manufacturing Service。粉飾会計に端を発した2001年秋頃からの米エンロン社は、その後の米国経済に大きな影を落とすことになった。しかし、オプション理論などを駆使した同社の卸売り事業(電力取引)のモデルそのものには、未だ研究対象として意味深いものがある。 | |
| (出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター[新保2001] | ||
|
| ||