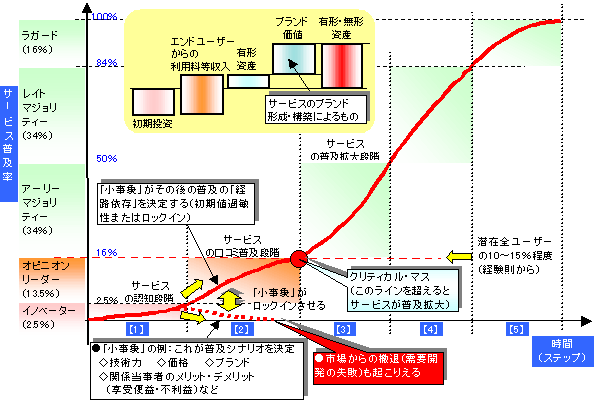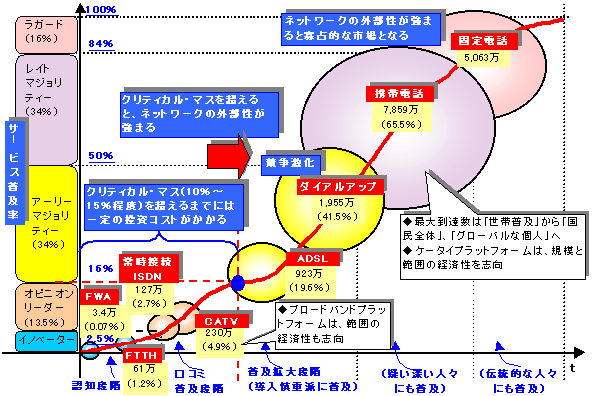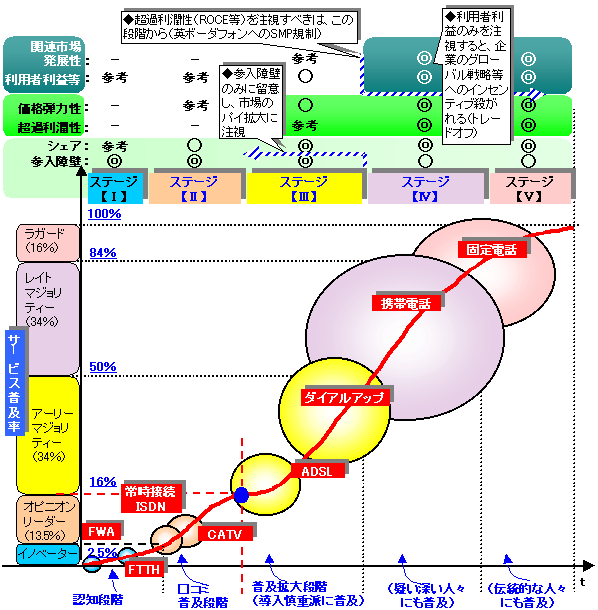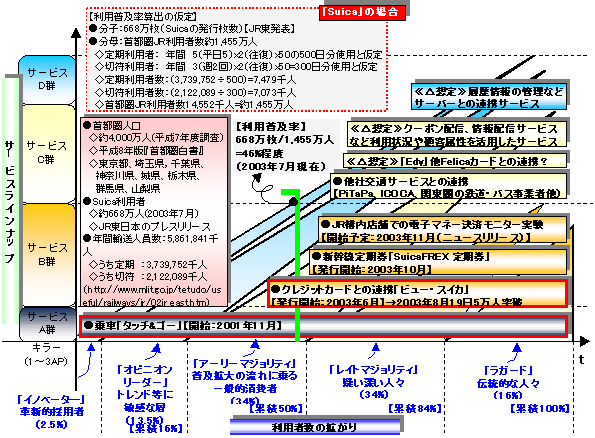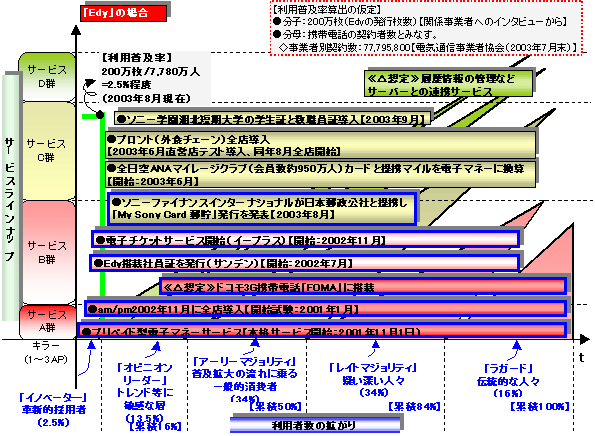普及シナリオを基にしたサービスの分析と評価
|
| |||
|
E.M.ロジャースの『イノベーション普及モデル』とブライアン・アーサーの『経路依存』を参考にした普及シナリオを用いて、サービスの普及状況や競争段階、サービス展開のフレームワークの分析・評価に応用できる。 | |||
|
| |||
|
▼▼▼ サービス普及シナリオ①(基本形) ▼▼▼ | |||
| ● | E.M.ロジャースの『イノベーション普及モデル』とブライアン・アーサーの『経路依存』を参考にし、新規サービスについての普及シナリオのイメージを示す。 | ||
| ◇ | 何が「小事象」となるのかを把握し、普及の段階ごとのシナリオを策定していく。 | ||
| ◇ | サービスのブランドを形成・構築することが重要である。 | ||
|
| |||
|
【図表】 新規サービスについての普及シナリオのイメージ | |||
|
| |||
| (注) | E.M.ロジャースの『イノベーション普及モデル』とブライアン・アーサーの『経路依存』を参考にし、新規PF利用サービスについての普及シナリオのイメージを示した。「クリティカル・マス」:商品が市場に浸透するための一定の需要規模、限界規模のこと。その規模を超えると、それまでの累積効果により爆発的な効果が現れたり、一気に普及が加速することがある。「ロックイン」:歴史的な偶然として一旦、初期段階である経路に落ち込んでしまうと(経路依存性)、そこから出ることが難しい状況のこと。たとえ不合理なものであっても、いつも合理的なものが生き残るわけではなく、この状況にはまり込んでしまう(あるシステムに組み込まれる)と、そのシステムを使うことの効用が増加し(ネットワーク外部性)、その不合理は継続・拡大していくことになる。 | ||
| (出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年6月] | ||
|
| |||
|
▼▼▼ ブロードバンドサービスの普及状況(2003年8月) ▼▼▼ | |||
| ● | 最近のブロードバンドサービスの普及状況も、E.M.ロジャースの『イノベーション普及モデル』を参考に示すことができる。 | ||
| ◇ | ADSLは普及拡大段階に到達。ネットワークの外部性が強まり、競争が激化する。 | ||
| ◇ | 「ネットワークの外部性」:一群の利用者のネットワークに新たに顧客が加わると、その顧客は既にネットワーク(やシステム)に属している利用者に対し、消費の補完性としての便益(価値・効用)を生むこと。規模・範囲の経済性のような生産に関するものではない。表計算ソフトをもつソフトウェア会社などの企業間競争のほか、VCRでのVHSやベータなどの異種技術間の競争にも影響を及ぼす。 | ||
|
| |||
|
【図表】 サービス普及率でみたブロードバンドサービスの普及状況 | |||
|
| |||
| (注) | 「サービス普及率」:2003年3月から2003年9月のデータを用い、携帯電話の場合、加入者数を人口(約1億2,000万人)で割り、その他サービスでは世帯数(約4,700万)で割ったもの。千の位で四捨五入。各サービス近傍の括弧内に%で表示。「FWA」:Fixed Wireless Accessの略で加入者系無線アクセスシステムのこと。「縦軸の5つの分類」:E.M.ロジャース教授(米国の社会学者)の普及モデルを参考にした。 | ||
| (出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年10月] | ||
|
| |||
|
▼▼▼ サービス普及率に応じた競争評価のポイント ▼▼▼ | |||
| ● | 競争評価はサブマーケット(当該サービス)の普及率(熟度)に応じポイント、重視すべき点が異なる。 | ||
| ◇ | 普及拡大段階に至るまではとくに「参入障壁」に注視する必要があり、「価格弾力性」や「超過利潤性」の評価を行うのに有効であるのは、50%以上の普及率を超えてからであるなど、普及率(熟度)に応じて評価ポイントが異なっている。 | ||
|
| |||
|
【図表】 サービス普及率に応じた競争評価のポイント | |||
|
| |||
| (注) | 「○」→「◎」の順に競争評価項目に合致している。「サービス普及率」:2003年3月から2003年9月のデータを用い、携帯電話の場合、加入者数を人口(約1億2,000万人)で割り、その他サービスでは世帯数(約4,700万)で割ったもの。千の位で四捨五入。各サービス近傍の括弧内に%で表示。「FWA」:Fixed Wireless Accessの略で加入者系無線アクセスシステムのこと。「縦軸の5つの分類」:E.M.ロジャース教授(米国の社会学者)の普及モデルを参考にした。 | ||
| (出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年10月] | ||
|
| |||
|
▼▼▼ サービス普及段階・利用者層別の多機能化への拡がりと例示①(Suica) ▼▼▼ | |||
| ● | 共通時間軸でサービスラインナップの拡がりを整理し、普及段階・利用者層別に分析することで、各段階においてドライバーとなるサービスの特性が把握できる。 | ||
| ● | 実際の時間軸とサービスラインナップとの具体的な関係を「Suica」を例に示すと、クリティカル・マスを超えた段階に入っていることが確認できる。 | ||
| ◇ | ICカード分野でベストプラクティスでもある「Suica」の例では、最初の第1段階で提供するサービスは「利便性」、「簡便性」に優れ、分かりやすく単純な「キラーアプリ」であり、次の段階でクレジット機能や電子マネーなどの決済手段といった「機能を追加」、さらに次の段階では、相互接続できる「サービスの幅を拡げていく」展開が見てとれる。 | ||
| ◇ | 普及が進むにつれ事業者が展開するサービスは複雑化していくが、「イノベーター層」や「オピニオンリーダー層」など利用者層が右よりであるほどサービスの受け入れ時期は早く、利用形態もより多機能化が進むが、「ラガード層」など左よりになればなるほど受け入れ時期が遅く、利用形態も少数の主要な機能のみに限定した利用となる傾向が示される。 | ||
|
| |||
|
【図表】 サービスラインナップと各利用者層別における共通時間軸での多機能化への拡がりと例示(Suicaの例) | |||
| ↑クリックで拡大図へ | |||
| (注) | E.M.ロジャース教授(米国の社会学者)のイノベーション普及モデルを参考にした。「AP」:アプリケーションの意味。 | ||
| (出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年8月] | ||
|
| |||
|
▼▼▼ サービス普及段階・利用者層別の多機能化への拡がりと例示②(Edy) ▼▼▼ | |||
| ● | 実際の時間軸とサービスラインナップとの具体的な関係を「Edy」を例に示すと、まだクリティカル・マス手前の段階にあることが確認できる。 | ||
|
| |||
|
【図表】 サービスラインナップと各利用者層別における共通時間軸での多機能化への拡がりと例示(Edyの例) | |||
| ↑クリックで拡大図へ | |||
| (注) | E.M.ロジャース教授(米国の社会学者)のイノベーション普及モデルを参考にした。「AP」:アプリケーションの意味。 | ||
| (出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年8月] | ||
|
| |||
|
| |||