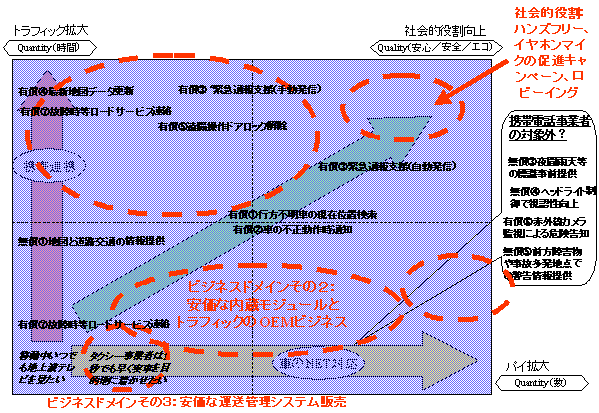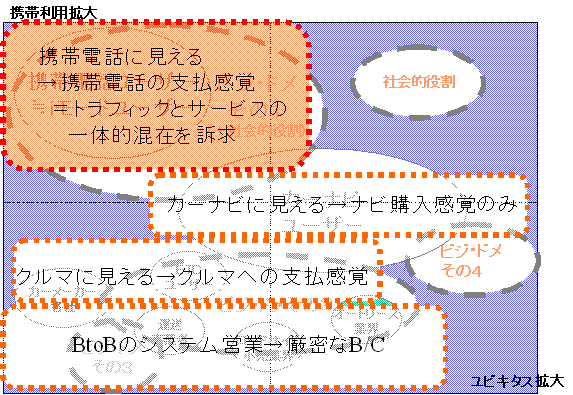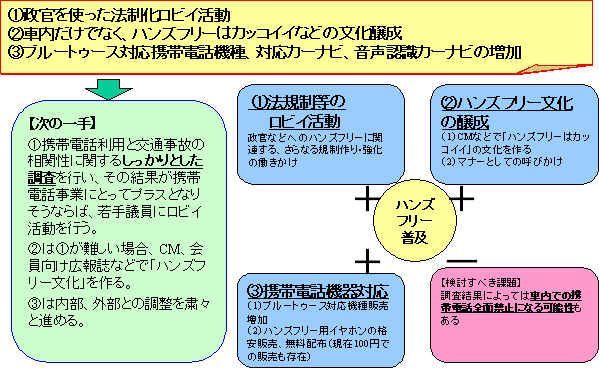携帯電話事業から見る カーテレマティクスのビジネスモデル
|
▼▼▼ 携帯電話事業から見るカーテレマティクスのビジネスモデル① ▼▼▼ | |||
|
● |
携帯電話事業にとって、ITSとくにカーテレマティクス(自動車内での無線通信利用による利便性向上サービス)は90年代半ば以降、長らく新規市場として注目に値する対象であった。 | ||
| ◇ | しかし日本人で1日平均60分程度の乗車、平均乗車人員1.3人(つまり4台に3台は1人で運転している)、最大のキラーコンテンツである道路交通情報が事実上利用料無料(カーナビとVICSのFM波受信)で提供されていること、しかも運転中に情報機能の操作が危険で困難であることも加味され、「接触時間の短いメディアに人はお金を払わない」というユーザーの志向に対して投資回収に相当する適切なビジネスモデルを構築することが長らくできずにいる。 | ||
| ◇ | 結果として2004年現在、カーテレマティクスは自動車メーカーが顧客に対する付加価値向上策として独立採算を取らない事業を構築し、携帯電話キャリア(兼端末提供事業者)は自動車ユーザーの前面に出ずに、通信料も含めた自動車部品調達先に成り下がってしまう傾向も見て取れる。 | ||
| ◇ | 携帯電話キャリアの生命線は、従量制を基本とし、既存/新規の通信システムの投資回収を可能とする利用料課金である。これを主導のカーテレマティクス「事業」として実現し、一方で既存の自動車メーカー主導のカーテレマティクスサービスとどう向き合っていくか、が重要な課題となっている。 | ||
|
【図表】 ビジネスドメインその1:携帯電話による保険的サービス(と安全・安心向上の訴求) | |||
|
| |||
| (出所) | 丸数字は、2002年3月日経BP調べの消費者ニーズ順位(有償/無償別)。それ以外は他の調査より | ||
|
| |||
|
▼▼▼ 携帯電話事業から見るカーテレマティクスのビジネスモデル② ▼▼▼ | |||
| ● | 携帯電話事業者としてのカーテレマティクスのビジネスドメインを考えるとき、通信料金のユーザー課金を目指す以上消費者ニーズに適応したものでなければならない。図では、収益源である「パイの拡大」と「トラフィックの拡大」を両軸に取り、ユーザーの重要ニーズをプロットした上で、対応するビジネスモデルで括ったものである。 | ||
| ◇ | 携帯電話自体はほとんどすべての運転手が所有している一方、自動車に乗車する時間の絶対量が少ないことから、有効なビジネスモデルの一つとして、短時間での高額課金、具体的には自動車の安全運転に関わる緊急事態の対応、保険的サービスが考えられる。 もちろん自動車メーカーに対する内蔵モジュールの納品、運送事業者に対する運送管理システムとしてのパッケージ納品も、採算に乗りさえすれば大きな収益源でありコストダウンとサービスの差別化に尽力する余地は大いにある。 | ||
| ◇ | さらに携帯電話とカーナビも含めた自動車の買い替えサイクル(約2年 対 約7年)の差を埋めること、すなわちカーナビの買い替えサイクルを自動車の買い替えと切り離して中古市場や買い替え市場を創出することが、結果として「新型カーナビ対応機種の充実」という形で携帯電話市場の拡大にも貢献できる、というビジネスモデルも多いに可能性を秘めている。 | ||
| ◇ | これに加えて、すでに道路交通法で携帯電話の走行中使用(ハンズフリーを除く)が禁止されていることから「携帯電話事業としての社会的貢献」の軸を設定さざるを得ないが、これを逆にハンズフリーキットや車載モジュールのビジネス拡大のチャンスと捉えることも可能である。この場合、現行の道路交通法に対し携帯電話事業に有利なロビーイングも可能であり、この方策を検討することも、既得権益を目指す重要なビジネスモデル形成活動と言える。 | ||
|
| |||
|
【図表】 携帯電話事業者としてのカーテレマティクスのビジネスドメイン | |||
|
| |||
| (出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2004年16月] | ||
|
| |||
|
▼▼▼ 携帯電話事業から見るカーテレマティクスのビジネスモデル③ ▼▼▼ | |||
| ● | これらビジネスモデルを実現に移すにあたって重要な留意点もまた、ユーザーニーズ、すなわち支払感覚へのニーズマッチングである。 | ||
| ◇ | 「積み立てまたは爆発的課金による、‘保険的’ サービスビジネス」については、すでにダイヤルQ2以来、電話事業者が料金回収代行をすることにユーザーの理解が浸透していると考えられるので、サービスそのものを保証する(とくに緊急通報による救命率の明らかな向上など)ことさえできれば、携帯電話課金という‘支払プラットフォ ーム’になじませること、すなわち「けーたいに見せる」が可能である。 | ||
| ◇ | 一方、カーナビとの連動で発生する課金サービスは、VICSが‘一件無料’であるように、カーナビのオプション機能であって携帯電話に課金されることはユーザーの支払感覚になじまない。したがってカーナビの拡販そのものに携帯電話事業が連携していかないと、90年代の事業的失敗を脱却できないということになる。 | ||
| ◇ | 運送管理システムの場合はITS全体の共通課題として①システム導入による投資対利益額のプラス効果、②その投資自体が運送事業者の身の丈の範囲内であること(安いこと)の2つを厳密に証明した上で販売していく必要がある。 | ||
| ◇ | そしてユーザーと接点を持てない「自動車メーカーへのOEMビジネス」は、自社ブランドのカーテレマティクスビジネスとは「別の顔(ブランド、採算、事業部)」 で行うべきである。 | ||
|
| |||
|
【図表】 携帯電話事業から見るカーテレマティクスのビジネスモデルのポイント | |||
|
| |||
| (出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2004年6月] | ||
| ● | 社会的貢献としてのハンズフリー携帯電話の普及については、すでに道路交通法が施行(手持ち携帯電話を通話/メールで使用しての運転は現行犯で取締、反則行為に)されていることから、携帯電話事業者に有利な形でのロビーイング(法規制強化、運用強化)をめざすことが可能である。 | ||
| ◇ | ハンズフリーキットの販売(自動車メーカーへのOEM含む)、ブルートゥース搭載機種(携帯電話、カーナビ)による1回線利用のハンズフリーシステムなど、新規市場が考えられるが、一方でハンズフリーイコール安全という科学的証明も十分なされておらず、きちんとした調査の上でロビーイング(行政に陳情するよりも国会対応させるほうが強制力がある)のアプローチを検討する必要がある。 | ||
| ◇ | 参考となる先例として、「チャイルドシート(法制化による義務付け)」、「エアバック(自動車メーカーが自主的に付け普及率も高く法制化はしていない)」があり、この経緯や背後の活動もきちんと調査することが必要だろう。 | ||
|
| |||