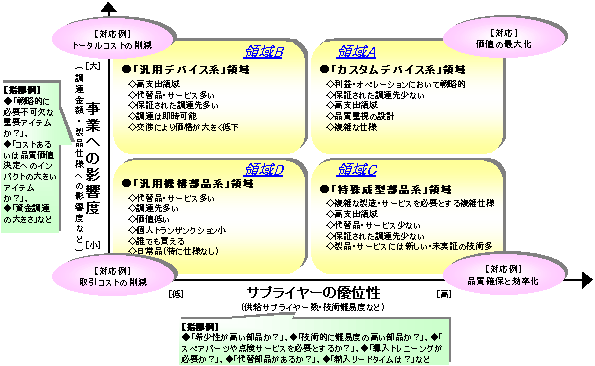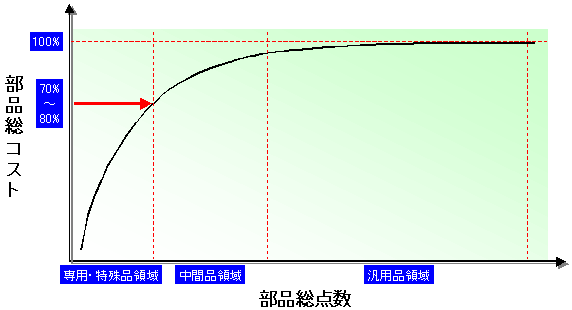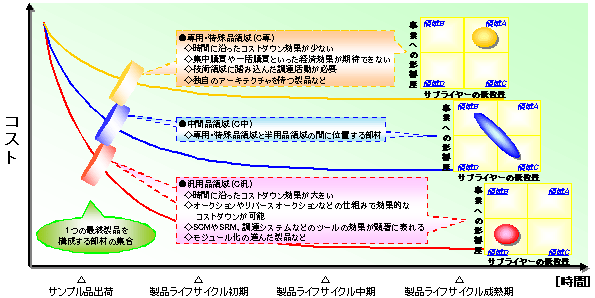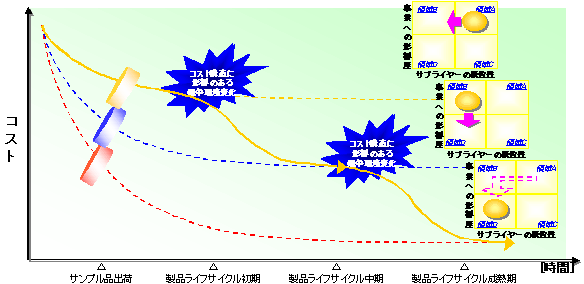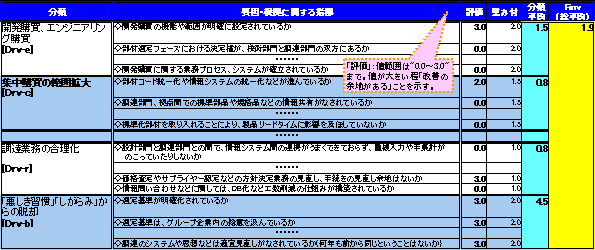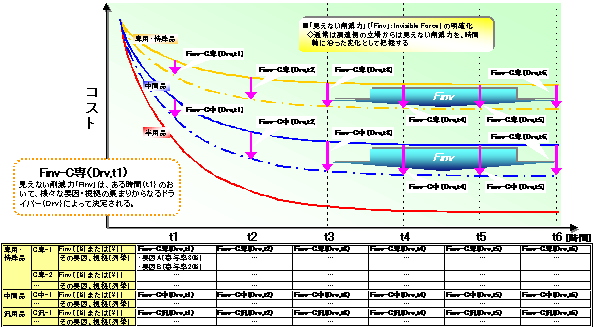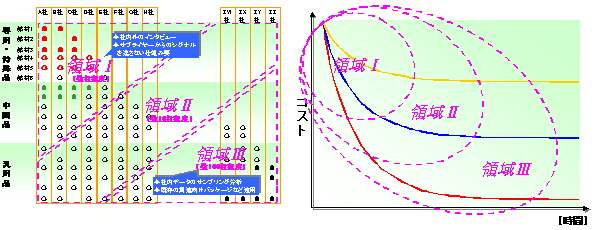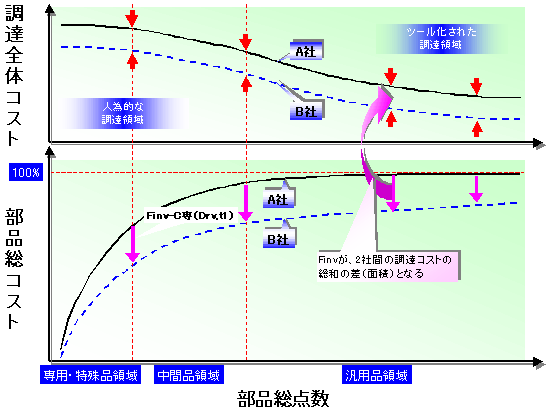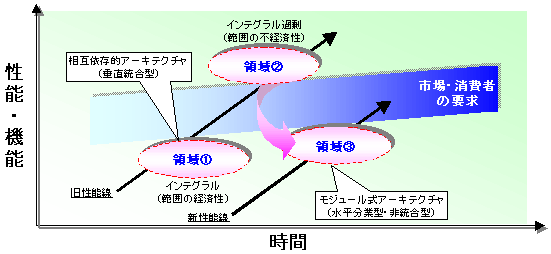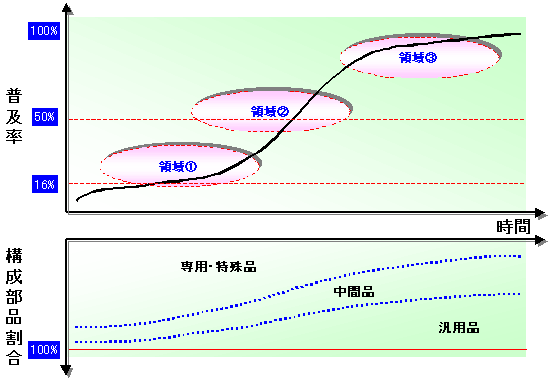|
戦略的ダイナミック調達管理が企業競争力を高める 日本総合研究所 研究事業本部 新保豊 主席研究員、浅川秀之 研究員 (2004年3月2日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1)はじめに 製造業企業における調達部門の一般的な業務は「必要な時に、適正な価格で、適正な購入先から、適正な品質のもの」をいかに調達するかということを基本としており、製品原価比率の低下や、棚卸資産の効率化といったことが主な目的となる。その活動成果が、利益率や資本回転率などに直結するため、当該企業に及ぼす財務的な影響は計り知れない。大手エレクトロニクスメーカーの年間資材調達額は数百億円から数千億円にのぼるとされている。このような状況下ではわずか数%といえども原価低減目標がクリアされると、これだけで数十億から数百億円規模の財務体質改善に貢献することになる。 (2)従来の調達方法と課題 近年消費者志向の多様化や変化周期の短期化が激しく、これにともない製品ライフサイクルの短期化が進んでいる。また技術革新スピードも一段と早くなり、さらには生産拠点の海外シフトや環境保全要請の高まりにともなうグリーン調達など、調達部門をとりまく環境はめまぐるしく変化している。単に「安くて品質の良いものを」といった観点だけで、従来どおり購買・調達業務に携わっているようでは、このような環境に追随できない。 このような状況に対応すべく「開発購買(エンジニアリング購買)」や「グローバル調達」といった手法を取り入れ、戦略的に購買・調達業務を推進する企業が増えている。このような企業では、できるだけ初期の段階から原価低減を意識した開発を行ったり、グローバルに最適サプライヤーを開拓することにより、製品原価をできるだけ低く抑えられるよう努めている。また対象部材に対して「コモデティポートフォリオマトリクス」(【図表1】)などを用いた分析を行い、企業の収益最大化をはかるべく「集中購買」「品目集中」「サプライヤー集約」「逆オークション」といった具体的施策へと結びつけている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【図表1】 コモディティポートフォリオの例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(出所) |
UNISYS「ソリューション&サービス:SRMのメリット」などを基に日本総合研究所ICT経営戦略クラスター加筆修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
様々な戦略的調達手法が各企業で取り入れられている一方で、その成果が効率的に現れている事例は非常に少ない。購買・調達業務を戦略的に推進する際の難しさには様々な要因が考えられる。開発購買といっても開発部門のノウハウがうまく調達部門に伝わらない現実があったり(その逆も然り)、全社戦略として取り組むべき調達改革がなかなか理解してもらえない組織体系であったりと、その要因は各企業において様々である。しかしながら、現在のような変化の激しい環境下において、数々の戦略的調達手法がうまく機能していない実態は「真のコスト構造をダイナミックに把握できていない」という根本的な理由に起因していることが多い。消費者志向の多様化や変化周期の短期化、製品ライフサイクルの短期化が進んでいるという現実は認識していても、このような変化に対応した真のコスト構造を把握できる概念や、それに基づく具体的なシステムの構築ができていない場合が多い。 (3)DPM(Dynamic Procurement Management)による企業競争力強化について 真のコスト構造を把握するためのダイナミックな調達管理手法であるDPM(Dynamic Procurement Management)についてその概要を述べる。 現在のような変化の激しい環境下においては、購入価格が一度決まればその後もその価格が一定に推移することは稀である。これまでのように、変化が穏やかであるような環境下であれば一定であると近似することも可能であるが、実際はそのような部材は少なく、製品全体の中における重要度も低い場合が多い。従って、ある製品のコスト構造を真に把握するということは、単に一時点のコスト構造だけを把握することではなく、時間軸に沿ったコスト構造の変化全体を把握するということにほかならない。通常一つの製品を構成する部材は、数十から数百(多い場合は数千)からなる。従って、全ての部材についてその時間変化を把握することは現実的に難しいため、コスト構造に大きく影響を及ぼす「キーコンポーネント」の抽出が必要となる。キーコンポーネント部材の場合、ある製品を構成する部品総数に比して部品点数としてはわずか数%を占める程度であったとしても、部品総コストにおける占有割合は非常に高い場合が多い(【図表2】)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【図表2】 部品総点数と部品総コストの関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(出所) |
日本総合研究所ICT経営戦略クラスター[新保・浅川、2004]作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ある製品を構成する部材を「専用・特殊品」「中間品」「汎用品」の3つに分類し、それぞれの分類を代表するキーコンポーネントのコスト変化を模式的に表すことができる(【図表3】)。 一般に汎用的部材においては、インターフェースの統一性や標準化などが進んでいるため、オークションなどの仕組みを利用したコスト削減施策が可能である。逆に専用・特殊品的部材の場合は、調達部門とサプライヤーとの間での綿密なすり合わせ交渉が必要となり、大幅なコスト削減効果は見込みにくい。また、各分類のコモディティポートフォリオマトリクス上における位置づけは、専用・特殊品領域に属する部材は領域Aに、汎用品領域に属する部材は領域Dに、中間品領域に属する部材は領域BおよびCにそれぞれ対応している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【図表3】 時間軸に沿ったコスト構造の変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(出所) |
日本総合研究所ICT経営戦略クラスター[新保・浅川、2004]作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
製品ライフサイクルの過程においては、「技術的なイノベーション」「新規競合他社参入」「戦略的価格設定」など、競争環境を攪乱させるような要因が発生することが多い。これらの要因により当該製品のコスト構造は大きく影響を受ける。時間軸に沿った動的な捉え方をすると、このような競争環境変化が発生した場合でも、コスト構造変化に追随した動的な調達戦略の推進が可能となる。競争環境変化要因が2度発生した場合のコスト構造の変化を模式的に表すと【図表4】のようになる。競争環境変化により、専用・特殊品や高付加価値調達品の一部が汎用品側へシフトすることを示しており、これにともないコモディティポートフォリオマトリクス上においても領域Aから領域Dへとその位置付けがシフトしていく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【図表4】 ソフトウェア分野のIT投資手段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
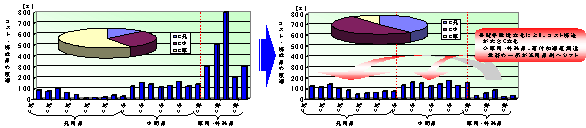 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(出所) |
日本総合研究所ICT経営戦略クラスター[新保・浅川、2004]作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
このような時間軸に沿ったコスト構造変化を分析するアプローチを用いることにより、「見えない削減力」(「Finv」:Invisible Force)の明確化が可能となる。「見えない削減力」とは実際に取引されているコスト構造と真のコスト構造との差分に相当する。この「見えない削減力」は、開発購買やエンジニアリング購買、集中購買範囲拡大、調達業務合理化などの観点からサプライヤー側のコスト削減余力(本来のコスト構造)を分析することにより数値化することが可能である。 Finvの算出例を示すと【図表5】のようになる。本例では、開発購買やエンジニアリング購買、集中購買範囲拡大といった分類を用いているが、これらの分類は、対象となる部材のサプライヤー市場領域(サプライヤー市場領域に関しては後述を参照)などに応じて適切に検討を加える必要がある。同図表に示した開発購買やエンジニアリング購買、集中購買範囲拡大といった分類は、どちらかというと汎用品的な部材に適しているといえる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【図表5】 Finv算出例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(出所) |
日本総合研究所ICT経営戦略クラスター[新保・浅川、2004]作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
このように数値化された「見えない削減力」Finvをコスト構造曲線に追記することにより、本来のコスト構造変化を把握することが可能となる(【図表6】)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【図表6】 「見えない削減力」の明確化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(出所) |
日本総合研究所ICT経営戦略クラスター[新保・浅川、2004]作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ここまで述べてきたDPMの仕組みは、汎用品領域よりは専用・特殊品領域に属する部材を管理する際に重要となる。汎用品の場合は既に各社から調達システムなどが豊富に提供されておりこれらのツールを利用することによりある程度「真のコスト構造」が明確化可能である(【図表7】の領域Ⅲに相当)。しかしながら、専用・特殊品の場合は技術的な障壁が高いこともあり、システム化された調達ツールへの適応が難しく、組織的な対応・能力が必要となってくる(「領域Ⅰ」に相当)。一般に、製品ライフサイクルにおいては初期段階のほうが組織的な対応・能力が必要とされ(「領域Ⅰ」に相当)、時間が経つほど汎用的な部品へとシフトしていく(「領域Ⅲ」に相当)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【図表7】 DPMにおけるサプライ市場分析のポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(出所) |
日本総合研究所ICT経営戦略クラスター[新保・浅川、2004]作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
見えない削減力Finvに起因してコスト構造の差異が生じている2社(A社およびB社)を例にとり、部品総点数に対する部品総コストおよび調達全体コストの関係を示すと【図表8】のようになる。同図表の下段ではB社の方がA社に比べてコスト構造が良好である例を示している。また、同図表の上段はこのFinvの差異が全体調達コストの差となって現れていることを示す。このようなコスト構造を持つ2社をサプライヤーにもつ企業の調達部門は、Finvが何によってきまっているかを分析することが重要となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【図表8】 部品総点数と部品総コストおよび調達全体コストの関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(出所) |
日本総合研究所ICT経営戦略クラスター[新保・浅川、2004]作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全くの新製品の場合、各開発担当部門間においてはある程度密度の高い意志疎通をおこないながら開発を進めていかなくてはならない。これはその製品の持つ技術の新規性などに起因するものであり、製品開発の流れの中においていわゆる「垂直統合型」開発体制が必要とされる領域である(【図表9】の領域①参照)。さらに製品ライフサイクルが順調に進行し、やがては消費者や市場の吸収可能な要求ラインを超えるまでに持続的技術革新が発展する。この領域(同図表の領域②参照)では、限界効用(顧客がある製品の購入、利用から得る満足の増分)が限界価格に比して小さくなるために、顧客はより良い製品に高い対価を支払う意志をなくしてしまう。つまり、既に消費者や市場の要求をほとんど満たすほどに技術的、機能的な革新が進んでおり、消費者や市場の要求は技術や機能の新規性よりも、価格重視へと変化していく。このような要求の変化に追随するためには、領域①から領域②に至るまでの間に構築された持続的な技術革新プロセスでは対応が難しい。近年、欧米を中心とした主にPCなどを製造するエレクトロニクスメーカーは、モジュール型(水平分業型)のアーキテクチャを採用することにより、基本的な機能や技術を維持しながらもこのような消費者や市場の要求に対応している(同図表の領域②から③への変化)。これらのことはクレイトン・クリステンセン[1999]や池田信夫[2004]が既に指摘していることである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【図表9】 技術革新と各製品開発アーキテクチャの関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(出所) |
クレイトン・クリステンセン[1999]や池田信夫[2004]を基に日本総合研究所ICT経営戦略クラスター[新保・浅川、2004]作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この製品ライフサイクルの一連の変化と、その製品の普及率との対応を示したものが【図表10】(上段)であり、さらに構成部材の内訳(専用・特殊品、中間品、汎用品の存在割合)を示したものが同図表(下段)である。ある程度普及するまで(普及率16%から50%程度まで)は、製品の新規性が高いために、当該製品を構成する各部材は比較的専用・特殊品が多い(領域①)。さらに持続的な技術革新が進み領域②に到達すると、この時点では消費者や市場にニーズはほとんどクリアされているため、必要最低限の機能を備えた低価格なものへとニーズが変化する。これにともない、汎用品や中間品の構成比率が比較的高い領域③へとシフトしていく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【図表10】 普及率と構成部品割合の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(出所) |
日本総合研究所ICT経営戦略クラスター[新保・浅川、2004]作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DPMの概念に基づいて「見えない削減力」を調達部門側でダイナミックに把握することは、主にサプライヤー側で管理されている「真のコスト構造」を把握することに他ならず、調達部門側にとって強大なバーゲニングパワーの源泉となろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||