RIM 環太平洋ビジネス情報 1998年1月No.40
香港金融市場の現状と今後の行方
1998年01月01日 さくら総合研究所 孟芳
はじめに
タイを皮切りに1997年7月に始まったアジア通貨危機が、10月には香港にも波及し、米ドルにペッグされている香港ドルに対する不安感が広がった。香港ドルを防衛する目的で、香港金融当局が金利を高めに誘導した結果、株価(ハンセン指数)は市場最大の下落幅を記録した。
香港金融当局は当面、株価や不動産市況の下落が続いてもペッグ制を維持する方針であるが、金融市場の低迷が長期化した場合、香港経済および中国系企業の資金調達などへの悪影響が懸念される。本稿では、香港経済の現状を踏まえ、国際金融センターとしての香港の将来を考えてみたい。
1.貿易・投資の自由化
97年10月23日、香港ドルへの売り圧力が強まり、香港金融管理局(HKMA)が香港ドルを防衛する目的で、市中に流通する香港ドルの量を極端にしぼり、短期金利を高めに誘導したこともあり(翌日物インターバンク金利は、一時300%を超える水準に急上昇)、株価が急落した。今回、香港ドルが売り込まれるきっかけとなったのは、香港と同様に外貨準備が豊富な台湾の金融当局が17日、台湾元相場の決定を市場実勢に委ねる方針を発表したことで、台湾元相場が97年7月以来の1米ドル=28.6台湾元前後の水準から、1米ドル=31台湾元まで下落(7%余り)したことである。
さらに28日には、ニューヨーク株式市場の急落を受けて、ハンセン指数が前日比1,438.31ポイント安と史上最大の下げ幅を記録し、9,059.89 ポイントまで下落した(図1)。その後、韓国の通貨危機などの影響を受けたものの、香港当局は再三にわたりペッグ制の維持を強調したことから、ハンセン指数は97年12月31日現在、10,722.53ポイントにまで回復した。
97年7月1日の中国への返還後、「一国二制度」が順調に運営され、香港の安定と繁栄の維持に自信を深めていた市民の間に動揺が広がり、香港金融当局は対応を迫られた。香港特別行政区の董建華行政長官は、就任後初めての大きなイベントである9月の世界銀行・国際通貨基金(IMF)年次総会を無事乗り切り、東南アジアや米国、日本、欧州などの外遊先で「香港は返還後も変わらない」と世界にアピールしていた矢先に、香港ドルが売り圧力にさらされた。
さらに、金融のグローバル化が進み、香港市場と先進国市場との連動性が強まるなか、香港株の急落を受け、東京、ロンドン、ニューヨークなど世界の主要株式市場が同時安を経験した。
2.香港の為替制度の特色
(1) 香港の為替制度
香港ドルの価値を米ドルに連動させるペッグ制が導入されたのは、83年10月のことであった。香港返還をめぐる中英交渉が暗礁に乗り上げた同年9月、香港社会の動揺と将来への失望で香港ドル売りが加速し、株式市場と金融市場はパニックに陥り、香港ドルの対米ドル相場は82年末に比べ30%余り暴落した。香港政庁は、香港の貿易に占める対米貿易のシェアが高いことを考慮し、それまでの変動相場制から1米ドル=7.80香港ドルを中心とする極めて狭い範囲に自国通貨の変動を抑えるペッグ制に移行した。
ペッグ制を維持する仕組みは図2の通りである。まず、中央銀行のない香港では、発券銀行3行が為替基金(Exchange Fund)に対し、米ドルを預託するのと引き換えに1米ドル=7.80香港ドルの固定レートで負債証明書(Certificate of Indebtedness)の交付を受け、同証明書相当額の香港ドルを発券する(香港ドルの価値は100%米ドルによって保証されることになる)。そして、1米ドル=7.80香港ドルで各銀行に香港ドルを供給する。
また、HKMAは、金融市場で香港ドルの流動性を調節することで、間接的にインターバンク市場金利を操作できることに加えて、市場金利も操作できる。10 月25日、HKMAは香港の公定歩合に相当する流動性調節枠(LAF)の調整による金利の変動幅を4.25~6.25%から4~7%に拡大すると発表し、市場金利を高目に誘導して、通貨の売り圧力に対し、金利引き上げによって対処した。その結果、HKMAより借り入れを行っている銀行は高い調達コストを負担することとなり、銀行部門は深刻な打撃を受け、市場全般にネガティブな影響を与えた。その後12月中旬まで、3カ月物インターバンク金利で15%前後に高止まりした。10月23日にプライムレート(最優遇貸出金利)が8.75%から9.5%に引き上げられた状況下で余りにも逆ざやが大きく、収益を圧迫していたが、97年末には、3カ月物インターバンク金利はようやく9%程度まで低下した。
(2) ペッグ制維持の背景
香港ドルはペッグ制が導入された83年以降、何回も投機筋に狙われてきた。87年のブラックマンデー、89年6月の天安門事件発生に伴う株価の下落、90 年の湾岸戦争、95年初のメキシコ通貨危機に伴う米国を中心とする機関投資家の新興市場からの資金引き揚げなど、多くの切り下げ圧力を過去に経験したにもかかわらず、香港政庁はペッグ制の維持してきた。
香港政府が香港ドルを死守する構えを崩さないのは次のような理由による。まず、香港の為替政策が、香港ドルの国際的信認を確保し、香港経済に活況をもたらしたことである。米国は中国と並んで香港の最も主要な貿易相手国であるため、香港ドルの対米ドル相場の安定は、単なる貿易の発展を意味するだけではなく、香港社会の安定維持にも重要である。また、返還後間もないことから、将来に対する不安が依然として残るなか、特区政府にとって社会の安定は最優先の政策目標となっており、そのためにはペッグ制を維持しなければならないとされている。
今回、香港ドル売りの動きに対して、董建華行政長官は「米ドルとの連動相場制は、過去14年にわたって経済を安定させ、国際的な貿易金融センターとしての信用確保に寄与してきた」、また、ペッグ制を放棄すれば「香港経済の先行き不透明となり、成長率はゼロ、インフレ率は2桁になる可能性がある」と語っている。また、曽蔭権・財務長官は「83年のペッグ制採用以降の経済実績は極めて良い。対外債務はなく、財政黒字は400億米ドルを超え、外貨準備は920億米ドル(10月末)ある。10月に香港ドルの売り攻勢が始まる以前の外貨準備高は880億米ドルだったが、(当局の介入後に)逆に外貨準備高が増えた。われわれは良好な経済実績を背景に、今後のペッグ制堅持に全面的な自信を持っている」とペッグ制を死守する考えを繰り返し表明した。任志剛金融管理局長(中央銀行総裁)も、香港と中国を合わせ2,200億米ドルの外貨準備高があることから、今後のペッグ制堅持に全面的な自信を表明している(図3)。
一方、香港では内外の資金取引に制限がなく、金利裁定が自由に働く。その結果、現行のペッグ制では、市中金利は米国金利と連動性が強くなり、金融需給は米国の金融政策によって決定されることとなる。また、実質的にドル本位制の下で、香港は高いインフレ率に悩まされているが、近年の香港金利は香港のインフレ率を下回っており、実質金利はマイナスとなっている。しかし、ペッグ制を廃止すれば、香港に対する信頼が失われ、急激な資金流出が生じ、不動産価格や株価が急落する恐れがあるからである。こうした事態が生じた場合、金融機関の経営にも大きな影響が生じよう。
3.香港経済のファンダメンタルズ
(1) 好調であった民間消費と投資
97年通年の香港の実質経済成長率は、民間消費と固定資本形成などの内需が堅調に推移して、96年以来の輸出低迷をカバーし、前年の4.9%を上回る 5.5%に達した見込みである。歴史的な主権返還を迎えた香港経済に対する信頼感が高まり、「返還効果」が広がったこともプラスに働いた。実質経済成長率は、97年第1四半期に前年同期比6.1%増、第2四半期には同6.4%増となり、94年第1四半期の同6.5%以来の高成長を記録した(図4)。
97年上半期は、株価や不動産価格が高騰したことで、民間消費意欲が高まり、第2四半期の個人消費は前年同期比8.7%増となった。また、機械・設備に対する投資の拡大に加えて、董建華行政長官が施政方針演説(97年10月8日)の中で、今後10年間、毎年8万5,000戸の住宅を供給することによって、公共住宅の建設をスビートアップさせると発表したことから、固定資本形成も大きく伸びた。
しかし、今後、高金利が長期化した場合、香港の個人資産に占める比重が高い不動産と株式市況が冷え込み、個人消費が低迷する恐れがある。香港では95年に、株価、不動産価格の下落による逆資産効果と失業率の上昇により、GDPの6割を占める民間消費支出が1.3%増と20年ぶりの低い伸びとなり、景気の足を引っ張ったことがあった。
(2) サービス業主体の産業構造
80年代以降、製造業の華南地域へのシフトに伴い、香港のGDPに占めるサービス産業の構成比は急速に高まった。GDPに占める製造業のシェアが80年の 23.7%から95年の8.3%に低下した半面、サービス産業は同期間中に67.5%から83.8%に拡大した(表1)。董建華行政長官も「香港経済の8割はサービス産業に依存しているため、通貨切り下げで競争力を維持するつもりはない」(97年10月)と言明した。
確かに、サービス産業の競争力は、専門知識、経験、ノウハウなど「ヒト」に帰属する要素で決まる側面が強く、為替変動の影響は製造業とは異なるが、ビジネスコストは着実に上昇している。また、香港の成長産業になりつつある金融、保険、不動産、通信、運輸、倉庫、流通分野の各市場は寡占状態となっているため、競争原理が十分に働いているとはいえない。加えて、香港の製造業は、華南に移動することで生き残りを図ったため、ハイテク製造業分野は弱く、旧香港政庁の支援政策も極めて限定的なことから、シンガポールや台湾と比較して産業の高度化が遅れている。
去る10月、董建華行政長官が施政演説の中で、情報通信の研究を中心としたハイテク分野を支援し、最高5億香港ドルの研究基金を設立するなどのハイテク産業振興政策を発表した背景には、こうした事情がある。
(3) 対外貿易
貿易は香港経済を牽引してきた。輸出額の対GDP比は、80年の68%から96年の117%に高まった。貿易部門はGDPの2割以上を創出し、香港の雇用の2割弱を引き受けている。貿易の拡大により、貿易関連サービス産業も急速な成長を遂げ、オフィス、倉庫などに対する需要の喚起や、不動産開発などによる果実を香港にもたらした。
香港は、中継貿易基地としての性格上、再輸出(香港に輸入された製品で、香港で製造・加工のプロセスを経ずに再び輸出されるもの)が大きなウェートを占めている。80~95年の期間に、再輸出の伸び率は年平均27%に達した(総輸出は同19%増)。輸出全体に占める再輸出のシェアは、88年に地場輸出を上回り、95年には83%まで上昇した。しかし、96年の再輸出の伸び率は、米中両国の輸入需要が減退した影響を受け、95年までの2桁台の伸びから 6.6%増に減速し、総輸出も75年以来の最低水準である4%増となった。さらに、97年1~9月には、香港のオフショア貿易(積み替えや香港を経由しない中国・第三国間の貿易)の増加、および中国の設備輸入関税の減免措置の見直しに伴い、香港からの投資が減少し、再輸出の伸びは3.9%まで低下した。
また、香港の貿易収支は恒常的に赤字を計上しているが、サービス収支(運輸、観光収支など)が大幅な出超を記録していることから、対外バランス(財・サービス収支)は、基調として黒字(ただし、95、96年は新空港建設関係の輸入が増加したことから赤字)を続けていた(図5)。ただ、再輸出は港湾使用料や貿易金融などを通じて、サービス収支に大きく寄与するため、再輸出の伸び悩みは対外バランスを悪化させる要因となる。
加えて、サービス輸出の4分の1以上を占める観光業が低迷しており、経常収支の赤字が拡大する恐れがある(図6)。香港を訪れる観光客数は年々増加し、 95年には1,000万人の大台を突破し、1,020万人(前年比9.3%増)を記録、さらに、96年には前年比14.7%増の1,170万人に達した。ところが、97年夏以降の東南アジア通貨切り下げを背景に、香港への観光客数は大幅に落ち込んだ(図7)。7月の伸び率は前年同期比35.2%減となり、特に、日本からの観光客は同47.4%減と急減した。
図6 香港のサービス輸出の構成比(1994年)
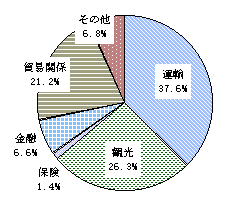
(資料)『Estimates of Domestic Product 1961 to 1995』
(4) 不動産市況
香港経済をみる上で、不動産部門の動向は極めて重要である。GDPに占める不動産関連部門の割合は、86~90年の平均5.4%から91~95年には同 8.1%へと上昇した。また、消費者物価指数A(A:全世帯の50%が調査対象)の構成を見ると、住宅関連部門が25%と、食料品部門の37%に次ぐウェートを占めており、不動産価格の変動は物価にも影響を与える。
また、香港株式市場でハンセン指数を構成する33銘柄のうち、不動産関連が9銘柄と不動産関連株のシェアが高く、不動産価格の株価に及ぼす影響が大きい(図8)。94年6月に、香港政府による土地取引規制導入の影響を受け、住宅用不動産の分譲価格もオフィス用の賃貸価格とともに大幅な下落をみせた。加えて、HKMAが95年9月に、香港域内貸し出しに占める不動産部門向け貸し出し比率の上限を40%程度に設定したことを受け、不動産価格が急落し、株価指数が下落したことは記憶に新しい。その後、96年には、海外移民者のUターン帰国や中国大陸からの移民が増加したため、住宅用不動産への需要が高まり、不動産価格は前年比30%上昇した。さらに、97年の住宅価格は根強い需要を背景に、上半期に前年比34%上昇し、住宅ローン残高は97年6月末で 3,796億香港ドルとなり、前年同月比26.1%増となった。
図8 香港株式市場の部門別時価総額構成比
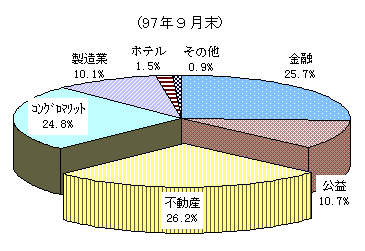
(資料)データストリームより作成
しかし10月以降は、HKMAによる香港ドル防衛を目的とした金利高め誘導を受けて、香港銀行協会が10月23日、プライムレートを8.75%から 9.5%に引き上げたことから、住宅ローン金利に先高感が広がり、不動産価格が大きく下落し、これを受けて香港市場最大の時価総額を誇る不動産株は急落した。97年通年のハンセン指数採用銘柄33社の騰落率ランキングによると、年後半のアジア通貨危機のため、上昇したのは6銘柄にとどまり、他の27銘柄はすべて下落した。そのうち、最も高い上昇率を記録したのはホンコン・テレコム(28.1%)で、逆に、不動産関連である長江実業(CheungKong)は26.2%下落し、騰落率ランキングで11位となった(図10)。最大手の新鴻基地産(Sun Hung Kai Properties)は 43%の下落で21位となった。
図10 香港ハンセン指数33銘柄(一部)の騰落率ランキング(1997年)
(単位:%)
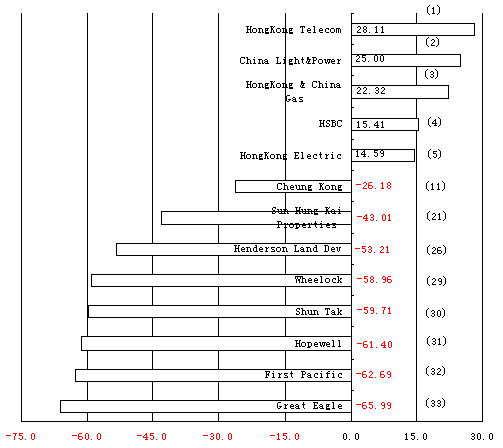
(注)( )数字は順位
(資料)「South China Morning Post」(98年1月4日付け)
株価急落と不動産価格の下落により、資産デフレが発生することが懸念されている。香港当局は、不動産価格の調整が適度な範囲にとどまれば、香港経済の高コスト体質が是正され、為替・株式市場の安定につながるとの認識を持っている。曽蔭権財務長官は「株価と不動産価格の下落はコストを引き下げ、国際競争力の強化につながる」と述べている。だが、香港の株式時価総額の4分の1以上を占める不動産関連企業にとっては、不動産価格の急落は企業業績の悪化や、自社の株価の下落につながる。
10月30日、米国の有力格付け機関であるムーディーズ・インベスターズ・サービス社は、香港上海銀行、恒生(ハンセン)銀行をはじめとする香港の銀行7行に対する格付けを引き下げの方向で見直すと発表した。為替、金利動向の波乱により収益基盤の安定性に懸念が出ていることに加えて、不動産向けの融資が多い(もっとも、香港の銀行では表2の通り一般的な傾向ではある)ことを理由に、7行の格付けを「安定的」から「悲観的(ネガティブ)」に変更することとなった。
(5) 対香港直接投資への影響
香港政府が97年3月に発表した直接投資受け入れ額統計[香港進出外資へのアンケート調査(非製造業の外国投資調査は94年から実施)に基づいて作成]によると、外国からの直接投資純資産累積額[非外国直接者から提供された第三者借款(銀行融資など)を含む]は、95年末まで7,778億香港ドルとなり、 95年の香港名目GDP(10,842億香港ドル)の72%に相当する。このうち、非製造業への投資は94%に相当する7,295億香港ドルで、製造業は 483億香港ドル(6%)となっている(図12)。非製造業については、金融関連、持株会社が約7割を占めており、金融市場の混乱はその活動の制約となる恐れがある。
また、香港の人件費、オフィス賃貸料は東アジアで最も高い水準にあり、外国企業にとって大きな懸念材料となっている。外国企業の香港からの撤退、アジアの他の国への移転などの影響が表れることが懸念される。
4.中国と香港の経済関係
(1) 中国と香港経済の一体化
中国と香港の経済関係は、貿易と投資のみならず、金融面でも深まってきている。まず、貿易については、中国の貿易窓口としての重要性は高く、香港の貿易相手国として中国が第1位(貿易総額の36%、96年)を占める一方で、中国の貿易相手国・地域として香港が第3位(貿易総額の14%、日本21%、米国 15%に次ぐ)を占める。次に、投資については、香港からの投資は中国の外資受け入れ額(約1,000億米ドル、96年現在での累計)の約5分の3を占めている。特に広東省では、香港からの投資が外資受け入れ額の約80%に達している。また同省では、400万人の労働者が香港系企業に雇われているが、これは香港の製造業部門の雇用労働者数の10倍に相当する。一方、中国の香港に対する投資累計をみると、95年末までの合計は1,075億香港ドル(約139 億米ドル)で、香港の受け入れ外資総額の20.2%を占め、英国に次いで第2位となっている。
(2) 中国系企業の資金調達
金融面では、香港株式の暴落が、香港を重要な資金調達の場としている中国の国有企業にも大きな影響を及ぼす恐れがある。中国政府は、93年7月に青島ビールが香港証券市場に上場して以来、国有企業の海外上場を進めてきた。香港の株式市場にはH株(香港市場に上場する中国企業株)に加えて、レッドチップ(中国系香港企業株)が上場され、97年10月末までH株上場会社は39社、レッドチップは約50社に達した(表3)。ハンセン指数にも中国系企業3社が加わり、返還を前後として中国系企業のプレゼンスの高まりは株式市場にも反映されている。特にレッドチップについては、92~95年には香港株式市場の時価総額に占める比率は2%に過ぎなかったが、97年9月末現在、レッドチップ指数に採用されている32銘柄[返還前の6月16日から「中資企業指数」(レッドチップ指数)が導入された]だけで市場全体の11.5%を占めている。さらに、中国国際信託投資公司(CITICパシフィック。業務内容は株式投資および融資など)や北京控股(北京市政府の投資会社)を加えると、その割合は14%程度に高まる。一方、中国からの資金流入も増大している。97年1~8月の株式市場を含む資金の流れは、400億香港ドル(約6,400億円)と、前年比30%増となった。
97年9月に、北京で開催された中国共産党第15回党大会は、国有企業の慢性的な資金不足解消のため、株式制の本格導入を打ち出した。特に優良企業については、香港をはじめとする海外市場に上場させる計画を明らかにした。今後、香港の株価低迷が長期化すれば、中国の国有企業の株式化政策に悪影響が出ることは避けられないだろう。
香港株価が急落した10月23日は、日本のNTTに相当する中国電信(チャイナ・テレコム)の上場日に当たっていた。同企業の上場は当初、97年5月29 日に上場された北京市政府系のレッドチップ企業である北京控股並み、もしくはそれを上回る大型企業の上場として注目を集めていた。しかし、株式市場の乱高下やレッドチップ株の低迷などが一般投資家の心理に大きく影響したため、公募は一般企業並みの申込み状況となり、上場初日は公募価格の11.68香港ドルを下回る10.55香港ドルで取引が終了した。
(3) 人民元
香港ドルの切り下げ懸念が表面化して以来、人民元の動向についての議論が活発になっている。94年1月に、公定レートと市場レートが一本化(公定レートを基準とすれば、33%切り下げられ、1米ドル=8.7人民元)されて以来、現在に至るまで対米ドル相場はごく緩やかな人民元高傾向を示しながら安定推移を続けている(97年10月末時点では1米ドル=8.28人民元)。
中国では、96年12月にIMF8条国への移行が実現し、上海・浦東地区の外国銀行8行に対し、限定的ではあるが試験的に人民元業務が開放されるなどの動きがみられる。93年の消費者物価上昇率を基準とした購買力平価(Purchasing Power Parity=PPP)でみると、96年末時点で人民元は米ドルに対して約23%過大評価されている。また、中国における国有企業の赤字、銀行不良債権の増加に加えて、アジア通貨の切り下げによる人民元の割高感から人民元が下落するのではとの見方が一部に出てきている。
しかし、これまでのところ人民元が安定してきたのは、中国の経済ファンダメンタルズがしっかりしていることや、通貨取引が経常取引に制限され、投機的な攻撃から守られていることによる。WTO加盟を目指すと同時に、むしろ人民元の上昇圧力を弱めるため、中国は97年10月1日から、輸入関税を平均23%から16%へと大幅に引き下げた。さらに、国有企業の金利負担軽減と他国通貨との実質金利差を縮小させるため、10月23日から貸出金利を平均1.5%(例えば、1年物貸出金利は10.08%→8.64%)、預金金利を同1.1%(1年物定期預金金利は7.47%→5.76%)引き下げている。
今後については、(1)96年以来、インフレ率が大幅に低下してきたこと、(2)豊富な外貨準備高(97年9月末1,341億米ドル)および貿易黒字(97年1~9月で305.7億米ドル)が大幅に拡大したこと、(3)外資流入が続いていることから、目下、国内経済環境をみると、人民元に大幅な切り下げ圧力が加わることは考えにくい。ただし98年以降、中国の輸出が予想外に低い伸びにとどまり、経済成長が大幅に減速する事態に陥った場合には、元の切り下げの観測が強まってこよう。加えて、他のアジア諸国通貨が米ドルに対して大幅に切り下がったことから、人民元の割高感が広がっている。いずれにせよ、WTO加盟、金融制度の改革、資本市場の自由化、人民元の完全交換性などの措置が実施されてくることを勘案すると、長期的にみて、人民元相場は人為的な要因ではなく、市場実勢を直接反映して、決定されることになろう。
5.今後の注目点
(1) 国際金融センターとしての香港
香港は世界有数の国際金融センターである。香港に拠点を置く銀行の資産を合計すると、96年末で79.7兆香港ドルに達し、世界第4位の規模である。為替市場の1日当りの売買高も910億米ドルと世界第5位に位置付けられている。また、株式市場の時価総額は97年9月末現在、約5,665億米ドルで、世界第4位となっている。
香港、東京、シンガポールを比較すると、まず、オフショア市場(東京=100とする)規模では、香港が93年時点で東京の88%から96年の98%へ拡大したのに対し、シンガポールは58.4%から71.2%へ上昇している。また、外国為替市場の出来高(一日当たり)をみると、香港は92年4月時点の 48.4%から95年4月には56.5%に高まり、シンガポールは日本の60.3%から65.2%へ上昇している。また、香港の銀行資産総額(96年末1兆221億米ドル)対名目GDP(同1,544億香港ドル)の比率は7倍であるのに対し、シンガポールでは(同、銀行資産総額1,792億米ドル対名目GDP941億米ドル)2倍近くの規模となっている。
香港は、金融市場に対する規制がない、為替管理が課されていない、資金の移動に制約がない、自由度の高い国際金融センターであることを加えて、香港ドルが米ドルにペッグされていることから、為替リスクが少ない市場とみなされてきた。こうした背景から、香港は世界各国の銀行、証券、保険会社が多数参加する極めてオープンな市場となっており、世界の銀行総資産ランキング上位100行のうち81行が香港に拠点を設けている。
さらに、上海市場が香港市場に追いつくまでには、金融システムの整備や、人民元の完全交換性の回復を始めとして多くの課題があることから、相当な時間を要しよう。従って、上海の国際金融センターとしての役割は香港に比べれば、当面極めて限定されたものに止まるのではないかと思われ、中国にとって、香港の国際貿易・金融センターとしての存在意義は極めて大きく、香港を経由する輸出入や対中国の直接投資、及び香港株式市場を通じての資金調達機能はますます重要となっている。
(2) ペッグ制の今後
それでは、香港ドルの将来についてどのような展開が考えられるのであろうか。今回の通貨不安は過去の例と異なる側面を持っている点にも注意が必要である。香港ドルがペッグ制を維持する限り、香港の金融政策の自由度は極めて限られるばかりか、ビジネスコストは他の国々より高い状態が続こう。だが、政治的要因が資本逃避を招きやすい香港にとって、ペッグ制は必要不可欠の制度とも言える。また、貿易と金融については、為替変動リスクを最小限に抑えられることから、香港の競争力を維持するためには極めて重要な制度であり、ペッグ制維持が香港経済にもたらすメリットは、デメリットよりもはるかに大きいと見られる。
しかし今後については、金利が高止まり、株価と不動産価格の低迷が長期化した場合、企業の負担が増大し、外国資本の流出が加速させ、対外バランス収支赤字がさらに拡大する。実体経済ヘの悪影響を考えると香港ドルの売り圧力がこれまで以上に高まる可能性がある。

