RIM 環太平洋ビジネス情報 1998年1月号No.40
ベトナムの自動車産業発展への課題
1998年01月01日 さくら総合研究所 高安健一
はじめに
ベトナム政府が対外開放政策を推進し、外国からの直接投資を受け入れるようになってからかなりの歳月が経過した。しかし、自動車産業に関する限り、外国の完成車メーカーの進出が相次いだものの、順調に発展しているとは言い難い状況にある。
ベトナムでは、1996年9月に、自動車産業に関連する省庁の代表で構成される自動車産業育成タスクフォースが形成され、諸外国の自動車産業を調査するとともに、自動車国産化(国産化率)計画の叩き台を数回にわたり作成してきた。早ければ98年初めにも、ベトナム政府から自動車産業育成政策が発表される予定になっている。
本稿では、自動車産業をめぐる内外の動向を整理した上で、ベトナムの自動車産業育成政策の在り方について述べる。
I.内外の経済環境の変化
1.貿易・投資の自由化
ベトナムは貿易・投資自由化への対応を迫られている。まず、2006年にアセアン自由貿易地域(AFTA)の共通効果特恵関税制度(CEPT)に参加する予定になっており、関税率の大幅な引き下げが実施されることになる。ベトナムは90年代に入ってから自動車産業の育成に着手したが、スタート時期が他のアセアン諸国よりもおよそ30年遅れているにもかかわらず、関税面では同じ競争条件の下に置かれることになる。すなわちベトナムは、自由化時代が到来するまでのわずかな間に、競争力のある自動車産業を育成しなければならないという難しい局面にある。さらに、他のアセアン諸国の通貨が97年7月以降、米ドルなどの主要国通貨に対して大幅に下落していることから、ベトナム製品の価格競争力は相対的に低下している。
また、ベトナムは現時点では世界貿易機関(WTO)に加盟していないが、今後加盟を目指すのであれば、差別的な自動車産業育成政策[貿易関連投資措置(TRIM)の適用除外]を実施することは困難になり、他のアセアン諸国がこれまで実施してきた国民車構想や国産化規制などの措置を選択できなくなる可能性が高い。すなわち、ベトナムは、かつて他のアセアン諸国が実施した、自由化を求める外圧を抑えつつ国内に進出している外国企業に対して国産化規制などを課すという戦略を踏襲できなくなる可能性が高い。
2.世界の自動車産業の潮流変化
世界の自動車産業の潮流変化は、ベトナムの自動車産業政策にも大きな影響を及ぼそう。第一に、主要完成車メーカーや大手部品メーカーは、グローバル規模での国際分業を一段と推進しており、その中に入れるか否かが当該国の自動車産業の発展の方向性を大きく左右する時代が到来している。さしあたりベトナムにとっては、外国の完成車メーカーのアセアン域内分業の一角に入れるか否かが大きな意味を持つ。第二に、環境問題や安全性への関心が高まる中で、企業の投資負担が急増しており、生産台数が極めて多くないと投資資金が回収できない状態にある。第三に、自動車の製造方法の変化や技術革新が急速に進んでおり、発展途上国が先進諸国にキャッチアップすることが難しくなっている。
3.国内経済環境
国内経済環境も、ベトナムの自動車産業を展望するに際して重要な要素である。7,000万人の人口を擁するベトナムの所得水準が向上するにつれて、自動車需要が急速に拡大するとの見方がある。そして、自動車市場の拡大と歩調を合わせ、生産面においても量産効果が発揮されるようになり、自動車の製造コストが低下するとの期待がある。しかし、96年以降、実質経済成長率は前年実績を下回る状態が続いており、98年についても97年の8.4%(見込み)を下回る 8.1%程度にとどまる見通しである。
さらに、自動車産業発展の鍵を握る外貨獲得能力にも疑問符が付く。自動車市場が拡大すると、完成車や自動車部品の輸入が増加し、自動車部門の貿易赤字が拡大する。現状、自動車部門の輸出能力は極めて低く、その貿易赤字を他の輸出品目で埋め合わせる必要がある。ベトナムでは、農産品(コメ)や軽工業品などの外貨獲得能力に陰りがみえ始めていることに加えて、油田開発が期待通りの成果を上げておらず、貿易収支の大幅好転が難しい状況にある。貿易赤字は、97年の35億米ドルから98年には40億ドルへと拡大する見込みである。加えて、ベトナムの外貨繰りと成長を支えてきた外国直接投資の流入ペースが大きくスローダウンしていることも不安材料である。
II.自動車産業の現状
1.狭隘な自動車市場
ベトナムの自動車市場は、表1にあるように、他のアセアン諸国と比較しても極めて小さい。しかも、市場拡大ペースは90年代初めに想定されていたよりも緩慢である。例えば、ある外国のシンクタンクは92年に、(1)自動車保有台数は2000年に40万8,000台に達する、(2)自動車販売台数は95年に4万台、2000年に8万台に達するとの予測を取りまとめた。しかし、市場規模(現地生産車、輸入完成車、輸入中古車の合計)は96年においても約2万台に過ぎない。そのうち、ベトナムで生産された自動車は5,523台(乗用車4,168台、商用車1,355台)であった。97年については、国内で生産された自動車の販売台数は1~8月に3,554台に達し、通年では前年並みの5,500~6,000台程度に落ち着いた模様である。
表1 アセアン主要国の自動車市場・生産規模
(単位:1,000台)
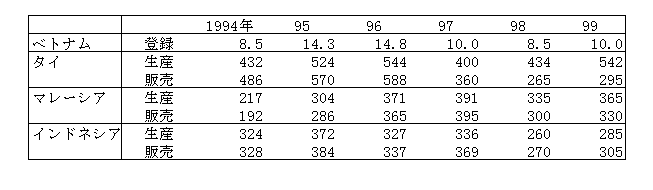
(注) 97~99年は予測値
(資料) EIU『Motor Business Asia-Pacific』4th Quarter, 1997
他のアセアン諸国の経験によると、一人当たりGDPが1,500~2,000米ドルを超えてから自動車の普及率が急速に高まった。ベトナムの一人当たりGDPは350米ドル程度(97年推定)であり、本格的なモータリゼーションの到来は当面望めない状況にある。自動車購買層をみると、政府機関や外国企業などの法人が大勢を占めており、高額商品である乗用車を一般消費者が購入する段階には達していない。
加えて、ベトナムの自動車市場の特色として、販売されている車種が30種程度(現地生産車)と極めて多いことが指摘できる。完成車メーカーは販売車種を増やすことにより市場シェアを高めようとしているが、このことにより、ただでさえ少ない1車種当たりの生産台数がさらに減少するというジレンマに陥っている。
また、市場拡大のためには、金融面からの支援が必要だとの指摘がある。割賦販売システムの普及や、関連の金融、保険、抵当に関する制度の早急な整備が望まれる。加えて、自動車の登録手続きや、そのために必要な提出書類の簡素化や統一化も市場拡大のためには欠かせない。道路整備や駐車場設置などインフラの整備を引き続き進める必要があることはいうまでもない。
2.過剰な供給能力
ベトナムの自動車産業の問題点として、過剰供給能力が指摘されている。93年に重工業省から発表されたマスタープランには、自動車製造ライセンスを商用車については3社、乗用車については2社に限定することが盛り込まれていた。しかし、実際には合計14社に対して製造ライセンスが供与された。
ベトナム政府筋によると、製造ライセンスを持つ完成車メーカーの生産計画(能力)を合計すると13万7,000台に達するという。政府は、2005年時点の需要を全生産能力の77%に相当する年産10万5,000台程度と想定しているので、供給能力は過剰ではないとの認識を持っているようである。政府は、 14社がすべて操業しても生産過剰には陥らず、むしろ、世界を代表する完成車メーカーが競争を繰り広げることにより、競争力のある自動車が生産されるとのスタンスをとっている。加えて、ベトナムでは古い自動車が多数使用されているので、買い替え需要は大きいとの見方をしている。
ベトナムに生産拠点を持つ完成車メーカーにとって、供給過剰は極めて深刻な問題である。設備稼動率は極めて低く、年産1万台の生産能力を持つ工場でも生産台数は500台程度に過ぎないケースもある。しかも、工場を建設して間もないことから、償却負担は重い。
ベトナムの自動車産業は現在、小さい市場規模→完成車メーカーによる量産効果の発揮困難→高い製造コスト→市場規模の拡大抑制という悪循環の中にある。この悪循環を断ち切らないと、完成車メーカーが投資意欲を失い、技術移転、人材育成、現地企業の育成などへの取り組みが後退する恐れがある。そうした悪循環を緩和するためには、少なくとも国内で生産されているのと同車種の自動車の輸入を禁止するなどの措置をとる必要がある。
III.自動車産業育成政策について
以下では、これまで述べてきたベトナムの自動車産業が置かれている状況を踏まえた上で、国民車構想と国産化率規制、部品メーカーの誘致と育成、ベトナム政府と外国企業との協調関係の重要性について述べる。
1.自動車産業の現在位置
図1は、発展途上国の自動車産業の発展過程と現在位置を示したものである。発展途上国は一般的に、第1段階:輸入ライセンスに基づく限定的な完成車(Completely Build Up; CBU)の輸入→第2段階:セミノックダウン(SKD)→第3段階:コンプリートノックダウン(CKD)の過程を経て、自動車の組み立てにかかわる技術を蓄積した後で、第4段階である国内での部品調達を本格化させる段階に入っている。ベトナムはちょうど第4段階に差し掛かったところである。他の発展途上国の過去のケースでは、この段階でどのような政策を選択をするかにより、その後の自動車産業の発展の方向性が大きく変わった。
2.国民車構想と国産化率規制
(1) 国民車構想
ベトナム政府は2020年に工業国に仲間入りすることを目標に掲げているが、その工業化マスタープランには自動車産業の育成も含まれているという。そして、ベトナムの自動車政策担当者の中では、ベトナムが国民車の生産を目指すべきか否かが議論されている。仮にベトナム政府が、研究・開発から始まり、部品の製造と自動車の組み立てをすべて自国で行い、自国ブランドの自動車を輸出商品化するという意味での国民車を想定しているのであれば、賛成できない。確かに、特定の完成車メーカーに対して便宜を供与することにより、国民車計画を推進すれば、1車種・1社当たりの生産台数が増加し、量産効果が確保できよう。しかし、国際経済環境の変化、現在のベトナムの自動車産業の水準、国内市場規模、多数の完成車メーカーの存在などを勘案すると、そうした意味での国民車構想は妥当性を欠く選択である。
ベトナム政府筋によると、92年に自動車産業育成マスタープランを外部機関に依頼して作成した際に、ベトナムもマレーシアのような国民車の製造を目指すべきとのアドバイスがあったとのことである。しかし、83年に国民車構想に取り組み始めたマレーシアと現在のベトナムでは条件が大きく異なる。マレーシアの国民車構想が一定の成果を収めた背景には、(1)外国からの技術導入が円滑に進んだ、(2)順調な経済成長を背景に国内需要が急速に伸びた、(3)国民車構想が国際ルールに抵触していなかった、などの好条件が揃っていたことを認識すべきである。
ベトナムが内外の経済環境が厳しい中で自動車産業を育成する合理性をどこかに求めようとするならば、それは、自国ブランドの自動車を保有することではなく、(1)雇用創出効果、(2)部品・素材産業の発展、(3)人材育成効果、(4)貿易収支の改善などであるべきである。
(2) 国産化率規制
ベトナム政府が熟慮すべきは、上記のような意味での国民車構想ではなく、いかにして短期間のうちに現地調達率を高めるのかということである。現地調達率の高い自動車の生産という点では、ベトナム政府と外国企業の利害は一致する。ベトナム政府が検討している国産化率規制はWTOとの関係で議論があるところだが、仮に導入するにせよ、次の点に十分に留意すべきであろう。
まず、ベトナム政府は、国産化率を高めるにはかなりの時間を要すること、国産化が容易な部品と難しい部品があること、国産化率の向上にも量産効果の発揮が重要なことなどを認識すべきである(例えば、タイの商用車のケースでは、国全体の生産台数が年間30万台を超えてから、国産化率が大きく高まった)。加えて、国産化については、エンジン、ボディー、高機能部品などの性急な国産化を目指すと、割高な自動車が生産される恐れが高い。投資額が大きく、モデルチェンジの頻度の高い部品の国産化も避けるべきである。また、ベトナムとしては、日本の完成車メーカーのアセアン域内での部品の相互補完ネットワークの中に入ることも重要であろう。
次に、どの部品をどのような設備・技術を用いて国産化するのかという点については、政府が特定の部品を指定するのではなく、基本的に完成車メーカーの裁量に任せるべきである。特に、日本の完成車メーカーは欧米や韓国のメーカーよりも、アセアンで現地調達率を高めてきた経験を持っている。
仮にベトナム政府が国産化率規制を導入するにしても、国産化目標の期限前達成、新技術の導入、輸出拡大に貢献した場合などには、国産化率に加算したり税制上の恩典等を供与することが望ましい。また、ベトナムでは、車種別に国産化率を設定するべきではない。1車種当たりの生産台数が極めて少ないことから、工場ごと、あるいは企業ごとに国産化率を設定しないと、企業は対応できない。
国産化率の算出方法については、部品ごとに価格を評価して集計するギブン・パーセント方式ではなく、卸売価格と輸入価格との差に着目した付加価値方式を導入すべきである。付加価値方式はCEPTで採用されている国際的に認知された方式であり、財務諸表から算出できるので、事務処理が容易である。ギブン・パーセント方式では、すべての部品について価格を評価して集計することになるので、事務作業は大きく膨らむ。しかも、部品の原価がメーカーごとに異なったり、同一企業が輸入する場合でも、時期によって価格が違うなどの問題がある。国産化率の計算は、付加価値方式をベースにして、輸出額および内製部品等の要素を加味して調整するのが望ましい。加えて、付加価値方式は、塗装設備などに多額の設備投資を行った場合や副資材を現地調達した場合も国産化の計算に含まれるので、企業の投資意欲を高めることになろう。
(3) 部品の選定
ベトナム政府が部品の国産化を検討する際に、過去のアセアン諸国の経験が参考になる。図2には、アセアンに拠点を持つ日系企業に対して行ったアンケート調査の結果が掲載されており、域内調達比率が高い順に並んでいる。この中で、アセアンでの域内調達(進出先の国での調達および他のアセアン諸国からの調達)に支障がない部品(域内調達を行っていると回答した企業の比率が80%以上の部品)は、バッテリーからトランスミッション・オイルまでの16品目である。このうち、他のアセアン諸国から調達された実績があるのはラジエーターのみであり、その他の部品はすべて国内で調達されている。こうした部品は国産化に適しているといえよう。
続いて、17番目のホーンから31番目のランプまでが、現在、域内調達をしている企業の比率が50%以上80%未満のものである。これらの部品のうち、ボディーパネル、バンパー、ショックアブソーバー、ホーン、ランプ、シートベルト、防音材、インテーク・アンド・エキゾースト・マニホールドは、域内調達されている実績がある。こうした部品は、域内相互供給ネットワークにのせやすい部品といえよう。
ミラー以下エンジンコンピュータまでの部品は、域内調達をしていると回答した企業の比率が50%未満であり、現地調達があまり進んでいない。ベトナムは当面、このカテゴリーに属する部品を国産化するのを避けた方が無難であろう。
続いて、図3は、アセアンにおける素形材・原材料調達の状況を示している。現状、域内調達をしていると答えた企業の比率が50%を超えているのは塗料のみである。冷間鍛造、鉄鋼(鍛造用)、鉄鋼(ボディー用)は、極めて低い水準にある。
3.部品メーカーの誘致と育成
現地調達率の向上は、完成車メーカーの力だけで達成できるものでは決してない。完成車メーカーが部品の内製化を進めたとしても自ずと限界があり、部品メーカー、部品のコンポーネントを製造しているメーカー、素材メーカーなどが揃わないと、国産化率は大きく高まらない。国産化率を高めるために無理に部品を内製化したとしても、日本よりも割高な部品が生産されるだけである。
現状、ベトナム国内で調達できる部品は、搭載用工具、ワイヤーハーネス、シート、バッテリー(一部の完成車メーカーが調達)程度である。今後、タイヤ、ガラス、フロアマット、泥除けマットなどが調達されるようになろうが、その他の部品については調達が難しい状態が続く見通しである。
部品産業を育成するためには、いうまでもなく外国の部品メーカーの誘致と地場の部品メーカーの育成が必要である。まず、外国の部品メーカーを誘致するためには、外資の出資規制の弾力的な運用、大幅な法人税の減免、部品を生産するための原材料の関税引き下げ、生産コスト(土地のリース代、エネルギー・コスト、インフラ整備)の削減を含む、思い切った政策が必要である。また、部品メーカーにとっては、顧客である完成車メーカーの工場がハノイ市周辺とホーチミン市周辺とに分散していることも進出のネックとなっている。南北を結ぶ道路や通信などのインフラがこれまで以上に整備され、流通網が充実することが期待される。
また、地場の部品メーカーを育成するためにも、量産効果の確保が重要になっている。ある自動車関係者によると、現状、地場の機械部品メーカーは、一つの工場で多くの部品、多くの工程を手掛けていることから、量産効果が働かないとのことである。こうした事態を打開するために、同じ工程の生産設備を多くの企業が持つのではなく、機械加工、溶接、メッキ等のそれぞれの工程に特化した形で部品メーカーを再編・集約することも一案であろう。また、品質管理を担う機関を設立することも、品質向上や各社の設備投資の重複を避ける意味から望ましい。
次に、関税政策も現地調達率に大きな影響を及ぼす。まず、完成車の市場規模を確保するためには、国内で生産されているのと同車種の自動車に対する関税率を高めに設定する必要がある。特に、国内で生産されている部品については、関税を高く設定することに加えて、部品メーカーが使用するコンポーネントの輸入関税を低く設定すべきである。
部品の製造に必要な中古の機械設備の輸入規制は、緩和すべきである。最新の機械設備の輸入しか認められない場合、外国企業は固定費が高くなるので投資・輸入を見送ることになろう。企業は採算性や品質を総合的に考えてどの機械設備を輸入するのかを決めるのであり、最新の機械設備を輸入するのか、それとも中古の機械設備を輸入するのかは、貿易バランスを極端に損ねない限りにおいては、企業の判断に委ねるべきであろう。
4.外国企業との協調関係の構築
本稿では、産業育成政策の目的は、政府による保護やインセンティブ供与がなくとも、国際競争力を維持できるレベルにまで当該産業の競争力を高めることと定義する。換言するならば、短期的に競争制限的な措置を実施するにせよ、長期的には規制緩和を実施し、市場メカニズムが働く条件を整えることが政府の役割であると考える。ベトナムの場合も、競争制限的な政策を当面継続するにしても、早晩自由化の洗礼を受けることを十分に考慮すべきである。
産業育成政策の初期段階で問題となるのは、当該産業を立ち上げるのに必要なセットアップコストを、誰(政府、企業、消費者)がどのように分担するのかということである。アセアンの自動車産業の歩みを振り返ると、政府は国内市場を外国メーカーに提供することと引き換えに、外国企業の経営資源を活用してきたといえよう。また、技術移転や人材育成等の分野においても、外国企業への依存度が高い。マレーシアのプロトン社にしても、外国企業の支援なしには今日のような発展は実現しなかったであろう。
ベトナムは、自動車産業に投入できる資源に制約があることを考えると、少なくとも自動車産業の創成期においては、外資企業の経営資源を積極的に活用すべきである。ベトナム政府が外国企業の資源を活用するには、まず、両者の間に存在する認識ギャップを埋める必要がある。ベトナム政府は、外国企業が利益を確保することが自由競争社会では当然の行為であることを理解すべきである。そして、問われるべきは、企業が獲得した利益をベトナムに再投資する環境が整っているのかという点である。ベトナム政府がどのような自動車産業育成政策を打ち出すにせよ、それが長期的な展望に基づいた事業計画を立てるにふさわしい内容でなければ、企業は継続的な投資を躊躇しよう。また、再投資を促すには、市場拡大努力や裾野産業をはじめとする生産基盤の整備もさることながら、行政組織や各種制度の整備も重要である。法制度が原則通りに適用されるとともに、突然に変更されることがあってはならないことはいうまでもない。
先進国市場では、一般的に、競争が激しくなるほど、企業が創意工夫を発揮し、消費者が利益を得ることができるといえよう。ベトナムでは、世界を代表する完成車メーカー14社が製造ライセンスを保有しているという意味において、競争は激しい。ところが、ベトナムでは、市場・生産規模が小さく、企業が創意工夫を発揮できる余地は極めて限られている。
また、自動車産業育成政策を策定するということは、企業競争のルールを策定することでもある。ルール策定に際して、すべての利害関係者の主張をもれなく取り入れることは不可能である。しかし、公平で内容がわかりやすいルールを作成し、その運用に際して透明性を確保することが大切である点を十分に意識する必要があろう。そして、外国企業と政府が信頼関係を高めるには、どれだけ多くの情報を共有できるのかが鍵を握ることから、定期的な意見交換の場が設営されることが望まれる。
ベトナムの自動車産業にとって最も懸念されるシナリオは、企業業績の低迷が長期化する中で、投資活動が停滞し、他のアセアン諸国との格差が拡大することである。消耗戦が続くうちに、資本力に優れた企業とニッチ市場に特化した企業とに二極分化していく中で、技術革新や消費者ニーズの充足を伴った競争が展開されないことも起こり得よう。自動車産業を取り巻く国内外の経済環境は厳しく、ベトナム政府と外国メーカーが意見調整に時間をかけている余裕はない。
おわりに
以上が、ベトナムの自動車産業が直面している諸問題の整理と、ベトナム政府が自動車産業育成政策を立案・実施するに際しての留意点である。
黎明期にあるベトナムの自動車産業は、他のアセアン諸国と同様に大きな選択を迫られている。すなわち、多国籍企業の国際分業ネットワークのある部分(特定の産業や部品)の一角を担うのか、それともベトナム・ブランドの自動車を持つことを目指すのかという選択である。この問いに対する答は、どちらの方法が長期的な視点からベトナムの産業全体の発展のために有益かという視点から慎重に検討されるべきであろう。
これまで述べてきたことの繰り返しになるが、ベトナム政府が自動車産業育成政策を立案・実施するに際しては、(1)ベトナム政府は外国企業との関係を良好に保ち、その経営資源を最大限に活用すること、(2)外国の部品メーカーの誘致と地場の部品メーカーの育成のために、あらゆる政策手段を動員すること、(3)割高な自動車の生産を助長する恐れがある国民車構想を推進するのではなく、現地調達率の高い自動車の生産を政策目標として掲げること、という3点に、特に留意すべきであろう。

