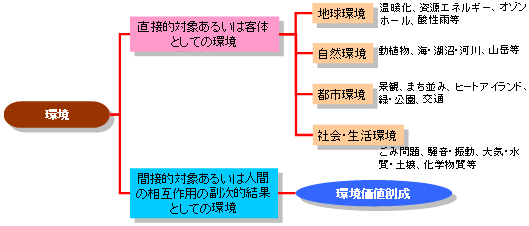コラム「研究員のココロ」
環境ビジネスのフロンティア<第1回>
~環境価値創成ビジネスの新展開~
2007年10月15日 吉田 賢一
1. 地球温暖化がもたらす環境ビジネスのチャンス
今年は連日猛暑が続き、内陸部では40℃を超す異常な夏となった。都市部ではいわゆるヒートアイランド現象による気温の上昇が問題となっており、都市を冷やす緑化などの環境ビジネスが話題となっている。こうしたことは、ハイリゲンダムサミットでも議題となった地球温暖化対策とそのための二酸化炭素削減への取組が背景となっている。温暖化については、IPCC第四次報告書でもより一層厳しい展望が示されており、その証左として北極の海が氷解し海面上昇と生態系への影響があげられる。
環境をモチーフとするビジネスという観点で見た場合、かつて企業にとって、環境はその活動を増加させればその分だけ負荷を与えるものであり、その証拠として、環境問題の発生形態は「多量、集中、短期、単独、確実」であった。4大公害病問題では、重厚長大型の産業構造そのものが問われたといっても過言ではなかったのである。
ところが、今日の環境問題は、「少量、広域、長期、複合、不確実」となり、複雑化、構造化、そしてグローバル化している。それは企業活動の影響範囲が社会的にも経済的にも拡大したことに起因していることが特徴的となっている。地球温暖化はまさにそうした複雑化、構造化そしてグローバル化した環境問題の最たるものとして、あらゆる産業部門に影響する課題となっている。
しかしながら、温暖化は環境ビジネスにとって極めて重要なモチーフであるものの、唯一のモチーフというわけではなく、環境に関わる様々なシーズがビジネスの可能性を秘めていることを本論では述べてみたい。
同時に、これまで企業にとっての利害関係者(ステークホルダー)といえば、資本を構成する株主であり、また、顧客や取引先であった。しかしながら、環境というキーワードで企業のパフォーマンスを見た場合、一気にその対象が拡大し明確な絞込みは極めて困難となってきている。これからの企業は、その活動が環境に負荷を与えることを前提に、環境負荷を軽減あるいは防止するために、いかなる取組みや経営政策を展開していくのか、そしてそれが環境投資家や環境消費者(グリーンコンシューマー)、周辺地域・社会といった新たなステークホルダーによってどのように評価されるかが問われており、企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility; CSR)に示さるような極めて複合的なリレーションシップの構築が必要となっている。
2.改めて問う環境ビジネスの定義
環境ビジネスとはいかなるものか。その定義については様々な形があり、一意的に決めることは困難である。環境省は、「環境ビジネス研究会報告書~環境と経済の統合に向けて~平成14年8月」において、「産業活動を通じて、環境保全に資する製品やサービス(エコプロダクツ)を提供したり、社会経済活動を環境配慮型のものに変えていく上で役に立つ技術やシステム等を提供しようというのが環境ビジネス」であると定義している。また、環境ビジネスは、「環境保全への取組の積極性や事業内容から見て日本の経済社会構造をグリーン化する大きな推進力となると同時に、環境に優しい製品やサービスの活用を通して、人々のライフスタイルそのものをより環境負荷の少ない持続可能なものへと変えていく可能性を開くもの」とも指摘している。
ここでは、私たち国民一人ひとりの生活様式を環境適負荷低減型のものに変えていくフィロソフィーが基底にあることが分かる。筆者が考える「新しい環境ビジネス」のモデルはそうした方向性の延長線上にあるものいえる。
3.環境ビジネスの実相
私ども日本総合研究所では、経済産業省が実施した平成18年度環境経営・ビジネス促進調査「環境ビジネス・配慮経営の動向に係る調査事業」を受託し、2015年の環境ビジネスの市場動向について調査を行った。(注1)
そこでは、環境ビジネスには様々な分野が存在するため、分野によって市場規模や、成長率が大きく異なることとなり、また、複数の分野にまたがることや学際的な領域もあるなどの理由から、参入企業の業種・業態も多種多様となっており、様々な課題等が浮き彫りとなってきているとの問題意識が提示されている。このことを踏まえ、現状の環境ビジネスに関する助成施策を整理することで、近年の環境ビジネスのおおよその変化を把握することとした。これらの環境産業におけるハード系およびソフト系の補助事業の整備状況をまとめた結果、エネルギー関連(新エネルギーや省エネルギー)、環境分析装置、環境技術等といった分野に対する事業が比較的多くある。その一方でこれまで対象とされることが少なかった排出権(量)取引、環境調和型製品(エコプロダクツ)や環境教育等に関するビジネスについてもレンジを広げて調査を行っている。
そこでわが国における環境ビジネスに関する試算を行った結果、現在(基本的に2005年度ベース)の約57兆円から、2015年度約76兆円に達し、雇用規模は、現在の約180万人から2015年度には約260万人に拡大しており、増減率では、現在に対して市場規模が+33.3%、雇用規模は+44.6%となるとの試算結果を得た。これを分野別に市場規模をみると、2倍以上拡大した分野は、「再生可能エネルギー・省エネルギー(2.9倍)」、「環境調和型製品(2.8倍)」、「環境教育・人材(3.2倍)」、「環境投資・排出権取引(6.3倍)」となっている。その他、「環境修復・環境創造(2.0倍)」、「環境調和型エネルギー供給(2.0倍)」も拡大している。従来型の環境ビジネスでは「廃棄物処理・リサイクル装置(プラントはほぼ横ばい)」、「下水・し尿処理(1.1倍)」などは、公共事業の削減等を背景にほぼ横ばいとなっている。
4.「環境」の定義の変化~環境の「価値」化現象
ところで、一般的に環境とは、「環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう」(環境基本法第2条3項)。
しかしながら、今日の環境対応の意味が公害問題への事後対応・救済から、地球規模の環境問題へのリスク対応・予防的取組へと変化していることを踏まえるならば、環境に新たな価値を見出しそれを媒介として実態経済を伴う多元的な市場取引をもって経済活動を活発化させる新たなビジネスの可能性が生まれていることに留意が必要となる。すなわち、環境の「価値化」とは、新たな経済的市場的価値を生み出す行為や様々なアクター(ステークホルダー)が関わることによる価値の創造行為(リサイクル活動、戦略的環境アセスメント、SRIなど)の結果である。そしてそこでいう環境とは、「間接的対象あるいは人間の相互作用の副次的結果」でもあり、この文脈で展開されるビジネスこそ、筆者がいう「環境価値創成型ビジネス」である。保全のみでなく保全するために用いる技術や製品開発、そして保全することで得られる利得(必ずしも経済的なそれではなく、安全・安心といった非貨幣的な価値性も含む)という観点から、いわば環境を価値化しそれを市場で交換することにより新たな経済的活力が生まれる可能性が生まれるのである。
同時に後述するようにこの環境ビジネスの新形態が重要な意味を持つのは、「地域」をキーワードとして、持続可能な循環型経済の理念にもっとも近い事業展開として具現化する可能性をも包含しているところにある。
一方でこの環境の価値化現象にはマイナスの側面もあり、それが知的財産保護とリサイクルが争われている事案や、ごみ袋有料化の独占禁止法抵触問題などに見られる、これまで市場経済の整序化を図ってきた各種の経済法との相克する可能性が見られることである。