コラム「研究員のココロ」
リスクマネジメント時代の大学経営<下>
2005年12月19日 吉田 賢一
4.リスクマネジメントの方向性
そこで、上述したリスクについて、具体的なマネジメントの方向性を提示してみたい。
(1)「マーケティング、学生募集」
ここでは、育成すべき人材像を明確にし、どのような質を持った学生をどこから呼び込み、そしてどう教育し社会に送り出すか、といった「エンロールメントマネジメント」の展開に即した募集戦略を策定することが重要となる。すなわち、マーケティングの基本が求められるのである。
それは場当たり的な学生募集を行うのでなく、卒業後もあらゆるチャネルでのつながりをネットワーク化することで、受験生の確保や寄付金の蒐集に帰結する好循環を創り出すことがポイントとなる。
同時に、当面の学生募集の強化がスタートともなることから、過去にどこに強みと弱みがあり、何を生かすべきかといった学生募集実績の分析を行い、新聞・雑誌・電車広告・インターネット・パンフレット等費用対効果を検討し広告媒体のデザインについても見直しが必要となろう。加えて、効果的なオープンキャンパスや模擬講義の出前による高校訪問作戦といった戦略的なコミュニケーション手法の整備も考慮しなくてはならない。
(2)「組織・人的資源マネジメント」
ここでは2つの側面からの対応が必要となる。すなわち、環境に適応した組織デザインと適切な人材活用のシステム化である。
前者については、外的な経営環境の変動を先取りしつつ柔軟に対応し、新規事業を展開できる体制になっているかが重要となる。また、後者については、組織活性化のための外部人材採用・能力開発プログラム、登用制度の改善、職員人件費抑制のための人事制度改革・退職金制度改定等を検討することが求められよう。
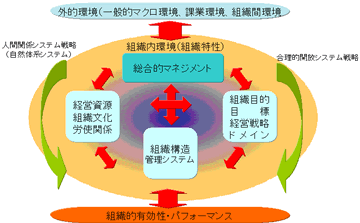
その際に避けて通れない課題が、事務組織と大学職員のあり方である。
ここではやや微細に及ぶが、筆者の分析をご紹介したい。
我が国の大学組織は、一般的に戦前はドイツ等の大陸型、戦後はアングロサクソン、とりわけアメリカ型にその範を取ったといわれている。しかしながら、それは主に建学者であると同時に、教育者・研究者でもあった大学創設者達を中心とした教員組織の系譜についていえることで、事務組織の淵源については、創設者達の雑用を中心とした「お手伝い」から派生した書生や秘書のような機能が想定される以外は、その具体的発展形態については不明な部分が多い。
一方で、戦後の教育制度の民主化の流れにして即して誕生した学校法人制度は、大学という特殊な組織体にあたかも企業経営のセンスを採り入れたかのように法人形態を取り、理事会の意思決定のもと大学を寄附行為において設置するシステムとなり、その後、それらの事務部門を支える職員組織の輪郭が徐々に浮き彫りとなってくることとなる。
その大学組織には、次の2つの特徴があるといえよう。
まず第一に、学校法人による私立大学と国立大学(ここでは特に断らない限り国立大学法人以前の組織形態を指す)及び公立大学は、前者が公益法人、後者が国家公務員と地方公務員制度に根ざした、いわゆる公的部門に属する組織体である。その特徴は、組織目的が公平性・公益性に重点が置かれていることから、収益性や営利性を第一義とする企業等私的部門の組織体とは本質的に異なっている。それに伴い、組織の制度設計も「神聖な事業としての教育を施す」、あるいは「学問の府の本義としての学問を究める」、といった観点から手続きの正当性や正確性に配慮された合理的かつ機械的で安定的な官僚型の組織が形成されてきたのであった。
第二の特徴は、プロフェッショナルとしての教員集団(教学組織)と官僚的な事務組織といった二重構造を有しているということである。すなわち、病院の医師や軍隊における制服組のように専門的な技能と知識を有した教員という集団の機能性を引き出し、その力を最大限まで発揮させることを目的としたロジスティック機能を担う事務部門として、医師に対する病院事務、制服組に対する軍属等が形成されてきたのと同様に、大学にとってはまさに職員組織が形づくられてきたのである。
しかしながら、ロジスティックを担う組織と一概に括っても、病院事務はレセプトを始め特有の病院会計システムに熟知した管理技能が必須となり、また、戦前の軍属においても文官等で一定のランク以上は所定の試験制度のクリアが必要となり、ある種一定水準の能力は確保されてきたとみることができよう。
しかし、大学組織については、私立大学、さらにその中でも戦前の大学令による大規模な大学(以下、伝統型大学)と戦後設立されたオーナー系の大学(以下、新設大学)では、その組織文化はまったくといってよいほどに異なっており、また、国立大学や公立大学についても公務員制度に根ざしていることから、組織文化について、安易に私立大学と同一視はできない。
早稲田大学、慶應義塾大学等の戦前の大学令によって生まれた大規模な伝統型大学は、当初は優れた経営者であると同時に優れた教育者・研究者でもあった創設者達を中心に組織形成、つまり学部学科の分離独立が図られ、これに伴い、教員の身の回りの世話から、大規模経営体化した大学の事務を司る官僚としての事務部門が発展したと考えられる。
これに対し、戦後の大学法人制度の下で生まれた新設大学には、いわゆるオーナーとしての理事長が圧倒的な支配力を有し、学長を筆頭とした教員組織を統制しているケースが数多く存在する。例えば、ある専門学校が設立した大学は、専門学校のオーナーが理事長に、親類縁者が理事にそれぞれ就任し、その下で専門学校の事務スタッフが大学経営の実態を掌握する、といった組織管理となっており、教員の雇用はオーナーの一存でいかようにもなることが多い。
いずれにしても、私立大学の場合は、学校法人と個人との契約関係によって事務職員が生まれることとなり、その実は横並びの側面が強いものの、建前は民間企業のごとく各大学によって個々に異なってくることとなる。
したがって、学歴や能力よりも縁故による採用が圧倒的に多く、研修制度の不備や事務組織内の昇進等にも明確な規程やルールが存在しないことから、情実によるケースが少なからず存在することが想定される。これが何を意味するかといえば、外面的な形としての組織はあっても、環境変動にあたかも生命体のごとく状況適合的に変化しうる「生きた」組織とはなっていないのである(注1)。
これに対し、国立大学と公立大学は公務員制度に根ざしており、前者は文部科学省に採用された国家公務員、後者は各都道府県ないしは市により採用された地方公務員となる。
そのうち国立大学についてみてみると、法人化前の事務組織は、教員集団という水平的な組織体が強い主導権を持つ大学業界の中でも、階統型の官僚組織で運営されてきた。すなわち文部省・文部科学省の附置機関・執行機関であり、各大学の事務組織は、人事・会計・庶務・学務等に関して、本省の事務組織が企画立案して決定する事項を、単に執行する役割を持つだけの「地方出先機関」として位置づけられてきたのである。本省の担当部局を頂点としたピラミッドを形成し、その底辺に大学現場の各担当事務組織を配置するシステムを取ってきたわけである。また、そのシステムを確実に機能させるため、本省が現場の管理職以上の職員(いわゆる国家Ⅱ種のローテーション組で、「移動官職」ともいう)についての人事権を掌握し、大学の事務局長にも、有力大学を中心に本省の国家Ⅰ種のキャリア組を充ててきた。これは文官のみでなく技官についても、ほぼ同様の運用システムであったといってよい。
したがって形式的には、個々の大学内での事務組織もその全体構造の相似形として、ミニ・ピラミッド型を構成しており、その実は、大学の運営ルールに関する重要事項については、独自の意思決定権限を持たない組織であったことの裏返しだといえよう。また、この構造はさらに個々の大学内において、学長直轄の大学本部(事務局)と各学部(部局)における事務組織の間の関係にも該当する。
しかしながら、デュー・プロセスを重んじる組織形態からすれば、この階統型組織は高度に訓練された能吏によって維持されており、その能力は公務員制度というオープンシステムによって任用されたという事実をもって、ある程度は担保されていると考えることができよう。
こうした官僚(公務員)の行動原理は、主として「前例主義」「横並び意識」「繁文縟礼」にある。行政運営にあたり、法令の覊束性を重視する公務員にとっては、その法令の適用と運用に当たって、裁量による恣意が入ってはならない。行政には継続性、安定性、予測可能性、そして何よりも正確性によるデュー・プロセスが重視されることとなる。「前例主義」「横並び意識」「繁文縟礼」は公務員にとっては、必須の行動原理であり、その実は、さまざまな実務にあたっていくための「能率的」な問題解決手法ともなっているのである。そのため、公務員は研修や職場(OJT)で、こうした行動原理を習得するよう、常にトレーニングを受けている。定型業務、ルーティン業務が主体であった時代には、こうした行動原理に体得した人材が最も優秀な「官吏」であったと評価されてきた。大学の事務組織の場合は、加えて、企画立案機能は持たず、本省が決めた方針を実行する執行機関だったという事情もあり、より一層、その傾向はより強かったといえよう。
しかし、法人化後においては、有能な「官吏」が「大学職員」としてその力量を有効に発揮できるとは限らない。事務職員にとっての取組むべきは非定型的な業務であり、そのためには、戦略的な視座からの企画立案能力を涵養し、他大学とは全く異なる新しいブランドの確立に資する働きが求められてくることとなるのである。
以上の分析を踏まえるならば、私立大学であれ国立大学であれ、様々な環境変動を予測しかつ機動的に適応していくタフな組織体制を構築していくためには、構造面では肥大化した部分をスリム化し、機能面においては、メカニカルな執行業務と企画立案業務とを区分し、システム化やアウトソーシング等と合わせた前者の省力化と、後者における高度専門化・組織運用の柔軟化が必須となる。
このように日常業務を例規に基づき正確に処理することを基本とした階統型組織を、外的な環境変動に柔軟に適応するサイバネティック型組織に変化させることがポイントとなる。
したがって、具体的には、学内の反発が予想される人的資源に対するリストラクチャリング等を目的とするのではなく、業務体系等をスリム化することで生まれる余力を、企画・政策立案業務や教員・学生支援等新しいソフト面でのサービス業務に振り向ける組織革新を目指すこととなる。だからこそ「業務再設計」あるいは「業務の構造改革」によって、仕事の仕組見直し、合わせて必要な人員とそのスキルを設定する戦略が必要となる。
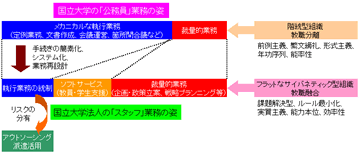
(3)「CSR・学外(産学官公地域)連携」
これは「マーケティング、学生募集」とも密接に関連しており、大学を取り巻く学生の父兄、地域社会や企業、行政等といったステークホルダーに対し、社会・経済・環境の側面から、適切な行動を果たしていることを伝え正確な社会への貢献度についての評価を受けるCSRの視点が重要となる。
これまでの大学の対外リレーションは、組織的な一体性が乏しく部局個別的で無機質的な情報発信のパターンが多かったといえよう。とりわけ財務データの開示は、各大学の判断であったため、無味乾燥で不透明なものが多い(注2)。
しかし、私立学校法の改正等の動きを踏まえれば、例えば、財務データによってその大学の経営体力を見極め、受験対象や寄付対象としての大学について評価を行う日もそう遠くはないといえよう。
そこで、「守り」から「攻め」の経営に資するよう単なる「周知」ではなく「知りたくなる」情報の提供に努めると同時に、企業のIR(インベスター・リレーションズ)と同様に、不利な情報ほど丁寧かつ説得的に説明できるノウハウと、そうした対応を可能とする外部とのコミュニケーションチャネルを円滑化しておくことが重要となる。いわば一方通行的なものではなく立体的、複合的な双方向のSR(ステークホルダー・リレーションズ)戦略が必要となるのである。
(4)「知財・著作権管理」と「コンプライアンス」
いずれも遵守すべき法制度の存在が前提となっており、まずはその法制度の解釈をきちんとなしうる能力とそれらを遵守するのみでなく活用しうるセンスも練磨する必要がある。
著 作権の適正管理では、教材作成に用いたコンテンツやデータを適切に管理できているか、著作権法等を遵守しているかがポイントとなり、また、知的財産の適正管理では、論文や実験データ等研究成果を適切に管理できているかが重要となる。
さらに、知財関係においては、そうした管理や戦略化業務を担うことができる人材の育成と組織体制の整備が急務となっている。
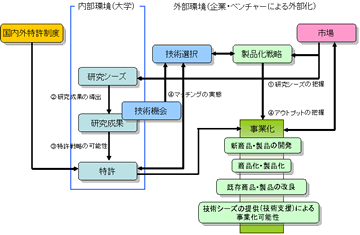
一方で「コンプライアンス」では、私立学校法や国立大学法人法、労働3法等の基本となる法令を遵守することは当然の前提として、例えば個人情報の保護では文書や電子データ等システムとの関係でコンテンツやデータを適切に管理できているかが重要となる。また、環境マネジメントの側面では、特定事業者に指定されている国立大学法人は環境配慮促進法等により、環境報告書の作成が義務づけられており、総じてハード、ソフト両面にわたって環境配慮がなされていか、キャンパスは環境対応型かといった観点からの整備計画の策定が必要となろう。
(5)「施設整備」
老朽化した施設のリフォーム、募集対策としてのキャンパスリニューアル、図書館リニューアル、学内IT化といった多様化への対応とともに、PFI等多様な手法を活用し、建設コストを抑え、経済効率的な事業整備をいかに立案していくかといった視点と、募金体制の整備、資産の有効活用、直接・間接融資等資金調達の手法をどのように活用していくかといった建設資金調達の視点からの計画策定が重要となる。
5.今後のあり方をめぐって
これまで述べてきた大学経営の「リスクマネジメント」は、あくまで一般論である。
大学の取り巻く経営環境を再度概観すると、東京大学大や京都大学、早稲田大学や慶應義塾大学といった一部の大規模総合大学を除いて、ある種の傾向が看取できる。
すなわち、2000年の地方分権一括法施行以来、依然として三位一体の改革は未完であるものの、分権化の潮流は確実な動きとなって、地方自治体に自立的な経営を促し、各地域において住民参加型の地域・まちづくりの萌芽が見られるようになっている。その中で大学が地域において果たす役割には、かつての研究拠点としての「象牙の塔」から「知のネットワークの集積」として、主要アクターとしての「受身」から「攻め」の活動が期待されているのである。
ここでは地域における大学のあり方を詳述することは避けるが、従来、行政は規制を中心に政策を展開してきたことに対し、財政の逼迫等により従来の規制のみの対応だけではなく、行政内部のコストや効率性を勘案しつつ、市場を構成する市民や企業が自発・自主的に地域の課題解決=マネジメントに取り組む「自主管理」化を目指した、新しい公共管理のあり方が問われてきていることを指摘することができる。人間社会の基本にある地域をベースに、市民/NPO、事業者、行政が共通の問題として設定し、それぞれが協働して複雑化した政策課題に、より適合的に対応していくという考え方が求められているのである。
その中で、まちづくりと人づくりといった枢要な役割を担う大学は、従来的な各大学別の縦割りによる経営ではなく、より積極的に「水平的」で「イッシュー・ネットワーク型連携」に基づいて、より地域の様々なアクターとともに地域価値そのものを向上させる役割が期待されているといえよう。そこでは大学の「社会性」を改めて位置づけ直すことで、より一層その機能の発揮を促進することが重要となるのである。
そのためには、従来の学内のリスクにのみ執着しその回避のための内向的なエネルギーの消費に執着するのではなく、より積極的に学外の諸アクターとのコミュケーションのためのチャネルを開き情報の流通を活発化させることで、地域の「知のクラスター」としての役割を果たすことが重要となる。それは大学の社会的責任(CSR)を達成することを意味するのであり、新しい大学のガバナンス実現に向け障害となる多様なリスクのヘッジが可能となるのである。
しかしながら、先に述べたとおり経営にとってのリスクには多様なものがあり、また、その構造も複合的である。単に発生した事象に対処するのみでなく、事前の防止に取り組むと同時に、不測の事態として発生した場合は極力その影響を最小限にとどめるべく組織力をもって臨むことが重要となるのである。
これまでの大学経営においては、トラブルや事件といった事象が発生した都度、対処をする組織体制となっているケースが多く見られたが、リスクマネジメントを適切に行うためには、統合的かつ客観的な取組が必須となるのであり、そのための組織設計や人材育成等が必要となることを改めて指摘しておきたい。
【脚注】
- (注1)
- なお、仏教等宗教法人の関連で設立された大学は、教義に基づく身分体系となっていることから一概に教員組織と事務組織の比較はできないことに留意する必要がある。また、無論、これらの組織形成の歴史過程においては、学園紛争等の影響を捨象することはできないが、個々の大学の置かれた状況によって程度が異なるため、ここでは論じないこととする。さらに、職員組合の存在も組織形成過程では無視できないが、ここでは省略する。
- (注2)
- 私立学校法の改正によって、平成17年4月より学校法人が公共性を有する法人としての説明責任を果たし、関係者の理解と協力をより得られるようにしていく観点から、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書等の関係者への閲覧が義務づけられている。

