市場を席巻していた製品や、その製品を構成する特徴的な技術などが、全く新しい技術によって駆逐されるという現象がある。「技術革新が巨大企業を滅ぼすとき」とは、クレイトン・クリステンセンの著書「イノベーションのジレンマ」の副題である。同著者は、様々な業界でこのような現象が観察できることを整理、分析した上で、この技術革新を「破壊的イノベーション」と定義し、その対応方法などについて述べている。
例えば「北米市場におけるホンダのオートバイ」は、この破壊的イノベーションの具体例である。1950年頃の北米では、ハーレー・ダビットソンやBMWなど、轟音を立ててハイウェイを爆走するようなイメージの大型バイクが主流であった。そのような環境の中、小型バイクで参入を試みたホンダは、既存の大型バイクメーカーからはほとんど脅威とみなされていなかった。しかしながら、徐々に「小型で安価であるにもかかわらず、故障しにくく、燃費もよく、取り扱いやすい」といったイメージが定着し始め、北米社会においてもこのような価値観が定着し始めた。結局ホンダの小型バイクはその後売上を順調に伸ばし、既存大型バイクメーカーを揺るがす地位にまで成長していった。現在では、この小型バイクでの成功を梃子に、大型バイクでもホンダの地位を確立しており、ホンダ以外にもスズキ、ヤマハ、カワサキがこれに加わっている。当時のハーレー・ダビットソンやBMWは、この新たな破壊的イノベーションに上手く対応することはできなかったのであろうか。
同様の興味深い現象が1980年代後半から1990年頃の「ハードディスクドライブ」業界に見られる。1985年頃のハードディスクドライブは1平方インチあたり約10Mbitという記憶容量であり、大きさは8インチタイプや5.25インチタイプのものが主流であった。さらに小型の3.5インチタイプのハードディスクドライブも1980年代前半から製品化はされていたものの、当時の市場は少々形状が大きくても、記憶容量の大きいものを求めており、各メーカーは、小型化というよりは記憶容量をいかに高めるかということに注力していたと考えられる。
しかしながら、1988年頃になると、記憶容量の劣る3.5インチタイプが、5インチタイプの生産量を上回るという現象が起きた。その約6年後には、記憶容量においても3.5インチタイプが5インチタイプを上回ることとなった。高機能(記憶容量の大きい)ハードディスクが、低機能(記憶容量の小さい)ハードディスクに駆逐されたことになる。このような状況下において、5インチタイプから3.5インチタイプへと、タイミングよく開発や生産を切り替えることができた企業が存在したかどうかは推測の域を出ないが、少なくとも5インチタイプを作り続けた企業は大きなダメージを受けたであろう。果たして、新たな技術の出現(この場合3.5インチタイプの出現)に、既存技術ベースの事業者(この場合5インチタイプを製造する事業者)は上手く対応することができるのであろうか。
ハードディスクドライブ業界の例では、「大記憶容量、5インチ」に見切りをつけ「小記憶容量、3.5インチ」に切り替える判断ができたか否かがその後の事業存続に大きな影響を及ぼしたといえよう。そのような見切りをつけるためには、当時の市場の要求が「記憶容量」という機能面から、「小ささ」へ変化していることに気付かなくてはならない。いつまでも「記憶容量」という機能面指標だけに固執しているようでは、イノベーションのジレンマを克服することはできない。
現在のパソコンやノートパソコン市場の状況を考えると、小型化の重要性は容易に想像できる。しかしながら、メインフレームや大型計算機のイメージが残る当時のコンピューター市場において、「記憶容量」の技術革新を捨て、新たな指標である「小型化」へシフトすることは相当に難しかったのではないか。
北米のホンダの事例においても、当時の北米のバイクユーザーにとって、バイクを選択する際の重要な指標は「大型」や「爆音」であったのかもしれない。そのような市場環境の中「小型」、「低燃費」という新たな指標を見出せるか、ということが重要となる。当時のホンダが、そのような市場の求める指標の変化を推測し、意識的に製品開発戦略を実行していたかどうかは推測の域をでない。しかしながら、同一の製品市場であっても、市場の求める指標は常に変化しており、自社の持つ技術的、組織的な惰性に捕われることなく、この新しい指標の変化を満たす技術革新を実行できるかどうかが、イノベーションのジレンマを克服することができるか否かの違いになるのではないであろうか。
研究部門、開発部門などの技術系部門では、これまでの自らが得意としてきた技術領域からの離脱を嫌う傾向にあり、従って「記憶容量」から「小型化」へといったような市場の変化に気付きにくい構造にあるといえる。近年は、ウェブアンケートなどを利用して、短期間にかつ低コストにて市場の変化を比較的容易に分析することが可能になってきている。定期的に市場環境の変化をウォッチすることにより、ユーザーの当該製品に求める「指標」の変化を予測し、このような変化に柔軟に対応可能な研究・製品開発戦略を実行することでイノベーションのジレンマを回避することもできるのではないか。
例えば、ある特定のサービスや製品において3つの重要とされる指標が存在するとする(仮に指標A~Cとする)。携帯電話であれば「デザイン」や「帯域(ブロードバンド性)」、「料金」などが重要な指標の候補であろう。この3つの指標に関して、ある人は携帯電話を購入する際に指標Aを最も重視するかもしれない。また別の人であれば指標Cは譲れないと考えるかもしれない。誰がどの指標を重視するかということは、まさに「市場の声」である。この市場の声を、ウェブアンケートなどを利用し統計的に分析することにより、当該サービスの普及状況を予測することも可能となる。
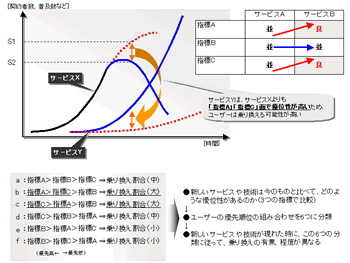
図表は3つの指標をベースとした普及シナリオの考察イメージを示したものである。例えば指標Aと指標Cに優れた新しい携帯電話を競合他社が製品化(サービスY)した時に、それに対して市場がどの程度反応するか、ということを示したものである(図表の例は、サービスXからサービスYへの「乗り換えの程度」を模式的に示したもの)。具体的には、顧客市場を6つのセグメント(a~f)に分類し、各セグメントにユーザーがどのように分布するかを、ウェブアンケート等を利用して収集する。普及予測という意味では、競合他社の状況や、技術的な動向、場合によっては当該市場に関する政策や規制の動向も考慮したいわゆる“シナリオ分析”も併せた評価が必要となるが、図表に示されるような市場動向の概念をもとに、最新の「市場の声」を抽出することが予測分析の重要な第一歩となろう。このような手法を系統的に適応することにより、当該製品やサービスに関する「指標」の動向を把握することができ、より不確実性が高くなりつつある市場動向に追随するための戦略構築の一助になるのではないか。
- (参考文献)
- ◆山本大輔、森智世『入門知的資産の価値評価』(2002年9月、東洋経済新報社)
- ◆クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』(2001年7月、翔泳社)、
- 同 『イノベーションへの解』(2003年12月、翔泳社)

