1.安全神話の崩壊
今年発表された「社会意識に関する世論調査」では、現在の日本で悪い方向に向かっていると思われるのは「治安」であり、昨年から大きく上昇し、まさしく「安全神話の崩壊」を裏付ける結果となっています(図表-1)。(「神話」が崩壊したということの証左ではありますが、「現実」としてどうなのかについては別途詳細な分析が必要となることは賢明な読者の方はすでにお判りのことかと思います。)
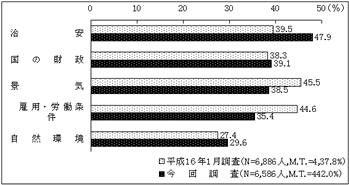
このような国民不安の払拭は、わが国の喫緊の課題となり、「安心・安全」というキーワードは、小泉総理の施政方針(注1)にも登場し、自治体のまちづくりにおいても大きな柱になりつつあります。「安心・安全」の概念は、マズローの欲求第2段階(safety-security needs)を見るまでも無く、極めて広範と考えられますから、ここでは、「安全・安心なまちづくり」イコール「犯罪に強いまちづくり」というかなり限定的な範囲で考えることにしましょう。
- (注1)
- 第162回国会における小泉内閣総理大臣施政方針演説(2005.1)
2.割れ窓理論とは
「割れ窓理論」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか?これはガラスの割れ方を物質工学的に説明するような理論ではありません。「割れ窓理論」における「割れた窓」は、縄張意識と当事者意識が低い地域の象徴であり、犯罪者が気軽に犯行に及ぶことのできる地域の象徴である、という米国のJ.Q.Wilson とG.L.Kelling両博士による理論です。逆に言えば割れた窓が1枚もない地域は犯罪者にとってやっかいな地域すなわち“犯罪に強い(の少ない)地域”ということなのです。このようなことを説明すると、「では地域の窓ガラスの取替え発生率と犯罪発生率が統計的に負の相関があると説明できるのか」などと考えがちですが、そういうことへのトライは時間の無駄なのでやめましょう。
この理論上重要な点は、個人個人の「管理意識」を「縄張意識と当事者意識」というかたちで地域に広げるべきであるというところなのです。もちろん意識だけではだめで、下図のとおり、ハードな要素とが合わさることが重要です。
ここまで読まれた賢明な読者の多くは、「それって昔の日本じゃないの?」と思われるかもしれません。実は正解です。「割れ窓理論」はかつての日本の地域社会が実践してきたに他なりません。
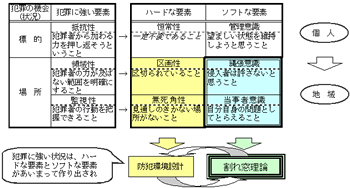
3.割れ窓理論とソーシャル・キャピタル
さて、ソーシャル・キャピタルは、「ネットワーク(社会的な繋がり)」「規範」「信頼」といった社会組織の特徴で、共通の目的に向かって協調行動を導くもの(注2)とされています。日本ではやや耳慣れなかったこの言葉もかなり浸透しつつあるなあという実感を持っています(先日はある自治体の「経済活性化とソーシャル・キャピタルに関する調査」のコンペがありました。)
割れ窓理論が規定するところの「縄張意識と当事者意識」が内部結束型すなわちBondingなソーシャル・キャピタルとかなり似たものであると思っています。Bondingなソーシャル・キャピタルは、実は強すぎると弊害があると言われています。すなわち「排他性」の問題です。民族的な結束は異民族を排除しようとする運動につながりますし、組織的には「長いものには巻かれろ」主義の蔓延につながり活力をそぐことになります。ソーシャル・キャピタルの議論では、Bondingよりも「橋渡し型」(Bridging)のソーシャル・キャピタルが重要と言われています。
犯罪に強いまちづくりのためには「縄張意識と当事者意識」が重要であるとの「割れ窓理論」と、その性格は強すぎると良くないというソーシャル・キャピタルの議論。これらをどこでどう折り合いをつけるべきなのでしょうか。
この大きな課題については、次稿以降整理していきたいと考えています。
- (参考文献)
- 「割れ窓理論による犯罪防止」小宮信夫監訳、文化書房博文社、2004
- 「ソーシャル・キャピタルって何だ??」東 一洋、2003
- 「ソーシャル・キャピタル:豊かな人間関係と市民活動の好循環を求めて」内閣府、2002

