Business & Economic Review 2007年03月号
【OPINION】
ハイテク・ベンチャー主導の成長戦略を-事業化リスク軽減が成功の鍵
2007年02月25日 藤井英彦
- はじめに
イノベーションを原動力とした成長戦略を指向する取り組みが、近年、先進各国を中心に一段と強まっている。グローバル化の進展に伴って、BRICs経済を筆頭にかつての中進各国が低価格を武器に飛躍的発展を遂げるなか、先進各国が、産業の空洞化や雇用の喪失、所得格差や地域格差の深刻化を回避するには、高い付加価値を上げる新たな市場を創出し、それによって国際競争力を維持して成長路線を確保する以外に根本的な方策が見当たらないからである。
例えば、2006年末の数カ月間をみても、そうした取り組みが相次いでいる。12月にはEUで2007年から2013年まで7年間にわたる科学技術革新計画が最終決定された。産学連携と基礎研究の強化、高度人材の確保と研究インフラの整備を4本柱とし、最先端の研究をベースに産業や雇用の創出へどのように繋げていくかが基本的な視座となっている。10月には、アメリカで連邦政府の科学技術政策を主導する国立科学財団(National Science Foundation)が、2006年度から2011年度までの戦略プラン「アメリカの未来への投資(Investing in America’s Future)」を公表した。国際競争力強化の源泉との位置付けのもと、最先端の研究推進と理工系人材の育成、研究インフラの整備と強力な研究サポート体制の構築が4本柱とされており、内容、スタンスともEUと相似する。
一方、わが国でも2006年に入り、イノベーションを原動力とする成長戦略実施に向けた施策が様々な分野で打ち出された。まず4月に2006年度から2010年度の5年間を実施期間とする第3期科学技術基本計画がスタートした。1996~2000年度の第1期、2001~2005年度の第2期の取り組みをさらに強化し戦略的推進を図ることで、研究成果を経済・社会に還元することを最大の眼目とする。次いで7月に経済成長戦略大綱が策定された。これは、5月に公表されたグローバル戦略、6月に決定された新経済成長戦略を統合した総合的プログラムであり、技術革新と生産性の向上、海外経済のダイナミズム活用の3本柱によって今後10年間にわたり実質2.2%成長を実現しようとする意欲的な計画である。さらに10月には、研究成果の活用に不可欠な知財権の保護強化に向け、世界最速の早期権利化とさらなる知財権の有効活用を目指したイノベーション促進のための特許審査改革加速プランが策定された。12月には2007年度税制改革大綱が発表され、特定中小企業が発行した株式に係る譲渡所得などの課税の特例、いわゆるエンジェル税制の適用期限を2年間延長する方針が打ち出されている。
そうしたなか、技術革新を梃子としたわが国競争力は、近年、一段と強さを増している。例えば、特許等使用料収支をみると、戦後長らく赤字傾向が定着していたものの、90年代後半、次第に受取額が増加した結果2003年に黒字に転化し、その後、年を追って黒字額が増加している。2006年も増勢が続いており、1~10月実績で4,490億円に達し、すでに2005年の3,288億円を大きく上回っている。しかし、イノベーションを原動力とした成長戦略を実際に推進していくプレイヤーをみると、アメリカでの特許取得件数でわが国大手メーカーが毎年上位にランクインするなど大企業を中心に既存企業の競争力は優れているものの、ベンチャー企業が果たしている役割をみると、少なくとも近年、主要各国に比べて低調である点は否定し難い。そこで本稿では、ベンチャー企業が果たす役割をその活動が活発なアメリカを中心に概観する一方、主要先進各国とわが国とのベンチャー企業の活動状況の違いを対比したうえで、今後、わが国が取り組むべき主な課題を取り上げてみた。 - ベンチャー企業の役割
(イ)まず主要各国のなかでも、とりわけベンチャー企業の活動が活発なアメリカについて、マクロ的視点からベンチャー企業のメリットを整理してみた。そもそも多くのベンチャー企業は、創業当初こそエンジェルなど個人投資家や親戚、友人から資金を調達するものの、事業が拡大し要資が増加するのに伴い、ベンチャーキャピタルから資金調達を行う。そのため、ここではベンチャーキャピタル投資したベンチャー企業とアメリカの企業セクター全体の雇用者数と売上高の増減率をみた(図表1)。
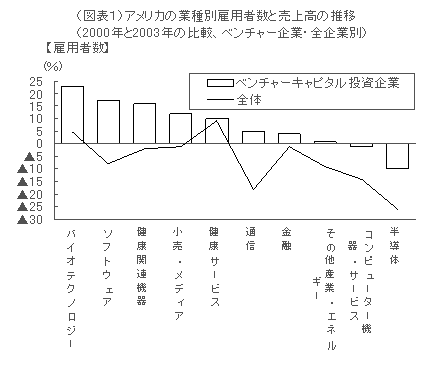
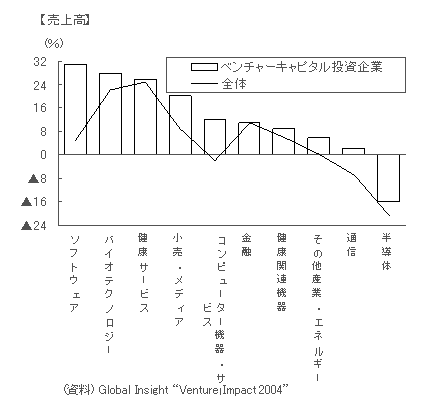
対象期間は2000年から2003年の3年間である。ITバブルが最も膨張した時期とITバブル崩壊によるマイナス影響が最も大きくなった時期を対比することになる。雇用動向についてみれば、この間、アメリカ全体で非農林業雇用者数が1億3,179万人から1億3,000万人へ179万人減った。
しかし、ベンチャー企業の雇用者数は逆に60万人増加しており、雇用情勢の悪化に歯止めをかけた。売上高でも、全体が6.5%の増加にとどまるなか、ベンチャー企業は11.6%とハイペースで増加した。業種別に雇用者数をみると、ベンチャー企業の増加率が大きかった事業はバイオやソフトウェア、健康関連機器、小売・メディア、健康サービスの5分野であり、それらは、順位は若干変わるものの、売上高でも増加率の上位5分野を占める。さらに、ベンチャー企業が牽引する傾向が強いバイオや半導体、ソフトウェア産業の雇用者の賃金増加率をみると、この間、民間雇用者の賃金が全体で11%増加するなか、バイオは18%、半導体は16%、ソフトウェアは14%と軒並み平均を上回って増加した。このようにみると、付加価値が高く成長性の大きい新たな市場の台頭によって魅力的な雇用を創出する一方、国全体として産業の高度化を実現し競争力を強化するという好循環を生み出すうえで、ベンチャー企業が果たす役割は大きいといえよう。
(ロ)一国経済を牽引するベンチャー企業の役割をアメリカ以外の各国を含め主要先進各国についてみるとどうか。そこで、ここではまず、サプライサイドから経済成長を実現する主要要素の一つとされる労働投入量と経済成長の関係をみた。具体的には、ITバブル崩壊に伴う不測のショックの影響を除去しつつ、可能な限り最新の動向を観察する観点から対象期間を2002~2005年とし、18~64歳人口に占めるベンチャー企業の活動に携わった労働者数の割合を労働投入量の代替変数として、各国の年平均実質経済成長率と対比した(図表2)。
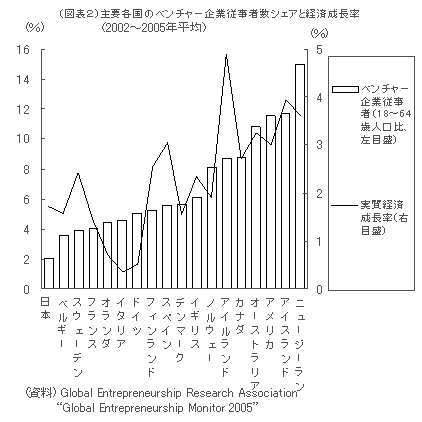
無論、各国の経済成長スピードは供給サイド、それもベンチャー企業の活動に対する労働投入量だけで決定されるほど単純なものではない。循環的な要素にも大きく左右されるし、ドイツやイタリアにみられる通り、EU拡大に伴う中東欧エリアへの資本移動がマイナスに作用している国々もある。一方、アイルランドのように、法人税負担の軽さや充実した産業インフラが外国資本を呼び込み、高めの成長軌道を続ける国もある。しかし、総じてみれば、主要先進各国についてみる限り、ベンチャー企業の活動に対する労働投入量が大きい国ほど、経済成長ペースが速い傾向が窺われ、両者には弱いながら相関関係が看取される。
グループ分けをすると、まずアメリカやオセアニア各国がトップを走っており、ベンチャー企業の活動に携わった労働者数の割合は1割強に達している。次いで、カナダやノルウェーが続き、労働者数の割合は8%と1割弱である。イギリスやドイツ、フランスをはじめ西欧主要各国の多くは三番手グループを形成しており、労働者数の割合は4~6%である。それに対して、わが国の場合、ベンチャー企業の活動に対する労働者数の割合は2%に過ぎず、主要先進各国に比べて際立って小さい。
ベンチャー企業の活動が活発であり、事業としての成長性が高いほど、資金需要も大きくなる筋合いである。そこで、ベンチャーキャピタル投資規模をGDP比率で主要先進各国で対比してみた(図表3)。これによると、若干の違いはあるものの、ベンチャー企業の活動に携わる労働者数の割合が大きい国ほどベンチャーキャピタルの投資規模が大きい。アメリカやカナダといった労働投入量の先頭および第2グループに属する国のベンチャーキャピタル投資はGDPの0.4~0.5%に及び、各国中最大である。一方、西欧各国をみると大きく二つのグループに分かれており、スウェーデンやフィンランドといった北欧各国やイギリスではベンチャーキャピタル投資が相対的に積極的であり、GDP比でみた投資規模は0.2%に達する。それに対してフランスやドイツなど大陸諸国のベンチャーキャピタル投資は慎重姿勢が強く、GDP比でみた投資規模は0.1%前後である。翻ってわが国をみると、ベンチャーキャピタル投資はGDP比0.03%であり、慎重な西欧大陸諸国に比べても3分の1弱に過ぎず、先進各国のなかで突出して規模が小さい。
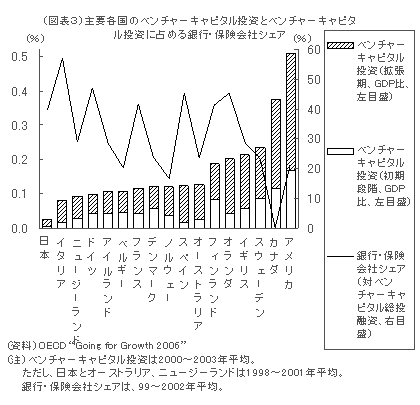
さらに、ベンチャーキャピタル投資を創立局面と事業拡大の局面に分けてみると、わが国の場合、とりわけ創立局面のベンチャー企業に対する投資が低調である。すなわち、創立局面のベンチャー企業に対する投資は、ドイツやフランスなど主要先進各国のなかで最も慎重な国々でもGDP比0.04%強であるのに対して、わが国では0.007%にとどまり、西欧大陸諸国の6分の1に過ぎない。
(ハ)ベンチャーキャピタル投資については、対象期間が2000~2003年であり、ITバブル期が含まれているため、とりわけアメリカについて、投資規模が上振れているという批判もあろう。確かにアメリカのベンチャーキャピタル投資額は2000年の1,044億ドルをピークに2001年以降大きく落ち込んだ。2004年以降から増勢に転じているものの、依然して年間200億ドル強と、2000年の5分の1の水準にとどまっている。
加えて、90年代からITバブル期にかけて、ベンチャー企業の出口戦略として盛んに活用されたIPOも依然として低迷している(図表4)。ベンチャーキャピタルが投資したベンチャー企業のIPO件数は99年の267件、2000年の242件をピークに2001年以降、大幅に減少した。2006年も58件と99年の5分の1にとどまっている。
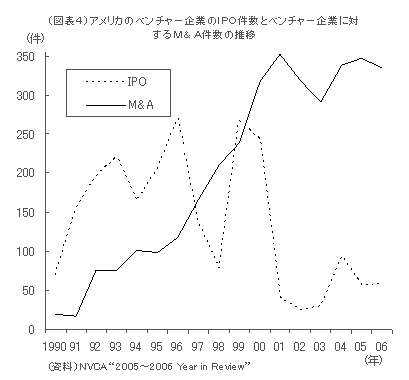
しかし、2001年以降、IPOに代わってM&Aが有力な出口戦略として積極的に活用されている。ITバブル崩壊によってIPOが難しくなり、緊急避難的にM&Aが多用された結果、2001年には年間353件と過去最大となった。その後減少して2003年には291件となったものの、2004年以降、340件前後と2001年並みの水準で推移している。
さらにコーポレート・ベンチャリングにも、近年、次第に明るさが拡がっている(図表5)。ちなみに、M&Aは、ベンチャーキャピタルがベンチャー企業の株式を他の企業に売却するスタイルであり、ベンチャーキャピタルにとって出口戦略の一つである。それに対して、コーポレート・ベンチャリングは、一般の事業会社が自社の一部門、あるいは子会社を専門部隊として直接ベンチャー企業に投資を行い、ベンチャー企業の成長度合いや社内外の諸情勢を踏まえながら、ベンチャー企業を社内組織の一部門に組み込んだり子会社化する、あるいはベンチャー企業の株式を他社に譲渡するなど、迅速かつ戦略的な事業展開を可能にする手法の一つである。
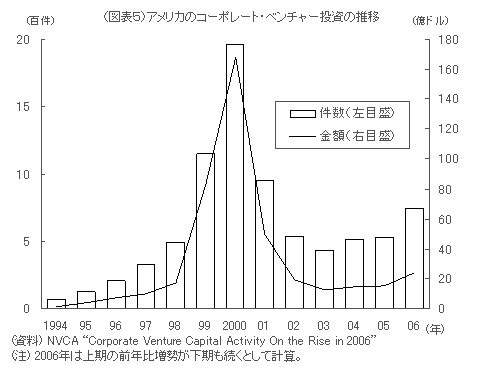
ITバブル崩壊によって一時的にコーポレート・ベンチャリングも下火となった。件数は2000年の1,960件から2003年には437件へ、金額も2000年の168億ドルから2003年には13億ドルへ大きく落ち込んだ。しかし、M&Aと同様、2004年以降、増加傾向に転じ、2006年に入って増勢が強まっている。上期の増勢が下期も続くとすると、2006年通年では件数ベースで746件、金額では24億ドルに達し、99~2001年のITバブル期を除くと、過去最大となる見込みである。
(ニ)このように近年、ベンチャー企業に対するM&Aやコーポレート・ベンチャリングに対する取り組みが盛り上がってきた背景として、次のような事情が指摘されよう。第1はグローバル競争の激化である。すなわち、BRICs地域をはじめとして、かつての中進国経済が低価格を武器に飛躍的成長を遂げるなか、先進各国企業が生き残るためには、新たな市場を創出したり、研究開発を通じて獲得された要素技術やノウハウをブラックボックス化することによって高付加価値の戦略的な事業分野を確保する以外に効果的な方策が見当たらない。
第2は企業セクターでのリストラの進行である。20世紀後半までアメリカ企業を中心に先進各国の有力企業では、基礎研究に取り組むセクションを企業内あるいは企業グループ内に抱え、次世代の事業シーズを育てるスタイルが定着していた。しかし、企業間競争が厳しさを増すなか、そうした事業モデルは次第に放棄され、企業のリソースを競争力の強化に最大限集中させる選択と集中の経営革新が強力に推進された。そうしたなか、中長期的な研究開発事業をアウトソースする動きが拡がっていった。
第3は技術革新や市場ニーズの変化が一層加速していることである。その結果、競争力の維持・強化を図るには、社内リソースに限定せず、最適の社外リソースを積極的かつタイムリーに活用して技術進歩や市場動向の変化に即応した事業展開を進めることが不可欠となった。M&Aやコーポレート・ベンチャリングによってベンチャー企業との関係を調節し、時に囲い込む手法は、研究開発コストの肥大化を回避しながら、最先端の研究成果を最大限活用するための方策として合理的との認識が拡がった。
さらに、こうした手法は、ベンチャー企業や一国経済全体からみても、メリットが大きい。まず、ベンチャー企業の立場に立てば、マーケティングや資金力といった不得意な分野を提携企業に任せ、自身が得意とする研究開発に専念することができる。また、一国経済全体としてみると、技術動向や消費者ニーズを踏まえた市場競争を通じて取捨選択が行われる結果、新産業創出に費消される経済資源が最適化される一方、有望な技術シーズが販売力や資金力不足によって事業化できない、いわゆる死の谷と呼ばれるミスマッチの克服が図られる。 - 今後の課題
(イ)近年、研究開発の成果を生かして経済成長を実現する戦略が各国で一段と強力に推進されている。冒頭、概観した通り、アメリカでは2006年10月、国立科学財団が2006~2011年度の戦略プラン「アメリカの未来への投資」を公表し、次年度予算への攻勢が強まっている一方、EUでは12月、2007~2013年の科学技術革新計画が最終決定された。アメリカやEUのみならず、ドイツでは8月、2009年を期限に総額146億ユーロを投入するハイテク戦略が策定され、産業界でのイノベーション促進を通じた150万人の雇用創出計画が公表された。イギリスでは10月、2004~2014年の科学・イノベーション投資計画の推進力強化に向けて、科学・技術・工学・数学分野での高度人材の育成を目指した基本計画書が策定されている。
こうした成長戦略を成功に導くには、単に意欲的な研究開発事業を推進するだけでなく、研究開発に続く事業化プロセスを市場ニーズの変化に即応しながらどれだけスピーディーかつ戦略的に行うことができるかが大きな鍵を握る。それだけに、ベンチャー企業、とりわけ技術革新型ベンチャーの果たすべき役割は重要であり、各国では、近年、ベンチャー企業の活動が経済成長プロセスのなかに着実にビルトインされ、その役割が増してきた。例えば、前章でみた通り、ベンチャー企業の活動に参画する労働者数が成年層の1割前後に上っているのも、その一例であろう(前出図表2)。また、ベンチャーキャピタルの投資資金のすべてがエンジェルや直接金融といったリスクマネーによって賄われているのではなく、2~3割の資金がリスク回避的な金融機関や保険会社から供与されている点に着目すれば、ベンチャー企業の事業活動に対してすでに一定の信頼が醸成されているとみることもできよう(前出図表3)。
翻ってわが国では、主要先進各国に比べてみると、ベンチャー企業の活動は依然として際立って低調であり、経済成長プロセスのなかにビルトインされるまでには至っていない。さらにファイナンス規模の違いをみても、ベンチャー企業の活動に対して諸外国で形成されたような信頼がわが国でも醸成されたと言うには程遠い。こうした状況を放置し、技術革新や市場変化への的確な対応をベンチャー企業に頼らず、既存企業群に依存する片肺飛行を続けた場合、いかにわが国企業が優秀であるとしても、社内あるいは自社グループのリソースを活用するだけでは競争力の相対的低下を招く懸念は否定できない。グローバル競争の一段の激化に伴って、今後、既知の要素技術と不連続な研究開発に迫られる局面が一層増えると見込まれるからである。
(ロ)それでは、今後、わが国が取り組むべき課題は何か。ベンチャー企業の活動を原動力として技術革新と経済成長のプラスサイクルを実現し、わが国に定着させていくには、米英独など各国の取り組みにみられる通り、高度人材の育成や研究・起業インフラの整備、リスクマネーの強化、さらにR&Dや研究開発に対するインセンティブ減税の拡充など、ヒト・モノ・カネといった経営資源をめぐり様々な側面から有効打を着実に積み重ねていく総合的な施策が必要である点は言を俟たない。
しかし、最大の課題は、研究開発から事業化に至るプロセスをどれだけ市場動向を睨みながら戦略的かつスピーディーに推進できるかにある。そうしたプロセスで重要な役割が期待されるベンチャー企業は、わが国と諸外国とを問わず、創業から間もない企業ほど見るべき過去の業績は存在しないし、総じて社内リソースは不足しているうえ、確固たるビジネスモデルが形成されていないにもかかわらず、各国ではベンチャー企業が一定の役割と信頼を勝ち得ている。こうした観点から各国の取り組みをみると、先端分野に通暁した研究者や起業ビジネスに精通した専門家から構成されるチームが一つひとつのプロジェクトを厳格に審査し評価するスキームのもと、ベンチャー企業へのサポートを含め、研究開発から事業化に至るプロセスに対してわが国より手厚い支援が、政府の裁量や恣意的介入を排除する形で行われている点が注目される。その結果、事業リスクが軽減されて民間の参入が促され、ベンチャー企業が活躍するチャンスが拡がる展開になっているといえよう。そうした取り組みのうち、とりわけわが国が見習うべきポイントを整理すれば、a.研究開発支援、b.事業化支援、c.海外リソースの活用、の3点が指摘される。具体的には以下の通りである。
a.研究開発支援
(a)まず、研究開発投資全体の規模をOECD主要先進21カ国についてGDP比で対比してみた(図表6)。なお、比較年次は最新データの2004年とし、東欧諸国やデータの採れないイタリアなど数カ国を除いている。それによると、最大は3.9%のスウェーデン、次いで3.5%のフィンランドと北欧2カ国の投資規模が際立って大きく、わが国は3.1%で第3位を占める。
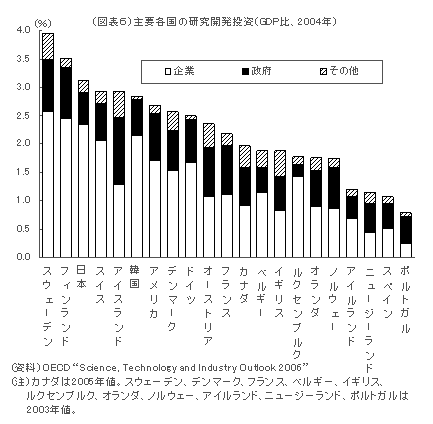
一方、投資規模の小さい国々をみると、農業経済が強いニュージーランドやスペイン、ポルトガル、あるいは外資導入が目覚しいアイルランドの4カ国はいずれも1%前後にとどまる。これら4カ国および上位2カ国を除くと、主要先進各国の研究開発投資は総じてGDPの2~3%の規模である。わが国の投資規模は北欧2カ国に比べれば小さいものの、大半の主要各国に比べれば相対的に大きく、投資総額からみる限り、大きな問題はないようにもみえる。
(b)しかし、投資資金の拠出主体別、すなわち、企業と政府、その他の3者に分けてみると、わが国の研究開発投資規模が相対的に大きいのは民間企業の拠出規模が大きいからであり、政府の投資規模は必ずしも大きくない(図表7)。この点を確認するために、改めてOECD主要各国について政府の研究開発投資資金拠出額をGDP比で対比してみると、2004年時点で最大は1.17%のアイスランド、第2位は0.93%でスウェーデン、第3位が0.92%のフィンランドで、北欧3カ国が上位を占める。それに対して、わが国は0.57%にとどまり、アイルランドやスペイン、ニュージーランドに次いで6番めに政府による投資規模の小さい国となっている。ちなみに、イギリスの0.59%を除くと、フランスが第4位で0.85%、アメリカは第5位で0.83%、ドイツ0.76%、カナダ0.67%であり、G5各国の水準は総じてわが国を上回っている。
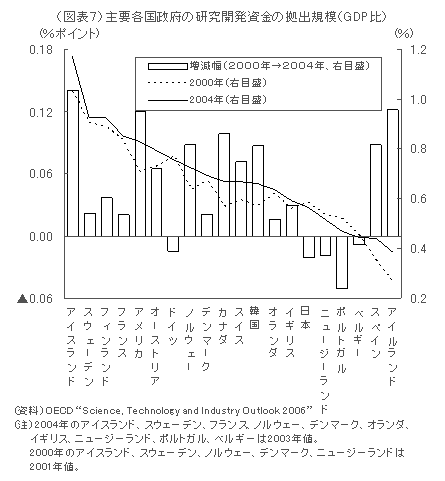
加えて、政府による研究開発投資について2000年から2004年へのGDP比率の変化をみると、大半の国で投資規模が拡大しており、経済成長を上回るペースで政府の投資が拡大している。そうしたなか、わが国はベルギー、ポルトガル、ニュージーランド、ドイツと並んでGDP比でみた政府の投資規模が減少した5カ国の一つである。わが国自身としてみれば、この間、厳しい財政事情を反映して財政再建に向け多くの予算が削減されるなか、意欲的な第2期科学技術基本計画が推進されたものの、OECD加盟の主要各国と投資規模の推移を対比してみる限り、わが国政府の研究開発投資に対するスタンスは相対的に積極性に欠けると言わざるを得ない。もっとも、わが国自身としてみれば積極的に科学技術政策を展開していただけに、むしろ、近年のグローバル競争を背景に研究開発に対して大半のOECD加盟主要各国が一段と積極的な姿勢を強めた結果、相対的にわが国が各国の後塵を拝する結果となったという見方がより正確な捉え方かもしれない。
(c)さらに、政府の研究開発投資資金のうち企業に供与された規模をOECD加盟の主要各国とGDP比で対比してみると、わが国の消極的スタンスは一層明瞭である(図表8)。まず2004年時点の各国をみると、最大は0.20%のアメリカで、次いで0.17%のスウェーデン、3位が0.15%のフランス、4位が0.13%のイギリス、5位が0.10%のノルウェー、韓国、ドイツであり、米仏英独の主要国とスウェーデン、ノルウェーの北欧2カ国などが際立って大きい。それに対して、わが国は0.03%と、ポルトガルやアイルランド、カナダに次いで小さな規模にとどまる。2000年から2004年への変化をみても、多くの国々で投資規模が拡大するなか、わが国では逆に減っている。
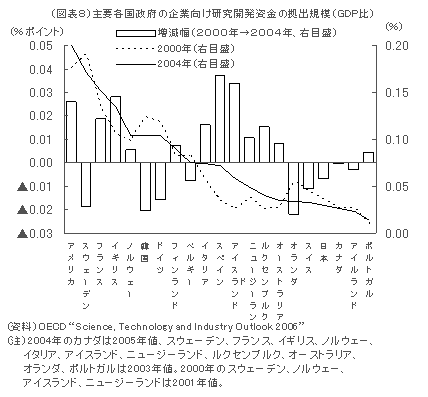
それでは、近年、各国政府が研究開発投資を積極化させ、さらに企業のR&D活動に対する資金供与を積み増した背景は何か。これには、前記、ベンチャー企業のM&Aやコーポレート・ベンチャリングが近年盛り上がってきた事情と裏腹の関係がある。すなわち、グローバル競争の激化に伴って先進各国が経済活力を維持・強化し競争力を確保していくために、研究開発の成果を原動力に経済成長を図るニュータイプの経済政策が重要性を増してきたものの、企業サイドでは事業化プロセスに一段と経営資源を集中させる傾向が強まった結果、基礎研究段階をはじめとして研究開発プロジェクトの推進に当たって、政府が直接に研究開発を推進したり、専門家集団を擁する企業に研究資金を供与して民間リソースの活用を図るなど、研究開発プロセスで政府の果たすべき役割が大幅に拡大したという情勢変化である。
(d)無論、主要各国といえども、多岐にわたる戦略的な研究開発を主体的に行うだけのインフラや人的リソースがすべて政府部内に蓄積されている国ばかりではないし、政策として事業化プロセスを視野に入れた研究開発の取り組みに政府が直接に関与すべきでないとする国もある。その結果、カナダやオランダなど、企業向けも含め研究開発に対する政府投資を限定的にしている国々では、企業に対してR&D投資減税を積極的に認め、企業セクターが事業化プロセスだけでなく、研究開発プロセスでも牽引役としての役割を果たすことが期待されている(図表9)。
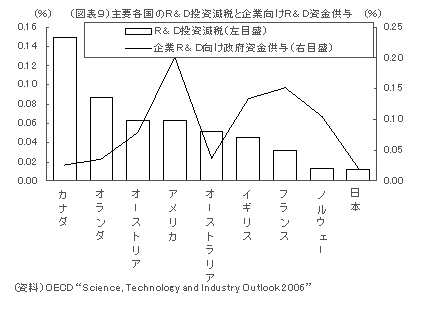
一方、アメリカやイギリス、フランス各国では、政府の企業向け研究開発資金供与が主要各国のなかでも際立って大きく、さらに企業に対してR&D投資減税も積極的に認められており、研究開発型成長戦略の実現に向けた強い姿勢が色濃く反映されたスキームとなっている。それに対して、わが国では、政府が企業に供与する研究開発資金の規模が主要各国のなかで最小グループの一つであるうえ、米英仏各国と比べてみる限り、企業に対するR&D投資減税も最小規模であり、研究開発に対する政府の支援は相対的に限定的なものにとどまっている。
(e)以上を要すれば、近年、主要各国で政府の研究開発活動が一段と積極化し、企業に対する研究開発資金の供与が増大したのは、技術革新の成果を原動力に経済成長を実現しようとするニュータイプの経済政策が本格化した結果であり、企業セクターの選択と集中の経営によって生じた研究開発プロセスでの推進力低下を補い、さらに強化する狙いがある。各国政府が積極的な支援策を競って推進するなか、諸外国を上回って強力なサポートが得られる国では、その分、研究開発リスクが軽減されて事業化の成功確率が高まり、海外からの参入も含め、事業化に向けた取り組みが盛り上がろう。こうした認識を踏まえ、改めて北欧諸国をみると、研究開発に対して米英仏独など主要各国を上回る支援を政府が行っており、社会福祉のみならず、新たな産業や雇用の創出を含め、総合的観点から充実したセーフティ・ネットの構築が目指されているといえよう。
それに対して、逆に相対的に諸外国を下回るサポートしか得られない国では、事業化に向けた取り組みがより手厚いサポートの得られる国へ流出しやすく、技術革新を梃子に経済発展を目指す成長戦略が必ずしも成功しないリスクが大きい。今日、ニュータイプの成長戦略は先進各国を中心に制度間競争の色彩を強めているだけに、わが国が科学技術立国政策で成功を収めるには、まず研究開発プロセスにおいて諸外国を上回る強力な支援体制を可及的速やかに構築することが求められているといえよう。
(f)なお、研究開発プロセスの推進力強化に向けて、TLOや産業・地域クラスター制度など、わが国でも産学連携の強化が図られてきた。しかし、OECD主要各国と対比してみる限り、わが国の企業セクターと高等教育機関との繋がりは必ずしも強くない。この点を確認するために、企業が高等教育機関に対して供与した研究開発資金の規模をGDP比で対比すると、次の通りである(図表10)。まず、2004年時点で最大は0.06%のカナダであり、上記、カナダ政府のR&D投資減税に対する姿勢でみられる通り、民間企業主導の色彩が強い。2位はアイスランド、3位は0.05%のドイツである。
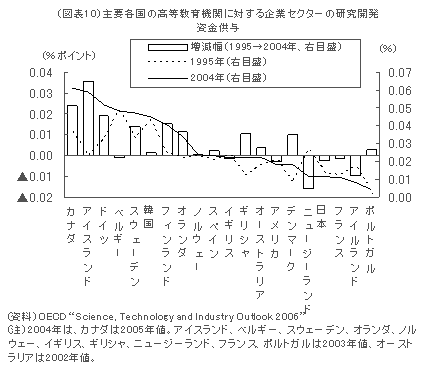
それらに対して、わが国は0.01%にとどまり、ポルトガルやアイルランド、フランスと並んで最小規模グループを形成している。さらに95年から2004年の変化をみても、大半の国々で投資規模が拡大し、産学連携が強化されてきたなか、わが国では若干ながら減少しており、相対的にみる限り、数少ない産学連携低迷国の一つである。企業セクターの選択と集中が不可避であるとすれば、産学連携による研究開発プロセスの推進力強化は有力な方策であり、今後、一段の推進が望まれる。
b.事業化支援
(a)研究開発を成功させたら、次の課題は、1日も早く、成果をフルに生かした新製品やサービスを作り出し、生産・供給・メンテナンス体制を構築して事業を軌道に乗せることである。しかし、そのためには、市場で受け入れられるコストダウンが可能か、新たな製品やサービスを安定して供給できるかなど、様々な問題を克服する必要がある。そのため近年、研究開発の成功は一里塚に過ぎず、研究開発から事業成功に至るプロセスを困難な局面、いわゆる死の谷とする認識が拡がるなか、各国政府では様々な支援メニューを提供し始めている。とりわけ、ベンチャー企業にとって死の谷を独力で克服することは困難であり、それが、このところ出口戦略としてIPOよりM&Aを選好する動きが強まっている所以でもある。
(b)そこで、ベンチャー先進国であるアメリカについて、事業化に向けた支援メニューをSBIR(Small Business Innovation & Research)制度に沿って整理すると、次の通りである。まず、SBIR制度は1983年にスタートしたベンチャー企業支援制度である。アメリカ経済が2度にわたる石油危機によるダメージに加え、日独によるキャッチアップによって産業空洞化の危機に直面するなか、新産業の創出こそ直面する苦境を克服する効果的な打開策という位置付けのもと、本制度が創設された。
これは、1億ドル以上の外部研究開発予算を持つ連邦省庁に対して、少なくとも当該予算の2.5%をベンチャー企業に供与することを義務付けるもので、供与フェーズは3段階に分かれる。まず第1段階で6カ月をかけてアイデアや技術のフィージビリティ・スタディーが行われ、資金は10万ドルを上限に供与される。次いで第2段階に入ると、第1段階で合格したプロジェクトを対象に2年間をかけて研究開発が推進され、事業化の可能性が追求される。資金は75万ドルを上限に供与される。最終フェーズである第3段階では、実際に事業化へ向けた取り組みが始まる。SBIRプログラムとして供与される資金はないものの、第2段階を合格したSBIRプロジェクトに対しては一般競争入札によらず、連邦政府からの政府調達を受けることができる。SBIRでは、このようにフェーズを分けプロジェクトの成否を一つひとつチェックすることで、無駄なリソースの投入を回避しながら成長性の高いプロジェクトの重点的推進が図られている。
(c)SBIRがハイテク型ベンチャー企業の創出に役立ち、さらにベンチャー企業がアメリカ経済の活性化や競争力強化の実現に重要な役割を担っているという認識が次第に浸透するなか、SBIRの規模は年を追って拡大してきた(図表11)。まず資金供与の規模をみると、第1段階は83年度の4,500万ドルから2003年度には4億5,500万ドルへ20年で10倍に増加した。第2段階はさらに大きく増え、84年度の6,000万ドルから2003年度には12億1,500万ドルへ20倍となった。総額では83年度の4,500万ドルから2003年度には16億7,000万ドルとなり、2004年度には18億6,744万ドルに達している。一方、件数をみても、第1段階が83年度の686件から2004年度に4,638件となり、第2段階も83年度の74件から2004年度に2,013件へ増えている。
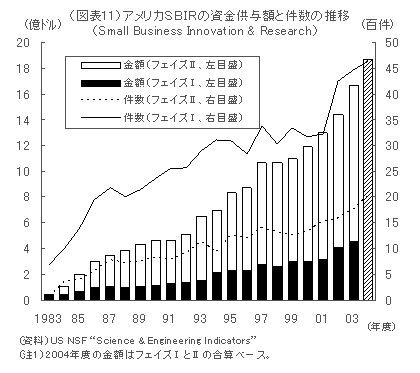
そうしたなか、第3段階での政府調達も次第に増加している模様である。ちなみに、SBIR対象企業に限定した調査はないため、中小企業からの政府調達額の推移をみると、90年代半ば以降、次第に増加傾向をたどり、2000年代に入り、増勢が加速している(図表12)。すなわち、中小企業からの政府調達額は、80年代半ばから90年代前半まで300億ドル弱の水準で推移した後、増勢に転じ、2000年度に388億ドル、さらに2005年度には796億ドルに達し、2000年度から5年間で倍増した。政府調達全体に占める中小企業からの調達シェアをみても、政府の中小企業育成に対する積極的姿勢の強まりを反映して、90年代半ば以降、趨勢的な上昇傾向が続いており、2005年度には25.4%と政府調達全体の4分の1を占めるまでに増加している。
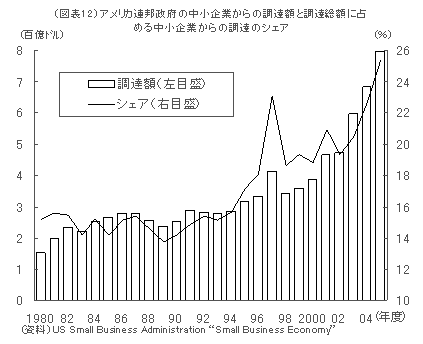
加えて、事業化に成功したプロジェクトが増え、プログラムへの信頼が高まった結果、厳しい競争を勝ち抜いて選定を受けたSBIRプロジェクト、さらに第2段階をクリアーしたプロジェクトに対して取引を始めたりM&Aを仕掛けるなど、積極的に働き掛ける動きが定着してきており、政府調達による売上増加や運転資金の確保と併せ、SBIRの政策目標、すなわち、ベンチャー企業を中心としたハイテク型中小企業の成長力強化が一層強力に推進される結果となっている。なお、アメリカでのベンチャー企業育成に対する政府調達の効果に注目が集まるなか、現在、EUでも新たな政府調達の枠組み作りが進められている。
(d)このようにみると、事業化プロセス、とりわけ、ベンチャー企業に対する支援スキームを整備・強化するうえで、わが国が参照すべき主な点を整理すれば次の通りである。
まず、ハイテク型中小企業をメインターゲットに一般競争入札と別枠の政府調達制度を設け、ベンチャー企業が直面する事業リスクの軽減を図るべきである。死の谷を潜り抜けようとするベンチャー企業に対して研究開発のみならず事業リスクも積極的に政府が取ろうとする動きが各国で一段と拡がっているなか、ベンチャー企業の成長を自助努力や市場競争にゆだね、政府の関与を増やさずに事業化プロセスを成功させ新たな高付加価値産業を生み出すことは必ずしも容易でない。
次に、政府の研究開発プロジェクトについて統合を進める一方、申請から合否理由の開示まで手続きの統一と簡素化を実現することが必要である。SBIR成功の要諦は各連邦省庁に跨る類似プロジェクトを統合することでリソースの分散に伴う推進力低下を避けるとともに、手続きの簡素化も併せて推進することで、より多くの強力な参加者による厳しい競争状態を作り出し、成功確率の向上を図ったことにある。どれほど巨額の予算を投入しても、各省庁がそれぞれ類似プロジェクトを進めては、一つひとつのプロジェクトの推進力は大きく減殺され、成功は覚束ない。
加えて、わが国の場合、一段の制度の拡充も望まれよう。まず予算面では、アメリカのSBIRが創設以来すでに20余年が経過しており、それに比べて99年度にスタートしたわが国のSBIRは依然歴史が浅いものの、2006年度の予算規模は370億円に過ぎず、2004年度18億6,744万ドルのアメリカを大きく下回る。さらに申請の可否やプロジェクトを評価するスキームの強化も重要である。ベンチャー企業サイドからみると申請が不合格となったりプロジェクトが打ち切りとなった理由が明確であるほど再チャレンジが容易になる一方、国全体としてみれば、事業化の見込みの薄いプロジェクトを排除しリソースを有望なプロジェクトに集中投下することで成功確率が引き上げられるからである。
c.海外リソースの活用
(a)このように、研究開発の成果を事業化へ円滑に結び付け、高付加価値の産業や雇用の創出を通じて力強い経済成長を実現していくためには、研究開発プロセスと事業化プロセスに政府が積極的に参画し、選択と集中による経営改革の結果、リスクの大きい研究開発や事業化プロジェクトを独力で遂行することが難しくなった企業セクターを戦略的に支援する必要がある。政府の支援によって事業化リスクが引き下げられ、企業の参入が可能になるためである。
逆にみれば、研究開発型成長戦略を成功に導く鍵は、どれだけ多くの競争力に富んだ企業の参入を実現できるかにあると捉えることもできる。そうした観点からみると、外国人による起業が一段と盛行している近年のアメリカには、政府の強力な支援の効果を最大限引き出す巧みなシステムがビルトインされているといえよう。近年の動向を整理すれば次の通りである。
(b)まず、ベンチャーキャピタルが投資したベンチャー企業のうち株式を公開した企業について設立時期別に1979年以前と80~89年、90~2005年の三つの時期に分け、外国人によって起業されたベンチャー企業の数が全体に占めるシェアをみると、79年以前では8社で6.5%に過ぎなかったものの、80~89年には48社で19.5%へ、さらに90~2005年には88社と社数が大幅に増加したうえ、全体に占めるシェアも24.7%と4分の1を占めるまで躍進している(図表13)。
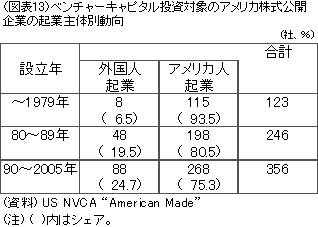
さらに、外国人が起業して株式を公開した企業の事業分野をみると、ハイテク型製造業が60社で4割、情報技術が34社で2割強、生命科学が30社で2割であり、外国人が起業した株式公開企業全体の8割強がこうした先端技術分野に属する(図表14)。雇用者数でも、ハイテク型製造業が28万人で7割、情報技術が5万人で1割強、生命科学が2万人であり、これら先端技術3分野で全体の8割強を占める。
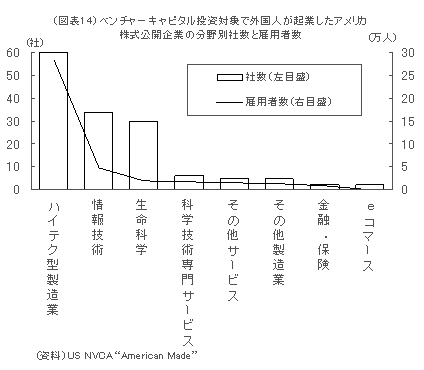
加えて、近年の主要先進各国をみると、グローバル化の進行を反映して外国企業による研究開発活動が総じて活発化している(図表15)。外国企業子会社による国内研究開発投資の規模を最新の2004年時点のGDP比でみると、最大はスウェーデンの1.3%で、各国のなかで突出して投資規模が大きい。スウェーデンは研究開発投資全体でも各国中最大であるが、それには、研究開発に向けた政府の手厚い支援に加え、外国企業が大きく貢献しているといえよう(前出図表6、7)。次いでベルギーが0.7%、アイルランドが0.6%、ドイツ0.5%と続く。その他多くの国々の投資規模は英仏米をはじめ0.3~0.4%である。それに対して、わが国は0.1%とポルトガルに次いで投資規模が小さく、外国企業の参入は依然として低調なものにとどまっている。
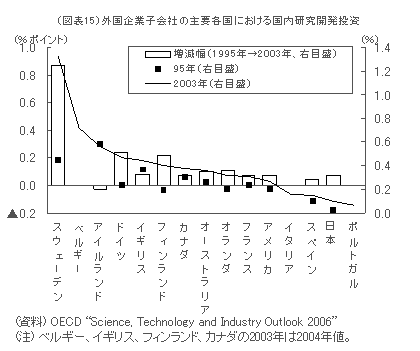
(c)こうした情勢下、近年、先進主要各国を中心に海外の研究・起業リソースの国内誘致に向けた取り組みが一段と強まっており、次第に競争激化の様相を呈している。すなわち、研究者や技術者、起業家など、外国の高度人材を積極的に呼び込む一方、外国の有力企業や研究機関の進出や国内への移転に向けて、魅力的な居住環境や利便性の高い事業インフラを整備したり、外国人や外国企業にも開かれたオープンな研究開発ファンドや制度を創設、さらに研究開発投資に対するインセンティブ税制の拡充や法人税率の引き下げを行うなど、様々な施策が推進されている。わが国でも、居住・事業環境の良さが研究者や企業を惹き付けるフランスのソフィア・アンティポリスを参照して、かずさサイエンス・パークが整備されたり、科学技術基本計画で研究プロジェクトのオープン化が重点目標と位置付けられる一方、99年度の税制改正でアメリカ並みまで法人税率が引き下げられるなど、多くの取り組みが推進されてきた。
しかし、現時点でみる限り、そうした取り組みの効果は必ずしも上がっていない。さらに、各国では即戦力となる研究者や技術者、起業家の誘致には限界があるとの認識が浸透するなか、近年、奨学金制度の拡充や現地案内センターの設置を通じて有望な学生を留学生として取り込もうとする動きが本格化しているのに対して、わが国の取り組みは遅れ気味である。
外国人の高度人材や有力な外国企業の国内誘致を進めるには、諸外国を上回る魅力を作り出し、それを積極的にアピールしていく以外に方策はない。各国が採用した政策の後追いに終始するだけではメリットは期待薄なうえ、相対的にみて魅力に乏しい状況が持続する結果、逆にヒトや企業、資本が国外へ流出する懸念が強まろう。資本の流出はわが国で看取される一方、ヒトの流出はすでにドイツで顕在化している。諸外国を凌駕する魅力作りに向け、成長戦略を標榜する安倍政権のリーダーシップ発揮が切望される。

