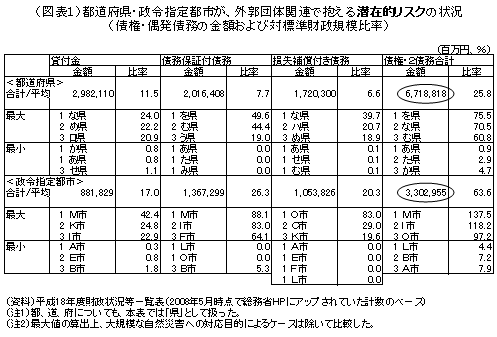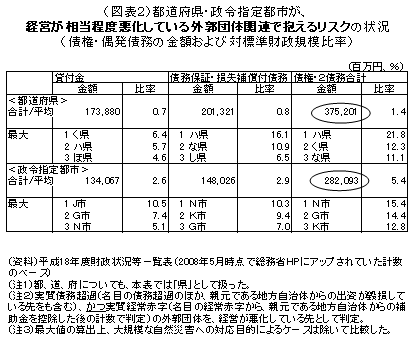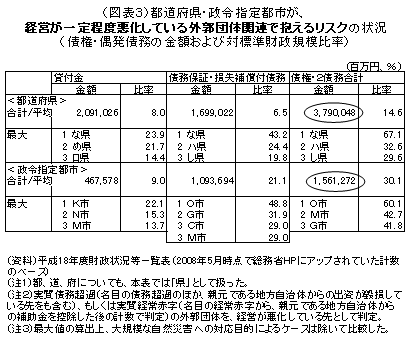- 自治体の外郭団体の経営問題の規模を把握すべく、公表資料に基づき、金利・信用リスクの大きさについて試算を実施(3ページ以降ご参照)。
- 試算結果が示唆する、この問題が今後の地方財政運営に与える影響および金融秩序において持つ意味を踏まえれば、今後、政策運営上望まれる方向性は以下の通り。
|
|
| 地方自治体の外郭団体経営問題と対応の方向性 |
1.「地域力再生機構」構想の問題点
- 現段階の「地域力再生機構」構想は、産業再生機構の成功体験に基づいているようにも見受けられるものの、この問題は、本質的に産業再生機構が扱った問題とは大きく相違。現段階の同構想が、実際に有効に機能するとは考えにくい。
- 第1の問題は、経営面で問題を抱える外郭団体のうち、経営状態がどういったレベルにあるところを対象とするのかが不明確で、試算結果(後述)に照らし合わせると、機構の資金面での手当てや、その他のスキーム面での設計が十分かつ適切とは考えにくい点。
-出資の規模(300億円)や借り入れに際して設定される政府保証枠の規模(1.6兆円)は、この問題の規模(3ページ参照)に比較すると相対的にかなり小さい可能性。
-出資元の自治体として、都道府県よりもむしろ大きな問題を抱えている政令指定都市が想定されておらず。
-外郭団体関連のリスクの規模について、自治体ごとのバラツキがこれほど大きいにもかかわらず、全都道府県が一律の金額で出資を求められている。
- 第2の問題は、地方自治体の外郭団体の問題について、あくまで個別案件ベースで解決を図るのか、国レベルで何らかの検討を行うのか、についても不明確な点
- どちらかといえば、個別案件ベースの解決が前提のように見受けられるが、実際には、個別アプローチでの解決は、相当に困難。なぜなら、これは産業再生機構の場合とは異なり、本質的に、わが国の準ソブリンである自治体による信用補完(債務保証・損失補償)が付与された債務の履行にかかる問題であるため。
-この点について、すでに最高裁決定(2007年9月21日第二小法廷決定)を含む司法判断が存在。
- 今後仮に、1件でも異例の対応がなされれば、わが国の金融秩序において極めて重い意味を持つことに。すなわち、債務調整によって、外郭団体の債務に関する債務保証・損失補償が、たとえ一部分でも履行されない事態が発生した場合、金融取引上、わが国の準ソブリンである地方自治体のデフォルト(債務不履行)の発生に相当。
-その場合、民間金融機関の、地方自治体向け債権に関するBISリスクウエート上の掛け目(各国の金融監督当局<わが国では金融庁>が設定。現行0%)を維持することは、かなり困難に。
-この掛け目が引き上げられれば、民間金融機関、とりわけ地域金融機関の経営や地域金融秩序に、大きな影響が及ぶ可能性も否定できず。
-同時に、地方自治体の民間からの資金調達コストも、上昇を余儀なくされる可能性が大。 |
2.総務省における検討の限界
- 本年7月の、総務省「債務調整等に関する調査研究会」再開時点では、「外郭団体の債務処理のために、地方債の発行を一定の条件下で認める」という方向で、今秋にかけ議論が進められる旨が報じられたところ。
- しかしながら、これは、第一義的に各外郭団体自身が負っている債務を、一定の条件の下で親元である地方自治体自身に付け替え、問題を債務の帰属の形を変えて先送りするものに過ぎず、金利上昇時には現状と同様の影響が自治体自身に及ぶなど、本質的・抜本的な解決にはつながらず。
|
3.今後の対応の方向性
- 今後は、「地域力再生機構」構想に関する上述のような問題点・論点に関し、国レベルで議論を行い、この構想を問題の本質的な解決を図るうえでより実効性の高いものへと描き直していくことが必要。
- まず、この問題は、個別レベルで解決可能な問題ではなく、国レベルでその解決に向け取り組むべき問題であることを明確に認識すべき。
- そのうえで、a.個々の外郭団体の事業の継続可能性、必要性の評価等にかかる、一定の客観的かつ横並びの基準を国レベルで策定する、b.その基準をもとに、全ての外郭団体をふるいにかけ、抜本的な対応を必要とするところを選別し、同時に、一定程度国が関与する機関を設立し、その下にそうしたところを移管したうえで対応する、といった方向性も含めて、検討を進めるべきではないか。
|
| 自治体が外郭団体関連で抱えるリスクの試算結果 |
1.金融的手法を多用
- 自治体からの外郭団体(公社・第三セクター)に対する経営支援(財政的支援)の手法としては、補助金といった使い切りの資金以外に、貸した資金が将来返済されることを前提とする金融的な手法、すなわち、c.貸付金(*1)、d.債務保証(*2)、e.損失補償(*3)、という手法が多用されている点が特徴的。
(*1)自治体が直接、外郭団体に資金を貸し付けるもの。
(*2)土地公社・道路公社に民間金融機関等が資金を貸し付け、その債務を自治体が保証するもの。
(*3)主として第三セクターに民間金融機関等が資金を貸し付け、その全部もしくは一部が返済不能となった際の損失を自治体が補償するもの。 |
2.全都道府県・政令指定都市が抱えるリスク
|
3.個別自治体が抱えるリスクの試算結果の評価
|
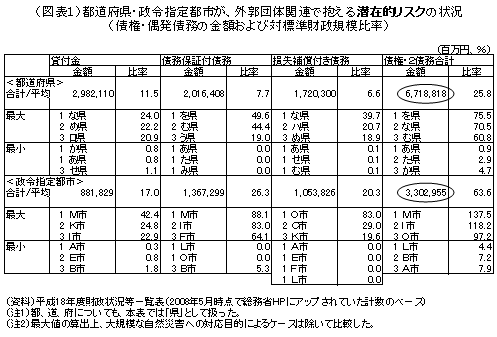 |
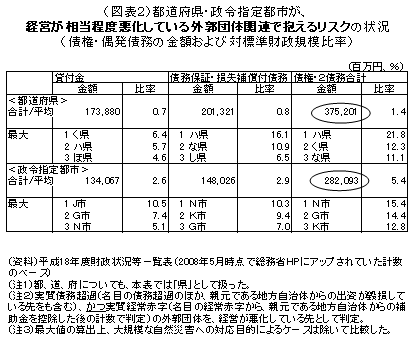 |
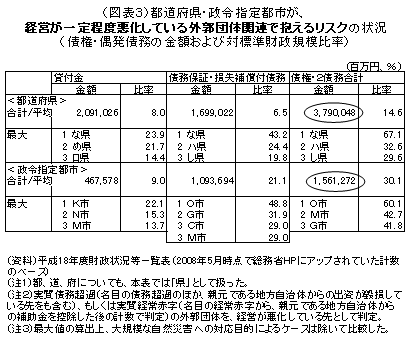 |
4.「将来負担比率」との関係
- 近々(本年9月末)発表される予定の、地方公共団体財政健全化法に基づく「将来負担比率」が相対的に高い自治体の顔ぶれは、本試算結果とは異なる可能性も。
- 同法はあくまで、「地方財政制度を運営するうえでの、公法上の規律付け」。そのため、運用上、財務諸表によらずに外郭団体の経営状況を判定する方法も認められている(後掲参考図表5)ほか、財務諸表によるとしても、外郭団体関連の負担にかかる様々な算入の例外規定が認められている(後掲参考図表7)等の事情が存在。
- よって、将来負担比率が現時点では相対的に余り高くはない自治体のなかからも、金利情勢等の前提条件が変化した場合、外郭団体の経営悪化が、親元の自治体の財政運営にまで影響を及ぼすケースが出てきかねないと懸念されるところ。
|