株式会社日本総合研究所(代表取締役社長:木本泰行 本社:東京都千代田区)では、内部統制の整備活動状況について上場会社を対象としたアンケート調査を2008年4月に実施し、今後の金融商品取引法対応上の留意点をまとめました。
2008年4月から金融商品取引法による内部統制の評価報告書の提出とその内容に対する監査制度が開始されましたが、内部統制報告制度の実務上の取り扱いがまとめられた実施基準、Q&A、実務指針等が公表された現在においても、各社の現場でさまざまな混乱が生じているように見受けられます。
今回、日本総合研究所が実施した「内部統制報告制度取り組みに関する実態調査」では、
1.進捗状況および整備・評価の体制
2.評価対象範囲の設定水準
3.内部統制の整備水準および整備の実務対応 の観点から施行開始時点での上場企業の対応状況を明らかにしています。
本調査により、内部統制の整備において、例えば質的重要性の採用などの判断基準は具体的に何か、有効であると判断できる一定の整備水準はどこか、などが曖昧なままであることが明らかになっています。こうした結果を踏まえ、今後の評価段階では個々の統制の評価を積み上げていくボトムアップ的な取り組みではなく、内部統制評価での自社の基準を確立させ、会社として重要な欠陥となりやすいリスクの高い分野から優先的に評価し整備を進めるトップダウンリスクアプローチへと視点を変えることの必要性を「J-SOX対応上の今後の留意点」の中で提唱しています。
本調査の質問票および調査結果の詳細につきましては、別紙「内部統制報告制度にどう取り組むか(上場会社の取組状況に関する調査結果)」をご参照ください。なお、調査概要は以下のとおりです。 |
|
【調査概要】 |
|
調査対象: 上場会社 3,932社
調査期間: 平成20年4月
調査方法: 質問票を郵送送付、郵送回収
回収数: 463社(回収率 11.8%)
|
|
【結果概要】 |
|
1. 進捗状況および整備・評価の体制 |
|
J-SOX対応をすべて自社で進めている会社は1割程度にとどまる。会計監査人とのアドバイザリー契約をはじめ、約9割弱の会社が外部機関の支援を受けている。会社独自で実施基準を解釈し適応することが困難であったと思われる。
3月期決算会社の進捗状況は、文書化完了までが40~55%となっており、評価の実施はこれからという状況である。また、評価体制の整備など社内でのJ-SOX対応では、規模の小さい会社ほどその負担が大きい。 |
外部機関の利用状況
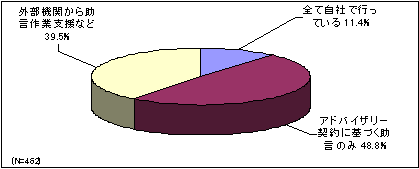 |
|
2. 評価対象範囲の設定水準 |
|
重要拠点の選定基準となる指標の採用についても各社間のバラツキが多い。量的基準としての売上高のみの単一指標を採用しているのは半数強であり、他は複数の指標を質的重要性の判断のもとに採用している。
同様に決算財務報告プロセスの文書化本数、その他の業務プロセスの文書化本数についても、会社毎にバラツキが見られる。特に、売上、売掛金及び棚卸資産以外の勘定科目に関する業務プロセスで、いわゆる重要な3勘定以外の固定資産関連、人件費関連、購買関連の業務プロセスを評価の対象範囲に入れた会社は、それぞれ約5割、約4.5割、約7割に及ぶ。また、これらの業務プロセスの選定については設定した会社の約30~40%が会計監査人のアドバイスを受けている点からみても、いわゆる質的重要性の基準を採用し、自社独自で評価の対象範囲とする判断が困難であったことがわかる。ITの全般統制の評価項目数の設定でも同様である。 |
売上、売掛金及び棚卸資産以外の勘定科目に関する業務プロセスの選択状況
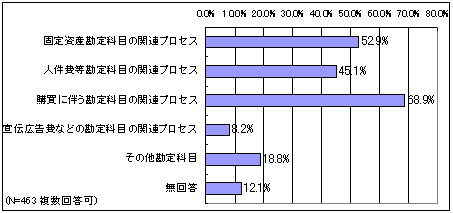 |
|
3. 内部統制の整備水準および整備の実務対応 |
|
整備の具体的な例として販売プロセス統制の整備水準の状況については、会社の規模による違いは見られなかった。ただし小規模会社で比較的簡素な組織構造を有している企業等の場合、その特性に応じた工夫を行っても良いと実施基準にあるものの、どの程度の整備水準を求められているか具体的ではないため、内部統制の整備運用の有効性の評価の段階で混乱する懸念もある。
また、ITのアクセスコントロールでは、整備した整備水準が実施基準が期待する水準であるかどうかが判らないとする会社が2~3割程度も存在した。実施基準では内部統制の整備は基本的に各会社の状況に応じて決めるとされているが、自ら整備水準を設定できない会社は最終的に監査人の判断に従わざるを得ない状況にあることに留意しなければならない。
内部統制の評価においても、個々の評価結果を全体としてどのようにまとめるのか、また、評価結果を業務プロセスの評価にどのように反映させるのかなどの点で実施基準の解釈は難しいと考えられる。同様に、キーコントロールの選定基準やRCMに表記するべき要件、業務フローの記載レベル等も解釈の違いが出てくる分野である。さらに記載の荒さなどの文書化作業レベルが直ちに内部統制の機能の不備として指摘される懸念もないわけではない。
このように実施基準の解釈や適応での各社の状況に応じて対応できる柔軟性が、具体的な実務にあたって戸惑いや混乱を招きやすい要因になっていると読みとれる。
このような中でも、J-SOX対応に対して概ね半数以上の会社は一定の意義があったと評価しているが、オーバーコントロールなどの是正を含め、業務処理の効率化に向けて、内部統制を効率的な仕組みに変革改善していく余地は大きいと考えられる。 |
具体的な対応がわかりにくい項目
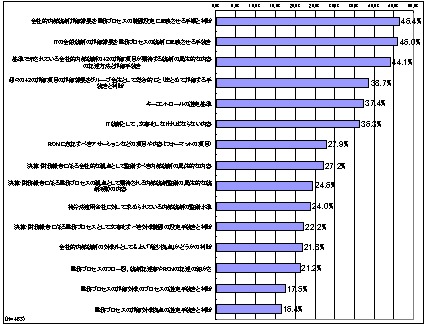 |
|
【J-SOX対応上の今後の留意点】 |
以上のように実施基準の解釈や適用においては曖昧な状況に置かれたままというのが実情である。特に経営者が自社の状況に応じて内部統制の有効性評価を行うことに対して、会計監査人は財務諸表監査の立場から監査リスクに対応しなければならないという両者の立場の違いには十分な考慮が必要である。
今後の評価過程の中では、実施基準の期待する内部統制の整備水準、経営者が有効と判定する内部統制の整備水準、会計監査人の財務諸表監査の立場での有効な内部統制の整備水準の違いをそれぞれの視点から調整していく作業が発生する可能性が高い。評価活動では会計監査人との協議が頻繁に実施されることが予想されるため、以下の二つの点に留意しお互いの立場を理解し尊重する形で対応を進めることが必要になる。 |
|
1. ボトムアップアプローチからトップダウンリスクアプローチへの視点の転換 |
実施基準は標準的な水準として利用するには具体的でなく、解釈の違いにより各社の整備水準が異なることが予想される。評価においても個々の統制項目の評価結果をボトムアップ的に積み上げる方式をとると、あまり重要ではない細かな不備の改善に追われる懸念がある。
内部統制の評価の目的は、財務報告の信頼性の確保に重要な影響を与える統制面での不備がないかどうかを判断することである。この目的を効率的に実現するには、重大な欠陥となりやすい分野から優先的に評価して不備の改善を進める必要があり、それにはいわゆるトップダウンリスクアプローチへと視点を変えることが欠かせない。 |
|
2. 内部統制に関する自社基準を持つ |
経営者による内部統制の評価結果を会計監査人が活用するか否かにかかわらず、経営者は自社の具体的な評価方針を明確にして会計監査人との協議に臨むことが必要になる。したがって経営者は重要な欠陥につながる可能性のある分野の選定や内部統制の有効性の判定を行ううえでの自社の判断基準を予め準備しておくべきである。
内部統制報告制度への準備がある程度完了した現在では、財務報告の信頼性に影響を与える可能性のある問題やリスクの存在箇所の整理はできているはずであり、今後は自社基準の設定を念頭に置いた評価活動を進めることになる。特に本年度は内部統制の評価を実施する初年度でもあり、重要な欠陥につながるかどうかについては前倒しで会計監査人と協議を行い、優先順位の設定を確認するべきである。 |
|
【株式会社日本総合研究所について】 |
株式会社 日本総合研究所は、三井住友フィナンシャルグループのグループIT 会社であり、情報システム・コンサルティング・シンクタンクの3機能により顧客価値創造を目指す「知識エンジニアリング企業」です。システムの企画・構築、アウトソーシングサービスの提供に加え、内外経済の調査分析・政策提言等の発信、経営戦略・行政改革等のコンサルティング活動、新たな事業の創出を行うインキュベーション活動など、多岐にわたる企業活動を展開しております。
(ご案内)
当社は、主として三井住友フィナンシャルグループ関連企業以外のお客さまに向けたITソリューション提供力の一層の強化を図るため、「お客さま向けIT事業」に特化する100%子会社「株式会社日本総研ソリューションズ」を、会社分割により2006年7月3日に設立いたしました。 |
| 項目 | 内容 | | 商号 | 株式会社 日本総合研究所(www.jri.co.jp) | | 設立年月日 | 1969年2月20日 | | 資本金 | 100億円 | | 社長 | 木本 泰行 | | 所在地 | 東京本社
〒102-0082 東京都千代田区一番町16番
03-3288-4700(代)
大阪本社
〒550-10082 大阪市西区新町1丁目5番8号
03-6534-5111(代) |
|