ある1つの新技術が一定期間を経た後にその意味が見出され、具体的な製品化につながり日の目を見るに至るまでには、様々な不確実要因の積み重ねが存在するはずである。
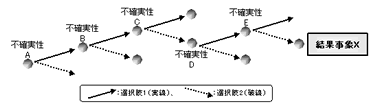
(出所)日本総合研究所ICT経営戦略クラスター作成
例えば上図表の例では、結果事象Xに至るまでにAからEまで五つの不確実性の積み重ねが存在することを示す。つまり、結果事象Xは、不確実性Aで選択肢1が選択され、不確実性B、C、Dを経て、最終的に不確実性Eで選択肢2が選択された結果、実現される。
結果事象Xを「AWGはWDM技術のキーデバイスとして不可欠なものとなる」と仮定すると、各不確実性としては技術的な問題点はいうまでもなく、その他にも「ブロードバンドアクセスの普及」、「通信業界の再編」、「専用線の衰退」、「光ファイバーインフラの整備状況」などが考えられる。それらの積み重ねにより最終的に「AWGはWDM技術のキーデバイスとして不可欠なものとなる」という結果に到達したと考えられる。
このようなシナリオツリー的なアプローチでの認識を適応すると、新しい技術の意味はある特定の時点で確定している訳ではなく、時間の経過とともに変化しているという捉え方ができる。例えば前述の図表を例にとると、不確実性AからEまでが同時に発生する訳ではなく、各不確実性は時間軸上に沿ってある程度順番に発生すると考えられる。ある時点で結果事象Xに到達する確率が30%であったとしても、次の不確定事象の選択如何によってその確率が変動する。つまり、時間軸に沿って各分岐点を選択していく過程で、その意味が時間とともに変化しているという見方ができる。つまり、シナリオツリー的なアプローチにより、時間軸上での動的な変化への柔軟な対応が期待できる。
このシナリオツリーの分岐点数、つまり不確定事象の数、そしてその積み重ねとして得られる結果事象の数が、このデスバレーの「深さ」に対応するという考え方ができる。例えば、ある研究開発対象に不確実性要素が全くなく、「顧客ニーズに合致した製品化が確実である」という結果事象が100%の確率で発生するのであれば、デスバレーは全く無いことになる(投資に対する障壁がない)。これとは逆に、不確定要素が多ければ多いほどデスバレーは深くなることを示す(投資判断が難しくなる)。
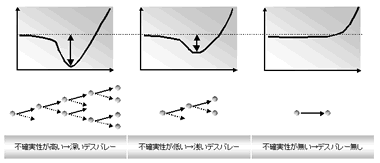
(出所)日本総合研究所ICT経営戦略クラスター作成
このように、単にシナリオツリーだけを用いて将来的なシナリオを考察するのではなく、デスバレーの深さとシナリオツリーとを関連付けることにより、デスバレーの深さを具体的かつ動的に認識することが可能となる。
近年、休眠状態にある知的財産や、製品化には無関係な技術に関する論文、その他具体的な結果として公開されるまでにも至らない数々の研究開発成果などに対する価値評価が注目されている。このようないわゆる「埋もれた技術」に対して、これまで述べてきたような動的な捉え方の適応が組織的に可能になると、思いがけない「掘り出し物」を発見することができるかもしれない。
下図表は、「埋もれた技術」に対して将来的な意味付けがなされる様子をグラフ化したものである。ある時間「t1」においては、技術P(破線)も技術Q(一点破線)もともに「埋もれた技術」であり、この時点では技術Pの方が重要度が高いと仮定する。しかしながら、将来的なシナリオを考慮した場合、技術Qの方が製品化の可能性が高いという場合もある。このように、ある技術に関する真の意味(重要度)を動的に捉えることができるようなシステムを構築することが重要となる。
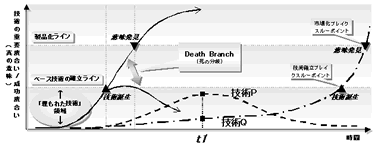
(出所)日本総合研究所ICT経営戦略クラスター作成
前もって新技術の意味を見出すということは、シナリオツリーが描け、各不確実性においてどのような選択がなされるかということが分かっていることが前提条件となる。これは非常に難しい。不確実性を考慮する際にはその技術そのものに関連する事項だけでなく、周囲のビジネス環境など様々な要素を考慮する必要がある。それら全ての不確実性を洗い出し、さらにどのような選択肢が選ばれるかを前もって予測することがいかに難しいかは想像できよう。しかしながら、不確定事象Xという選択肢がどのような確率で発生するかを前もってある程度認識できているかどうかということは、研究開発に対する投資継続の可否判断という重要な経営判断に大きな影響を及ぼすことは間違いない。
本稿は2004年1月23日付『日本工業新聞』の「シンクタンクの目」に掲載された内容と同様である。
[参考文献等]
新保豊、NIKKEI BizPlus連載企画「”IT革命第2幕”を勝ち抜くために」、第38回「ITを駆使する研究開発戦略(上)―研究者の知を高める仕掛け、2003年12月26日
※コラムは執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

