問題解決の先送りへの懸念
合併特例法のもと、平成16年度内の特例法の期限内の実現を目指して、全国各地で市町村合併の動きが活性化している。現在、合併後の新しいまちづくりビジョンの検討や、事務事業の調整など、合併に向けた準備作業が進められている。
しかし、「合併こそが地方行財政改革の切り札」と言われている一方で、筆者が知る得る限り、必ずしも合併後の中長期的な展望を持ちながら、真に自立的で効率的な行政経営を推進していこうという取組みは多くないように思われる。
「まずは、合併を成立させる」という一大ミッションを成し遂げるのは勿論のこと、他方で合併後の望ましい地域経営体制のあり方を具体的に検討し、将来的な筋道をつけることに取り組まなければ、結局は問題解決の先送りになりかねない。
何がおかしいのか
合併後の望ましい地域経営体制の確立を求める上で、現状の取組みには以下のような問題が散見される。
○長期的な観点からの地域将来像や、地域経営体制のあり方等についての議論のないままの合併協議
・短期的なメリット/デメリットに終始する合併議論
・財政の特例制度に対する「鵜呑み」の姿勢
○本来の行政改革を先送りする合併推進
・合併前の駆け込み投資
・建設計画での水ぶくれ需要積算
・高水準・低負担調整による事務事業改善の先送り
○合併後も、組織・体制・意思決定システム等が一元化できないなど、そもそもの合併効果が未発揮
○以上の点をそもそも疑問視しない、合併推進体制の現状
成功する合併に向けて
それでは、上記の問題を回避し、「成功する合併」を実現するためには何に取り組むべきなのか。
(1)長期的視点に立った地域経営ビジョンの立案
地域の将来的・長期的な発展の観点に立ちながら、地域資源の最適配分を目指すビジョンを立案し、それを実行していく体制の構築が必要である。
そのためには、新市建設計画等の策定に先立ち、地域社会動向や施策・事業の現況・課題を十分に踏まえた「地域経営基本ビジョン(新市将来構想)」を立案し、地域において求められる政策・施策の方向性だけでなく、ヒト・モノ・カネの投入資源についての基本的な方針について明確化しておく必要がある。
また、合併後の組織・人材について、職員・組織に求められる役割や資質を明確化し、統合後の組織体制・人事制度についての基本的な方向性などを示す「組織・人材ビジョン」を立案することも考えられる。
ビジョンを受けて、具体的な達成目標やスケジュール等の導入を検討し、実行性のある真の「計画づくり」が求められる。
(2)ビジョンの実現に向けた最適資源配分のシステムづくり
一方、ビジョンの実現に向けた最適な資源配分を実現する具体的な「仕掛け」を検討しておく必要がある。合併協議に先立って、事務事業等の現況の「洗い出し」を、原課を巻き込みながら実施することが不可欠であるが、その際、事務事業の外形的な内容のみならず、その背景や目的、住民ニーズ、事業の成果、コスト構造等についても把握・分析しておく必要がある。
ビジョン実現に資する事務事業等の調整・改廃や、事業体系の再整理、組織編成など、最適な資源配分の検討は、こうした詳細な現況調査を経てはじめて可能になるものである。
現況調査時に共通の調査フォーマットを作成し、詳細なデータベースを構築しておくことで、上記の様々な検討を効率的かつスピーディに実現することが可能である。また、合併後の総合計画の立案やその進捗管理、事務事業評価システムの導入、組織・人事管理等にそのまま活用していくことで、新市における行政体制・事務事業の不断の改革・改善につながることになる。(下図参照)
現況の洗い出しイメージ
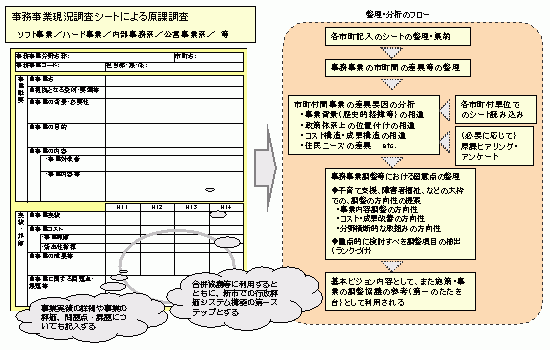
上の図をクリックすると拡大表示いたします
事務事業現状調査~協議・調整~合併後の展開イメージ
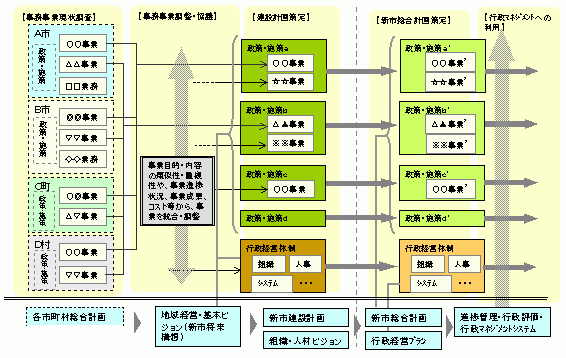
上の図をクリックすると拡大表示いたします
まだ時間はある
先般、平成16年度内の合併特例の期限について、事前に意思決定(協定締結)がなされた場合のみ延長されるとの報道がなされている。事務手続きには、やや時間に猶予はできるといえるが、これから具体的に取組みをはじめる地域にとっても、また既に取組みをはじめている地域にとっても、今一度、真に自立的かつ効率的な地域経営体制を構築するという、合併の原点に立ち返った検討を期待したい。

