| 2004年06月30日 |
| デフレ脱却の展望と金融政策のあり方 |
| 【要 約】 |
| 1.消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、2001~02年にかけて1%近い下落傾向が続 いた後、2003年入り以降、徐々にマイナス幅が縮小。この要因としては以下の二点。 [1]デフレギャップの縮小…90年代末からの物価下落の要因として大きかったのはデフレギャップの拡大。しかし、2003年後半以降景気回復が明確化することでデフレギャップが急速に縮小し、物価下落を緩和させる方向に作用。 [2]輸入浸透度の頭打ち…中国をはじめとしたアジア諸国から安価な製品が急激に流入してきたこともデフレの要因として無視できず。その動きを反映して輸入浸透度が急ピッチで上昇。しかし、この点に関しても2003年以降輸入浸透度が低下傾向に転じており、安価な製品輸入が国内価格体系を押し下げる動きが一巡しつつあることを示唆。 2.労働集約分野におけるアジア諸国との生産コスト格差が縮小し、輸入浸透度の上昇がデフレ圧力として作用した状況が一段落するなか、デフレギャップがいつ解消するかが、デフレ脱却の時期を占う際の重要なメルクマールに。 そこで、一定の前提(潜在成長率:1.5%、実質成長率:2.5%)のもとでGDPギャップがゼロになる時期を試算すると、2005年1~3月期に。この面から判断する限り、2005年中にはとりあえずデフレから脱却する目処が立つものと判断。 3.2005年中にデフレから脱出できる展望が開けてきたものの、以下の理由からデフレ脱却後も基本的にはディス・インフレ基調が続く公算。 [1]生産性上昇が原材料コスト高を吸収 [2]名目賃金低迷がサービス物価を下押し 4.わが国における長期金利と名目成長率の推移をみると、90年代のバブル崩壊後の超低金利局面を別として、80年代の「正常時」には、金利が2~3年のラグを伴って成長率の動きに収束するという動き。 デフレ脱却後も当分の間は「ディス・インフレ」状態が定着することが予想されるもと、景気回復が持続した場合でも、数年先までの名目GDPの安定的な成長率はせいぜ い2%強にとどまるとみられる。 名目成長率との間の過去の関係を前提にすれば、長期金利は2004年度中は1%台後半で推移し、2005年度以降1~2年かけて2%台が定着するというゆっくりした上昇にとどまる見通し。 5.問題はこうしたポスト・デフレ期における物価・金利状況についてのコンセンサスができていないことが投資家心理を不安にさせていることにあり、一定のコンセンサスが形成されれば量的緩和を解除しても大きな混乱は生じないはず。 量的緩和の解除が遅れることの副作用よりも急いで解除することによるリスクの方が大きい点を念頭におけば、2004年度中は量的緩和を継続し、その後も”移行期政策”を導入することで、解除までに十分な時間的余裕を設けるべき。 6.このところ、量的緩和からの”出口政策”についての議論が盛り上がりはじめている。景気が予想外に好調を示し、デフレ脱却の展望が見え始めた現在、金融市場の無用の混乱を避けるためには、今から金融政策正常化に向けたシナリオについて十分に議論し、コンセンサスを形成していく必要。 |
| デフレ緩和の背景 |
| (1)緩和に向かうデフレ |
| イ) | 消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、2001~02年にかけて1%近い下落傾向が続いた後、2003年入り以降、徐々にマイナス幅が縮小し、2003年末から2004年初めにはほぼゼロに。 2004年度に入って、医療費自己負担増加による押し上げ影響が剥落したことから4月に再びマイナスに落ち込んだものの、前年比▲0.2%と前年比下落率は数年前に比べ大幅に縮小。 |
| ロ) | 内訳をみると、食品で前年比プラス基調が定着してきたことが大きく寄与しているほか、被服・履物分野でもマイナス幅の縮小が目立つ。一方、交通通信、教養娯楽分野ではデフレ基調が持続。 |
| (2)デフレ緩和の背景 |
| イ) | CPI下落率縮小の要因 [1]デフレギャップの縮小…90年代末からの物価下落の要因として大きかったのはデフレギャップの拡大。しかし、2003年後半以降景気回復が明確化することでデフレギャップが急速に縮小し、物価下落を緩和させる方向に作用。 [2]輸入浸透度の頭打ち…中国をはじめとしたアジア諸国から安価な製品が急激に流入してきたこともデフレの要因として無視できず。その動きを反映して輸入浸透度が急ピッチで上昇。しかし、この点に関しても2003年以降輸入浸透度が低下傾向に転じており、安価な製品輸入が国内価格体系を押し下げる動きが一巡しつつあることを示唆。 |
| ロ) | 計量的検証 以上の点を計量的に検証すれば、GDPギャップ、輸入浸透度ともに、CPI変動率の原因となっている可能性を示唆する結果に。すなわち、GDPギャップおよび輸入浸透度はCPI変動率に対して「グレンジャーの意味で因果関係がある」可能性を相応の有意水準で棄却できず。 |
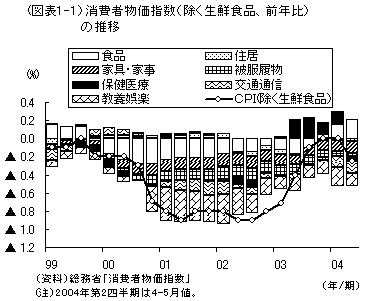 |
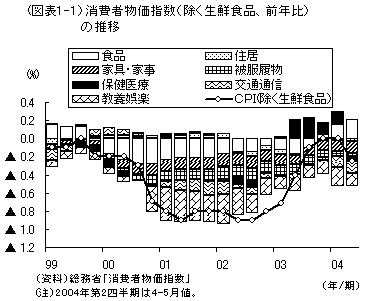 |
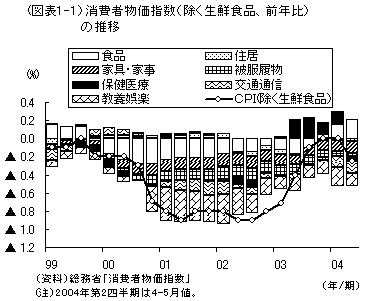 |
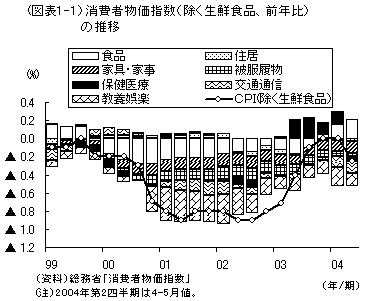 |
| 底流に日中の貿易・産業関係の潮流変化 |
| (1)わが国にとっての中国の位置付けの変化 |
| 中国の日本企業の位置付けは、90年代末から2002年ごろまでは「生産拠点」であったものが、 昨年ごろからは「販売市場」へと徐々にシフト。これを映じて対中貿易収支が大きく改善する方向。 すなわち、香港経由で中国本土に輸出されるケースが多い点を勘案し、中国・香港合計で貿易 収支の動きをみると、デフレ懸念が高まった2001年には、中国からの輸入品急増を受けて貿易収支が赤字化。しかし、その後鉄鋼・一般機械をはじめとした中国向け輸出が急増してきた結果、2002年半ば以降は貿易黒字に転じ、中国の景気過熱に伴い黒字幅はこのところ大きく拡大。 |
| (2)日本企業の生産体制の変化 |
| 日本企業はここ数年来、労働集約分野への中国・アジアへの生産拠点の移管を進める一方、国内工場を高付加価値製品の生産拠点として位置付け、デフレに強い製品開発を推進。 すなわち、国内では2000年以降、過剰設備の廃棄・集約が進展する一方、国外生産が困難な高度な技術分野を中心に国内生産力の維持・強化が行われ、国内生産の選択と集中が進展。この結果、輸出品目の高付加価値化が従来を上回るスピードで進展。 |
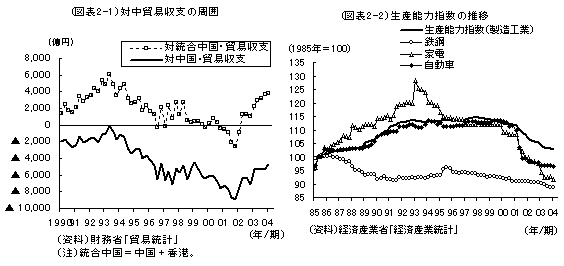 |
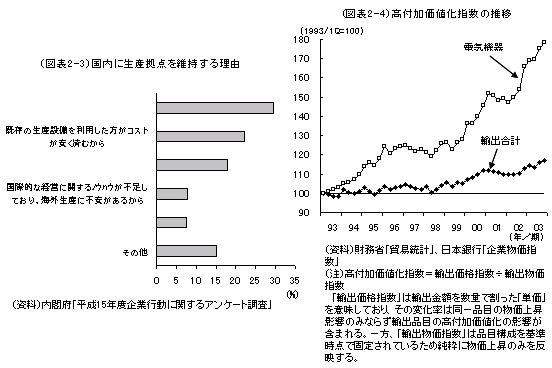 |
| 2005年中にデフレ脱却、その後も物価は安定 |
| (1)デフレ脱却の時期 |
| イ) | 労働集約分野におけるアジア諸国との生産コスト格差が縮小し、輸入浸透度の上昇がデフレ圧力として作用した状況が一段落するなか、デフレギャップがいつ解消するかが、デフレ脱却の時期を占う際の重要なメルクマールに。 |
| ロ) | そこで、一定の前提(潜在成長率:1.5%、実質成長率:2.5%)のもとでGDPギャップがゼロになる時期を試算すると、2005年1~3月期に。GDPギャップとCPIには過去半年~1年程度のラグがみられるため、今後とも景気が順調に回復していけば、2005年中にはとりあえずデフレから脱却する目処が立つものと判断。 |
| (2)物価安定は持続 |
| 2005年中にデフレから脱出できる展望が開けてきたものの、インフレ率が加速していく公算は小。以下の理由からデフレ脱却後も基本的にはディス・インフレ基調が続く公算。 [1]生産性上昇が原材料コスト高を吸収 [2]名目賃金低迷がサービス物価を下押し |
| (3)生産性上昇が原材料コスト高を吸収 |
| 原材料コストの高騰が川上段階の物価を押し上げはじめているものの、川下に進むにつれて上昇圧力は各段階で吸収されている状況。これは競争激化を背景に企業が不断の生産性向上を行っているため。2000年以降の単位労働コストの低下スピードは70年代以降では最も速いペース。 |
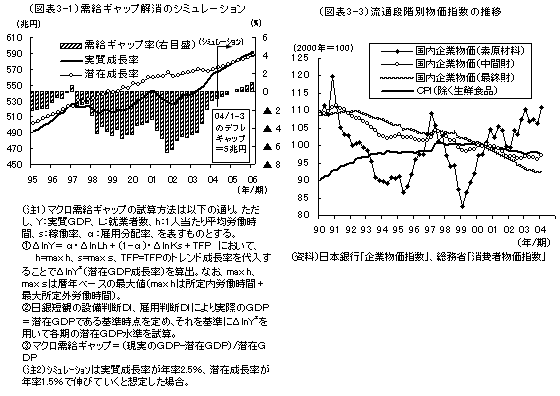 |
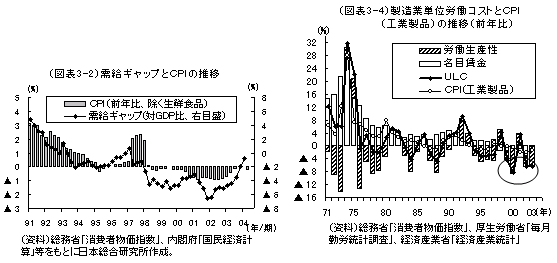 |
| 人件費抑制スタンスがインフレを抑制 |
| (4)名目賃金低迷がサービス物価を下押し |
| イ) | 素材価格の上昇が続けば、消費者物価段階の財価格は緩やかながらもプラスに転じてくる可能性がある一方、サービス価格は引き続き横ばいないし弱含みの動きに。この背景には、企業の人件費抑制スタンスが継続されるなか、消費者の価格に対する厳しい目が変わらない一方、人件費コストの大きいサービス業に合理化の余地が生まれているとの事情。 |
| ロ) | 実際、消費者物価と名目賃金の関係をみると、両者の間には相互に因果関係が認められる(グレンジャー・テストの結果) |
| (5)根強い企業の人件費抑制スタンス 日本企業は中期的に予想される以下のような経営環境を背景に、今後とも人件費抑制スタンスを維持する見通し。 |
| イ) | 国際的な競争の激化…欧米企業のみならず、中国・アジア系企業が着実に競争力を強化するなか、日本企業は不断のコストダウンに取り組む必要。とりわけ、技術革新スピードの速いエレクトロニクス分野では、価格下落テンポが速く、一段の効率化が迫られている状況。 |
| ロ) | 将来的な社会保険料の持続的上昇…厚生年金保険料が今後2017年までに4.72%ポイント(労使折半)引き上げられるほか、将来パートタイマーにも社会保険加入が広げられる可能性。さらに、健康保険料・介護保険料の引き上げも不可避な状況。確定している厚生年金保険料引上げだけで企業収益を3.5兆円圧迫するものと試算され、これらの保険料は賃金に比例的にかかるだけに、今後企業の賃金抑制を促す要因となる可能性大。 |
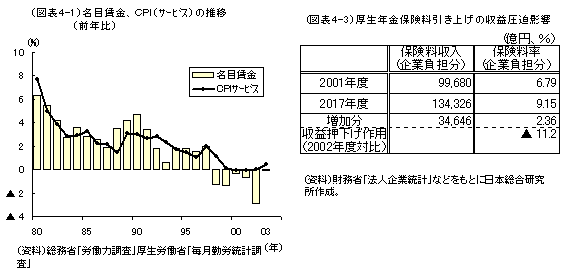 |
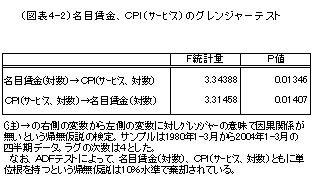 |
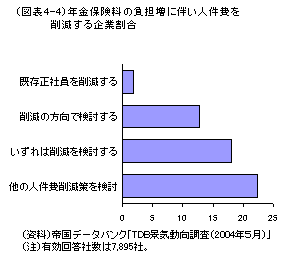 |
| ポスト・デフレは物価の二極化 |
| イ) | 平均でみた消費者物価の下落率は縮小してきているものの、全般的に物価下落幅が縮小しているのではなく、一部に大幅に上昇する品目(輸入ブランド品、婦人・子供向け衣類)が出て来た結果として、平均値としての下落率が緩和されているという形。下落傾向にある品目はなお数多く存在。統計的にみても、2001年度から2003年度にかけて、「二極化」の結果として物価変動率の分散(バラツキ)が拡大していることが確認される。 |
| ロ) | 以上の物価の二極化という実態は、今回のデフレの緩和が需要サイド主導よりは供給サイド主導で生じていることを示唆。すなわち、インフレ期待が強まり、消費者の低価格志向が消滅してしまったからではなく、企業努力の成果として、消費者に受け入れられた高付加価値商品の価格が主に上昇。 |
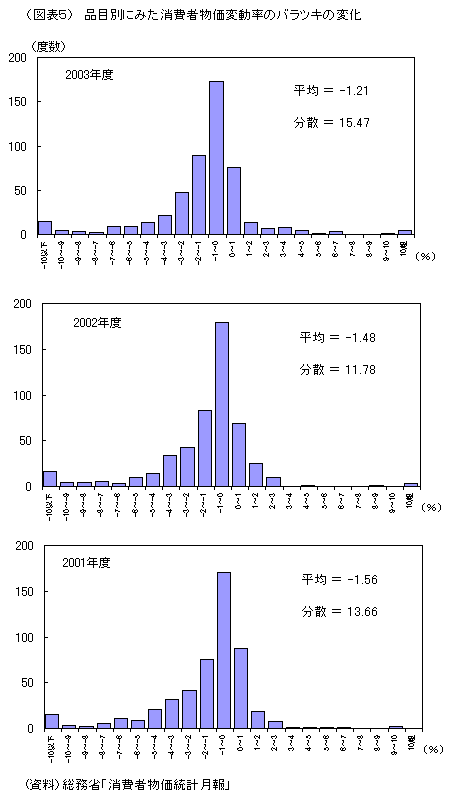 |
| 長期金利はどこまで上がるか |
| (1)長期金利と名目成長率の相関 わが国における長期金利と名目成長率の推移をみると、90年代のバブル崩壊後の超低金利局面を別として、80年代の「正常時」には、金利が2~3年のラグを伴って成長率の動きに収束するという動き。 デフレ脱却後も当分の間は「ディス・インフレ」状態が定着することが予想されるもと、景気回復が持続した場合でも、数年先までの名目GDPの安定的な成長率は2%強にとどまるとみられる。名目成長率との間の過去の関係を前提にすれば、長期金利は2004年中は1%台後半で推移し、 2005年度以降1~2年かけて2%台乗せが定着するというゆっくりした上昇にとどまる見通し。 |
| (2)長期金利の均衡水準 長期金利、実質成長率、GDPデフレータの長期的関係を前提にすれば、長期金利の水準決定要因としては、実質成長率よりもデフレータによる影響が大きい。このため、実質成長率が高くともデフレが続く2004年度中の長期金利は1%台後半で推移。その後、実質成長率が巡航スピードに減速する一方デフレが緩和される結果、2005年度中に2%台に乗せるという、マイルドな上昇にとどまる見通し。 |
| (3)戦後米国の経験からの含意 ちなみに、戦後の米国の長期金利の水準の推移をみると、70年代までは金利が名目成長率を持続的に上回ることはなかった。80年代以降は金利は名目成長率よりも高まるが、これは巨額の財政赤字によるリスク・プレミアムが経常収支の赤字化により顕在化したため。わが国は現在のところ経常黒字国であり、国債の大半が日本国民により保有されているため、財政リスク・プレミ アムが直ちに顕在化する状況には至っていない。 |
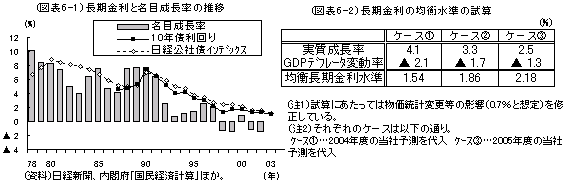 |
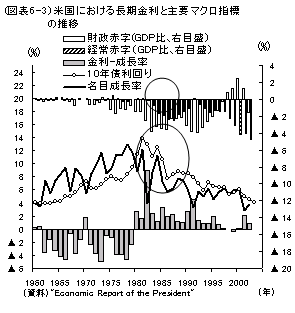 |
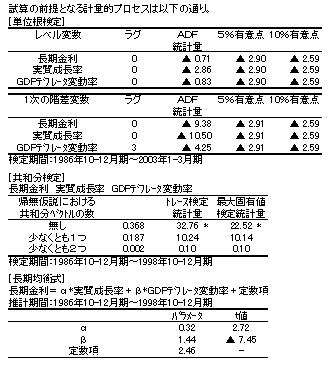 |
| 量的緩和解除のタイミング |
| (1)量的緩和早期解除の功罪 |
| イ) | 早期解除に伴うリスク [1]金利上昇のインパクト…金融政策正常化後の金利体系についてのコンセンサスが存在しないもとで、量的緩和の解除を急げば金利が急騰するリスク。その場合、過剰債務解消が遅れる中小企業非製造業分野で倒産が急増する恐れ。 [2]業況改善の二極化…平均値で業況が改善しているとはいえ、90年代後半以降では業況の二極化が最も色濃く発生。平均値で語られる以上に、依然業況の悪い企業が多く存在することに留意する必要。 |
| ロ) | 解除遅滞の副作用 [1]インフレ加速の可能性…フィリップス曲線を前提とした場合、持続的に失業者を減らすことが可能な経済状態(需要不足失業率=ゼロ)における物価上昇率は2%弱。これは、インフレを加速させない物価上昇率(*)に対応するとみられるため、CPIがプラスに転じてきても小幅であれば、量的緩和解除を急ぐ理由はない。 [2]資産インフレの可能性…一部の都市部地価等を除き、全般的な資産インフレのリスクは小。(*)いわゆる「自然失業率」に対応するもの。(図表3-1)におけるGDPギャップ=0となった状態は①設備面での調整進展によるデフレ緩和影響を含んでいる、[2]労働時間延長によるデフレ緩和影響のみを算定し、雇用量増加による影響は勘案していない、という二点において、ここで考えている状態と異なる。 |
| (2)量的緩和解除のタイミング |
| イ) | デフレ脱却後もディス・インフレ状態が持続することが予想されるなか、長期金利は名目成長率の回復にややラグを伴って上昇するが、その水準は今後2~3年かけて2%台乗せが定着するという、緩やかなテンポにとどまる見通し。問題はこうしたポスト・デフレの姿の物価・金利状況についてのコンセンサスができていないことが投資家心理を不安にさせていることにあり、コンセンサスが形成されれば量的緩和を解除しても大きな混乱は起こらないはず。 |
| ロ) | 量的緩和の解除が遅れることの副作用よりも急いで解除することによるリスクの方が大きい点を念頭におけば、2004年度中は量的緩和を継続し、その後も”移行期政策”を導入することで、解除までに十分な時間的余裕を設けるべき。 |
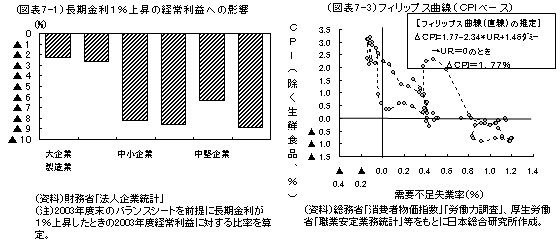 |
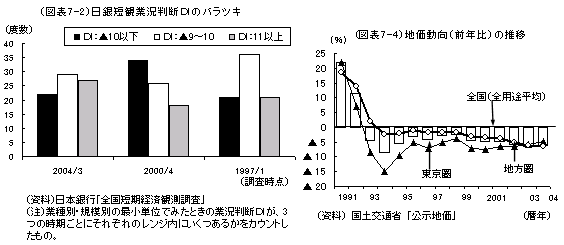 |
| ポスト・デフレに向けた金融政策のフレームワーク |
| イ) | このところ、日銀の要人の発言も含め、量的緩和からの”出口政策”についての議論が盛り上がりはじめている。景気が予想外に好調を示し、デフレ脱却の展望が見え始めた現在、金融市場の無用の混乱を避けるためには、今から金融政策正常化に向けたシナリオについて十分に議論し、コンセンサスを形成していく必要。その際、クリアすべき論点は[1]デフレからの確実な脱却、[2]長期金利の安定、[3]短期金融市場の正常化の三点。 同時に重要なのは、「ポスト・デフレに向けた新しい金融政策のフレームワーク」を提示することにより、政策決定の「透明性」を向上させることで市場とのコミュニケーションを深め、安定した政策運営が行なわれやすい環境を創り出すこと。 [2]業況改善の二極化…平均値で業況が改善しているとはいえ、90年代後半以降では業況の二極化が最も色濃く発生。平均値で語られる以上に、依然業況の悪い企業が多く存在することに留意する必要。 |
| ロ) | そうした問題意識に基づき、あくまで議論のたたき台として、ポストデフレに向けた望ましい金融政策のあり方を提示してみれば以下の通り。 |
| 【第1ステップ:現行量的緩和の維持】 当面は現状の量的緩和を継続し、2004年10月の『経済・物価情勢の展望』発表に併せ、 「量的緩和の段階的縮小」という”移行期政策”を導入することを表明(当局が政策変更を緩やかに行おうとしている意思を示すことで金融市場に安心感を与える)。 ※インフレ参照値は当面は時間軸効果を持つにしても、日銀が一定程度のインフレを許容するとの見方から長期金利を上昇させてしまうリスクがあり、この段階で導入すべきではない。 |
| 【第2ステップ:移行期政策と新しいフレームワークの提示】 3つの”解除条件”の充足、ペイオフ解禁の影響を見極めたうえで、日銀当座預金残高の漸次縮小に着手。この間、コール金利はゼロのまま推移する見通し。具体的な残高縮小については、一定のレンジを提示しながらそのレンジを徐々に切り下げ、景気・物価動向に応じてレンジ内で柔軟に調整(予想外に景気が下振れる際にはレンジの引き上げも許容する)。 同時に、透明性向上を通じた安定した金融政策運営の環境整備の観点から、以下のような新しいフレームワークを提示。 |
| ・ | 「政策参考指標」として、いくつかの経済指標を提示することで、日銀が政策決定上重視している要素を明確化し、市場とのコミュニケーション力を向上。具体的には、インフレを加速させない失業率(NAIRU)、単位労働コスト、GDPギャップ、資産価格指標、 実質実効レート等が考えられるが、局面により政策参考指標は柔軟に入れ替える。 |
| ・ | 「インフレ参照レンジ」の導入を表明。ただし、導入時期は第3ステップ。イングランド銀行方式に習い、物価指標の2年後の予測値がインフレ参照レンジに収まるように政策変更を行う方式とする。なお、ここでのインフレ参照レンジはわが国のデフレ進行下で議論されたインフレ期待惹起のためのものではなく、あくまで伝統的な金利政策のもとで物価安定を図る一つのツールに過ぎない。 |
| 【第3ステップ:新しいフレームワークに基づく金利政策への移行】 日銀当預残の縮小進捗後、短期金融市場の機能正常化および景気・物価動向を見極めながら新しいフレームワークに基づく金利政策へ移行。「政策参考指標の公表」および「インフレ参照レンジ」の導入は、金融政策の柔軟性を奪うものであっては本末転倒であり、あくまで中央銀行と市場のコミュニケーションを円滑かつ密にすることにより、中央銀行の独立性を維持しつつ金融政策のパフォーマンスを向上させることが趣旨。 ※なお、上記の政策移行時期の目処は、第2ステップへの移行が2005年後半、第3ステップの移行は2006年後半となるが、景気・物価動向で柔軟に決めるべき。 |
| ハ) | 一方、金利体系正常化の円滑な実現は、単に日銀のみの課題ではなく、マネーフロー正常化に向けて政府も同時に取り組んでいく必要。 [1]強固な金融システムの確立に向けた金融機関の体質強化・再編推進 [2]健全な金利決定メカニズムの形成の前提となる公的金融の正常化(民業の補完化) [3]財政健全化に向けた説得性あるビジョンの提示 |
| 以上 |

