Nikkei Net「BizPlus」連載企画 "IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第46回「"新・この国のかたち" 【2】-コモンズの上のダイナミックな競争(下)」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2004年4月22日
第45回では、ブロードバンドインフラ整備のための管路や光ファイバーは、国民のコモンズ(公道)としての位置付けにふさわしいのではないかを概観した。スウェーデンの場合それは、管路やダークファイバーに関するコロケーションなどのルール化(ソフトウェア的な手立て)、さらにはストーカブ公社による光ファイバーインフラ構築(ハードウェア的な手立て)により、その枠組みをつくってきた。
(1)インフラ設備間の競争を促したスウェーデン独自の方式
インフラ設備間の競争を促したスウェーデンモデルは、他国とは一線を画すものである。スウェーデンのダークファイバー市場において、ストーカブ公社とテリアとの間の競争が起き、結果、同国のブロードバンドサービスの普及が大きく促進された。
ドミナントのTeliaと新興のストーカブ公社との間で「インフラ間の競争」が促され、結果、光ファイバーインフラに接続することでサービスが提供できる、多くのベンチャー等の事業者が生まれた。また、共通の光ファイバーインフラの上でダイナミックなサービス競争がもたらされ、同国のブロードバンドインターネットの普及は、他の欧米諸国に比べ大きく進んだ。
具体的には次のようなことである。図表をご覧頂きたい。
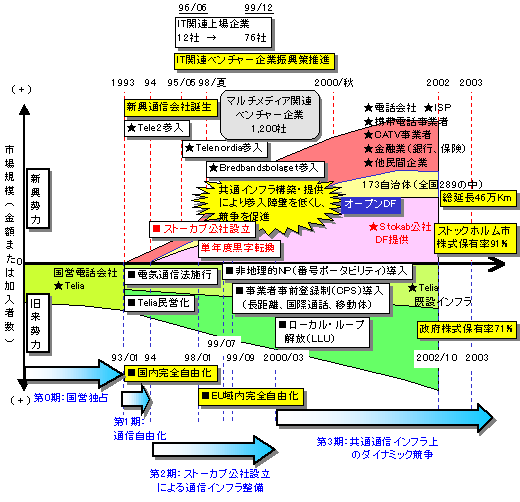
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成
通信自由化の【第1期】(1993年~1994年)、ストーカブ公社設立による通信インフラ整備の【第2期】(1994年~1999年)、共通通信インフラ上のダイナミック競争の【第3期】(2000年~2003年)、そして、【第4期】(2004年以降)には、このダイナミック競争の促進が続くのか、といった4つの区分とすることができよう。
政策面では、【第1期】に電気通信法施行、Teliaが民営化された。【第2期】では、1994年にストーカブ公社が設立され、IT関連ベンチャー企業振興策推進、非地理的番号ポータビリティ導入、事業者事前登録制導入、IT法案(パソコン法案)成立、そして、IT委員会が発足した。続いて【第3期】では、LLU解放がなされ、公的部門管理局(SAPM:Swedish Agency for Public Management)、公的部門の 24時間オンラインサービスの提供が決定された。2000年3月には「全国民のための情報社会(An Information Society for All)」が発表され、2003年までの3年間に6億クローネ(約87億円)がICT(情報通信技術)インフラ整備に投入された。
旧来勢力の動きとして、【第2期】には1994年Teliaが ATM交換機の設置を始め、1995 年末までには同国全土でATM網への接続が可能となり、1997年にデジタル化が完了。【第3期】にはフィンランド大手通信会社Soneraと合併、 Telia・Soneraが生まれた。その後、2004年2月Teliaは上下128kbpsのIP電話サービスを開始した。これは、a)電話通話料は加入者同士無料であり、b)TV電話、チャット、電子メールが利用可能で、c)インターネットアクセスは500kbpsから10Mbpsの4つのサービスが用意されているものである。
新興勢力の動きとしては、【第1期】にTele2が参入。【第2期】にはTelenordia、Bredbandsbolaget(B2)など新規参入が相次いだ。【第3期】には一層の競争促進により新規参入は大きく増えた。一方、これら新興事業者は事業拡大を一気に目指したものの、市場は需給バランスを崩し、B2などにおいては、海外サービスからの撤退を余儀なくされるところもあった。しかしその後、再び積極的な動きが見られ、2004年1月時点で BoStreamは、DSLサービスにおいて9万以上の一般加入者、3,000のビジネス加入者の契約を獲得し、256kbpsから1 Mbpsの3つのサービスに加え、ストックホルムでは26Mbpsのサービスを提供している。
(2)光ファイバー基盤の上のダイナミックな競争
スウェーデンの通信市場を総括すると、【第1期】の成果は概ね良好といえる。それは、市場競争の導入に伴い、新興事業者の参入も出てきて、事務用や住宅用ユーザーの電気通信料金が値下がり、事務用では購買力平価米ドル換算税抜きで、1992年の440.92ドルから1993年には434.17ドル(前年比1.6%%減)、そして、1994年には372.36ドル(同14.2%)まで下がった。
【第2期】の成果として、ストーカブ公社の設立で安価なダークファイバー市場が登場したこと、家庭のパソコン保有率が48%から67%へと急激に上昇したことでEC市場が大きく拡大した。またICT分野での雇用は6万人増加(同期間の新規雇用者数14.1万人の43%)した。さらに、B2社の社内LAN 接続を直接提供するなどのモデルやら、さまざまな新しいブロードバンド事業が相次ぎ開始された。
【第3期】の成果としては、この前の期ではストーカブ公社のシェアは100%に近く、ドミナントのTeliaは動かなかったが、この時期にはストーカブ公社とTeliaの光サービス市場でのシェアはほぼ50%ずつとなるなど、インフラ間の競争が進展した。また、スウェーデンではこの時期、オンラインバンキングの利用率が世界1位(2002年米Nielsen/NetRatings調査)であったり、ITに注力している世界55か国で4年連続首位のパフォーマンスを示している(IDC調査)。さらに、2000年でのベンチャーキャピタルの平均成長率は過去5年間で188%(3i社、PWC調査)を記録するなど、ベンチャー企業の活性状態が続いた。あるいは、学校でのインターネット接続は100%であり、うち50%がブロードバンドに接続しているなどの取組みにも成功した。
ではストーカブ公社の事業パフォーマンスはどうであったか。日本の道路公団などとは規模の点で比べようはないが、同公社の2000年~2002年の総収入は45億円から67億円(47%増)へ、EBITDA(Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization:金利・税金・償却前利益)、すなわち、支払利息・法人税・減価償却費を差し引く前の利益は24億円から35億円(49%増)へ、あるいは税引後最終利益は6.4億円から5.1億円へ転じている。税引後最終利益だけはわずかに減じているが、最終利益はしっかり確保している。同公社は従業員数140人前後であるにもかかわらず、光ファイバーは総延長で4,000km(50万心km)から5,000km(100万心km)へ拡張した。
具体的には次のようなことである。図表をご覧頂きたい。
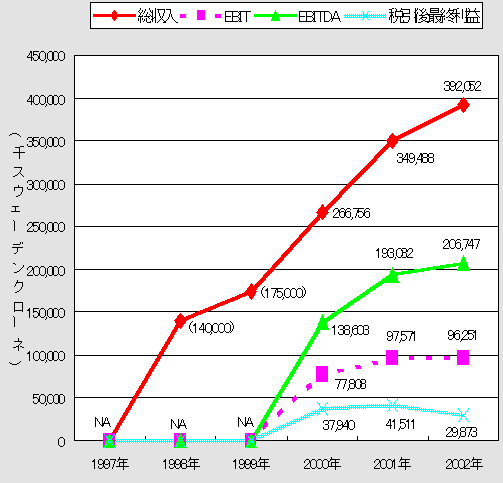
(注)◆ 「総収入、EBIT、減価償却費、EBITDA、税引後最終利益の単位」:1,000スウェーデンクローネ(2003年10月、1スウェーデンクローネ=約17円)。◆「( )内の数字」:ストーカブ公社アニュアルレポートのグラフから概算。◆「EBITDA」:EBIT+減価償却費+有形固定資産売却・除却損(この項目は除いた)の意。
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成
人口約894万人(2004年3月)のスウェーデンのGDPは2,403億ドル(2002年OECD統計)であり、これは日本の同3兆9,339億ドルの 6%程度であることを考えると、さしずめ2002年度の総収入規模が1,120億円(67億円の100分の6倍)程度となる公社ということだ。
投資については、同年度約150億円(2002年度の同社アニュアルレポートによると8億7,400万クローネ)、すなわち総収入の13.4%をかけて光ファイバー等の建設および設備などの拡充を行っている企業となる。この150億円を日本の市場規模に換算(100分の6倍)すると2,500億円。スウェーデンの経済規模はわが国よりもかなり小さいが、光ファイバーインフラの整備割合は決して小さくない。むしろ、わが国と比べかなり大きいのだ。
NTT東西の光ファイバー投資規模は、これまで毎年2,000億円程度の水準にある。2003年度のアクセス網の光ファイバー化向け投資は2,300億円程度(NTT東900億円+NTT西1,400億円)である。これは、NTT東西における2002年度総収入4.23兆円(東2.18兆円+西2.05 兆円)の5.4%(東では4.13%、西では6.83%)を占める。つまり、厳密には過去のストック(総投資量)で判断せねばならないが、過去数年程度のみの比較では、ストーカブ公社の投資割合が13.4%であることを考えると、スウェーデンではNTT東西以上の割合で同国への光ファイバー整備を進めていることになり、大変興味深い。
(3)市場競争のみでは限界のあるダイナミックな競争の創出
スウェーデンの場合、ドミナントキャリアであるテリアに対抗する新興事業者として、それにふさわしい民間企業が存在しなかったため、公社(ストーカブ)を新設して、市場競争をつくり出した。"公社"というと、自由化の進んだ先進国では時代を逆行する響きがある。
しかし、ブロードバンド産業の発展を促すには、あるいは国家の産業競争力を高めるには何が、その国にとって最も有効かを考えることが大事である。
スウェーデンの場合、それに公社という対抗軸をもってきた。そして、テリアの重い腰を上げさせた。さらには、テリア自身もストーカブ公社の顧客となっている(同公社の光ファイバーを利用する)ことで、レッシグ教授のいうコモンズの「物理層」(公道)が、かなり整備されたかっこうになった。
一方、とくに米国では、民間事業者間の市場競争を金科玉条とする政策的な伝統がある。しかしながら、ブロードバンドの普及には、通信バブルを経た今日、特に韓国や日本に大きく水を開けられたという危機感も根強く、先日(2004年3月)ブッシュ政権が光ファイバー整備を含むブロードバンド政策への転換を示唆する動きも出てきた。これは米国のこれまでのブロードバンド産業政策の失敗を、事実上認めたとも解釈できよう。
1985年より前、NTTは電電公社であり、このときの電話網の建設は国が主導で行った。つまり、多大な投資が不可欠な自然独占性の働く領域では、その方式が合理的であった。そして、NTTがメタル網という負の資産問題に悩むなか、新たなデジタルインフラ(光や無線)を今後、全国レベルのアクセス領域までを整備するには、まだ膨大な投資を強いられる。
ユニバーサルサービスやデジタルデバイド問題などを考慮に入れ、全国規模の光ファイバーインフラ整備を行うとなれば、とても採算が合うものではない。電話会社も電力会社も投資のインセンティブ(回収の目途)を見出せない。つまり、とくに電話会社がメタル網の不良資産化を目の前にして、新たなデジタルインフラを整備するという、民間事業者のみの競争に委ねるのは限界があるのだ。
もちろん、そんなインフラは今の日本には無用であるということであれば、公的枠組みを云々してまでやるということではない。しかし、e-Japan戦略IIにおいても、わが国のブロードバンド産業の競争力を高めることは最重要課題であろう。
「この国のかたち」シリーズにおいて、後日、光ファイバー投資による経済効果についてもその見通しを示したいが、光ファイバー投資がもたらす経済効果は、2003年末に決定した地上デジタルTV放送の効果よりずっと大きいのである。
その前に次回は、「通信と放送の垣根論争の行方」について考えてみたい。つまり、技術革新により「放送」は、「通信」手段でできてしまう。放送は通信の一形態とみなすことができるにもかかわらず、いまだ両者の垣根があることは、経済合理性の観点からは不自然である。

