"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第45回「"新・この国のかたち" 【2】-コモンズの上のダイナミックな競争(上)」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2004年4月15日
情報通信産業版「この国のかたち」では、今回、スウェーデンのストーカブ(Stokab)公社方式などを例に、「コモンズ上のダイナミック競争」について概観してみたい。ブロードバンド時代においてその国の屋台骨(バックボーン)となる光ファイバーの敷設に関することである。
ドミナント電話会社(キャリア)が所有するメタル電話網に相互接続することで、他事業者は通信サービスを行ってきた。ドミナントキャリア所有のボトルネック施設に対するアンバンドリング化(ボトルネック施設等の分離)、すなわち、接続業者が必要なもののみを細分化して利用できるようにすることで、 ADSLブロードバンド市場は急速な発展を遂げた。次代の光ブロードバンド市場ではどうだろうか。
(1)コモンズとしての管路が自由に利用されれば
スタンフォード大学のローレンス・レッシグ教授の整理によれば、物理層、コード層、コンテンツ層の3つで区分した情報通信産業のレイヤーにおいて、インターネットは下の2つの層が「フリー(自由)」であった。
レッシグ教授は、この「フリー」の意味を重視する。それゆえにインターネット上に、大規模かつ多様な技術革新(イノベーション)がもたらされたと。社会におけるコモンズの必要性をインターネットの原理と発展形態に重ねて分析している。いわく、コモンズの表象するものは「フリー」です。「フリー」でない社会は停滞、後退し、「フリー」である社会は発展する、と。原理(コード)として「フリー」の要素そのものを内包していたインターネットが、コード層およびコンテンツ層において所有権の強化がなされ、その「フリー」が危機に直面していると説く。
ここで「フリー」とは、人がそれを他人の許可を得ずに使えること、あるいは必要とされる許可が中立的に与えられていることを意味する。同教授の著書名ともなっている『コモンズ』とは、共有地と訳され、例えば、私たちの周りにある公園や公道のようなもの。利用料金はゼロでも対価を取ってということでもよい。ポイントは、アクセス料金が必要な場合であっても、それが中立的で一貫して適用され、無許可で使えるものであればよい。
インターネット(IP網)は今や、誰もが自由に活用できるコモンズとなった。一方、光ブロードバンド網の整備はIT先進国のなかでもまちまちであるが、最近のバックボーンは概ね光ファイバーで敷設されている。問題はアクセス網、つまり電話局や基地局から各家庭またはエンドユーザーまでの加入者線である。ドミナントキャリアの場合、このアクセス網を自前で保有している。スウェーデンではかつての国営Telia(テリア)というドミナントキャリアが所有している。ドミナント所有のアクセス網相当のネットワークを競争的事業者が自前で敷設できるようになれば、インフラ間の競争が期待できる。アクセス網を敷設するためには、そのための空間が必要になる。つまり、とう道、電柱などを含む管路(conduit)の開放が求められる。
管路領域では自然独占性が働き、国が主体で整備したものであれば、国にとってコモンズ(共有の資産)ともいえよう。コモンズとなれば、競争的事業者は自由にそれを利用できることになり、アクセス網の構築も可能となる。ただ、アクセス網敷設には膨大なコストがかかる。したがって、資金力のない競争的事業者にとっては、ドミナントのアクセス網にただ接続して、それを利用するしかない。この相互接続のスキームでは、利害が相反する両者間でさまざまなあつれきを生むことが必至である。これが旧来からの相互接続問題といわれるものだ。
(2)管路やダークファイバーに関するコロケーションなどのルール化(ソフトウェア的な手立て)
管路が自由に使えるようになれば、あるいはドミナントと同等の条件で競争的事業者が利用できるようになれば、管路に光ファイバーを敷設し各事業者はインフラを構築できる。その際、財務力に乏しい新興の競争的事業者(新興キャリア)が、光ファイバーを使って通信ネットワークを構築することは難しい。そこで、新興キャリアは自身の通信ネットワークを構築するために、それに必要な装置やダークファイバーをドミナントキャリアから借りて、ドミナントキャリアの建物やとう道、電柱など含む管路に設置する(これをコロケーションと呼ぶ)方法を活用する。
しかしながら、ドミナントキャリアからの新興キャリアへの妨害(貸し出しを渋る、作業完了までの期間を長引かせる、貸し出し価格を高めに設定するなど)により、コロケーションが機能しないことを回避するために、規制当局が両者に分け入りルール化することで、解決をはかることがなされている。
例えば、EU相互接続指令 (Directive 97/33/EC)のArticle 11 (Collocation and facility sharing)では、「事業者の設備設置権が法律によって保証されている場合、各国の規制当局は、管路等設備の共同利用を促進しなければならない。コロケーションもしくは管路等設備の共同利用に係る協定は、通常は、当事者間の商業的および技術的協定とすること。また、各国の規制主管庁は、紛争の解決のため介入することができる。加盟国は、適切な公の諮問期間を経てのみ、費用配分を含む管路等の共同利用に係る方法を義務づけることができる」とされている。
(3)ストーカブ公社による光ファイバーインフラ構築(ハードウェア的な手立て)
スウェーデンでは1994年に電気通信市場の完全自由化がなされたが、テリアの独占的地位を突き崩すほどの動きは見られなかった。テリア所有のアクセス網に接続した状態で、コロケーションなどのルール化(ある種のソフトウェア的な手立て)のもとでは、換言すればある種従属した関係のままで競争的事業者がまともに勝負できるはずはない。それでは折角の市場自由化も絵に描いた餅となってしまう。そう考えたスウェーデン当局は、ストーカブ公社を設立し高速ネットワークを構築すること(ハードウェア的な手立て)でテリアに対抗することとした。
図表をご覧頂きたい。具体的には、管路を整備し、ストックホルム市全域にダークファイバーを敷設して物理的な伝送路インフラを公的に構築し、ダークファイバーをホールセールする事業に乗り出した。そして、その伝送路利用を自由に認める方針をとった。
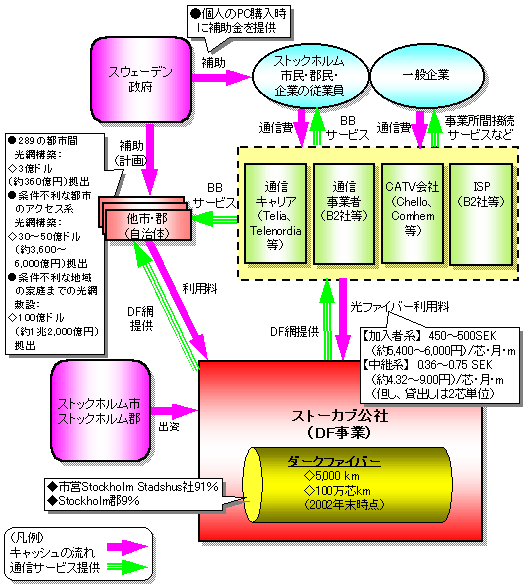
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成
同国ドミナントキャリアであるテリアにとって、大きな投資を伴う光ファイバー網の整備を行う十分な経済的誘因が見出せない状況があった。そこへ公的主体(ストックホルム市とストックホルム群)により、ストーカブ公社が1994年に設立された。同公社は、通称ゼロ種事業者のうち、とくに光ファイバーを卸す(ホールセールする)事業者である。日本でいえば、第1種電気通信事業者(自前で電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業者)へダークファイバー(光信号が通っていない未使用のファイバー)やドライカッパー(通信データが通っていない銅線)を貸し出し、電気通信役務を提供する事業者である。
同国の電気通信事業者、ケーブルテレビ会社、ISPは、このダークファイバーを安く利用し、最近ではブロードバンドサービスを提供できるようになり、サービス間の競争が生まれた。ユーザーのなかには、金融機関などの一般企業も含まれ、これら企業は自前で調達した通信機器をネットワークに接続し、企業活動の効率化など多種多様な利用状況が出現するに至っている。
もしブロードバンドインフラ整備のための管路や光ファイバーが、国民のコモンズ(公道)としての位置付けにふさわしいものであり、そのように機能するのであれば、そのコモンズ(公道)の上のダイナミックなサービス競争も期待できるのではないか。それは、グローバル規模でのインターネットとその上の技術やコンテンツの発展(イノベーション)に見るように、ということだ。
次回は「"新・この国のかたち"【2】-コモンズの上のダイナミックな競争(下)」として、スウェーデンを例に、ダイナミックな競争の状況を概観したい。

