"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第24回「フィンランドのIT戦略に学ぶ(下)――日本企業復権へのヒント」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2003年4月3日
(1) SMEや大学への支援は実効的であり官公設機関の役割と成果は明瞭
SMEの育成には官公設機関であるサイエンスパーク方式が導入されている。
ヘルシンキ隣町のエスポーやインノポリなどに加え、筆者も案内してもらったヘルシンキ市郊外のアラビアンランタなど、工科系大学に隣接するサイエンスパークが18ほどあるようだ。
ドイツ州政府による開設・援助のある「アン・インスティチュート(大学近接研究所)」と似た環境(産学連携の条件)をもつ。フィンランドのサイエンスパーク構想には、他国のケーススタディがよくなされた形跡があるように思われる。
日本の工業団地開発に近い形態であり、独立経営型で資金支援は受けていないにもかかわらず黒字経営をしているのは立派である。
またSME強化には、大学などの研究機関も大いにかかわっている。
TEKESは大学等研究機関に対しても技術開発から製品開発まで支援し、大学教官がスピンアウトして起業することを積極的に推進する。フィンランド工科大学などの広大なキャンパスには民間会社の看板が林立し、大学から技術移転を受けたベンチャー企業が製品化するまでその大学に住み込んでいるそうだ。こんな風景は今の日本の大学には想像がつかない。
またSMEの海外展開では、語学力が欠かせない。これを説明するために、少々私的な話を容赦願いたい。
FINLANDIA(ウォッカ)を飲みながらの会話だったゆえ記憶はやや不鮮明なのだが、先月(2003年2月)中旬、筆者の自宅に招いた際のフィンランドセンター初代所長Dr. Jukka Viitanenによれば、英語のヒアリング試験では次の3種類の英語も含まれるそうである。
スコットランド人が話す「スコティッシュ」、華僑などの中国人がビジネスで話す「ピジョン・イングリッシュ」、ジャマイカなどの中米現地人が話す「クレオール・イングリッシュ」のことである。これら独特な癖のある英語も聴取できるような実用性を重んじているようだ。
しかも小学校から哲学も授業に採り入れ、その後、中学で第2外国語、高校で第3外国語、そして大学では第4外国語を学ぶという。「冗談ではないか」と尋ねると真顔でそれを肯定する。単なる教育熱心を超えた、フィンランドの強固なグローバル戦略が垣間見られるような気がする。
【図表】 サイエンスパーク方式を通じた産業クラスターの地域波及
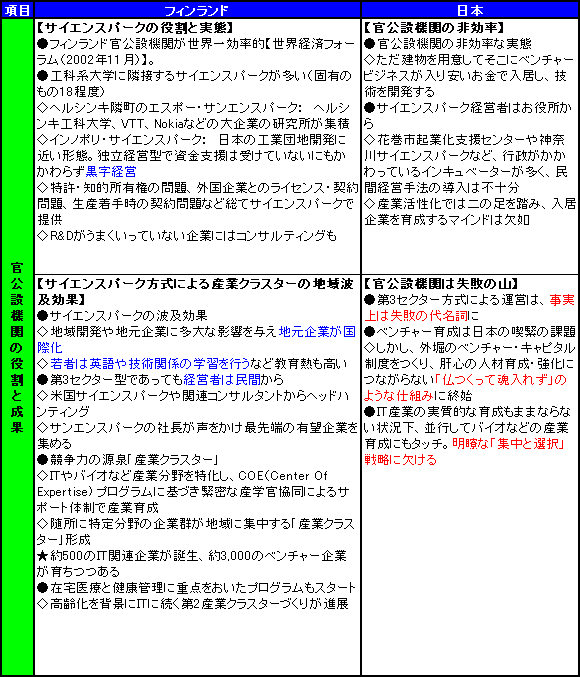
(出所)フィンランド情報については、フィンランド大使館フィンランド技術庁(TEKES)鷲巣栄一氏資料(2002年8月)やTEKES発表資料を参考に、日本総合研究所ICT経営戦略クラスター作成
(2)日本企業復権のためのヒントとは
さてフィンランドという国の取組みを学び、一体何が日本企業復権のためのヒントになるだろうか。
国と企業との取組み・連携も重要な課題である。一方、今も昔も"企業は人なり"は不変だ。その意味で現在の不況や自信回復には、起業人にメスを入れることは大切な取組みである。しかし、経済産業省だったか、最近のベンチャーを含むSMEにおける人材開発プログラムには、いろいろと欠如している視点がある。
それは次のようなもので、結果的にまたも税金の無駄遣いになりそうな、「仏つくって魂入れず」のような仕組みのものが相変わらず登場するといった印象を与える。
| ● | ベンチャーキャピタルの存否や資金調達に関する円滑な仕組みなどが不十分だとする問題はあくまで「外堀」の議論。 |
| ● | また、ベンチャー・キャピタルをわが国で生み出すための人材開発カリキュラムなどが検討されているが、これも同様に「外堀」の視点。 |
| ● | これまでの国の取組みには、橋や道路や建物といった箱物づくりに象徴されるものが多くあった。そして、ITやソフトウェア、サービスへの産業上のウェイトが高まる今日においても、やはり制度やプログラムといった、外見のことが中心になっている。 |
| ● | そ こに資金を投入しても、期待するほどの効果は得られない。Eビジネスやeコマース分野において、当時、国の産業・企業育成プログラムとして相当に税金が投 入されたが、これといった企業は出現もしなかったし育成もされて来なかった。より本質的なものにメスを入れなかったからだ。 |
| ● | 強い企業、市場で生き残れる企業とは、経済的に合理性のあるプロセスを通じ、顧客への価値創出ができたかどうかどうかにあるが、国のプログラムではそこまでは無理。但し、そこへの橋渡しの役割は存在する。 |
これでは 第22回(上)で書いた「空気」ひいては組織の「DNA」を変革できるような契機づくりには決してならない。
では、国と民間との連携を通じそれができないかというと、そうでもなさそうだ。
例えば、少し前に金融危機に直面した韓国がIMFからの勧告を受け、国を挙げて「集中と選択」を行い、見事に世界トップクラスのブロードバンド大国、あるいは半導体などの分野でトップの地位を得ることに成功した。効果的な膨大な資金と優秀な人材の集中的な投入と、その背景としての危機感、修羅場的な雰囲気(空気)が、幸か不幸か当時、国全体にできあがっていたといえる。
1990年初頭のフィンランドとよく似ている。
翻ってわが国、あるいは日本企業の実態を眺めてみると、前述の顧客への価値創出の点で、自らの強固なこだわりや思い入れなどについて、韓国や米国シリコンバレー、イスラエル、そしてフィンランドなどの企業戦士に負けているのではないか。
今の時代に、戦士などとは古臭いかも知れないが、戦う志(気持ち)の無い状況で、現在の戦争である企業競争に勝つことはできない。
その前提があって、例えば、商品開発などのプロセスにおいては、すぐにはリターンが得られそうもない、現実から遊離・超然とした状況下のR&D 活動などを通じ「セレンディピティ(serendipity)」が個人やチームに備わってくる。この能力の獲得を通じてこそ、企業組織の空気を変え、 DNAを変革できるようになる。
(注) 「セレンディピティ」:一見偶然の事象から本質を見逃さない洞察により、創造的発見を導く造作や能力のこと。
わが国のマーケット成長において、最近随所で閉塞感が漂うように見えるのは、成長が飽和している場合が多いからであろう。飽和は「イノベーション→差異化→低コスト化」というマーケットの流れの最終局面で起こる。
わが国の大企業の多くが、現下、価格競争に陥っているのはその証左といえよう。低コスト化のフェーズに長く留まり過ぎている。
まさに日本の企業あるいは企業(起業)人には低コスト化の段階からイノベーションへの転換を迫られている。どう変革するか。
閉塞状況の日本の企業を変える方法には「黒船効果」がある。外国人を自陣に送り込み、外圧により変化の「契機」を与えイノベーションを引き起こすのだ。
今回ケーススタディとしたフィンランドの企業が、本当に日本にも進出する(したい)のであれば、日本企業はこの「黒船効果」をレバレッジとして利用し、両国ともに実のある成果を収める算段はないだろうか。これが日本企業復権の鍵を握ると思われる。
ただ、この算段とその具体的な中身については、紙面の都合によりまたの機会に譲りたい。

