"IT革命第2幕"を勝ち抜くために
第19回「ナノテクに見るハイテク国家戦略――模倣障壁と事業バリュー」
出典:Nikkei Net 「BizPlus」 2002年12月25日
(1)ハイテクを叫ぶ前にわが国の初等中等教育は大丈夫か?
第18回では、「ナノテクに見るハイテク国家戦略――国益の追求」について取上げた。そもそも今の若者ましてや小中学生には「国益」など、関心事の蚊帳の外にあるものだろう。ここでは決して、偏狭な民族主義的なことを言及しているのではない。国家とか国益などという形容が付くことが、何となく後ろめたい感覚を覚えるとしたら、相当偏向した教育や思想に毒されていると考えるべきだ。
米国の現下のブッシュ政権も、英国の政権党である労働党ブレアであっても、国家戦略、言い換えればグローバル戦略をしっかりと堅持している。前回では、特に中国の戦略の一端にも触れた。彼らの判断基準は実に明快だ。国益にかなうかどうかだ。
ハイテク産業の維持・強化は、明瞭な国家戦略である。ナノテクにしろ、このハイテクの育成・強化は一朝一夕ではいかない。前回、東京都大田区のケースを取り上げ、主に現在の企業規模に応じた連携、あるいは「裾野」の意義やその重要性を説いた。今回は、わが国の次世代を担う子供たち・若者に関し、現在起こっている由々しき問題についても取り上げたい。
先日、「学力の低下傾向を裏付け 10教科で前回下回る」(毎日新聞2002年12月13日)という記事が物議をかもした。主な内容は次の通り。
| ● |
文部科学省は2002年12月13日、全国の小学5、6年生約21万人と中学生約24万人を対象に実施した「学力テスト」(教育課程実施状況調査)の結果を公表。 |
| ● | 1994年から3年間かけて実施した前回調査と同一の問題では、46%の問題の正答率が前回を下回り、小5〜中3の延べ23教科のうち社会、数学を中心に10教科で前回を下回る問題が過半数に達した。 |
| ● |
明確に傾向が出ないのは10教科で、成績が前回を上回ったと見られるのは3教科だけだった。子供の学力の低下傾向が指摘されてきたが、国の調査でそれが初めて裏づけられた。 |
| ● | そして、文科省は20教科については学習指導要領の目標が「おおむね良好」に達成されたと判断した。 |
実際の競争や厳しいビジネスや産業上の問題に直面する経済産業省などに比べ、文科省(特に旧文部省)が相手にする先は、競争とはこれまで縁遠い世界であった。「おおむね良好」とは実にのん気で、お手盛り評価の極みである。身内のことは見えないものだ。
(2)「独創的障壁」づくりは知的エリートのみの代名詞ではない
研究でも技術開発でも忍耐力が不可欠だ。そんなに簡単に発見や発明、あるいはビジネスのブレイクスルーなど起こりはしない。
中村修二教授の「勘」と「やり抜く力」で達成した青色発光ダイオード開発の成功も、2002年ノーベル受賞者の田中氏による「偶然の発見」も、一握りの天才ゆえの快挙であろう。これら知的エリートとそれを支える広範な知的中堅層の基盤の維持・強化が今後の日本の課題であるはずだ。
しかしながら、この学力低下は現在のデフレ経済や不良債権にあえぐ金融機関の状況よりも深刻なことだ。旧大蔵省の指導のもと、殆どグローバル競争に晒されることもなくその競争力を失墜した銀行のごとく、旧文部省の言う通りにしていたら、わが国の科学技術も危ういのは目に見えている。
経済や不良債権問題などは、最良のタイミングで一気に大鉈(パンチ)を振るえば(これが難しいのだが)、本来解決できてしまうもの。幾つもの国で既にできたことだ。しかし、教育の問題は、ボディーブローのようにじわじわと効いてくる。だから難しい。早く方向を転換する必要がある。
一部のノーベル賞級の天才というわが国の知的財産は、過去の蓄積(ストック資産)から来るものであり、現在の教育制度(フロー資産)からは今後も、知的にも体力的にも世界に通ずる巨人が輩出される保証はない。過去の人智・英知のストックの中には、決して真似のできない、ある種の「独創的障壁」が存在している。
この独創的障壁とは、平易に解釈すれば、自分らしさ、私しかできないことだ。科学技術でも芸術でもスポーツでもよい。しかし、この障壁を築くには、一定のしきい値(スレッシュホールド)超えが必須となる。何でも一流になるには、あるラインを超えなくてはいけないのだと教えることと同義である。このしきい値を超えるまでは、様々な試行錯誤が生ずる。強烈な野心(志)をもち、自己を律するエートス(行動規範)のもと、トライ&エラーの不安感や不確実な連続に打ち克ち初めて、その先のまだ見ぬものを手にする。これは万民に等しく与えられる原理原則のプロセスだろう。
理想主義のみに走るとこの現実は見えてこない。小学校での「ゆとり教育」や中学校英語授業の「時短」など一例だろう。最大級の問題は、機会の平等を取り違えた「平等主義」だ。人間は生まれた時から不平等であり、各人の固有のしきい値を超えること、すなわち誰一人として同じでないことを教えることが重要である。これがなされなければ決して「その先のまだ見ぬもの」を見ることはできないのだろう。このまま行けば、前回また前回とどんどん学力が落ちていくことは必至となる。
(3)「補完財(模倣障壁)」がナノテクビジネスにも不可欠
ビジネス・ウォーにおいては、「模倣障壁」が存在する。わが国産業の基礎においては一部の天才が不可欠である。そして、産業力強化には、ビジネス面での野心をもった(起業の志をもった)人材が続々と輩出される必要がある。そうでなければ、ビジネスの天才である、井深大や本田宗一郎が到達した世界、国際的な優位は実現しない。
井深や本田が創り上げた世界や事業には、その推進において基本となる、「組織風土、戦略、ビジネスモデル、そして、報酬体系などを含む人材マネジメント」における卓抜性・独自性を発揮できたことゆえの、勝ち戦を今日、結果としてもたらした。これはナノテク分野でも変わらない。
わが国がナノテクにおいても、かつての製鉄や自動車、近年のエレクトロニクス、半導体などで世界を席巻するほどの勝ち戦とするためには、もう一つ決め手となる要素が不可欠だ。
IT・ネットバブル時において、多くのベンチャー企業群のMBAホルダーが明瞭な戦略を策定し、戦略を実現する美しいビジネスモデルを描き、それを特許化し、風通しのよい自由闊達な風土をつくった。資金提供者からの、実際には彼らの身の丈を超える多額の資金調達にも成功し、報酬面でも大企業と遜色のない水準で野心家たちを引き留めた。
しかし、負け戦を強いられた。なぜか?
補完財、言い換えると「模倣障壁」が無かった。たとえそれに気付いていたとしても、少なくとも勝負できる期間内でそれを構築することができなかった。模倣障壁とは、例えば、流通チャネル、顧客基盤(CRMや当コラムの第4回で示したCRB)、あるいは供給者との関係構築などの要素において、競合他社からの差異性・差別性という壁のこと。この障壁を打ち立てることができたかどうかが勝敗の鍵を握った。
(注)CRM:Customer Relationship Management、CRB:Customer Relationship Buildingのこと。
模倣障壁とは、手数(ジャブ)が多くフットワーク軽く動き回るルーキーが、老獪なボクサーの敷詰めた何重もの網(知恵と経験という基盤)の前ではまるで歯が立たないがごとく、短期間で手にできるものではない。
(4)意思決定の曖昧さが成否を分ける
さらに、メカトロニクス、オプトエレクトロニクス、バイオニクスなどの複合的な技術が入り組んでいるナノテク分野では、「次数中心性」とか「媒介中心性」といった要素が意味をもってくる。
前者は、関係者ネットワークにおいて、当該企業(研究者)というノードに流入する情報量(入次数+出次数)を指す。後者は、人的ネットワークにおいて、当該ノードがネットワーク全体の価値にどれだけ寄与しているかを測る度合いことであり、例えば、アライアンス、コミュニティ参画、共同論文(IT活用)などがその度合いを測る指標となる。
(注)「次数中心性」および「媒介中心性」の両者は、何れも米ウォートンスクールのロリ・ローゼンコフ教授によるもの。
当該事業推進のための基本的な要素と補完財(模倣障壁)に加え、「ネットワーク優位性」を縦軸に、そして横軸に自社と競合関係にある他社のケースを比較しつつ分析・評価する際のイメージを示す。実務では、空欄のセル内を埋める作業が発生する。
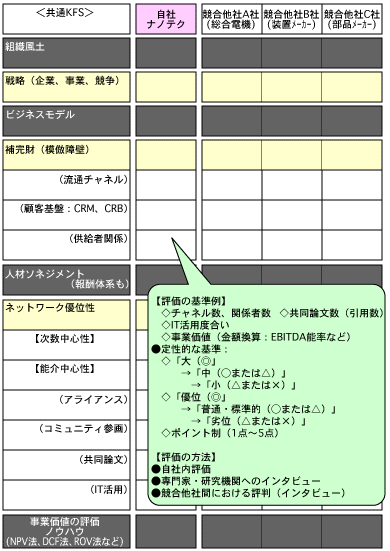
「ネットワークの優位性」とは要するに、ナノテクのようなハイテク先端分野では、その時は一見取るに足らない情報や知識が自国または自社(研究者など)へ、いかに流入しやすくできるか、あるいはそれらの集積・蓄積がなされる環境やポジションにどれだけあるかの問題である。これが競争の勝ち負けを決定する。
米国はもちろんシンガポールなどが、そして、最近では韓国や中国が、こうした「ネットワークの優位性」についてのポジション確保のため、ハイテク国家戦略を策定しその具体的なアクションを取っている。彼らがこうした背景・からくりに気付いている証左だ。
(5)事業バリュー評価などのスキル強化と文科省機構の再改革の必要性
ナノテクなどのハイテク事業における現在の実力を財務的に測るには、事業価値の評価ノウハウ(NPV法、DCF法、RO法など)を身に付ける必要がある。
(注)NPV:Net Present Value、DCF:Discount Cash Flow、ROV:Real Option Valueのことで、順に事業の不確実性などを考慮した価値をダイナミック・柔軟に評価できる手法。
(注)EBITDA倍率:企業価値(株式時価総額に純有利子負債を加えたもの)をEBITDA(Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization、金利・税金・償却前利益)で割った尺度。
現在、わが国において大変ホットな話題に不良債権問題がある。
2002年10月30日の経済財政諮問会議(平成14年第31回)で、提出された「金融再生プログラム−主要行の不良債権問題解決を通じた経済再生−(竹中金融担当大臣提出資料)」では、不良債権の資産査定の基準について、市場評価との整合性を図るため、引当に関するDCF的手法など具体策を早急に検討することがうたわれている。
金融分野に限らずDCF手法はよく用いられる伝統的なものであるが、実際のマーケットメカニズムでは極めて切実な、事業を取り巻く「不確実性」がまったく考慮されていないという点で決して十分な手法ではない。
一方、ハイテク事業は今後、金融機関などの比にあらず競争の激化に一層さらされるであろう。つまり、技術的な難易度(テクニカル・リスク)があったり、開発に多額な資金を要する実態や、その開発には多段階のプロセスが不可欠であったり、経営上のオプションがあるような、幾層もの不確実性が伴うハイテク事業では、DCF手法ではなくROV手法が有効となる。ただ今回は、その詳細を述べる回ではないため、別の機会に譲りたい。
今後のわが国ハイテク国家戦略には、不良債権問題の処理以上に、幾つもの高度なスキルが問われる。大田区の中小・零細のエンジニアや大企業の技術者、あるいは大学の研究者には、技術そのものや開発プロセスの高度化や模倣の障壁をうまく築いていくことが急務である。
加えて、経営学修士(MBA)の工学版にあたる学位であるMOT(Management of Technology)を強化するなど、その事業や技術の財務的評価(バリュエーション)に関するスキルを開発・蓄積していけるかどうかも、一層問われている。
ハイテク国家戦略の構造にはまず、底辺から上位レイヤーまで忍耐と創意工夫が鍵を握る「裾野」の広い技術マターがある。その次に事業(ビジネス)マターがあり、そして、産業(国家戦略)マターへと連なる。つまり、教育の問題(旧文部省)と技術開発(旧科学技術庁など)の間には、事業や経営の問題がある。この3つをうまくつなぐ仕組み構築が問われている。
旧文部省はマーケットのこうした実態に目を向けなくてはいけないのだが、現在は「学力の低下」問題に見られるように、余りにも浮世離れした実態を「おおむね良好」とし満足しているのが情けない。幸いにして、旧科学技術庁と一緒になったのだから文科省には、今後、勝てるハイテク国家戦略を実際に牽引できるような能力とセンスの向上を期待したい。しかし、今のままでは無理だろうから、そのために民間企業のメソッドやマーケットのことをケーススタディしつつ、文科省の機構再改革と人材刷新が喫緊の課題として一層クローズアップされるべきであろう。

