プロフェッショナルの洞察
イノベーション推進のための手がかり 02 イノベーションの歴史
2006年09月01日 佐久田昌治
 「今ある技術をどう使うか」という観点だけではなく、過去において偉大な技術開発がどのように行われ、いかに発展、商業化したか、そのプロセスの考察もまた大切である。
「今ある技術をどう使うか」という観点だけではなく、過去において偉大な技術開発がどのように行われ、いかに発展、商業化したか、そのプロセスの考察もまた大切である。技術開発において新しい原理、原則を考えた人が偉人であることは確かだが、それだけではイノベーションは起こらない。より重要なことは、技術の実用化、商業化を考えた人が存在したことであり、そうでなければ当該技術は社会に広く普及されることなく、単なる一つの発明で終わっていたはずだ。
たとえば蓄音機の事例が分かりやすい。ご存知の通りこれはエジソンが発明したが、彼は使い道について10通りを考えたという。具体的には「遺言を録音すること」、「盲人用の本の朗読」、「英語の綴りの録音教材」等々。しかし、音楽の録音再生などは邪道であるとエジソンは考えていた。だが、誰かは知らないが、音楽を録音し、商売にすることを考えた人がいた。名も知らぬ後者のほうが、イノベーションという観点からは大きな役割を果たしたと言える。
一方、自動車を今の形に発展していったのはドイツのダイムラーベンツの前身である。1885年に自転車をオートバイにし、その10年後にはトラックを造った。だが、当時はトラックが現在のような輸送の主役になるとは想定もしていなかった。人類は6000年の間、馬を輸送手段として使ってきた。そのため、トラックが発明されてからも20、30年は馬が主役だったのだ。トラックが主役になったのは第一次大戦後のことであり、誰かがトラックによる輸送のシステムを考えたからこそ、こうした産業が起こったのである。
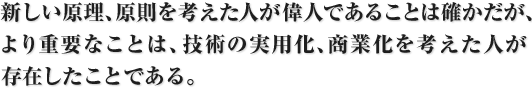
 こうしたイノベーションはどうすれば実現できるか。アメリカやヨーロッパ諸国、さらには中国、韓国、台湾なども積極的に議論し、戦略を立てている。それに対して日本はようやく国レベルでのイノベーション戦略をスタートさせたばかりだ。
こうしたイノベーションはどうすれば実現できるか。アメリカやヨーロッパ諸国、さらには中国、韓国、台湾なども積極的に議論し、戦略を立てている。それに対して日本はようやく国レベルでのイノベーション戦略をスタートさせたばかりだ。日本の国民も政治家も、科学や科学技術に理解は必ずしも高くない。とりわけ政治家の意識が低いのが実情だ。アメリカでは、科学が政治の争点にもなるが、日本では政治の話題にほとんど上らない。なぜ、そんなに国民も政治家も意識が低いのだろうか。それは、これまで企業が自らイノベーションを行ってきたからであり、特に政治が議論する必要がなかったからだと思われる。
しかし、基礎研究で遅れをとる日本の場合、イノベーションにおける原理原則は欧米に依存している。科学が将来の経済に及ぼす効果を研究者がもっとアピールすべきであり、政治においても活発な議論が必要だ。そうでないと日本の成長がストップしかねない。
こうした中で、地方自治体は今、ようやく科学技術の計画を作り始めた。伝統的な産業と科学技術をどう組み合わせるかに注目しており、まさにこれから考えるべき大きな課題といえる。
世界では、地域の産業を複合的に組み合わせて新しい技術を開発するとともに、発展、商業化させる取り組みが進んでいる。これはクラスターと呼ばれており、端的なのがアメリカのシリコンバレーだ。1930年代にスタンフォード大学の卒業生が自然発生的に自ら事業を起こすことによって世界最大の知的クラスターとなった。最近になってイギリスのケンブリッジほか、ドイツ、スウェーデン、デンマークなどでも進んでいるが、その原型はシリコンバレーであり、いずれも大学が絡んでいるとともに、国または地方公共団体が強いリーダーシップを発揮している。
日本でも、科学技術振興において地方自治体と大学、そして地元企業が、産学官で協力して取り組んでいくべき時代が来ている。
次回は、日本企業においてどのようにしてイノベーションが起こったのか、その実情の分析と、目指すべき今後の取り組みについて述べたい。
| 国 | 「基礎科学または基礎工学」の振興によって得たメリット |
|---|---|
| アメリカ | ●第二次世界大戦を終結させた、マンハッタン計画による原子爆弾の製造 ●第二次大戦後の幅広い産業分野(素材、自動車、情報通信、バイオ他)でのリーダーシップに ●「科学に投資する政府」は国民の圧倒的支持を得やすい |
| イギリス | ●産業革命以降のさまざまな技術の起源を創出 ●産業革命以降、エネルギー、鉄鋼、セラミックスなどの主要な産業をリードし、植民地支配の有力な手段として活用した。第2次世界大戦までは実質的に世界を支配 ●財政難からサッチャー政権では科学研究予算を削減したが、ブレア政権は科学技術の可能性を再評価し、徐々に予算を増加 ●科学およびアカデミズムに対する国民の信頼は厚い |
| ドイツ | ●第2次世界大戦以前は科学および産業の分野で世界のリーダー ●Siemens AG, BASF AG, Bayer AG, DaimlerChrysler AGなどに代表されるさまざまな先進技術の発明により、ドイツの伝統的な電気・機械・化学その他先進工業を確立 ●ただし、第2次世界大戦および東西ドイツの統一を経て、国の財政難により科学予算は削減を余儀なくされたが、国民の科学技術に対する信頼は根強い |
| 日本 | ●明治維新以降、独自の科学を形成し、ポテンシャルとしては相当に高い。しかし、そのメリットを国民が実感できたかどうかは疑問 ●かつて鉄鋼、自動車、半導体、家電などで世界市場のリーダーになったが、これらの産業の基盤技術はすでに欧米諸国によって発明されたものであり、その起源を日本人が確立したものではなかった ●無意識のうちに国民は「基礎科学」や「基礎工学」は外部からもたらされるものと考える傾向 |
出所:経済産業省委託調査(委託先:株式会社日本総合研究所)、産業技術政策基盤調査、平成16年3月をもとに作成
関連リンク
- 01 企業の研究開発力に支えられている日本
02 イノベーションの歴史
03 普通の技術者がイノベーションを起こす日本の強み

