プロフェッショナルの洞察
社会の変容と企業リスクマネジメント 02 企業リスクマネジメントの現代的課題
2007年03月01日 鈴木敏正
 この10年ほどで、リスクマネジメントは少しずつではあるが日本企業に浸透してきた。企業リスクマネジメントは、当初、“何か不測の事態が起きた際でも、企業として生き延びるための方法論”つまり“自らの生き残りのための手段”として導入された側面が強い。また、せいぜい当該企業の特定のステークホルダー、例えば、業界、株主、従業員などの利害をどう守るか、あるいはそれらの不利益の回避がその重大な関心事の一つであった。いわば“村社会”の維持のための有効な手段として受け入れられた。
この10年ほどで、リスクマネジメントは少しずつではあるが日本企業に浸透してきた。企業リスクマネジメントは、当初、“何か不測の事態が起きた際でも、企業として生き延びるための方法論”つまり“自らの生き残りのための手段”として導入された側面が強い。また、せいぜい当該企業の特定のステークホルダー、例えば、業界、株主、従業員などの利害をどう守るか、あるいはそれらの不利益の回避がその重大な関心事の一つであった。いわば“村社会”の維持のための有効な手段として受け入れられた。しかし、そのような意図で受け入れられてきたリスクマネジメントの役割は、ここ数年で大きく変化してきている。それは企業に対する社会の意識が大きく変わったことに起因する。社会は、企業が単に儲けるための集団であることを許さなくなり、少なくとも社会、社会の成員に対して、不利益や危険をもたらすことが“意図的”に行われていたのならば論を待つまでもなく、たとえ“無意識的”、“無過失”であっても発生した被害の軽減の第一義的責任は当該企業にある、と考えるようになってきた。社会に被害を与える可能性のある企業行動を“意識的”あるいは“過失”で行った場合、その結果がたとえ出ていなくても(まさに、これがリスクなのであるが)社会的に指弾される状況となってきた。コンプライアンスが叫ばれるのは、このような社会的意識の変化の反映であると捉えることも出来る。今や、社会への被害の可能性を知りながら企業利益に走り、コンプライアンス違反を意図的に行うような企業に対しては社会からの退場勧告も辞さないという状況にもなっており、企業も相当な覚悟が必要である。また社会は企業に対し、どのような社会貢献が出来るのか、企業活動を通じてどのような価値を社会に提供し得るのかを自ら表明することを要求する時代にまで入ろうとしている。社会からの認知が企業存立の基盤になるという時代の到来も非現実的なものではない。CSR(企業の社会的貢献)、企業市民といった言葉はまさにそのような時代を反映したものである。企業は自らの活動に伴う社会への悪影響を予想し、その防止として適切な対応を準備すること、また不幸にして顕在化した被害を社会が許容する範囲まで軽減化させるための対応を行うことが出来る企業のみが社会から認知されるという状況の中で、企業リスクマネジメントはその役割を大きく変えてきた。
実際の事例を挙げてみよう。たとえば自社工場が何らかの原因の爆発事故で、有毒ガスを外部に放出し、住民の避難に発展してしまった場合である。爆発事故自体が企業活動の停止につながり大きな損失をもたらすが、それ以上に近隣地域や自然環境など社会へ被害を与えてしまうことに対する責任が大きく課せられる。さらに加えて、最終的な責任の有無に関らず、事故時の被害救済活動、あるいは被害拡大阻止に向けての活動の適切性が厳しく問われる。そのために行政など社会的救済機関への協力、適切な情報提供など、事故後つまり起きてしまった後の減災活動(被害を許容できる範囲に抑える活動)への対応の適切性が問われることになる。
 同様に、問題のある商品を世の中に出してしまった場合を想定してみよう。公的あるいは自主的基準を設け、それに従って生産・出荷するのは当然のことだが、それでも不適合な製品を出して問題が発生することはある。このような場合、その時点での責任の有無に関らず、企業は関係者の救済、被害の軽減、拡大阻止にあらゆる経営資源を使ってでも対処することを社会は要求する。企業活動に直接関係ない人々に対し、一方的に被害を与えてしまった場合は尚更である。企業の責任の有無に関わらず、被害を受けた人々への救済が最優先されるべきだと社会は考えるようになってきているのである。
同様に、問題のある商品を世の中に出してしまった場合を想定してみよう。公的あるいは自主的基準を設け、それに従って生産・出荷するのは当然のことだが、それでも不適合な製品を出して問題が発生することはある。このような場合、その時点での責任の有無に関らず、企業は関係者の救済、被害の軽減、拡大阻止にあらゆる経営資源を使ってでも対処することを社会は要求する。企業活動に直接関係ない人々に対し、一方的に被害を与えてしまった場合は尚更である。企業の責任の有無に関わらず、被害を受けた人々への救済が最優先されるべきだと社会は考えるようになってきているのである。一昔前なら、明らかに企業責任が認められる場合を除いては、当該企業による被害者救済、減災活動を強く求められることは少なかった。また、当該企業による、そのような活動への消極性が社会的に厳しく追及されることも多くはなかった。しかし、社会は日々着実に変化しており、当該企業に対し、何よりも当事者責任として被害者救済、減災活動を求めるようになってきている。社会意思の変化に応じて企業も変化し、社会の意思に的確に応えることが求められている。しかし、それに未だ気付かず、分かっていてもそれに対応出来ていない企業も数多く存在するというのも実情である。時代は、そのような企業や、実際に問題を起こしてしまった企業がその責任を果たす能力がないと判断した場合には、社会の舞台から退場することさえ、仕方がないと思うまでになっていることを我々は深く自覚すべきであろう。
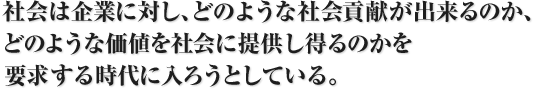
 これまでのリスク顕在時における日本社会の特徴の一つとして、まず責任の所在追求、それからその原因者に対する断罪があった。もちろん、再発防止のための原因究明と責任追求が重要であることに疑いはないが、現在は、それよりも優先して被害軽減活動への取り組みが何よりも求められる。そのためには、状況の的確な把握、残されている、あるいは使用可能な経営資源の把握、その上で被害軽減の対象・目標の設定を行い、対応策の計画・実行という過程を経なければならない。これら一連の行為をリスクマネジメントと呼び、緊急時対応を強調する時は特に危機管理と呼ぶ。とりわけ危機と呼ばれるような緊急時にあっては、使用できる経営資源は極めて限られており、このような事態においては、経営資源の効果的・効率的な運用のために、対策実行の対象の重要性に関する順番を明確にしておかなければならない。つまり、リスクマネジメント・危機管理の実行にあたって、最も大事に考えているものは何かを、予め決めておくことが必要となる。例えば、守るべき対象や重要度の最も高いのは、自らの顧客なのか、従業員なのか、株主なのか、あるいは業界秩序なのかなどを明確にしておくことが必要となる。これをせずして限定された経営資源の効率的使用は出来ないし、そもそも対策選択の合理性を持つことも出来ない。守るべきものの優先順位付けは、その組織の価値観、企業風土、社会への対応姿勢などすべての反映であり、これを誤ると、その後の対応がまったく無為に化す事も稀ではない。行われるリスクマネジメント・危機管理は、その企業の根本を映し出す“鏡”であると共に、そこには、その時点での“経営者”の“質と人間性”が如実に現れることになる。
これまでのリスク顕在時における日本社会の特徴の一つとして、まず責任の所在追求、それからその原因者に対する断罪があった。もちろん、再発防止のための原因究明と責任追求が重要であることに疑いはないが、現在は、それよりも優先して被害軽減活動への取り組みが何よりも求められる。そのためには、状況の的確な把握、残されている、あるいは使用可能な経営資源の把握、その上で被害軽減の対象・目標の設定を行い、対応策の計画・実行という過程を経なければならない。これら一連の行為をリスクマネジメントと呼び、緊急時対応を強調する時は特に危機管理と呼ぶ。とりわけ危機と呼ばれるような緊急時にあっては、使用できる経営資源は極めて限られており、このような事態においては、経営資源の効果的・効率的な運用のために、対策実行の対象の重要性に関する順番を明確にしておかなければならない。つまり、リスクマネジメント・危機管理の実行にあたって、最も大事に考えているものは何かを、予め決めておくことが必要となる。例えば、守るべき対象や重要度の最も高いのは、自らの顧客なのか、従業員なのか、株主なのか、あるいは業界秩序なのかなどを明確にしておくことが必要となる。これをせずして限定された経営資源の効率的使用は出来ないし、そもそも対策選択の合理性を持つことも出来ない。守るべきものの優先順位付けは、その組織の価値観、企業風土、社会への対応姿勢などすべての反映であり、これを誤ると、その後の対応がまったく無為に化す事も稀ではない。行われるリスクマネジメント・危機管理は、その企業の根本を映し出す“鏡”であると共に、そこには、その時点での“経営者”の“質と人間性”が如実に現れることになる。さて、昨今の企業不祥事露見時などの企業トップ記者会見などで、「今回の事態について私はまったく知らなかった」、「このようなことになるとは、まったく予想していなかった、言うなれば想定外だった」という言葉を耳にすることがある。このような企業トップは企業の社会的責任の重みが以前に比べ大きく変化した中、企業の原因責任は言うに及ばず、企業の結果責任も厳しく問われる時代となってきているということをまず自覚すべきである。
裁判においても、顕在化した事態に係るリスクについて、予め「知っていたかどうか」を争うのでなく、「知るべきであったのに適切に知ろうとする努力を怠ったこと」が問題になるようになっている。これは企業に限らず、国、行政においても同様で、BSE問題やHIV問題での国会論議、裁判事例がそのいい例だろう。リスクに対する対応に関しての追求は、場合によっては、時間を遡って行われ、その時点において、十分な情報収集が行われたか、適切な検討の下に合理的で適切な判断がなされたかが問われ、その結果、時間を超えて責任を追及されるという、これまでとはまったく違う責任追及の仕方がなされるようになってきたとの認識はこの時代に生きるものとして極めて重要である。
これは、企業が社会的に果たすべき役割が向上したと言うことも出来るし、企業に対する人々の要求、期待度が大きく変わってきたことの反映であるとも解することが出来る。
次回は、想定外のリスクが発生した場合、つまり危機が実際に起こってしまったときを想定して企業はどのように行動すべきか、またまだ見ぬリスク・危機に対する望ましいリスクマネジメント方法論とはどのようなものであるか、加えてそれを適切に計画・実行するために求められる仕組み、あるいはそれを担う人材はどのような資質を備えるべきなのかなどについて考えてみる。
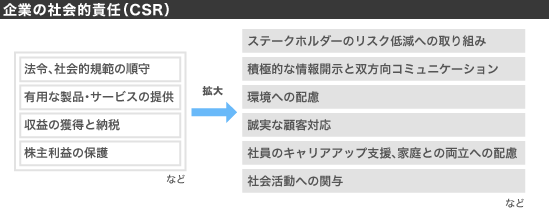
関連リンク
- 01 防災からリスクマネジメントへ
02 企業リスクマネジメントの現代的課題
03 リスクマネジメントのための組織作りと人材育成

