オピニオン
企画展示「Ichigaya Innovation Days 2025 ~参加型の未来~」
2025年10月20日 創発戦略センター、リサーチ・コンサルティング部門
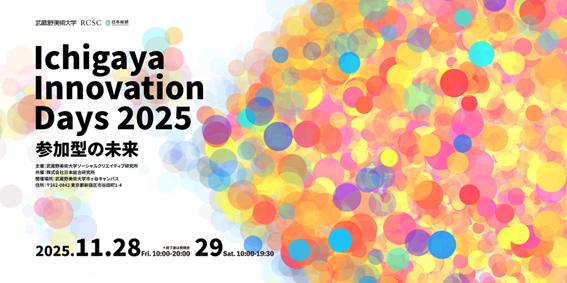
武蔵野美術大学が運営するソーシャルクリエイティブ研究所と株式会社日本総合研究所(以下「日本総研」)は、共同研究と実践の成果を発表する祭典「Ichigaya Innovation Days 2025」を2025年11月28日(金)、29日(土)に武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスで開催します。
本イベントの中で、日本総研の活動を紹介する企画展示「耳をすませ、今と未来のあいだを歩もう。」の詳細をご紹介します。
1.イベント概要
(1)Ichigaya Innovation Days
 概要
概要■日程:
2025年11月28日(金)10:00-20:00 (終了後に懇親会を実施予定です)
2025年11月29日(土)10:00-19:30
■会場:武蔵野美術大学 市ヶ谷キャンパス(東京都新宿区市谷田町1-4)
■Webサイト:https://rcsc.musabi.ac.jp/2025/08/29/ichigaya-innovation-days/

■参加費:無料(懇親会は別途会費をいただきます)
■参加方法:どなたでも参加可能です。スムーズな入館のため、下記Peatixより事前申込をお願いいたします。
URL:https://peatix.com/event/4544104

■主催:武蔵野美術大学ソーシャルクリエイティブ研究所
■共催:株式会社日本総合研究所
(2)日本総研の企画展示「耳をすませ、今と未来のあいだを歩もう。」概要
私たちは「”次世代起点でありたい未来をつくる。傾聴と対話で、多様な個をつなぎ、共にあらたな価値をつむいでいく。”」をパーパスとし、20以上のテーマで社会的価値の創出を通じて経済的価値へとつなげていく活動に取り組んでいます。
どの活動も、コンセプトを掲げるだけでなく、テーマに飛び込み、様々な人びととともに当事者の視点で課題解決と価値創出に挑む姿勢を重視しています。
しかし、未知の未来に飛び込むのは誰しも勇気や覚悟が必要であり、はじめの一歩がなかなか踏み出せないものです。この文章を読む“あなた”も感じることではないでしょうか。
今回の企画展示では、私たちがテーマに飛び込み続けてきたからこそ見えた真に解決すべき課題とそれを克服するアプローチの現状を4つの大テーマに沿ってお示しします。失敗例を含め、きれいごとだけではない、当事者の視点でともに創ろうとするからこそ見えるリアリティをぜひ感じてください。
そして、ありたい未来の姿に「やっぱりそうだよな」と共感くださる方は、ぜひご一緒に未来を創りましょう。社会的価値の創出と経営や事業との両立に頭を悩ませている方も、「日本総研となら、ちょっとのりだせるかも」そんな風に思っていただき、“あなた”の取り組みのヒントになれば幸いです。
■大テーマ1 自分の心の声と向き合う世界
人生のあらゆる場面、例えば進路選択や身じまいなどで、誰もが自分に関わることを主体的に決め、希望を持てる社会を実現したい。しかし、人が減り社会の形が大きく変わっていくなかで、これまでとは違うやり方への戸惑い、「きっとそんなニーズないだろう」という思い違い、一人ひとりが「自分はどうしたいか」を自覚しにくい環境が、目指す姿の実現を阻んでいます。
そこで私たちはまず、子どもや高齢者などが自分のニーズを見つける、気づく機会を創り、見えてきたニーズを企業や行政などの方々と共有し、思い込みを取り払いながら新たな仕組みやプログラムを創り上げていく活動を行っています。
今回の展示では子どもや高齢者を対象とした活動を紹介しますが、同じような課題は全ての世代に関わりますから、多くの個人向けのサービスや事業における新たな価値創造のヒントにして頂きたいと思います。
| 展示名 | 概要 |
|---|---|
| 子ども社会体験科 しくみ~な® | 学童期の子どもたちに、社会のしくみの学びを通じ「生きる力」を身につけるきっかけを提供する、独自カリキュラムのご紹介 |
| Futures Literacy | 中高生の進路選択をテーマに、子どもたちの未来と意思決定をデザインする活動のご紹介 |
| SOLO Lab(Social Connectivities for Local well-being Laboratory、ソロラボ | おひとりさまの高齢期~死後のプロセスにおける繋がりの構築活動のご紹介 |
| Narrative Speaking | 高齢者の意向や悩みを引きだす対話AIサービスの取り組みのご紹介 |
■大テーマ2 聞こえづらい声もすくい上げる世界
すべての人の尊厳と人権が守られるだけでなく、その声をもとに事業や制度のイノベーションを起こし、持続可能で成熟した社会を実現したい。しかし、これまでに作り上げられた消費・流通のしくみ、働き方の構造、地方と国の関係性を形づくる制度や慣習、そして何より「そんな声を拾っても経済的に意味がない」というあきらめや打算が、目指す姿の実現を阻んでいます。
そこで私たちはまず、聞こえづらい声をすくい上げつつ持続可能な新たな事業にもつながるしくみを小さく創り、ともにチャレンジに参加する方々と検証し、その結果をもとに緩やかでありながらさらに大きなしくみへと成長させる活動を行っています。
今回の展示では将来世代や消費者、発達障害のある方だけでなく、埋もれがちな地方の声をすくい上げて新たな事業を目指す取り組みを紹介します。ここで挙げた対象以外でも、同じような課題の解決に挑む研究開発や新事業開発の取り組みのヒントにして頂きたいと思います。
| 展示名 | 概要 |
|---|---|
| 子どもコミッションイニシアティブ | 子どもの声を聴くことによる、企業経営へのインパクト、デジタル社会や地域との連携を考える活動のご紹介 |
| GML(Green Marketing Lab、グリーン・マーケティング・ラボ) | 自治体・企業と共に、“楽しく”生活者の行動変容を促す活動をご紹介 |
| ReCIDA(Renewing Community Infrastructure in Depopulated Areas、リシーダ) | 過疎地域の声を聴き、その豊かな自然から得た再生可能エネルギーを、地域交通のEV電池を通じて活用するモデルのご紹介 |
| ニューロダイバーシティ | デジタル領域において発達障害がある人の特性を強みとして生かす活動のご紹介 |
| 生涯キャリア | 定年延長時代にキャリア・プラトーに直面したミドル・シニアの経験資本と成長意欲を活かす仕組みづくりをご紹介 |
■大テーマ3 自然の声を想像し、社会に反映する未来
急速な人口減少が進むなか、日本がもつ自然資本の豊かさを捉え直し、まだ掘り起こされていない経済的だけでない多面的な価値を分かち合える社会を実現したい。しかし、成長過程を前提に作り上げられてきた分業が、担い手が減少する現状に合わなくなっているひずみ、あるいは長らく続いた分業によって形づくられた過度な役割分担や権利の意識、「こうあらねばならない」という思い込みが、変革を阻んでいます。
そこで私たちはまず、目指すべきインフラや制度の構造を提言し、共有のビジョンを持って変革に挑戦しようとする企業や行政などの方々とともに自然資本のもつ多面的な価値を顕在化させるのに最適な方法を検証し、さまざまな方々との対話を重ねて段階的に市場や制度を形づくっていく活動を行っています。
今回の展示では農業、サーキュラーエコノミー、防災など既存の市場構造や制度が大きく、ステークホルダーも非常に多様なテーマにおいて自然資本の価値創出に取り組む活動をご紹介します。ここで挙げたテーマ以外にも、同じように自然資本が持つ潜在的価値に着目した変革に挑む皆さんにとって、アプローチのヒントにして頂ければと思います。
| 展示名 | 概要 |
|---|---|
| サステナブルスマート農業 | 生成AIやAIエージェント等の最新技術の活用により農業者の栽培業務や経営管理業務を支援する“V-farmersモデル”のご紹介 |
| BACE(Battery Circular Ecosystem、ベース) | EV及び車載電池の循環利用によるサーキュラーエコノミー市場の創出に向けた活動のご紹介 |
| CCI(Carbon Cycle Innovation) | 農林水産業地におけるバイオマス由来CO2を資源とした地域循環産業モデルの構築への経緯・方針をご紹介 |
| 流域DX | 流域全体の総合管理による高度な治水・利水の実現を目指す当社主宰の研究会活動のご紹介 |
■大テーマ4 挑戦と意思決定の裏側
いまや、多くの企業が経済的価値だけではない社会的価値も同時に生み出し、持続可能な事業やしくみを次々に創出する社会を実現したいと考え、インキュベーションに取り組んでいます。しかし、研究開発や新事業開発を進めるうえで、組織内外の合意形成や資金提供者の賛同の獲得に多くの壁が存在するものです。
本大テーマでは、私たちが社会的価値と経済的価値の両立のために実践している「インキュベーションモデル」をご紹介するとともに、私たち自身がさまざまな立場の方々との対話で大切にしている工夫やその経験談をご紹介します。
社会的価値と経済的価値の両立はきれいごとではなく簡単ではないからこそ、思いを持った人びととのつながりを育み、試行錯誤を積み重ねるしかありません。インキュベーションに挑み、悩む皆さんと経験と工夫を分かち合う機会にできればと思います。
| 展示名 | 概要 |
|---|---|
| インキュベーションの4phase モデル | 独自に築いてきたフレームワークや、本社部門との連携をどう進めているのかのリアルをご紹介 |
| B Corp™ ムーブメント支援 | 利益と公益を両立する「良い会社」の国際的な企業認証制度であるB Corp™の国内ムーブメントの促進や教育活動に関するご紹介 |
| フィランソロピー | 富裕層の資金を社会課題解決のための寄付につなげ、コレクティブな動きを加速させる活動のご紹介 |
※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。
関連リンク
■Ichigaya Innovation Days 2025 ~参加型の未来~
企画展示「Ichigaya Innovation Days 2025 ~参加型の未来~」日本総研の企画セミナー・ワークショップ概要
価値共創のための“参加のあり方”を探究する研究・実践発表の祭典 「Ichigaya Innovation Days 2025 ~参加型の未来~」開催
■創発戦略センター紹介ページ

