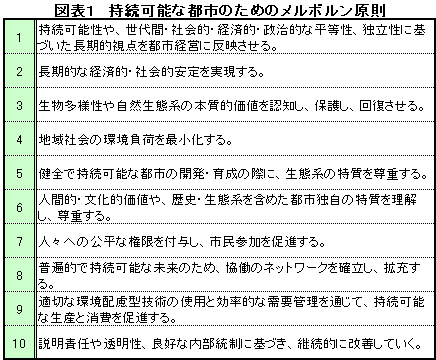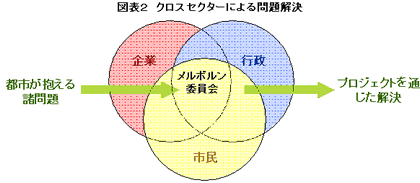コラム「研究員のココロ」
地方自治体の政策機会としてのCSR
~持続可能な地域づくりのために~
2006年10月06日 柿崎平
■政策機会としてのCSR
産業界ではCSR(企業の社会的責任)への取り組みが広がりをみせてきている。そこでは、「社会からの信頼・尊敬を獲得できる企業」を目指し、様々な自己革新活動や社会貢献活動が展開されている。こうした産業界の動向を踏まえ、自治体はどのような政策課題を見出し得るのか、具体的にはどのような施策展開を図っていくことが可能なのか、以下、その方向性を検討してみたい。
地域内外の環境変化を的確に把握した上で、地域の価値向上につながる諸施策を打ち出していくことを自治体の政策と呼ぶならば、産業界に浸透しつつある「CSR」は自治体に新たな政策展開の機会を提供していると見ることができる。CSRの広がりという社会現象を捉まえた自治体の政策展開の方向性は大きく3つ考えられる。1つ目は「事業者のCSRに対する取組みを促進すること」、2つ目は、「行政組織の運営にCSRの考え方を組み入れていくこと」、3つ目は、これが最も重要な取組みだが、「クロスセクターによる持続可能な地域づくりを推進すること」である。
■CSR政策1:地域内事業者のCSRに対する取り組みを促進していく
CSRとは企業が自らの持続可能性を求めて行う自発的な活動であるが、地域内企業にCSRが定着することは結果として当該地域にも一定の便益をもたらすことになる。
例えば、工場等の環境配慮行動が強まれば、水や大気の浄化につながり、住民の健康や、生物、植物の生態系維持を強化するのみならず、住民生活の安心感という心理的な側面にも好影響をもたらすだろう。また、女性や高齢者、または障害者の活用に注力している企業は、地域の雇用機会を豊かにする。結婚し子供が出来た女性が、生活状況に合わせて柔軟な働き方ができる職場作りは、その企業の中長期の競争力に影響を及ぼすのみならず、子育てがしやすい地域づくりにも寄与し、延ひいては出生率の向上に結びついていくかもしれない。地域の少子化対策という意味では、男性の働き方も重要だ。ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進は、個々人の創造性等を養っていくという意味では企業側に大きなメリットがあるが、同時に個人の家庭での生活充実度向上にもつながっていく。なおかつ、それが妻の「結婚満足度」の向上に、さらには、妻の出生意欲の向上につながっていくという研究成果も報告されている(注1)。
このように、企業の行動が地域の将来に一定の影響を与える以上、それを促進ないしは抑制していくことは自治体が採り得る政策の選択肢となる。実際、CSR政策とは呼ばずとも、これまでも数多くの施策を展開してきた。たとえば、高齢者雇用の促進施策であれば、専門家による相談・助言にはじまり、各種の助成金や奨励金を支給するなどの促進メニューが用意されている。また、環境関連であれば、環境保全施設の設備投資費用についての融資制度や、ISO14001の認証取得を目指す企業への専門家派遣や助成制度などが一般化している。
今後は、企業の1つひとつの行動を個別に支援していくと同時に、CSRに取り組む企業を地域全体さらには社会全体で応援する仕組みづくりの場や機会を作っていくことが行政の重要な役割になってくるだろう。
■CSR政策2:行政の組織運営にCSRの考え方を組み入れていくこと。
CSRの考え方が必要な組織は企業に限定されるわけではない。現在、ISOでCSRの国際規格化作業が進められているが、当初、「CSR(企業の社会的責任)」という言葉を使用していたところ、社会的責任を負う主体は企業だけではないという意見もあり、最終的には、SR(Social Responsibility)という呼称になった経緯がある。経済的主体とみなされる企業においても社会的責任が不可欠だという議論が目立つだけであり、その他の組織にも当然ながら社会的責任はある。行政も例外ではない。
行政の組織運営にCSRを組み入れていくとは、具体的にはどのようなことなのか。1つは行政組織の運営を社会的価値、環境的価値、人間的価値の側面から見直していくことであり、具体的には、「人権への配慮」、「コンプライアンスの確保」、「女性活用の促進」、「障害者の雇用」、「就業形態の多様化」、「ワーク・ライフ・バランスへの配慮」、「能力発揮機会の提供」、「メンタルヘルスへの配慮」などが相当する。また1つは、行政が行う施策にCSR的価値をさらに組み入れていくことである。例えば、入札制度を単なる価格競争から企業の質的側面を加味したもの、いわゆる「CSR調達」へ転換していくこと等が考えられる。環境保全の成果を挙げている企業、障害者雇用に積極的な企業、高齢者や女性に配慮した職場作りを進めている企業等を一定の基準により評価し、価格面の評価と合わせて調達先の選定を行うものである。
また、個々の施策を超えて、行政組織の運営メカニズムそのものにCSRの考え方や方法論を応用していく方向もある。CSRの本質は、多様な価値観を持つステークホルダーの声を積極的に受け止め、企業活動の軌道修正などにつなげていくことであるが、行政組織においてもその重要性は年々高まってきている。行政組織にとっては議会が代表的なステークホルダーであることは今も変わりは無いが、市民の価値観が多様化し、さらには自律的・自立的な地域運営が求められている昨今、数年に1回の投票で選ばれる議会だけの意見ではもはや効果的な地域経営は難しくなっている。真のステークホルダーである地域住民の声を多様なチャネルで的確に受け止め、それに基づいた政策目標を掲げ、その実行過程を自ら報告し、そこからまた新たな声を受け止めていくというPDCAサイクルを強化していくことが求められている。CSRの議論ではステークホルダー・エンゲージメントと呼ばれているが、その方法論を基に行政組織の現状をチェックしてみることは新たな発見をもたらすに違いない。指摘するまでもないが、企業のCSRをそのまま真似ようとするのではなく、行政組織なりの方法論を確立していくことが必要である。
■CSR政策3:クロスセクターによる持続可能な地域づくりを推進すること。
これは、企業の社会的責任、行政の社会的責任、さらには市民の社会的責任(Citizen/Consumer Social Responsibility)等々の意識・行動の連携を強化し、地域が抱える課題をセクター横断的に解決していく仕組みを構築していくという方向である。地域が直面する課題はますます複雑化、高度化し、行政だけで解決できる、あるいは解決すべき範囲が狭くなる傾向にある。財政面、知識面の両面で限界が見えており、あらゆる領域で官民協働が迫られているが、それを個々の事業単位の効率化策に留めず、地域づくりの理念にまで高めることで、地域の総力を戦略的かつ機動的に活用していこうとする動きである。
この観点から注目すべき事例としてメルボルン市(注2)の取組みをあげることができる。メルボルンは2003年に国連グローバル・コンパクト(注3)に地方政府として最も早く署名した都市(注4)であり、同時にグローバル・コンパクトの理念を地域経営に応用させたシティ・プログラムの具体化を牽引してきた地域である。国連グローバル・コンパクトのシティ・プログラムの基本的目標は、企業・政府・市民団体間の地域の横断的なパートナーシップを有効に活用して都市生活の質的向上を継続的に図っていくことであり、メルボルンでは、域内企業経営者の有志で行使されるメルボルン委員会を中心にした取り組みが進められてきた。メルボルン委員会には、市内の企業、行政、NPO、大学、労働組合等170以上の組織が参加し、都市特有の課題解決のためにいくつものプロジェクトを行ってきている。持続可能な地域づくりのビジョンである「メルボルン原則(→図表1を参照)」の下に、例えば、交通システム改善プロジェクト、公共料金債務軽減プロジェクト、2020年ゼロエミッション・プロジェクト、メルボルン・ケア(企業が従業員に地域貢献ボランティアの機会を提供するもの)などがあり、いずれもクロスセクターの取組みが進められている。正に、企業の社会的責任、行政の社会的責任、さらには市民の社会的責任が噛み合い、単純総和以上の力を発揮している例である(図表2)。
メルボルン市という行政が政策として掲げて主導したわけではないが、委員会と市は頻繁に会合をもっており密接な相互協力を行っており、連携環境の整備という点で一定の役割を果たしている。また、行政として、あるいは市としてのスタンスを明確に示す意味で、グローバル・コンパクトへの署名を世界の都市に先んじて署名し、従来の動きをさらに本格的に展開していこうと企図している。つまり、この第3の方向を促進する政策というのは、特定の事業を行政が行うという意味での政策ではなく、地域価値向上に向けた多様な主体の自主的な取組みを緩やかに連携させていくというものである。行政が声高に叫んでも他の主体が動かなければ何も始まらない。各主体が動いても、そこに共有できる理念や、具体的なプロジェクトを生み出していく仕組みがなければ、それぞれの主体が行う活動は分断されたままだ。自発性・自主性に基づいたダイナミックな相互連携を生み出していくことが出来るかどうかが、持続可能な地域づくりを推進していく際のカギとなってこよう。そのために行政が行うべきことは何か。地域の歴史、文化、地理的条件などにより異なってくるだろうが、理念づくり、関係づくり、さらには各主体の相互学習を促進できる環境づくり等を担っていくことが期待されると考えて間違いないだろう。
- 参考資料
- 「企業の社会的責任(CSR)の視点に立った持続可能な社会づくりを考える~全国に先駆けた'かわさきコンパクト'の作成に向けて」平成17年度政策課題特別研究チーム、川崎資料
- 注1
- 独立行政法人経済産業研究所、「ワーク・ライフ・バランスと妻の結婚満足度:少子化対策の欠かせない視点」 山口一男
http://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0198.html - 注2
- メルボルン市は、英国の経済誌The Economist の「世界で最も暮らしやすい都市」で、2002年、2004年に1位を獲得している。2005年は2位(1位はバンクーバー)。
- 注3
- 国連グローバル・コンパクトについては次のホームページを参照のこと。http://www.unic.or.jp/globalcomp/
- 注4
- 日本では、2006年1月に川崎市が署名している。川崎市では、グローバル・コンパクトの理念のもとに、様々な主体が持続可能な地域社会づくりに貢献するための「かわさきコンパクト」の構想が議論されている。