コラム「研究員のココロ」
会社を「少し良くする」視点
2006年09月11日 柴田 隆夫
私の専門分野は事業再生のコンサルティングで、この5年ほどで40社以上とお付き合いをさせていただいております。この活動の中で感じることは、「会社を良くして行くことは、小さなことのつみ重ねが大きい。」ということです。
企業再生案件の場合、会社存続のために「大鉈を振るってほしい。」というご希望で案件がスタートするケースは多いのですが、そんな場合でも、一区切りついてコンサルティング活動を振り返って見ますと、会社の建て直しに真に効果があったのは、人員整理といったことではなく、現場で働く社員のみなさんの小さな改善の積み重ねであることが多いというのが、偽らざる実感です。
ここでは、そんな「小さな改善」の視点について事例を交えながら挙げて行きたいと思います。
1.「すばらしい内容の改善」よりも「全員が取り組む改善」を目指す
先日、ある企業の工場見学の機会があり、その工場の壁には、現場改善の記録が掲載してありました。それは、パートの方が実践した改善で、製品不良を削減するという課題に対して、きちんとした分析に基づき対策が立てられていました。
案内されていた工場幹部の方に「すばらしいですね。」と申し上げたのですが、幹部の方の対応は、意外なことに、「改善活動に取り組んでいるのですが、効果が上がってこないのです。」というものでした。内容をお聞きすると、従業員・パートを含め1000人を超える工場ですが、活動で上がってくる改善が年間100件に満たない状況で、「やれる人だけがやる改善運動」になってしまっており、「活動内容を変えるつもりである」とのことでした。
私がお付き合いした工場の改善運動で、活動スタート後半年ほどたったところで「最近、工場の意識が変わってきたように感じる。この前現場に行ったら、タバコのポイ捨てがなくなっていたよ、なかなかできない課題だったんだけどね。」と常務から言われたケースがあります。
この工場は、従来何回か改善活動にチャレンジして長続きしなかった、という背景がありましたが、再々チャレンジにあたり、「すばらしい内容の改善よりも、みんなができる改善をやろう」ということで、「内容のレベルは問わない、分野も問わない、ただし、現場のすべての人間が改善に取り組むということを優先しましょう。」ということでスタートしました。この「全員参加を優先」させ、うまく定着したことが、常務のコメントにつながったと考えています。
多くの企業が現場改善に取り組んでいますが、なかなか定着しない、期待された効果が現れない、という企業も多いのが実態といえます。このうまくいかないひとつの要因が、「改善効果を期待しすぎる」ことにあると考えています。「改善効果を期待しない改善活動などありえない」と感じられると思いますが、「現場改善運動」の原点は、改善効果そのものというよりも、「現場の社員一人一人が、自らの業務を見直し、改善(変化)を行う機会を提供すること」「その改善(変化)実践が、当たり前のことになること」を目指す、言い換えれば、「現場の意識改革の実現」にある、というのが私の持論です。
先の事例でも活動スタートの時点で、「ポイ捨て」をやめましょうという課題をあげていたわけではありませんが、活動に取り組む中で、現場意識が変わってきたことが、効果につながったと考えています。
改善活動に取り組む場合に、「効果を最優先に求める」のは望ましくないと考える理由は、つぎのような負の現場の意識を作り上げてしまうと考えるためです。
たとえば、コンスタントに「良い」改善を続けるのはなかなか難しもので、2年も活動を続ければ、ネタ切れになります。効果があがったのだから改善活動を打ち切ればよいと考えることができますが、そのことは、「改善は必要なときにだけ取り組むもの」「普段はやらなくてもよい活動」というメッセージを社員に送ることになります。さらにこのような「効果を最優先に求める」活動が行われては消え、行われては消えという状況が続くと、「改善は、優秀な誰かがやるもので、自分がやるものではないと考える現場」「掛け声をかければ動くが、かけないと、元に戻ってしまう現場」「新しいことをやり始めても“どうせ又、元に戻る”と思って対応する現場」を作り出してしまうことにもなりかねません。極端な視点かもしれませんが、実際このような因果関係で現場が荒廃している企業も見受けられます。
当然ながら、「効果」を求めることは悪ではありませんが、短期的な「効果」よりも中長期的に「効果」を生み続けられる「基盤」整備が大切であると考えます。この基盤が整備できれば、効果は自然とついてくる、これが「内容よりも全員参加を重視する」背景といえます。
2.「改善の中身」以上に「継続の仕組み」を重視する
ある工場のコンサルティングを行っているとき、社長より「うちの社員はだらしがない、いくら掃除をしろ、といっていても、いつの間にか元に戻ってしまい、工場の中がごみだらけになってしまう。」という悩みを聞いたことがあります。
この際に、まったく掃除が行き届かないのですか?とお聞きしたところ、「工場団地の掃除だけはやっているなぁ。」ということでした。説明を付け加えると、その工場は、工場団地の中にあり、毎月第一木曜日と第三木曜日は、工場団地全体の掃除の日に決まっており、各工場が工場の外周や、共用部分を掃除するルールがある、ということでした。「自分の工場の掃除はやれないくせに、ほかの掃除はしているんだなぁ」と社長は笑っておられましたが、ポイントは掴んだようでした。
その後、この工場では、木曜日を掃除の日に決め、第1/3週は外周、第2/4週は内部の掃除をするということが定着しました。
又、あるスーパーで、週間単位の店長レポートの作成・提出を決めた際、店舗運営部の統括常務は、それと同時に、下記のような提出チェックリストを作り、「期限までに提出されたら○、期限遅れや内容不備は△、未提出は×と書いて全店に回覧する。」と会議で宣言されました。
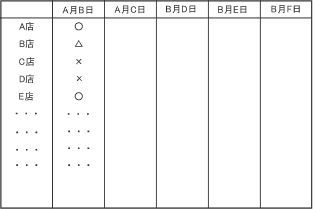
このチェックシートの効果は抜群で、3週間目には、全店の店長からレポートが提出されるようになり、新しいレポートの作成が定着化しました。常務は、「こうゆうものは最初が肝心ですから。」と笑っておられましたが、「継続の仕組みの大切さ」をご理解されているな、と感心しました。
改革、改善について、何が一番難しいのか?といえば、改革や改善そのものの実施よりも、それをどのように定着させるかです。上の例では、掃除をする、レポートを書くということ以上に、掃除をし続ける、レポートを書き続ける、ということが大切なことであり、これをどう定着させるかが、改革・改善の成否を分けるといっても過言ではありません。
又、この場合のキーワードは「ルール作り」と「チェックの仕組み」になります。
改革・改善が定着するかどうかは、「わかりやすいルールかどうか?」「実施しやすいチェックの仕組みがあるか?」という点に大きくかかわっています。極言すれば、「わかりやすいルールや実施可能なチェックの仕組みのない改革・改善は必ず失敗する。」ということにもなります。
改善・改革の実践という観点では、実務的にいかに定着させるか、が重要であり、そのためにはルールや仕組みが実施可能かどうかを吟味して行くことが大切で、「内容以上に継続の仕組みを考える」ことの意義であると言えます。
3.「正確性」よりも、「時間」を優先する
月次の収益管理を行っている際に、資料取りまとめの担当者より、「締め切りの関係で、前月の経費支出の確定値が出るのに3週間かかります。」といわれたことがあります。これについて、経費については、月別の支出想定額を作成し、月初には暫定値で月次計数が把握できるようにしましょう、と申し上げたところ、「そんな不正確な計数を役員に上げるわけにはいきません。」と強い抵抗を受けたことがあります。
又、違う会社で、暫定値ベースで収益管理を行ったところ、ある役員から「月次決算の数値とブレが出るが、この原因は何でしょう?」と質問を受け、「収益管理を行う場合、その原因を追究しないことが、肝要なポイントなんです。」と申し上げ、役員の目を白黒させたことがあります。
企業内で、数字を取り扱う場合、その多くは、財務会計に関連する数字であるため、まず「正確性」が求められることになります。財務会計、決算では、極端に言えば1円の違いでも大きな問題になりえます。そんな中で、「月次の損益が100万円違おうが、1000万円違おうがたいしたことではありません。」などと申し上げれば、なんといういい加減な、という感覚をお持ちになるのも当然といえば当然のことです。
ただし、この場合、こちらが申し上げるのは、「目的を考えて判断しましょう。」ということです。財務会計の目的は「過去の企業活動の内容を、社外の利害関係者に正確に伝える」ことであり、この意味で、1円たりともおろそかにしない対応が必要になります。一方、収益管理などは、過去の数字を良くするためではなく(やれば粉飾になります)、これからの数字を良くする、「将来の業績を改善させること」を目的に実施します。数字を見るだけではなく、「収益改善の行動」につなげることがなければ、収益管理を行う意味がありません。この意味で、正確性よりも、時間を優先させ、可能な限り早期に実績を把握し、その対応策を早期に実施する、たとえば商品売り上げが計画を下回っているのであれば、その増加施策の実施を、顧客別採算が悪化しているのであれば、特定顧客との採算改善折衝の実施を意思決定し、企業活動につなげていくといった活動が収益管理においてぜひとも必要になります。それが、「正確性」を求めることで阻害されては活動を行う目的に反するといえます。
収益管理に限らず、企業活動にはすべて目的があり、その目的達成が活動を行う意義なのですが、現実には、しばしば、「常識」的な視点で、本来その活動目的とは違う、時には相反するような目的が付与され、目的達成の障害になってしまうケースがあります。上記の例では「数字は正確であるべき」という常識が、目的達成の障害になっており、「正確性よりも時間を」優先することは、活動目的を十分に認識し、常識的な視点に惑うことのないようにするということです。
以上、3つの視点が参考になれば幸甚です。

