コラム「研究員のココロ」
新会社法下の中小企業経営
~あるべき機関設計のあり方~
2006年04月03日 豊田憲和
昨年6月に成立した新会社法は、一般的には日本の企業の大部分を占める中小企業の個性に合わせたものであり、各社の実態に対応できるような規制緩和が図られている。つまり、中小企業が経営しやすくなるよう改正が行われたことになる。会社の機関に関しても例外ではなく、定款自治の拡大とともに、幅広い機関設計が可能となった。しかし一方で、自由度が高まったのはいいが、自社にとってはどのような機関設計が望ましいのか悩む中小企業も少なくないのではないだろうか。
そこで本稿では、今回の改正が会社の機関について具体的にどのような影響を与えることになったのか、それを受けて、新会社法下における中小企業の機関設計はどうあるべきかについて考察する。
1.新会社法により変化する会社の機関
新会社法下における会社の機関構成のパターンは、2つの切り口のマトリックスで区分される。1つは大会社か大会社以外の会社か、もう1つは公開会社か非公開会社かという切り口である。
前者の基準はこれまでと同様であり、資本金では5億円、負債総額では200億円を境に大会社かそうでないかが区分される。
後者の基準は、全部の株式について譲渡制限が付されているかどうかということになる。つまり、定款上発行し得る株式の一部についてでも株式譲渡制限が付されていない場合は全て公開会社となり、全株式について譲渡制限を付している場合のみが非公開会社に分類される。
そして、それぞれの切り口によりどのマトリックス区分に会社が分類されるかで、機関構成のパターンが変化する。具体的には以下の表のようになる。
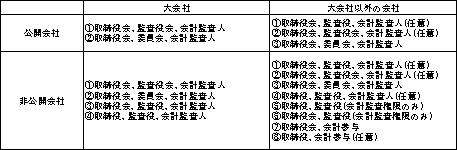
※株主総会は全てに共通するため省略
なお、会計参与に関しては、基本的にはそれぞれの会社で任意に追加設置することが可能となっている。
上述のような機関設計は、会社区分による制約さえクリアすれば、定款にそのことを記載することで行い得る。新会社法では定款自治がかなり拡大されたと言えるだろう。しかし、その一方では、自由度が高まったのはいいが、信用力とコストの両側面を考えた際に、自社の機関設計はどうあるべきかに関して悩んでいる経営者も少なからず存在するのではないだろうか。
例えば、新会社法においては、最低資本金を機軸とする債権者保護の仕組みの撤廃、配当の頻度に関する制限の撤廃による配当の自由化(453条、454条1項)等、債権者側にとってはその保護が後退したともとれる改正が行われている。そのため、取引先や外部の出資者から安定的な取引や資金調達を確保する必要のある企業にとっては、外部からの信頼確保はこれまで以上に重要であり、機関設計はその基礎となるため、十分な体制を整える必要がある。とはいえ、必要以上に機関を充実させることは、余分なコストをかけるに過ぎず、新会社法の恩恵を十分に享受できないことから、会社経営上好ましくないと言えよう。
2.中小企業における機関設計の考え方
それでは、中小企業の機関設計はどのようにあるべきだろうか。上記表のうち、大会社以外の会社に関して、パターン別に検討する。
(1)非公開会社の場合
このタイプの企業としては、基本的には、所有と経営が分離していない、いわゆる同族会社が想定される。これらの企業では、仮に取締役会が設置されていたとしても、実質的には機能していないような場合が多い。従って、実態に即して機関設計を行うのであれば、取締役のみ(小体企業であれば一人)という形がコスト面からは最も有利であろう。この場合、監査役を設置するかどうかを選択することができるが、こういったタイプの中小企業においては、これまで名目的な監査役を設置してきた企業が少なくないことから、積極的に監査役を設置する理由はないと思われる。
ただし、同族会社であったとしても、役員である同族関係者の数が多く、複数の利害関係が生じやすい場合は、取締役会の設置が必要となろう。この場合は監査役の設置が義務付けられるため、機関構成としては、取締役会、監査役又は監査役会となる。
また、従業員規模が一定以上の企業の場合も、役員を同族のみで固めることは望ましくないと考えられるため、取締役会及び監査役又は監査役会を設置する必要があると思われる。ここで、監査役又は監査役会の代わりに委員会を設置するという選択もあるが、委員会を設置するには社外取締役を過半数入れることが必要になるため、後に述べるように上場準備に入っているような場合を除けば、非公開会社にとっては抵抗感のある場合が多いように思われる。
なお、会計参与については、確かに信用力の面では銀行等にアピールはできるものの、社外取締役と同様の責任が課される分、報酬もある程度必要になることが想定される。従って、非公開会社に関して言えば、監査役や会計監査人、委員会等と併用することは、コストパフォーマンスを考えた場合あまり有用ではない。会計参与を置くのであれば、取締役又は取締役会と会計参与という構成が妥当であろう。
非公開会社であったとしても、上場準備に入っているような企業の場合は、上場前の段階から会計監査人を設置して公開に備える必要がある。また、公開企業を目指すのであるから、機関設計は、取締役会、監査役又は監査役会、会計監査人となる。上場に際して、積極的に社外の知見を取り入れるという方針を打ち出すのであれば、監査役又は監査役会の代わりに、社外取締役を含めた委員会を設置することも考えられる。これらの機関設計については、早めに準備を行い上場後の会社運営に慣れておくことが望ましい。
(2)公開会社の場合
このタイプの企業は、ベンチャーキャピタルや銀行等に出資してもらっているなど通常所有と経営がある程度分離している段階にあることが多いと想定される。このため、取締役会及びそれを監視する機関が必要になる。低コストでの設計を行うのであれば、取締役会、監査役という機関設計になるが、この場合監査役には業務監査及び会計監査の十分な実施が期待されることとなり、中小企業においてそういった人材確保ができるかどうかが問題となる。
会計参与に関しては、企業の方針にもよるが、通常会計監査人と併用することまでは必要ないと思われる。従って、会計参与と会計監査人についてはどちらかを選択して設置するという形が妥当であろう。
(3)子会社の場合
子会社の場合には、親会社による子会社管理や監査体制が十分であれば、取締役一人のみという形も可能であろう。ただし、当該企業がグループの中で重要な位置付けにある場合には、取締役会、監査役又は監査役会、必要に応じて会計監査人を設置する等、それなりにしっかりとした体制を構築することが望ましい。
3.まとめ
本稿では、新会社法によって機関設計がどのように変化するかを整理した上で、中小企業のパターン別に、あるべき機関設計に関して検討を行ってきた。今後はこれまで以上に信用力とコストを考慮して、自社にふさわしい機関を設計しなければならない。自社の発展段階に応じて、適切なガバナンスを確保できるような機関設計を行うことが重要である。
<参考文献>
- 酒巻俊雄監修、株式会社ミロク情報サービス税経システム研究所編「新会社法と中小会社の実務対応」中央経済社、2005年
- 相澤哲、石井裕介「株主総会以外の機関(上)」旬刊商事法務、第1744号(2005年10月5日)
- 相澤哲、石井裕介「株主総会以外の機関(下)」旬刊商事法務、第1745号(2005年10月25日)

