コラム「研究員のココロ」
現場第一線が持つ情報をビジネスチャンスにつなげるために
2005年05月09日 高村将文
「いいものを作れば必ず売れる」。このような思い込みが失敗を招く例は決して少なくない。商品の良し悪しを最終的にジャッジするのは、あくまでも“顧客”だからである。だからといって、顧客との接点が多いとされる現場第一線の営業マンに商品案を出させても、真に有益な情報を吸い上げるのは簡単でない。情報取得を単純に営業マンへ任せてしまうと、特注対応や値下げの要求など、顧客から言われたことをそのまま伝えてくるケースが多いからだ。現場第一線が持つ情報をビジネスチャンスとして活用するためには、まず、本社部門が、営業マン等の現場第一線に、有益な情報を取得するためのポイントについてアドバイスを与えたり、適切な書式を整備して情報の洗い出しを手順化したりする等の仕掛けが必要であろう。
本稿では、私の知人が経営者の1人として活躍している企業(A社:医療機器メーカー)の事例をご紹介する。
A社では、営業活動を商品開発に活かすために、営業マンに新商品企画に役立つアイディアの提供を義務付けている。それは、『商品アイディアシート』という指定された用紙に、“顧客との面談内容”と、“その面談から思いついた商品アイディア”を自由に記述するものである。しかし、提出されるアイディアは、売れる見込みの薄い商品案がほとんどで、制度自体が形骸化しかけていた。そこでA社では、社内調査を行い、次のような問題点を明らかにした。
- 問題点1
- 営業マンは「顧客にとってのメリット」 を重視して記述している意識があるものの、実際は、「思いついた商品機能」を並べているだけだった。
- 問題点2
- 営業マンは「具体的な提案」を記述している意識があるものの、仕様を細かく書いているだけで、商品企画部門の社員が読んでも、開発検討のステージに進めるための具体的な判断材料になっていなかった。
そこでA社では、「商品アイディアシート」を次のような考えに基づき変更した。
- 「商品機能」と「顧客にとってのメリット」を分けて考えさせる。
- 「商品化への判断材料」について共通した認識を持たせる。(例:営業として許容できる販売価格の目安はいくらか。その価格で販売した場合、どの程度の販売量が見込めると考えているのか。競合との兼ね合いからいつまでに発売してほしいか、等)。
変更内容
シート上段には、まず、思いついた商品の概要を記入していただく。ここでは、開発への判断材料となることを意識して記入する。なお、判断材料の項目例(現場からみた市場性、ターゲット、許容価格、開発期限、競合情報 等)を、記入欄の横に、予め記しておく。そして下段には、その商品によって、顧客自身にどのようなメリットがあるかを記入していただく。 “顧客が不満に思っていること”等、意識すべき視点は、記入欄の横に予め記しておく。「顧客の4C視点(Customer solution、Customer cost、Convenience、Communication」等も参考にした。
A社では、このように再設計した「商品アイディアシート」でテスト運用を行い、提出された情報の特性に変化があったかどうかを、KeyGraph(※注1)とよばれるデータマイニングツールで検証した。
- (※注1)
- KeyGraph:データマイニングツールの一つ。文章形式データの各単語の関係性を、黒丸、赤丸、実線、点線 で可視化する。同じ文章に出てくることの多い単語は、黒丸と実線で囲まれた“島”で表される。赤丸は、黒丸より頻度の低い語であるが、“島”と“島”の“橋渡し”を行うような単語で、意思決定にとって重要なキーワードやビジネスチャンスにつながるヒントが含まれていることがある。〔詳細は、『ビジネスチャンス発見の技術』(岩波アクティブ新書)をご参照いただきたい。〕
テスト記入で提出されたもの
- 過去に提出したシート
- 新フォーマットで、Aと同じアイディアを書き直したもの
- 新しいアイディア(新フォーマット)
まず、旧シート内容に基づくKeyGraph(図A)と、同内容を新シートで記述したもののKeyGraph(図B)を比べると、図Aでは、“島”がほとんどなく、赤丸もゼロであるのに対し、図Bでは、複数の“島”と赤丸が出現した。これは、同じアイディアについての記述でも、新シートに変更することで、情報の内容が豊かになったことを示唆している。
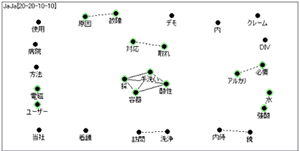
図A : 旧シートでのKeyGraph (情報7件)
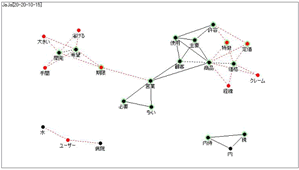
図B :新シートでのKeyGraph (情報7件)
図Bに新しいシート2枚の内容を加えたKeyGraph(図C)では、さらに“島”と“橋”がはっきりと現れた(※KeyGraphの設定はA~Cいずれも同条件)。KeyGraphの見かたをご存知ない方でも、何となく違いはお分かりいただけると思う。
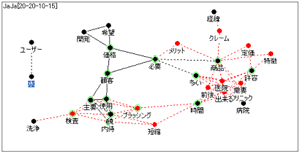
図C :新シートでのKeyGraph(B)に新規シート2枚追加 (情報9件)
商品アイディアシート(改訂版)に対する各社員の感想
- 営業マン
- 「新シートではポイントが明示されているので、筋道を立てて記入できる。」
- 企画部門
- 「観察力の向上に繋がり、無駄な情報シートが少なくなるだろう。」
- 技術開発部門
- 「実際に、これまで出ていなかったキーワードや顧客の不満点が現れている。」
上記KeyGraphの結果や読み手である企画部門・技術開発部門からの評価をみても、ポイントを押さえながら記入できるシートに変更することで、営業マンが適切に有益情報を導き出すことへの期待が高まるといえよう。ここでのポイントは、(1)顧客(買い手)の立場になりきることと、(2)評価者(読み手)の立場になりきることである。実際にA社では、これらのテスト結果を受け、新たにこの制度を本格的に見直すことになった。
以上、A社の事例をご紹介したが、一般的にも、本社側からきちんと「仕掛けていく」ことで、営業マンの情報の捉え方が変わり、より的確に有益情報を掴めるようになると思われる。(※ちなみにA社では、「商品アイディアシート」のフィードバック体制が未確立であったり、この制度に対する社員の考え方に齟齬が見られる等、その他の課題が多いことも付記しておく。)
- 参考文献:
- ・Ohsawa Yukio; McBurney 他:『Chance Discovery』 2003年
- ・大澤幸生:『チャンス発見の情報技術』東京電気大学出版局2003年9月 他

