コラム「研究員のココロ」
本物の専門職の養成を
~分権時代の自治体と職員の自立の両立~
2004年04月05日 山中 俊之
「職員の行政マンとしての専門性を高めないといけない。」
「これまでのようなジェネラリストでは対応できない。」
自治体の組織人事改革を専門とする筆者が、多くの自治体関係者から聴く言葉である。確かに、「何でも屋」職員では、分権時代の複雑化高度化した住民ニーズに対応できない。職員の専門性を高めることの必要性は論を待たないであろう。
一方、「あなたは将来管理職として働きたいですか。専門職として働きたいですか。」というある自治体での全職員アンケート調査結果を見ると、全体として専門職志向が強いことがわかる。特にこの自治体の場合、20代、30代の若い世代の職員に専門職志向が強いことが分かる。
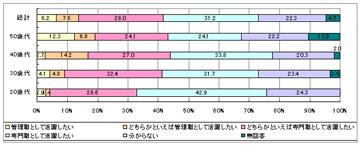
このような、自治体側の職員の専門性を求めるニーズと職員が専門職志向を有していることを両立させること。これが、分権時代の自治体改革の一つのポイントであろう。
では、一体どのような点に留意して、専門職を養成していくことが望ましいのであろうか。これまで、多くの自治体職員に人事改革についてインタビューをしてきた経験や自らの前職の公務員経験から、以下の点に留意することが肝要であると考える。
第一に、高度専門家と単なる習熟者を峻別することである(後掲の図参照)。自治体の場合、比較的定型的な業務に長年従事している職員を専門職として位置付けている場合が多い。しかし、これらの職員は、専門家というよりも習熟者として位置付け、高度な専門知識(例:公認会計士に匹敵する会計学の知識、大学で教える程度の福祉の知識)を有する専門家を別途養成することが必要である。これらの高度専門家は、外部からも積極的に採用することが望まれる。
第二に、30代半ばまでは広い分野を担当して経験を積ませて、30代後半に、個人の希望や適性、専門性の有無などによって、専門職と管理職を峻別する。管理職と専門職は、給与など処遇上は基本的に対等にする。一部の外部から採用した高度専門家(例:企業誘致に関して卓越した実績の有るコーディネーター、多くの外郭団体の経営改善の実績のあるコンサルタント)には、自治体幹部を上回る給与を出す。専門職になることが決して処遇上不利ではないことを明確にすることが、専門職養成のポイントである。専門家は高度な専門性を有する人材であるので、そのような高度な専門性がない場合には、専門家とは認めない。高度な専門性もなく、管理職に昇進できない場合には、習熟者やその他職員として、昇進・昇格などの処遇面では一定の不利益を受けることはやむを得ない。
第三に、管理職と専門職との垣根を低くして、両者の移動を容易にしておくことである。専門職の職員となったが、その後一定の要件を満たせば、管理職に就任することも認める。一方で管理職の職員でも専門性は当然ながら必要である。例えば課長がその専門性を生かして、専門家として部下なしの専門家になる可能性を残す。これは、人事配置の流動性・柔軟性を確保することにも繋がり、また職員個人としての選択の可能性も高めることになる。
以上の内容を図で表すと以下の通りである。
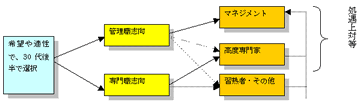
このような専門職制度の導入は、自らの専門性向上に向けて、自治体職員に自立的な行動を促すであろう。また、外部専門家の採用もより簡易になるであろう。効果的な専門職制度の導入が、職員個人の自立を促し、ひいては自治体全体のパフォーマンスを高めることは間違いない。
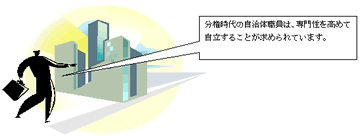
※コラムは執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

