コラム「研究員のココロ」
テレビゲームに学ぼう!
~ユーザーを惹きつけて離さないWebサイト構築のコツ~
2008年01月21日 足代 訓史
1. テレビゲームはなぜ止められない?
先日、実家に帰省し友人の家を訪ねた際に、ある大ヒット商品のテレビゲーム(以下、ゲーム、と表現)で遊ぶ機会がありました。中学校・高校時代には友人同士で集まって延々ゲームに興じたものですが、最近はゲームで遊ぶことが皆無になった私は、懐かしい気持ちでゲームのコントローラに手をかけました。
「最近のゲームは何だか難しそうだし、まあ、自分ももう学生じゃないし、そんなにゲームに夢中になることもないか…」などと考えゲームを始めた私の予想は見事に裏切られました。そのゲームは操作方法が非常に明快で、そして「ハマってしまう」ものだったのです。結局その日は友人同士久々に、延々とゲームを楽しんでしまいました。
いきなり筆者のプライベート・トークから入ってしまいましたが、読者の皆さんの中には上記のような経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。なぜ、ゲームにわれわれは「ハマってしまう」のでしょうか。そしてハマってしまう理由を、何か他の設計に活かすことはできないでしょうか。
2. ゲームに夢中になる理由
われわれがゲームに夢中になってしまうのにはどのような理由があるでしょうか。操作やマニュアルが簡単で遊びやすい、ゲームの中で主人公の成長を仮想体験できる、ストレスが発散できる、など理由は人それぞれかもしれません。
このようなゲームに夢中になる理由を、ゲームクリエータで立命館大学教授でもあるサイトウ・アキヒロ氏は、ゲームに夢中にさせるノウハウである「ゲームニクス(注)理論」として体系化しています(図1参照)。
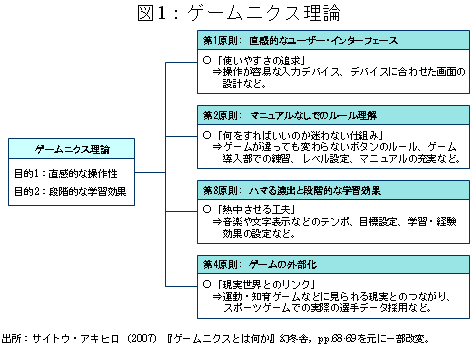
サイトウ氏によるとゲームニクス理論には2つの目的があります。この目的は、ユーザーに夢中になってゲームに取り組んでもらうための必須条件のようなものともいえます。1つは、誰でもすぐにゲームを動かすことができる「直感的な操作性」を実現すること。もう1つは、ユーザーをゲームに続けて取り組ませるための「段階的な学習効果」を実現することです。
そしてこの2つの目的を実現するために、大きく分けて4つの原則が存在します。
第1の原則は「直感的なユーザー・インターフェース」です。これは、操作が容易なゲームのコントローラの設計などに代表される、使いやすさの追求ともいえるものです。
第2の原則は「マニュアルなしでのルール理解」です。ゲームで遊んだ方ならお分かりかもしれませんが、ゲームソフトが違っても操作方法が似通っていることはしばしばあります。また、ソフトを入れてゲームを始めるとまず操作方法を練習する画面が出てくることがあります。こういった設計はユーザーが「何をすればいいのか迷わない仕組み」といえます。この仕組みによってわれわれは気楽にゲームを進めることができるのです。
第3の原則は「ハマる演出と段階的な学習効果」です。これは、ゲーム内に流れる軽妙な音楽や、ゲーム内で成長していく主人公、ゲームの進行度によって変わるレベル、などを想像していただければお分かりかと思います。こういった設計によってついついゲームに熱中してしまうことは多々あるでしょう。
第4の原則として「ゲームの外部化」があります。最近流行した脳をトレーニングするゲームソフトなどはゲームの世界に閉じることのない内容であり、われわれの日常生活とのかかわりを持っています。また、近年の野球ゲームやサッカーゲームなどは、通常の競技のファンがうなるほど精巧に選手の能力データや動作が作り上げられています。現実世界とのリンクがあるからこそわれわれはまたゲームに「ハマッてしまう」のです。
3. Webサイト構築におけるインセンティブ設計
上で見たユーザーをゲームに夢中にさせるノウハウを、他のものの設計に活かすことはできないでしょうか。筆者は日々、クライアント企業のWeb関連の新規サービス立ち上げや業界リサーチに従事していますが、Webサイトの構築には、このゲームに夢中にさせるノウハウが存分に活用できると見ています。
企業のWebサイト・Webサービスにユーザーを惹きつけて離さないためのインセンティブ設計には下記の2つがあります(図2参照)。
○物質的インセンティブ
○心理的(非物質的)インセンティブ
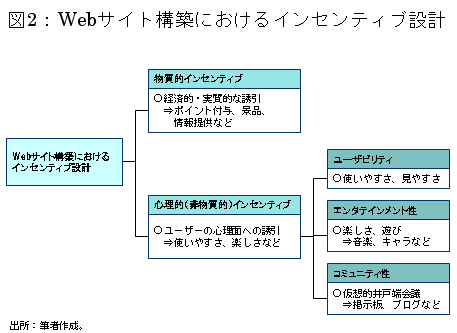
前者の物質的インセンティブとは、たとえばユーザーへのポイントの付与や、景品の提供などに代表される、経済的・実用的な誘引といえます。ECサイトにおいて商品を購入するごとに購入金額に応じたポイントが溜まるためそのサイトを使い続けてしまう、という方も多くいらっしゃるかと思います。また、企業がホームページで企業情報を発信することも、ユーザーを惹きつける物質的(実用的)なインセンティブ設計といえるでしょう。
一方、後者の心理的(非物質的)インセンティブとは、表示が簡単であるためそのサイトを気楽に使える、そのサイトにある掲示板にコメントを残したり、コメントをもらったりすることが楽しい、といったユーザーの心理的側面に訴えるものです。心理的インセンティブはさらに3つに分類することができます。
- ユーザビリティ
- エンタテインメント性
- コミュニティ性
ユーザビリティとは、一言で言ってしまえば「使いやすさ」です。どこに目的のページがあるのか良く分からないような複雑な構造のページはユーザーを辟易させますが、「道案内の良くできている」サイトはユーザーを安心させ、繰り返し訪問してもらえるようになります。
エンタテインメント性とは、そのサイトが提供する「楽しさ」です。たとえば、綺麗な映像や音楽がサイトで流れる、ユーザーの分身をキャラクターとして登録できる、といった「遊び」に近い感覚のサービスが提供されているサイトはユーザーを惹きつけていることが多いです。
3つめのコミュニティ性とは、掲示板やブログといったサービスに代表されるような「仮想的な井戸端会議」のことを指します。自身の興味があるテーマに関して他ユーザーと掲示板やメールを使って自由に意見の交換を行うことに楽しさを覚えるため、そのサイトからユーザーが離れられなくなるのです。
筆者はこれまでにいくつもの企業のWebサイトやWebサービスを見てきましたが、その成否を分けているのはこれら心理的インセンティブの設計如何にあると見ています。心理的インセンティブの設計が成功の要因と言われているサイトは多くありますが、たとえば、日本におけるSNS最大手のmixi(ミクシィ:www.mixi.jp/)の成功の要因の1つとして、その分かりやすい画面設計や日記を媒介とした仮想コミュニケーションの提供が上げられています。
実際、ユーザーを惹きつけることができていないサイトには「使いにくく分かりにくいサイト」「無味乾燥としたサイト」「サイト上で他ユーザーとのコミュニケーションが取れない、企業からの一方的な情報発信しかないサイト」が多いのです。
4. 「ハマッてしまう」Webサイトを構築するために
このWebサイト構築にとって重要な心理的インセンティブの設計を行う際に、ゲームに夢中にさせるノウハウを羅針盤として活用できると筆者は考えています。
たとえば、上で見たゲームニクス理論(図1参照)の第1原則「直感的なユーザー・インターフェース」は、サイトのユーザビリティを検討する際に、第2原則の「マニュアルなしでのルール理解」は、サイトで提供するサービスの簡便な利用方法を設計する際に、活用することができるしょう。
第3原則の「ハマる演出と段階的な学習効果」は、エンタテインメント性やコミュニティ性を検討する際の手本となります。たとえば、自身の生活日記を付けていくことでユーザーが自己投影できるキャラが育っていくサービスの提供や、他ユーザーから評価されるコメントを掲示板に残せばそのユーザーの「番付」が上がっていくようなサービスの提供が考えられるでしょう。
第4原則の「ゲームの外部化」も、たとえばダイエット日記やユーザーのキャリアアップのための学習コンテンツの提供といった、現実とリンクしたサービス提供の参考となるのではないでしょうか。
Webサイト構築にはWebサイト構築のノウハウがあるため、ゲームに夢中にさせてしまうノウハウをそのままWebサイト構築に活用できるとは筆者も考えていません。しかし、上記で見た通りWebサイト構築の心理的インセンティブの設計に繋がる部分は十分にあるのではないでしょうか。
読者の皆さんが日々夢中になって訪ねてしまうWebサイトには、皆さんがゲームに夢中になるのと同じ仕掛けが潜んでいるかもしれません。如何でしょう、思い当たる節はありませんか。
少しでもピンと来た方は如何でしょうか、「ハマッてしまう」自社のWebサイトを構築するために、日本のお家芸の1つであるゲームからそのノウハウを学んでみませんか。
- (注1)
- サイトウ・アキヒロ氏による造語。「テレビゲーム」に、エレクトロニクスなどの「ニクス」という接尾語を加えて、「ゲームニクス(GAME-NICS)」となった。「ゲームを科学した」という意味を持つ。
【参考文献】
サイトウ・アキヒロ(2007)『ゲームニクスとは何か 日本発、世界基準のものづくり法則』幻冬舎。

