クローズアップテーマ
4-9.米国における疾病予防:疾病管理(Disease Management)編(1)
2007年10月16日 山田敦弘
■疾病管理への期待
Disease Management Programs(以下疾病管理プログラム)が必要な人すべてに提供されるためには、医療改革に組み込まれる必要があると米国疾病管理協会(The Disease Management Association of America)の第9回総会で提案された。米国の総医療費のうち75%が予防可能な疾病への治療費として費やされており、協会は疾病管理などの予防へシフトするべきであると考えている。米議会等でも医療費抑制策として注目されており、次期Health Reform(医療改革)が実現するならば、何らかの形で盛り込まれる可能性が十分にある。
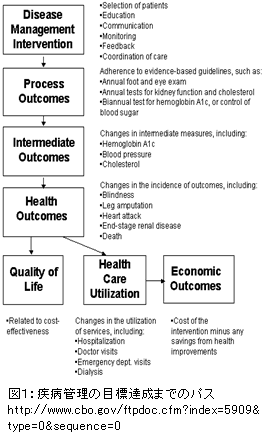 ■疾病管理の手法
■疾病管理の手法 米国でいう疾病管理プログラムは、疾病管理介入(Disease Management Intervention)を行い、手法の適正をみるプロセス成果(Process Outcomes)、検査値の変化をみる中間成果(Intermediate Outcomes)を明らかにしながら、症状の改善などの健康状態についての成果(Health Outcomes)を達成し、その結果として生活の質の向上(Quality of Life)や医療費の削減(Economic Outcomes)を実現する手法である(図1参照)。その特徴を2点あげると、ひとつは、介入やテストを何度も繰り返し実施することである。介入は主に電話により行われており、そのノウハウが疾病管理プログラムの中核となることから、疾病管理プログラムを実施する団体の9割以上が自前のコールセンターを保有している。もうひとつは、対象者に自己管理を徹底させることにある。Web画面や紙シートを使って、対象者が自ら目標を設定し、その達成を電話やメールなどを使って専門家が助言をする手法で行われている。ITが進展しても、対象者が自ら意識しなければ達成は困難であることや、サポートするのは人間であることは変わらないようである。次に具体的なプログラムを紹介する。
■Indiana Chronic Disease Management Program(ICDMP)の取り組み
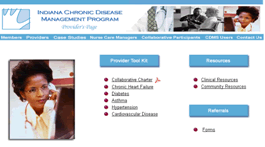 ICDMPは、州や自治体からの依頼を受けメディケイド(貧困層対象の公的医療保険)の対象者に、疾病管理サービスを提供している団体である。ICDMPでは、面談、コールセンター、教材や情報システムを使った情報提供の3つ手法を使って、ハイリスクの対象者には看護師が、またその他のすべての対象者にはコールセンターのオペレーターが個々にアプローチする方法で、疾病管理サービスを提供している。オペレーターによる相談は、疾病に関することに限定せず、医師や医療機関とのかかわり方やコーディネイトから生活環境にかかる相談にまで幅広く対応する。
ICDMPは、州や自治体からの依頼を受けメディケイド(貧困層対象の公的医療保険)の対象者に、疾病管理サービスを提供している団体である。ICDMPでは、面談、コールセンター、教材や情報システムを使った情報提供の3つ手法を使って、ハイリスクの対象者には看護師が、またその他のすべての対象者にはコールセンターのオペレーターが個々にアプローチする方法で、疾病管理サービスを提供している。オペレーターによる相談は、疾病に関することに限定せず、医師や医療機関とのかかわり方やコーディネイトから生活環境にかかる相談にまで幅広く対応する。■ICDMPの事例から読み取れること
ICDMPが疾病以外の課題も解決する狙いは、あらゆる障壁を取り除き、対象者の自己管理を可能にすることにある。その先にこそ、前述した生活の質の向上(Quality of Life)や医療費の削減(Economic Outcomes)の実現があると認識しているようである。
平成20年度から日本で実施される特定健診・保健指導の義務化では、対象者に対するアプローチを手法×回数(時間)=ポイントという仕組みで実施し、成果をあげようとしている。しかし、この仕組みでは、ポイントを積み上げることに重点を置き、ICDMPの事例で紹介したような、何度も対象者にアプローチし自己管理の妨げとなる問題点を解消しながら、対象者に合ったアドバイス・指導方法を探り当てるような重要なプロセスを確保できない可能性がある。成果をあげるために、何をするべきなのかを常に念頭に置いた保健指導の実施が望まれる。
【参考文献】
「Reporter's Notebook; Disease-management group looks to larger role」Modern Healthcare Online, September 18, 2007
(http://modernhealthcare.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070918/FREE/309180024)
「An Analysis of the Literature on Disease Management Programs」Congressional Budget Office, October 13, 2004
(http://www.cbo.gov/ftpdoc.cfm?index=5909&type=0&sequence=0)

