第10回 「ゼロからの研究開発戦略」シリーズを終えるにあたって
2005年7月1日 浅川秀之
(1)「ゼロからの研究開発戦略」:これまでの9つの小論を振り返って
第8回「顧客の要求曲線を意識したイノベーション・マネジメント」においては、主に顧客の要求、つまり製品やサービスを受け入れる側(=市場)の要求を意識したイノベーション・マネジメント方法について、ハーバード・ビジネススクールの教授であるクレイトン・クリステンセンの提唱するイノベーション理論を参考に、特に顧客の要求と技術の不確実性の両面を考慮した分析手法の提案を行った。さらに具体的な製品を例にとり、この分析手法のケーススタディを試みた。第9回「技術および市場の不確実性に柔軟に対応するためには」においては、市場側の要求やその不確実性の捉え方に加え、技術の不確実性も合わせたマネジメントの重要性について述べた。
先に紹介した2つの小論の共通的な示唆は、「技術の不確実性と市場の不確実性に柔軟に対応することの重要性」ということである。それ以外の小論(第1回~第7回)に関しても、直接的に上記の示唆に関与する内容となってはいないものの、いずれも昨今のような変化の激しい市場の状況、技術変化などにいかに柔軟に対応していくべきか、ということを主な課題とし、それに対する何らかの見解や示唆を述べたものが多い。
例えば、第4回「不確実性やリスクを指標としたアウトソーシングマネジメントについて」においては、製品開発や研究開発の一連の流れ(研究開発における線形リニアモデル)の中において、各手順におけるアウトソーシングの際の留意点について述べている。この中で述べられているポイントは、「自社内の不確実性・リスク分布を的確に把握した上で、必要に応じてアウトソーシングを実行する」ということである。アウトソーシングとインソーシングの判断について、コストという特定の指標に頼るのではなく(勿論コストという指標を軽視している訳ではない)、製品開発サイクル一連の流れの中での、不確実性・リスクを意識したアウトソース、インソースのマネジメントが重要であるということについて述べている。
「ゼロからの研究開発戦略」という本シリーズの表題からもわかるように、当初からある一貫したテーマを持った上で各回の小論をまとめてきたわけではない。その時々に応じて個人的に興味深いと思われる内容を短いながらも論文形式でまとめたものとなっている。そのような中、敢えて示唆的なものを抽出するのであればそれは、先に述べた「技術の不確実性と市場の不確実性に柔軟に対応すること」という点であろう。全10回という限られた範囲内において、この「柔軟に対応することの重要性」について僅かではあるが分析、整理ができたのではないかと考えている。しかしながら、実際の現場でアクションを起こすための具体的な示唆、つまり技術や市場の不確実性に対して、企業の経営陣や各開発担当者はどのように対応すべきかということや、いかに研究開発の効率性を向上させるのか、といったことについてはほとんど触れることができなかった。また、ケーススタディや文献等をベースとした調査分析という意味でも十分という訳ではなく、まだまだ課題が残る。これらの点に関しては、次のシリーズにてさらに調査分析、研究を進めていきたいと思う。
本稿後半では、本シリーズを終えるにあたり、これまでの小論作成や簡易分析結果などをもとに、いくつかの仮説を立て、これら仮説の検証・分析およびさらなる仮説の追加などを次シリーズ(「研究開発の効率性を高めるためには(全10回)」)の目的(課題)としたい。
(2)研究開発戦略を考える上で重要な視点~5つの仮説~
1)研究開発成果をトレースすることの重要性
製造業企業やサービス提供事業者にとって、いかに「自社の“強み”を活かして“ニーズ”に合致した“製品やサービス”を提供できるか」ということが重要となる。
“強み”とは、自社の持つ技術的もしくは組織的な強みや、マーケティング力など、各企業によって様々であり、いわゆるコア・コンピタンスと呼ばれるものである。以降においては主に製造業企業の研究開発戦略を想定するため、ある特定の技術的な“強み”を想定していただきたい。いかにこの“強み”を発揮するかということは、まさに技術マネジメント(MOT:Management of Technology)の問題である。ここで重要な点は、技術だけに注力していては、製品には結実するかもしれないが、利益には結実しない可能性が高いということである。つまり自分では“良い”と思って製品化しても、市場の“ニーズ”には往々にして合致せず、結果として利益に結びつきにくいということである。このような状況を回避するためには、市場の“ニーズ”を考慮した上で“良い”と判断できる、何らかの具体的な仕組みを自社内に確立することが必用となろう。
下図表は、技術の重要度をトレースする概念(DOTS:Dynamic Outcome Trace System)を示したものである。
【図表】 DOTS(Dynamic Outcome Trace System)のイメージ 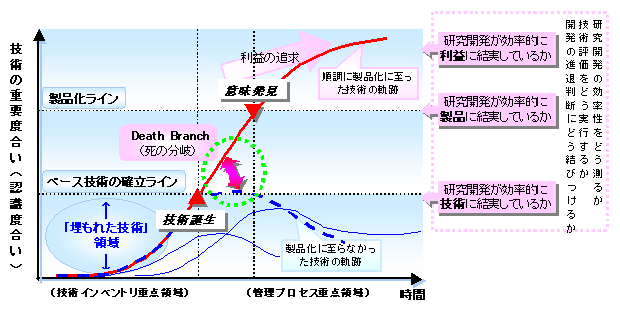
(出所) 日本総合研究所通信メディア・ハイテク戦略クラスター新保・浅川[2004]
DOTSの概念で重要な点は、ニーズは常に変化するということ、及びそれに応じて技術の重要度もダイナミックに変化するということである。技術そのものが他関連事項とほとんど影響を受けず発展、進化していくことはあろうが、ニーズやその他関連技術などとの相対的な関係や、当該技術に付随するビジネスモデルの優劣によってもその重要度が変化するということに注目せねばならない。このようなことを念頭に置いた上で、自社内に眠る何百、何千という技術群をダイナミックにトレースする仕組みが必要となろう。
⇒【仮説1】:“強み”を活かして“ニーズ”に合致させるためには、当該技術の重要度をダイナミックにトレースする系統だった具体的な仕組みを自社内に持つことが必要ではないか。
≪補足:DOTSの縦軸に沿った位置付けを考える上で参考となる視点など≫
西村吉雄(2003)[注1]は、研究開発の価値を2種類で分類するシンプルな枠組みを示している。1つは「(a)専門的な研究者コミュニティの内部で評価される学問的な価値」であり、もう1つは「(b)専門分野外の一般生活者に提供する価値」である。1980年代のいわゆるバブル時期では、日本企業の多くは経済的な利益に直結しないような基礎研究においてもこれを強化する傾向にあり、大学に頼ることなくノーベル賞指向の研究も企業が担うという傾向が見られた。つまり、先に示した2つの価値のうち、前者の価値(a)を追及するというスタンスである。
しかしながら、このような状況はバブル経済崩壊とともにデフレ経済へと一変し、日本企業は、基礎研究所や中央研究所の縮小を急がざるを得ないこととなった。このような状況は現在においても尾を引いており、基礎研究所や中央研究所の存在意義が問われるようになってきていることからも伺える。
エレクトロニクスメーカーやその他の製造業企業は、営利企業であることは言うまでもなく、従って研究開発投資によっていかほどの利益を効率的に得ることができるのか、ということが重要な課題の1つとなる。専門的な研究者コミュニティの内部で評価される学問的な価値というものも勿論重要であるが、学術的な観点からの科学技術の発展や、知の創造という観点では、利益に結びつかせることが必ずしもその誘因となっていない。しかしながら、当該企業が営利企業である以上「専門分野の外の一般生活者に提供する価値」をいかに効率的に創出していくか、という点を重視した研究開発のあり方を考えることが求められる。つまり、当該技術を前述のDOTSの縦軸に位置付ける際には、(a)の価値に従った判断を下さなければならない。
[注1]西村吉雄『産学連携―中央研究所の時代を超えて』(2003年、ダイヤモンド社)参照のこと。
当該技術に関するDOTSの縦軸での位置付けを考える上で、安部忠彦(2004)[注2]の示す「技術に結びつく程度(技術結実度)」、「製品に結びつく程度(製品結実度)」、「利益に結びつく程度(利益結実度)」に分けた分析手法は示唆深い。
[注2]安部忠彦「なぜ企業の研究開発効率が利益に結びつきにくいのか」(『富士通総研Economic Review』 、2004年)参照のこと。
技術結実度とは、研究開発によって当該企業の今後の技術戦略、製品戦略に資するような技術に、いかに効率的に結びついているかという尺度である。製品結実度とは、研究開発の効果がいかに効率的に製品に結びついているかという尺度であり、利益結実度は研究開発の効果がいかに効率的に利益に結びついているかという尺度である。時間軸に沿った並びとしては、まずは技術結実度を追求し、その後製品結実度、利益結実度を追及するという順番が一般的であろうか(勿論これらが並行して進む場合もあろう)。このような分類モデルは、一見当たり前のように捉えられがちであるが、当該技術の重要度を評価する際には重要な視点と考える。
2)当該市場の構造的な変化を捉えることの重要性
近年における市場の多様化、変化周期の短期化は著しく、各製造業企業にとって、どのようなタイミングでどのような製品をリリースするべきか、ということは大きな課題である。高度成長期や、市場がまだ成熟していないような環境下では、需要予測がそれ程困難ではなく、需要予測から導き出される目標が決まれば、後はひたすら研究開発を進めるといったようなオペレーションが可能であった。
しかしながら、現在では一旦スタートした研究開発が、当初の目標(市場の求める一定の機能やタイミングなど)を達成したからといって、売上高や利益に結びつくという保証はない。“目標”は、あくまで市場の当初の予測値であり、その変化が激しい現在においては、目標が達成された時に、その目標が予測していた当初のニーズと合致しているかどうかは不確実性が高い。
このような状況を回避すべく、敢えて自社のコア技術を捨て、外部から技術を取り込むことにより、研究開発のスピードアップ、リスク低減を図る企業が増えている。このような外部からの技術の取り込みは、市場の多様性、短周期化に対応する手段としては有効であろう。しかしながら、製品ライフサイクルの中~後期に訪れる“コストダウンの圧力”や、その後の製品アップグレード(機能拡張)必用時には、当該技術が自社独自のものではないことからくる対応力の限界が大きな問題(ボトルネック)となってくるのではないか。ある程度中長期的な製品開発戦略を考える上では、特にコア技術に関しては、自社独自のものであることが好ましいことは言うまでもない。
市場の多様化、変化周期の短期化 に対応するためには、研究開発に柔軟性を持たせる必用がある。ここでいう柔軟性とは、ニーズの変化に対して、研究開発や製品開発も柔軟にその対応を変化させるということである。しかしながら、一度スタートした研究開発や製品開発に対して、その目標や仕様、スケジュールを変更することは、当該研究開発の規模にも依存するが、通常は大変難しいことである。従って、柔軟にその対応を変化させるとはいっても、ある程度は当該研究開発の置かれた市場の変化を想定した上で、その変化に耐えうるようなプラットフォームを構築し、そのプラットフォームの上で研究開発を進める必用がるのではないか。プラットフォームとは、研究開発の目標が変更されたとしても、変更する必要のない、後戻り工程の必要のない“土台”的な部分を示す概念を指す。
つまり、将来は何が起こるか分からないから、その時に対応を考えるというのではなく、ある程度市場の変化を想定した上で、柔軟に研究開発、製品開発の方向性を変更するというスタンスである。この市場の変化を想定する際に重要となるのが、当該研究開発が属する「市場や産業の構造的な変化」を捉えるということではないか。
コンピューター産業の歴史(IBMのメインフレーム時代から現在の小型パソコン時代に至るまでの変遷)や、日本の通信市場のIP化にともなう構造変化の様相などから分かるように、「市場や産業の構造的な変化」を捉えることの重要性は、特にIT・情報通信産業やそれに関連する産業において顕著であるといえよう[注3]。
[注3]「市場や産業の構造的な変化」を捉えることの重要性については、新保(日本総合研究所主席研究員)からの示唆による。
⇒【仮説2】:当該研究開発が属する「市場や産業の構造的な変化」を捉えた上で、その変化に対応可能な“プラットフォーム”をベースとした研究開発戦略の実行が必要ではないか。
3)市場や産業構造の変化に即した組織構造の重要性
「モジュラリティーの罠」[注4]という概念に示されるように、研究開発戦略の具体的なアクションに加え、それらと相互補完的な関係にある「組織の変革(ソフト面の変革)」が重要となってこよう。
市場や技術の変化によって動態的に変化する製品アーキテクチャに対して、企業の組織がその製品アーキテクチャの変化にしばしば追いついていけないことがある。この製品アーキテクチャの変化と組織変化の乖離を「モジュラリティーの罠」という。日本の製造業企業はこれまでいわゆる“垂直統合的”製品開発を得意としてきた。このような特徴を持つ企業が、急に米デル社のようなBTO(Built To Order)方式のビジネスモデルへ移行したり、パソコンのようなほとんどモジュールアーキテクチャ製品を製造するようになったりしたとしても、なかなか成功することは難しい。
このような難しさの大きな原因の一つが「モジュラリティーの罠」である。特にIT産業の場合、製品の「モジュール化」「オープン化」という観点は大変重要であるが、「組織面」も含めた産業構造の変化への追随が重要となる。モジュール化ということで単にハード面(製品そのものをモジュール化する)だけで対応するのではなく、「組織面」もあわせた戦略立案、実行が必要となろう。
[注4]藤本隆宏、武石彰、青島矢一『ビジネス・アーキテクチャ』(2001年、有斐閣)参照のこと。
⇒【仮説3】:「市場や産業の構造的な変化」に即した組織構造、組織戦略が必要となるのではないか。
4)「研究開発の効率性」の定量的判断の重要性
近年、研究開発投資をいかに効率的に実践するかということが各企業の注目を集めている。わが国では通常の大手製造業企業の場合、売上高比約4~5%程度の研究開発費が毎年投じられている。研究開発の効率性とは、この研究開発費が実際にどの程度利益に結びついているか、ということを示すことが求められるが、これを定量的に示すことは大変難しい。
特にエレクトロニクス製品の場合、1つの製品は無数の技術や特許から構成されているため、ある特定技術の研究開発効率性だけを追求できたとしても、当該技術の製品に対する利益の寄与を算定することがいかに難しいかは想像に難くない。製品の構造(アーキテクチャ)にも依存するが、通常は複数の技術が、相互補完的に絡み合うことにより、ある1つの製品価値を形成しているのである。そのような状況において、特定の技術や特許の全体的な利益への寄与を評価することは大変難しい。
ただし、医薬品などの場合、1製品が少数の特許、技術で構成されることが多く、その点では技術の価値評価を実践することが可能である場合が多い。実際に、一部の医薬品企業では、独自の手法にて当該技術の将来価値も考慮した資産価値を算出し、これを研究開発の効率性向上や、経営の意思決定に反映させている。
例えば、協和発酵工業株式会社[注5]では、研究開発途上の新薬などから将来得られるであろうキャッシュフローをもとに現在価値を計算し、「未来資産」としてその資産価値を高める戦略をとっている。ここでいう「未来資産」とはパイプライン(一連の研究開発の流れ)にある新薬候補の期待現在価値の総和であり、上市後20年間の予想キャッシュフローの現在価値から将来の開発コストの現在価値を差し引いた額として算出されている。同社は、研究開発段階にある新薬候補を未来資産として具体的数値によって開示するとともに、経営の意思決定に反映させている。
同社のように、ある程度研究開発投資に関するコスト、および得られるキャッシュフローの現在価値を定量的に算出するスキームを確立している企業であれば、当該研究開発の効率性を分析し、その結果を研究開発戦略へフィードバックすることも可能であろう。しかしながら、一般の製造業企業の場合(ここでの一般とは、医薬関係とは異なり無数の特許や技術から特定の製品が形成されているような場合を指す)、このようなフィードバック手法を確立することは難しく、現在様々な試行が試みられている段階にある。近年、知的財産の有効活用や技術移転の重要性などが指摘されるようになっており、技術の価値評価や、研究開発の効率性を定量的に判断できる手法を確立する必要性が高まっている。
[注5]「協和発酵工業株式会社」の研究開発動向については山本大輔、森智世『入門知的資産の価値評価』(2002年、東洋経済新報社)から抜粋。
⇒【仮説4】:「研究開発の効率性(研究開発投資の投資効率など)」の定量的判断手法を構築することが必要ではないか。
加えて、研究開発への投資は、投資が行われた会計年度内にその効果がすぐに現れるわけではないことや、研究開発投資といっても実は組織や教育などの目に見えない部分(インタンジブルな部分)への投資が、本来の研究開発投資との間に補完的な関係があり、欠かすこのとのできない重要な部分を占める可能性がある、といったことなどへの留意も重要となろう。
エリック・ブリニュルフソン[注6]の研究では、IT資本と組織的資本に対して同時にかつ最も積極的に投資している企業の方が、どちらか一方にだけ投資している企業よりはるかに高い収益を上げているとされている。ここでIT資本とはコンピューターなどのハードウェア資本を指している。研究開発投資とは概念が異なるが、研究開発投資についても、研究開発用の装置やその他ハードウェアなどに対する投資だけを考慮するのではなく、人的資産、研究開発ビジネスモデル、開発支援ツールなどのインタンジブルな組織的資本に対する投資の重要性、存在も認識した上で、その効率性を分析する必要があろう。
[注6]エリック・ブリニュルフソン『インタンジブル・アセット』(2004年、ダイヤモンド社)参照のこと。
5)ビジョン、大儀、規律、パブリックマインドと研究開発戦略との関係
企業やその経営者の持つビジョンや大儀、規律、パブリックマインドといった概念は、研究開発現場の効率性とは一見直接的な相関は無いように思われる。しかしながら、近年のように多様化、短周期化の進んだ不確実性の高い市場環境下では、企業全体の方向性を明確に示したビジョンや大儀といったものの重要性が逆に高まっているのではないか。市場の多様化に対応するという目的から、研究開発現場で各研究員、エンジニアが全く好き勝手にバラバラな研究開発を進めていては、いくら市場に即した研究開発を実践しているとはいっても、効果的な研究開発には結びつかないであろう。
1ベンチャー企業であるならばともかく、ある一定規模以上の製造業企業であれば、配下の技術の全てについて経営のトップやCTO(チーフ・テクニカル・オフィサー、最高技術責任者)が把握することは事実上難しい。だからといって、研究開発現場は市場の多様化に合わせて好き勝手に行動して良いという訳ではない。
不確実性の高い環境であるからこそ、企業のビジョンや大儀、そこから自然と生み出される規律やパブリックマインドといったものが、研究開発全体の方向性を指し示す“羅針盤”として重要な位置付けとなるのではないか。当該研究開発の投資判断を定量的に行うことは重要であるが、その研究開発が企業のビジョンや大儀に沿ったものであるかどうかという点も重要な判断指標になってくるのではないか。
⇒【仮説5】:ビジョン、大儀、規律、パブリックマインドなどの明確化が研究開発戦略に必要ではないか。
これら5つの仮説の検証および分析、さらなる仮説の追加などを次シリーズ(「研究開発の効率性を高めるためには(全10回)」)の当初の目的(課題)と位置付けたい(これらの仮説を基にさらなる研鑚を深めたい)。

