第1回 製品開発フェーズからマーケティングフェーズに至る“一貫性”の重要性
2005年7月1日 浅川秀之
(1)「一貫性」の重要性
近年の社会・経済の複雑化にともない消費者ニーズの多様化、変化の短周期化が著しい。様々な消費者ニーズが存在し、これらの変化周期が年々短くなっている。このような状況に対応すべく「曖昧な消費者ニーズにいかに対応するか」という研究が数多くなされており、これらの研究結果から得られる重要な示唆の1つに「一貫性」がある。
ここでいう「一貫性」とは、製品やサービスが消費者に対して投げかけるコンセプトやメッセージが、研究・製品開発フェーズやマーケティングフェーズなど、どのようなフェーズにおいても一貫しているということである[注1]。例えば、店頭で売り出される際の製品コンセプトと、TV広告の打ち出し方にも一貫性が必要である。また、ユーザーが製品やサービスを利用した際に、謳われていたコンセプトと実際の利用とでそのイメージが異なるようでは、消費者の信用を失ってしまう。一旦消費者の信用を失ってしまうと、今日のような競争の激しい市場環境化では致命的となってしまう。これまでは「製品開発フェーズ」における一貫性の追及と「マーケティングフェーズ」における一貫性追求は別々に捉えられる傾向が強かった。
[注1]:「一貫性」の重要性については郡司倫久「化粧品の製品開発」『成功する製品開発』(2003年、有斐閣)から示唆を得た。以下に示す同重要性に関する記述については同著書の一部を引用したものである。
製品開発フェーズにおける一貫性の重要性については様々な研究がなされている。ある特定の産業において何が製品開発プロジェクトの成否を分けるかについて論じているものが中心であり、特徴的な成功パターンを論じたものが多い。いずれも、マーケティングフェーズとは区別された、主に製品開発フェーズのみに注目した議論となっている。
マーケティングフェーズにおける一貫性の重要性についても様々な研究がなされている。しかしながら、例えばマーケティング・ミックスの4P論、ブランド・マーケティング論、関係性マーケティング論などは、暗黙のうちに製品を所与とし、その上で価格・広告・売り文句の製品への適応を論じたものである。つまり、製品開発や研究開発フェーズも含めた議論はほとんどなされていない。
このような各フェーズに閉じた「一貫性」の追及が重要であることは言うまでもない。しかしながら、真に製品の一貫性を追及するのであれば「製品開発フェーズ」から「マーケティングフェーズ」に至るまでの全フェーズを総合的に鑑みた上での「一貫性」を打ち出すべきであり、製品ライフサイクルのいかなる点においても徹底した一貫性を持たせることが顧客に対する真の訴求力となろう。
【図表】 マーケティング・ミックスの一貫性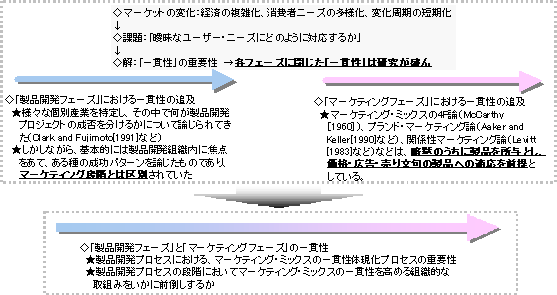
(出所)郡司倫久「化粧品の製品開発」『成功する製品開発』(2003年、有斐閣)を基に筆者(日本総研浅川)作成
ここまで述べてきたような、「製品開発フェーズ」から「マーケティングフェーズ」までも含めた「一貫性」の重要性について、群司倫久氏は化粧品産業を例にとり詳細な分析をおこなっている。以下は同氏の論文(「化粧品の製品開発」『成功する製品開発』2003年、有斐閣)の一部を抜粋し(“(2)化粧品市場を例にとったケーススタディ”および“(3)化粧品の製品分類と製品特性”)、さらに浅川の私見((4)「一貫性」から導きだされる研究開発戦略のポイント)を加えたものである。同論文は、化粧品産業以外の製造業企業における研究開発戦略を考える上でも示唆深い。
(2)化粧品市場を例にとったケーススタディ
化粧品産業は次のような特徴を持っており、製品開発・マーケティングの一貫性の重要性を分析する際の対象として最適である。
◇消費者ニーズの多義性が高く、製品コンセプトの創造が重要
◇化成品であるためコンセプトどおりの製品を開発することが技術的に困難
◇広告・販売を通じた消費者への製品コンセプトの伝達が重要
つまり化粧品の製品開発においては「商品が語ること、広告が語ること、セールスマンが語ることなどがすべて一致している」マーケティング・ミックスの一貫性が重要となる。この一貫性の実現のためには製品開発プロセスの段階からマーケティング・ミックスの一貫性を作りこむことが非常に重要となってくる。
化粧品産業に代表されるような「製品のメッセージ(コンセプト、アイデア、イメージ)がどれだけ消費者の共感を呼ぶか」ということで製品の成否が左右されるような市場では、製品メッセージは以下の3つの経路で消費者に伝達されると考えられる。
◇消費者が実際の製品を使った体験(製品機能)
◇店頭販売員による「売り文句」(製品のセールス・ポイント)
◇CM・広告によるイメージ形成(製品イメージ)
この3つの伝達経路を総合したものは「消費者と企業のコミュニケーション」を表しており、このうちの1つでも欠けていると製品のメッセージが正確に消費者に伝達されない。
消費者に正確に製品メッセージを伝達するためには、3つの伝達経路から伝達されるメッセージを製品開発の早期の段階に前倒しして考えるということが重要となる。通常プロモーション活動の策定や量産化といった後工程になればなるほど製品メッセージの整合性を確保するための調整コストが大きくなるとされている。このため製品開発の初期段階で、各部門に技術翻訳される「ストーリー」[注2]を創造することによって、後工程でかかるコストを削減し、部門間の調整をとりやすくすることができる。つまり自動車産業などで重要性が指摘されている製品機能の作り込みに加えて化粧品では「販売員の語る『売り文句』を考えながら製品開発をすること」が重要となる。
[注2]:「ストーリー」:製品、CM、売り文句等のマーケティング・ミックスへの一貫した翻訳の展開手順を組み込んだコンセプト・構想のこと。
(3)化粧品の製品分類と製品特性
分析対象となる化粧品を「ポイント・メイク」製品と「スキンケア」製品の2種類に分類する。この2つの製品は製品特性やマネジメントの方法が大きく異なる。
◇ポイント・メイク:口紅、マスカラ、ネイルエナメルなど
★消費者への訴求ポイントが感性的であり、消費者の購買決定要因は色、CMキャラクター、ブランド・イメージ、製品メッセージとなる場合が多い。
★コンセプト作成の際には、世界流行色境界、フランスのプルミエール・ビジョンで発表される流行色や質感が参考にされる。これらのトレンドに各社独自のコンセプトが追加される。
★製品イメージが重視されるため、CMに起用するタレントやキャッチフレーズなどが重要な要因となる。
◇スキンケア:化粧水など
★消費者への訴求ポイントは機能面になることが多い。
★キャッチフレーズや広告、販売方法も機能面を全面に押し出す必要がある。
★製品コンセプトを作成する際に参考にされるのは、皮膚科学学会のトレンド。さらにはアパレル、食品、医薬品なども参考にコンセプトが創造される。
スキンケアとポイント・メイクの特徴を以下にまとめる。
【図表】 スキンケアとポイント・メイクの特徴
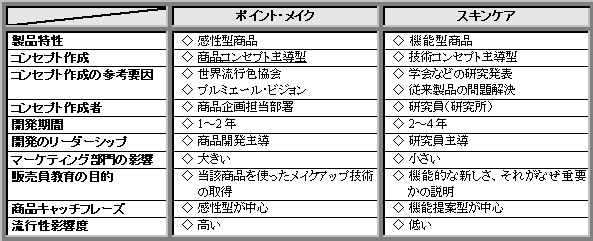
(出所)郡司倫久「化粧品の製品開発」『成功する製品開発』(2003年、有斐閣)を基に日本総合研究所作成
このような特徴の違いから、製品開発フェーズやマーケティングフェーズにおける各フェーズにおける重要ポイントも大きく異なってくる。
【図表】化粧品におけるマーケティング・ミックス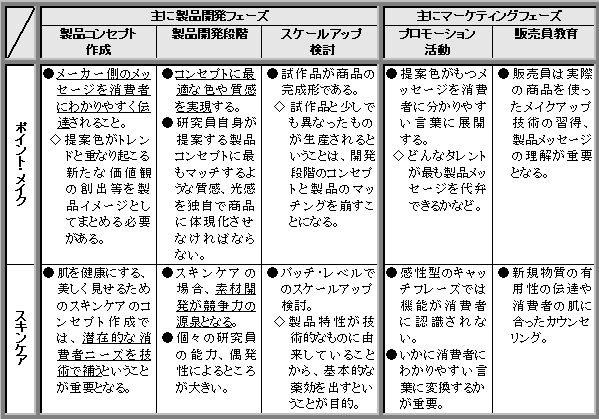
(出所)郡司倫久「化粧品の製品開発」『成功する製品開発』(2003年、有斐閣)を基に日本総合研究所作成
(4)化粧品の製品分類と製品特性
ポイント・メイクの開発においては、「消費者への訴求ポイントが感性的」、「商品コンセプト主導型」、「コンセプト作成は商品企画担当部署」、「開発リード・タイムが比較的短い」といった特徴からもわかるように“マーケットイン”的な発想が必要となる。
反対に、スキンケアの開発においては、「消費者への訴求ポイントは機能面」、「技術コンセプト主導型」、「コンセプト作成は研究員主導」、「開発リード・タイムが比較的長い」といった特徴からも分かるように“プロダクトアウト”的な発想が必要となる。
このように化粧品産業においては対照的な2つの製品特性が共存しており、それぞれに応じた最適な“製品開発フェーズからマーケティングフェーズに至る一貫性を意識した”製品開発戦略が選択されている。この化粧品産業のケーススタディから、同じ産業に属する製品やサービスであっても、闇雲に「プロダクトアウト的発想がよい」、「マーケットイン的発想がよい」と戦略を決めつけてしまうのではなく、取り扱う製品やサービスの特性や、当該製品のライフサイクル上での位置付けなどに応じた最適な戦略を実行する必要がある、ということが示唆として導き出される。
例えば、「技術コンセプト主導」で研究開発を進めるのか、「商品コンセプト主導」で進めるのかについては、当該製品の訴求力を見極めた上で判断する必要があることが分かる。これによって、プロダクトマネージャーの、研究員(技術系)を据えるべきか、商品企画担当を据えるかといった判断も異なってくる。また製品開発期間についても、商品コンセプト主導の方が相対的に短く設定することが多く、製品開発スケジュール策定にも大きな影響をおよぼすことになる。

