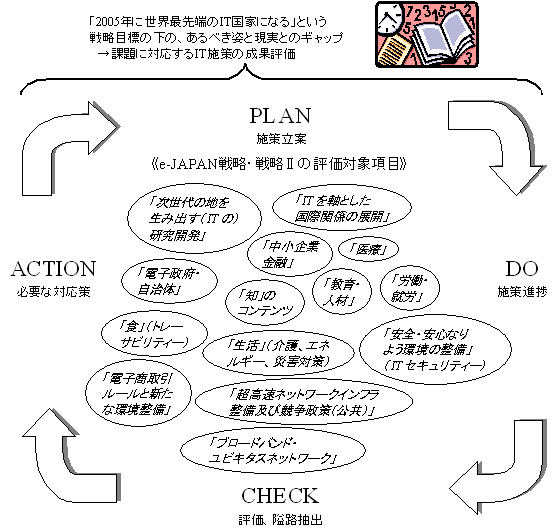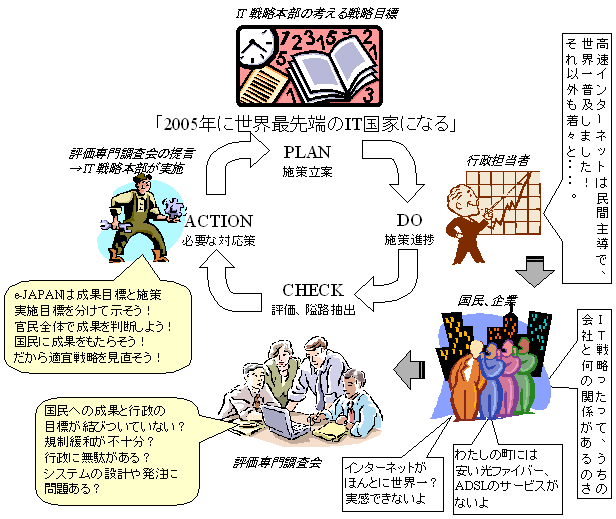「e-JAPAN」を評価するということ
|
▼▼▼ 「e-JAPAN」を評価するということ① ▼▼▼ | |||
| ● | いわゆるe-JAPANの策定主体であり、「2005年までに世界最先端のIT国家になる」ことを掲げてIT政策を主導する官邸政策会議「IT戦略本部」に2003年12月から「評価専門調査会」という下部機関が設置された。 | ||
| ● | IT基盤整備そのものの国際的な遅れを危機に感じて取り組み始めたのが、1999年のe-JAPAN戦略(Ⅰ)だったわけだが、2001年頃に至って、戦略目標以上のペースで高速インターネット網(しかもADSLという予期せぬ新技術で)の整備が進む一方、ITの利活用が進んでいないという認識が、2002年のe-JAPAN戦略Ⅱ策定につながった。 | ||
| ● | e-JAPANが「戦略」である以上、「最終的にあるべき姿」と「そこに到達するための方策」の両方が描かれていなければならないはずだが、文面には「2005年に世界最先端のIT国家になる」という‘通過点’‘社会的手段’しか示されておらず、「国際競争力を強化」「経済の活性化」という目的にしても何ら具体的な指標を持って語られてはいない。 | ||
| ◇ | もちろん個々の施策と目的との因果関係も示されていない。結果、毎年のe-JAPAN重点計画では個々の施策の予算化と施策の規模的到達目標が示されつづけるにとどまっている。 | ||
|
【図表】 e-JAPAN戦略、戦略Ⅱの評価に対するPDCAサイクルの導入 | |||
|
| |||
| (出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2004年5月] | ||
|
| |||
|
▼▼▼ 「e-JAPAN」を評価するということ② ▼▼▼ | |||
| ● | 「これでは評価しようがない。まず評価する礎を作らねば」という問題意識が、評価専門調査会の(第1回中間報告(2004.3))に如実に描かれている。 | ||
| ● | e-JAPAN がもたらす日本社会の「最終的にあるべき姿」とは、「IT政策の成果が、広く、継続的に、国民に還元されること」につきる。 | ||
| ◇ | この最終状態に対して施策群の成果評価を行うべきであり、評価が次の施策立案に直結する「PDCA(計画→実施→評価→改善)サイクルを確立すること」、それを基点に①戦略は達成できたか? ②どの施策がどう貢献したか?に加え③戦略自体は適切か?まで言及して主張されている。 | ||
| ● | 今回の報告書の中では具体的な評価は行えていないが、近年の政策評価、政府事業投資評価に対してさらなる強いしばりを加え、長らく国民が直接触れることの難しかった「霞が関の仕事の評価」に、国民の信託(IT戦略本部は全閣僚が出席しており、IT戦略本部の結果は事実上の閣議決定であること、その内閣は議院内閣制によって国会選挙と直結していること)を結びつける重要な変化の第一歩が記されたと見るべきであろう。 | ||
| ◇ | 参照文献:IT戦略本部評価専門調査会 中間報告(2004.3) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hyouka/dai4/4gijisidai.html | ||
|
| |||
|
【図表】 「最終的にあるべき姿」への成果評価の、具体化の雛形例 | |||
|
| |||
| (出所) | (出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[[2004年5月] | ||
|
| |||