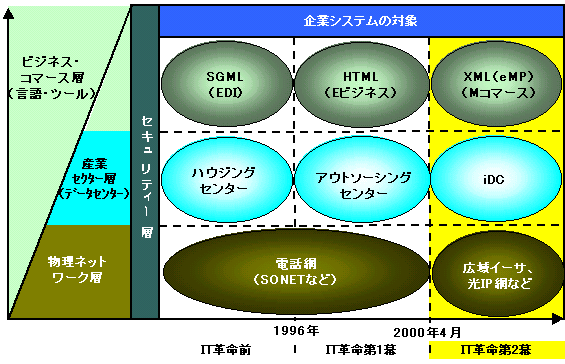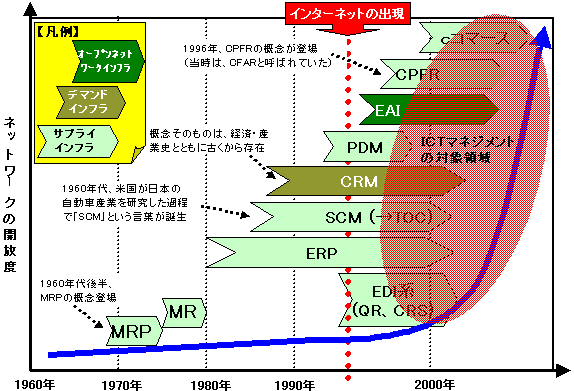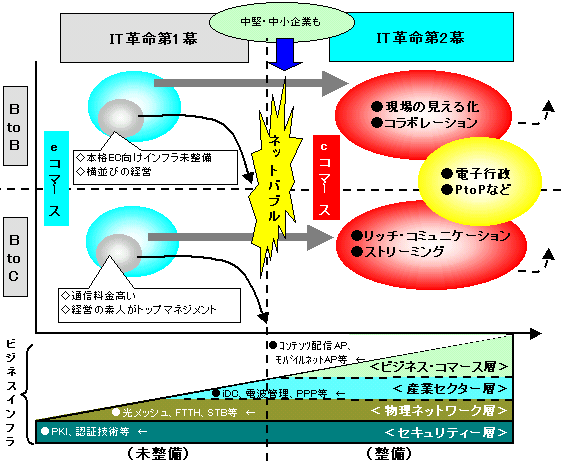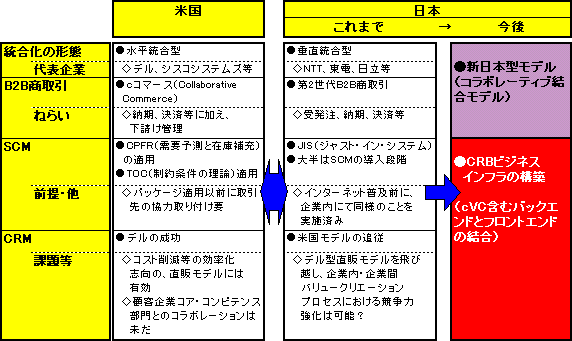ブロードバンド時代のビジネスインフラが企業競争力の鍵を握る
|
| ||
|
▼▼▼ ブロードバンド時代のビジネスインフラが企業競争力の鍵を握る① ▼▼▼ | ||
| ● | 企業活動やその活動の総体としての産業が円滑な成長と発展を遂げるには、「ビジネスインフラ」が不可欠となる。 | |
| ◇ | ビジネスインフラは、主に、①物理ネットワーク層、②産業セクター層(データセンタ-など)、③ビジネス・コマース層(言語・ツールなど)などに分類することができる。 | |
|
【図表】 ビジネスインフラの例 | ||
|
| ||
| (注) | SGML:Standard Generalized Markup Language、HTML:HyperText Markup Language、 XML:Extensible Markup Language、Mコマース:モバイルコマース、 iDC:Internet Data Center、SONET:Synchronous Optical NETwork | |
| (出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター[新保2001] | ||
|
| ||
|
▼▼▼ ブロードバンド時代のビジネスインフラが企業競争力の鍵を握る② ▼▼▼ | ||
| ● | 企業システムは、ITの発展とともに進化してきた。古くは1960年代の米国における生産系プロセスの効率化の領域を中心に、最近ではcコマース(collaborative commerce)に至る領域の動きに至っている。 | |
| ◇ | 米国を中心にかたちづくられてきたノウハウ・手法は、日本企業のそれに触発されたものも少なくないが、企業システムのパッケージとして完成されている。 | |
| ◇ | 同企業システムは、大きく、①サプライインフラ系、②デマンドインフラ系、③オープンネットワークインフラ系などで構成される。 | |
| ◇ | 1994年のインターネットの商用化を機に、これら企業システムは現在ではインターネット(IP)が基礎になっている。 | |
| ◇ | 別記の「ICTマネジメント」では、最新のITを駆使した企業システムの効用を、最大限に取り込むことを前提としている。 | |
|
| ||
|
【図表】 企業システムの変遷とICTマネジメントの対象領域 | ||
|
| ||
| (注) | MRP:Material Requirements Planning(資材所要量計画)、 MRPⅡ:Manufacturing Resource Planning(MRPの資材所要量計画に、要員、設備、資金など製造に関連するすべての要素を統合して計画・管理するもの) ERP:Enterprise Resource Planning(汎用基幹業務パッケージソフト)、EDI:Electronic Data Interchange QP:Quick Response、CRS:Continuous Replenishment Service、TOC:Theory of Constraints SCM:Supply Chain Management、CRM:Customer Relationship Management、 PDM:Product Data Management CPFR:Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment(需要予測と在庫補充のための共同事業) EAI:Enterprise Application Integration(企業アプリケーション統合)、cコマース:Collaborative Commerce | |
| (出所)小池良次氏資料に日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター[新保2001]加筆など | ||
|
▼▼▼ ブロードバンド時代のビジネスインフラが企業競争力の鍵を握る③ ▼▼▼ | ||
| ● | IT革命第1幕で「eコマース」は失速した感がある。ネットバブル(ITバブル)となった2000年春以降、IT革命第2幕がスタートした。革命はいよいよ本番モ―ドに入った。第2幕は、企業自身およびそれら企業の事業の選別の時代といえる。 | |
| ◇ | ブロードバンド時代と重なる第2幕では、第1幕の主にB2C向けeコマースから、B2Bも対象とした「cコマース」が注目される。単なる「e」(電子的なネットの世界)から、「c」(コラボレーティブな人のコミュニケーション)の世界へ軸足をシフトしている。 | |
|
| ||
|
【図表】 インターネット・ビジネスインフラとIT革命第2幕 | ||
|
| ||
| (注) | CRB:Customer Relationship Building(CRMとは別の概念) PtoP:Peer to Peer、FTTH:Fiber To The Home、STB:Set Top Boxes PPP:Public Private Partnership(PFIの次に位置づけられる官民連携のフレームワーク) PKI:Public Key Infrastructure(公開鍵基盤/公開鍵暗号基盤) | |
| (出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター[新保2001] | ||
|
▼▼▼ ブロードバンド時代のビジネスインフラが企業競争力の鍵を握る④ ▼▼▼ | ||
| ● | ブロードバンド時代となり、光ファイバーを筆頭にインフラ整備の意味はより一層大きなものとなってきた 。しかし、ハードウェア的な通信インフラに留まらない、「ビジネスインフラ」が重要な意味を持って来た。 | |
| ◇ | わが国において、米国の単純な追従とはせず、ビジネスインフラを活かした、製造業を含む戦略産業を再起させることが喫緊の課題となっている。そのためには、新しい日本型のモデルを打ち立てることが必須となってきた。 | |
| ◇ | 米国においても、1990年代後半からは、半導体や電子部品等の分野での米国企業の躍進が伝えられている。例えば、半導体のST Microelectronicsは、2001年に6,360百万ドルの売上高を記録し世界第3位まで上り詰めた 。これはむしろ、製造業に特化したゆえのものと言える。 | |
| ◇ | なお、2001年頃からの米国の無線LANに関する抜本的な規制緩和を通じた、ワイヤレスメッシュ技術による新しい地域網インフラの整備は注目される。わが国でも、同技術により、FTTHのシナリオや携帯電話事業に与える影響が出てきそうだ。 | |
|
| ||
|
【図表】 日米の経営システムの相違と今後のビジネスインフラ | ||
|
| ||
| (注) | ●SCM:Supply Chain Management ●cコマース:Collaborative Commerce ●cVC:collaborative Value Creation ●CRB:Customer Relationship Building ●CRM:Customer Relationship Management ●CPFR:Collaborative, Planning,Forecasting and Replenishment | |
| (出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター[新保2001] | ||
| ● | 1970年代、日本の産業界に遅れをとっていた米国では、産業競争力強化政策として、1979年の「産業技術革新政策に関する教書」に続き、1985年レーガン大統領の諮問機関「産業競争力委員会」にて「ヤング・レポート」発表。以降、製造業を中心に急速に自信を深め、国力を回復・強化できた。 | |
| ◇ | 1987年にはマルコム・ボルドリッジ賞 が制定され、品質管理に実績を上げた企業を大統領が表彰する制度が始まった。 | |
| ◇ | しかし、こうした品質管理に力を入れる一方で、米国政府は個々の企業への支援ではなく、競争力のインフラ整備を国家戦略の柱に据えた。 | |
| ● | 米国の製造業弱体化が深刻化していた時代に、同レポートを作成したことが、危機感醸成という点で大きな役割を果たし、強い競争力の実現に繋がっているとの見方は多い。これとは異なる見方 を「ヤングレポートの真意」として補足し次に示す。 | |
| ◇ | 製造業復権路線を採択し強い米国を目指したのは、同レポートに沿った訳ではない。産業界も一貫し製造業一般の復権など目指さなかった。 | |
| ◇ | 安いモノが海外から入手できる国内製造業などには注力せず、捨て去る政策をとった。例えば、IT機器製造は台湾や日本企業等に委託し、資本効率が圧倒的に高い産業構造確立に力を注いだ。 | |
| ◇ | 競争力向上のためグローバル覇権を握れるハイテク・高収益分野、具体的には、同覇権を梃子に雇用創出効果が大きいサービス産業(特にソフトウエア)育成に注力した。 | |
| ● | 以上は明快な資本の論理に基づいており、人材育成が必要な面倒なモノつくりを放棄してきたのが、現時点までの米国流経営スタイルといえる。 | |
|
| ||