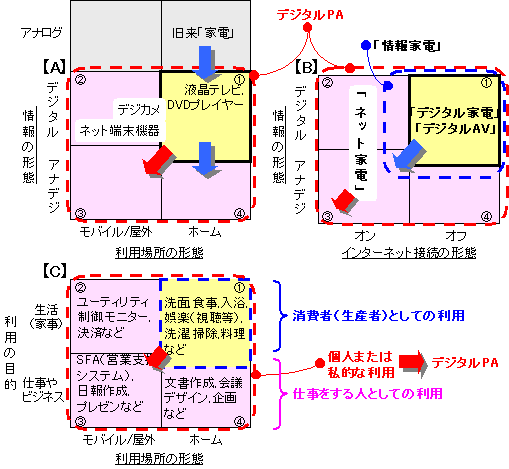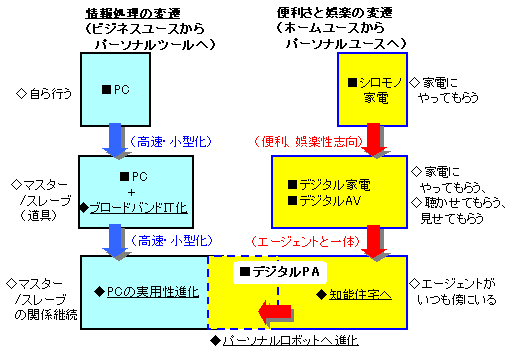|
|
|
連載企画 「デジタルPA産業創造の戦略を考える」
第1回「デジタル家電やデジタルAVを超えるものに?」 (その1)
日本総合研究所 研究事業本部 新保豊 主席研究員
(2004年6月11日掲載) |
|
|
|
2004年5月17日のNIKKEI NETでも、「ロボットなど7分野を300兆円市場に育成・経産省方針」の記事のなかで、中川昭一経済産業相が5月19日の経済財政諮問会議で報告する、新産業創造戦略の全容が明らかになったことが報じられた。「燃料電池、情報家電、ロボットなど日本が世界最先端の技術を有する7分野を政策を総動員して支援し、現在200兆円強の市場規模を2010年に300兆円に育て上げる。有望事業への投資を促し、産業部門の好循環を加速させて景気を持続的な回復軌道に導く。」というものだ。
果たして本当にそのようにできるのだろうか。
"デジタル家電"や"デジタルAV"は、"新3種の神器"と呼ばれ、日本経済の景気回復の切り札としての期待も大きい。本稿ではその範囲を広げ、かつ今までの延長にない産業としての"デジタルPA"(筆者の造語)について考えてみたい。"PA"とは、Personal Agent(個々人の代理人またはその機能)またはPrivate Assistant(私的な助手またはその機能)を意味する。これからは「家電」でもなく「AV」(Audio Visual)機器でもなく、「PA」がキーワードになっていくのではないか。
もちろん、Personal AssistantでもPrivate AgentあるいはPersonal Administrator(管理者またはその機能)でも同様である。
経産省の「新産業創造戦略」では、世界市場をリードする先端産業に据えるものとして「情報家電」「燃料電池」「ロボット」「(アニメ・映画などの)コンテンツ」の4分野を挙げている。そして、社会のニーズに対応した新産業として「健康・福祉」「環境・エネルギー」「(人材派遣や経営サポートなど)ビジネス支援」を対象としている。本稿で主張したい"デジタルPA"とほぼ全分野と重なるものだ。
(1)デジタルPAの定義
筆者の問題意識は、わが国の戦略産業としての要件を満たしているのか、あるいはその要件獲得には何が必要か、ということだ。言い換えれば、日本人の感性や技術力を大いに活かせそうなデジタルエレクトロニクス産業を、単に消費者にとっての便利さのみを追求した商品にしてよいものかということだ。あるいは同産業が、単なる「家電」や「AV機器」のような位置づけに留まるのであれば、また"いつか来た道"にならるのではないか、という懸念を抱いている。
つまり、【1】わが国の家電メーカーの事業展開が適度に大きな日本市場のみに終始し、米国市場などをも視野に入れたグローバル戦略に欠けていたり、【2】中国などから技術を模倣され、低価格のコモディティー商品競争を自ら招いてしまったり、さらには、【3】Wintel(ウィンテル)が突き進めた水平分業型モデルからの攻勢を受け、パソコン産業での心臓部(コア)に相当する領域を自らつくることも、それをハンドリング(需要をコントロール)することもできず、低収益性にまたも甘んじなくてはならないのだろうか、などといったことが頭をよぎる。
デジタルPA産業の戦略を考えるに当たり、まず、デジタル家電の定義から始めてみよう。
産業技術総合研究所森彰氏は「ネット家電や情報家電の定義は、日常生活レベルの動作や語いで"思いのままに"使える家電、ということだと思う。肝心なのは使い勝手であり、ネットやデジタルは手段に過ぎない」とする【NIKKEI NETデジタルコア・レポート2004年4月16日】。
この定義は、「消費者」(需要側)の立場からみたものだろう。その意味でポイントを言い当てている。そして、"思いのままに"というのは、テレビに見られるような受動的(ながら的)な側面が強調されている旧来家電からは一歩踏み込んだ意味に解される。
つまり、これからのデジタル家電ないしデジタルPAは、個人的(パーソナル)な欲求・欲望(ウォンツ)を満たせるよう、"ネットやデジタルという手段"とをつなぐ橋渡し(エージェント)に進化していくことだろう。
一般に需給が合致するところに商品価値を見出せるわけであるから、供給側としては、PA(パーソナルエージェント)としてのa)機能・性能、b)信頼性、c)利便性、d)価格の点で、いかに需要を満たすものかを考えなくてはいけない。これらa)からd)の購買階層にしたがって需要側のニーズはシフトしていくため、それに合わせた取組みが企業には求められる。そして、競合他社との競争の観点から、自社の優位性を出し、それをいかに長く維持できるかが喫緊の課題となる。
一方、経済産業省の福田秀敬・IT産業室長は2002年12月20日、パシフィコ横浜で開かれたイベント「オープンソースウェイ」で講演し、デジタル家電の"PC化"を「強力なCPUとプロプライエタリ(特定メーカーの)OS、それに支えられたアプリケーションという組み合わせになること」と定義し、「これを崩すには、OSはLinuxやTRONなどのオープン系、半導体の部分はCPUに依存しないアーキテクチャにする必要がある。組み込み系にはLinuxを使って欲しいと各メーカーへ強烈に言っている。はっきり言えばWindowsを使うな、ということだ。そうしないと(日本は)勝てない」と強調した。
このデジタル家電の"PC化"を回避すべきと説く福田秀敬氏の警笛は、傾聴に値する。わが国は、Wintel(ウィンテル)モデルを凌駕するもの、あるいは新しい日本独自のWintelモデルを早急に構築せねばならない事態に直面している。
デジタルPAの定義としては、誰もがイメージを共有できるシンプルなものが望ましい。今のところ筆者が改めてここで加筆するほどのものないように思われる。それよりも、デジタルPAの範囲がより重要であろう。
(2)デジタルPAの範囲
デジタルPAの範囲については、次の図表をご覧頂きたい。 |
|
|
【図表】 デジタルPAの範囲 |
|
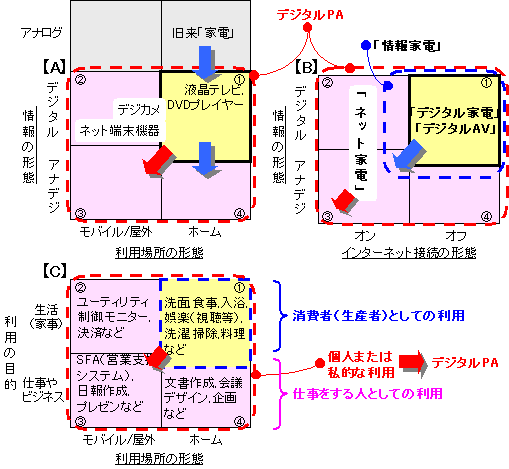
|
|
(注) |
◆「デジタルPA」:デジタル・パーソナルエージェント(個々人の代理人またはその機能)またはデジタル・プライベートアシスタント(私的な助手またはその機能)を意味する造語。 |
|
(出所) |
日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター(新保〔2004年5月〕)作成 |
|
|
「情報の形態」(デジタル、またはアナデジ)を縦軸、「利用場所の形態」(家庭、またはモバイルか屋外)を横軸にした平面【A】、あるいは縦軸は同様で横軸に「インターネット接続の形態」(オフかオンか)なる平面【B】、さらには、縦軸を「利用の目的」(生活や家事、または仕事やビジネス)とし、横軸に「利用場所の形態」をとった平面【C】で示すことができる。
これら平面【A】において、"新3種の神器"(①液晶テレビ、②DVDプレイヤー、③デジカメ)を位置づけてみた。アナデジをキーワードとしているのは、デジタル技術のみでは中国などから不正に模倣される懸念があるから、またはデジタル化が進むほどアナログ技術の役割が増すからだ。
つまり、単なるデジタル技術に留めず、アナログ技術を組合せたアナデジ混在の設計にすることで、ブラックボックス化をより強力にで仕立てることができる。アナログ技術にはデジタルに置き換えられない、簡単に真似のできない"人手"的要素が少なからず盛り込まれている実態があるからだ。
実際、デジタル技術により当該製品の高集積・高速化が進むほど、例えば、電子回路素子への電圧制御には微妙なコントロールが求められたり、微細加工の施されたミクロ素子内では高周波ノイズ防止・除去の設計が求められ、これらにはアナログ技術が不可欠となる。
また平面【B】では、デジタル家電またはデジタルAV、情報家電、ネット家電を位置づけてみた。これら4つに明確な定義があるように思えないが、概ねこの図表のような捉え方ができよう。デジタルPAは、これら4つの位置づけよりも広範なものとなる。差し詰め、ICタグやユビキタス環境をも意識したものとなる。
さらに、平面【C】において、デジタルPAは第1象限の洗面、食事、入浴、娯楽(視聴等)、洗濯、掃除、料理などの利用の目的に加え、第2象限のモバイルまたはユビキタス環境や、第3象限または第4象限のビジネスユースを意識したものが考えられる。ただ、図表の下側(第3象限または第4象限)つまり仕事やビジネス用途としては、今後もパソコンを主とした流れが続くであろう。
ここでパソコンと家電の流れを整理した上で、デジタルPAまでの変遷を次の図表を使ってみ眺めてみよう。 |
|
|
【図表】 デジタルPAまでの変遷 |
|
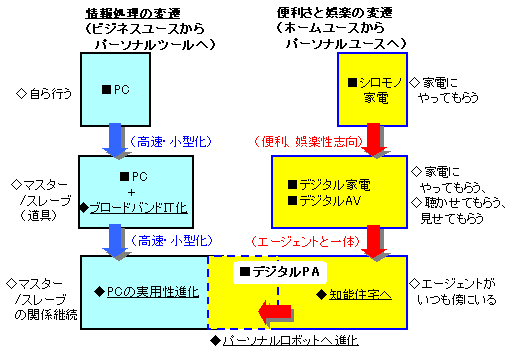
|
|
(注) |
◆「デジタルPA」:デジタル・パーソナルエージェント(個々人の代理人またはその機能)またはデジタル・プライベートアシスタント(私的な助手またはその機能)を意味する造語。 |
|
(出所) |
日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター(新保〔2004年5月〕)作成 |
|
|
「情報の形態」(デジタル、またはアナデジ)を縦軸、「利用場所の形態」(家庭、またはモバイルか屋外)を横軸にした平面【A】、あるいは縦軸は同様で横軸に「インターネット接続の形態」(オフかオンか)なる平面【B】、さらには、縦軸を「利用の目的」(生活や家事、または仕事やビジネス)とし、横軸に「利用場所の形態」をとった平面【C】で示すことができる。
これら平面【A】において、"新3種の神器"(①液晶テレビ、②DVDプレイヤー、③デジカメ)を位置づけてみた。アナデジをキーワードとしているのは、デジタル技術のみでは中国などから不正に模倣される懸念があるから、またはデジタル化が進むほどアナログ技術の役割が増すからだ。
つまり、単なるデジタル技術に留めず、アナログ技術を組合せたアナデジ混在の設計にすることで、ブラックボックス化をより強力にで仕立てることができる。アナログ技術にはデジタルに置き換えられない、簡単に真似のできない"人手"的要素が少なからず盛り込まれている実態があるからだ。
実際、デジタル技術により当該製品の高集積・高速化が進むほど、例えば、電子回路素子への電圧制御には微妙なコントロールが求められたり、微細加工の施されたミクロ素子内では高周波ノイズ防止・除去の設計が求められ、これらにはアナログ技術が不可欠となる。
また平面【B】では、デジタル家電またはデジタルAV、情報家電、ネット家電を位置づけてみた。これら4つに明確な定義があるように思えないが、概ねこの図表のような捉え方ができよう。デジタルPAは、これら4つの位置づけよりも広範なものとなる。差し詰め、ICタグやユビキタス環境をも意識したものとなる。
さらに、平面【C】において、デジタルPAは第1象限の洗面、食事、入浴、娯楽(視聴等)、洗濯、掃除、料理などの利用の目的に加え、第2象限のモバイルまたはユビキタス環境や、第3象限または第4象限のビジネスユースを意識したものが考えられる。ただ、図表の下側(第3象限または第4象限)つまり仕事やビジネス用途としては、今後もパソコンを主とした流れが続くであろう。
ここでパソコンと家電の流れを整理した上で、デジタルPAまでの変遷を次の図表を使ってみ眺めてみよう。 |
|
|
|
|
|
|
第1回 → 第2回 |