コラム「研究員のココロ」
「地方発」排出量取引の時代へ<第2回>
2008年08月11日 吉田 賢一
インセンティブ付与型の政策群
前回に引き続き、温暖化防止にかかる地方自治体の政策群について見ていこう。
実施レベルの政策のタイプには、規制、経済的利得へのインセンティブ、そして情報による喚起や啓発がある。しかしながら、実際にはこれらのタイプのハイブリッド型で設計するケースが増えている。その中で、特に「やれば得になる」というレントシーカー(利益追求者)の動機を出発点として、当初は補助金を基本とするものが多く見られた。しかしながら昨今では、ある種の人間が持つ非金銭的な「名誉」や「社会的な責任感」に訴える手法が注目されており、その政策事例が増えている。このことは、環境価値という経済的視点のみでは測定できない公共財について、その価値保全や増大に取り組めば、めぐりめぐって自身のプラスにつながるという「得」を求める動機が働いているものと考えられる。
この類型に整理される先駆的な事例は、以下のとおりである。
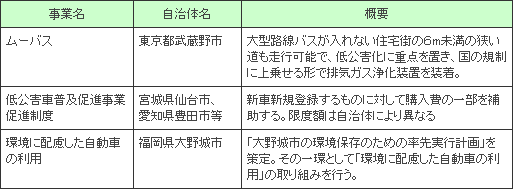
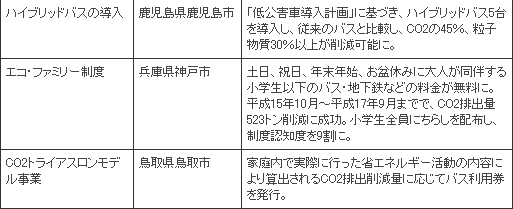
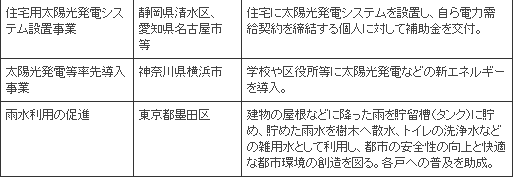
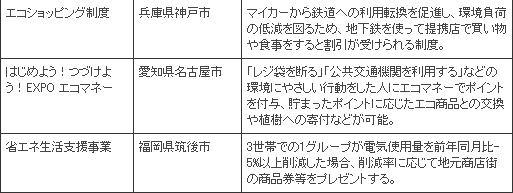
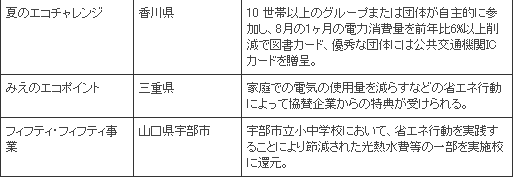
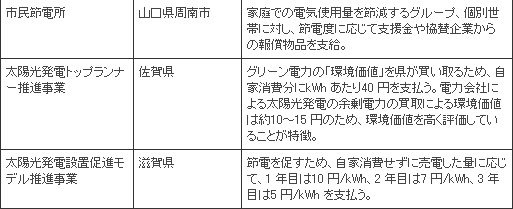
※ 有限会社イーズ, イーズ調査レポート No.1「地方自治体の温暖化対策目標と政策に関する調査」(2008 年3月21日)及び各自治体ホームページを参考に筆者作成。
市場指向型の政策群
インセンティブ付与型はあくまでも「きっかけ」を与えるものであって、その後の経済的行動は各自に委ねられている。そこで、さらにその後の経済的行動をも奨励する「仕掛け」を持った政策フレームの設計が始まっている。
経済的な利得へのモチベーションは同じでも、一定の枠組みを設定し、そこで価値あるものの等価交換を行うのが市場である。今般、G8洞爺湖サミットも大きな話題となったCO2など温暖化効果ガスの排出量取引の市場化を制度的に整える動きが、世界各国の国レベルだけではなく、地方自治体レベルでも進められていることは注目に値する。
まず、温暖化防止への取り組みで熱心なEU(欧州連合)では、域内排出量取引制度(EU‐ETS)を2005年1月からスタートさせており、これは現存する唯一のキャップ&トレード型のものである。現在、第二フェーズ(2008~2012)に入っており、発電所、石油精製、製鉄、セメント等のエネルギー多消費施設(約11,500)が対象で、CO2排出量のカバー率は実に49%に達している。(注1)一方、サミットでも慎重な姿勢を取っていたアメリカでは連邦レベルでリーバーマン・ウォーナー法案(2008年6月に上院本会議で審議、採決に至っていない)があり、石炭使用設備、天然ガス・石油の生産施設・輸入等を対象に、過去の実績に基づく無償割当とオークションを組み合わせて、段階的にオークションの割合を高めていくこととしている。これに呼応してUSCAP (United States Climate Action Partnership)では、民間企業27社、6団体がキャップ&トレード型を主張しており、民間ベースでも、自主参加型の排出量取引制度を有するシカゴ気候取引所(Chicago Climate Exchange: CCX)が、CCXとの契約により削減目標を設定している。そして自治力が強い州レベルにおいては、2009年度開始を目指し発電所を対象とした北東部10州による排出量取引制度地域温室効果ガスイニシアティブ(Regional Greenhouse Gas Initiative: RGGI)、排出上限規制の2012年導入を予定しているカリフォルニア州の地球温暖化対策法(Assembly Bill 32, Global Warming Solutions Act: AB32)、参加各州の合計で2020年までに温室効果ガス排出の2005年比15%削減を目指し米国西部7州とカナダ2州が参加している温室効果ガス排出削減に向けた西部気候イニシアティブ(Western Climate Initiative: WCI)、米国中西部6州とカナダ1州で温室効果ガス排出削減を目指す中西部地域温室効果ガス削減アコード(Midwestern. Greenhouse Gas Accord: MGGA)などがある。
こうした動きは我が国でも、環境省や経済産業省を中心に、自主参加型の排出量取引制として検討が進められている。
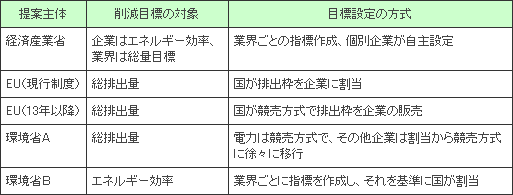
※ 日本経済新聞日本経済新聞2008年6月26日朝刊より筆者作成。
- (注1)
- 環境省, 「諸外国における排出量取引の実施・検討状況」(2008年7月3日),p.14.
(次回に続く)
【参考】- 環境省,「欧州連合排出量取引制度調査報告書」(2008年3月)
- 環境省資料,「諸外国における排出量取引の実施・検討状況」(2008年7月3日)
- 欧州委員会,「欧州議会ならびに欧州委員会指令2003/87/EC に基づくGHG(温室効果ガス)排出量のモニタリングと報告に関するガイドラインの制定」(2004年1月29日決定)
- 有限会社イーズ, イーズ調査レポート No.1「地方自治体の温暖化対策目標と政策に関する調査」(2008 年3月21日)

