コラム「研究員のココロ」
病院人事リスクマネジメントの進め方
2008年05月26日 大野 勝利
このコラムは病院人事リスクマネジメント研究会(荒木主席研究員、加子上席主任研究員、鈴木主任研究員、綾研究員の5名の共同執筆です)
1. 病院経営と人事リスクマネジメント
(1) 病院人事リスクマネジメントとは
1)医療事故防止リスクマネジメントとの相違
近年、企業経営においては、様々な業務分野で発生するリスクへの対応(リスクマネジメント)が重要な経営課題として強く認識されており、内部統制システムにおいても「トータルなリスクの評価・認識」、「リスクへの適切な対応」がコーポレートガバナンス等と並ぶ重要な評価として挙げられています(「コーポレートガバナンス及びリスク管理・内部統制に関する開示・評価の枠組みについて」経済産業省「企業行動の開示・評価に関する研究会」2005年8月)。
リスクマネジメントは、従来から、病院等の医療機関においても医療事故防止のための重要施策として広く認識されており、多くの医療機関では「ヒヤリハット」報告制度の確立、リスクマネージャー任命等の組織的な取り組みが行われています。
以下に説明する「病院人事リスクマネジメント」の概念も、広い意味では医療機関に特徴的なリスクマネジメントに包含されるものですが、とりわけ病院における人事労務管理体制やその運用状況に起因する人的リスクの多様さ、リスクの高さが特徴的であるといえます。
一例を挙げると、ある病院では人事制度の抜本的な改革を行い、賞与原資を利益と連動させるシステムに変更しました。しかしタイミング悪く経営環境の悪化が重なり、新人事制度の導入即賞与切り下げとなり、多くの看護師が一斉に退職してしまいました。しかも、退職者を通して経営危機による賃下げの噂が他病院の職員や大学医局にまで広まりました。このような賞与システムは民間企業では一般的であり、決して不利益変更とはいえないものです。しかし当病院では制度設計及び導入、運用にあたって周到な準備が行われませんでした。つまり人事労務管理面におけるリスクの予見と対応の視点が欠落していたわけです。
このように、病院においては、医療事故防止のためのリスクマネジメントと並んで人事労務に関するリスクの予見とその対応を目的とした「人事リスクマネジメント」が重要になっています。
(2) 病院において増加・深刻化する人事リスクの顕在化
病院の人事労務管理体制は、職員の高度な専門性・高い流動性、これと表裏一体ともいえる組織統制の脆弱性、そして医師を中心とした過重労働傾向等に起因して、自治体や民間企業と比べより多くの高いリスクを抱えています。
近年、民間企業において労働基準法関係のコンプライアンス違反に対する監督官庁による指導や勧告を受けるケースが増加しています。また、成果主義を標榜した人事制度改革あるいは人事制度改革に名を借りた賃下げ等の不利益変更による従業員のモチベーション低下や人材流出、組合との紛争等は残念ながら枚挙にいとまがありません。これら民間企業で顕在化したリスクは、より大きな脅威となり病院経営に影響を与える事が予想されます。
2. 病院における人事リスクの抽出と分類
(1) 病院人事リスクの分類基準
病院人事リスクの予見・評価と対策の立案に当たり、最初にリスクの分類整理を行う必要があります。
まず、発生し得るリスクを顕在化速度に従って展開(急性→慢性軸上に10項目)、あわせてそれらリスクの要因となる経営事象を外発的要因と内発的要因に分類(23項目)しています。
この分類基準は次の通りです。
1)慢性的リスクと急性的リスク
リスクの要因となる施策や制度がどの程度の速さでリスクとして顕在化するかに着目します。慢性的リスクは、比較的長い時間をかけて徐々に高まっていくリスクであり、経営側もその重要性に気づかないうちに突然大きなトラブルに結びつくものをいいます。急性的リスクは、制度改定、法令改正、経営者交代のような時々の事象に起因して発生するリスクをいいます。
2)外発的要因と内発的要因
外発的要因とは経営者の交代、医療制度改革、地域の過疎化など、病院を取り巻く外部環境に起因する要因です。内発的要因とは組織風土や体制等、病院の内部環境に起因する要因です。
これらの要因とリスクの組み合わせのうち、発生確率の高いグリッドをまず抽出しました
(確率は本研究会メンバー5名の重複回答を集計し、◎、○と印なしの3段階に相対評価した結果)。
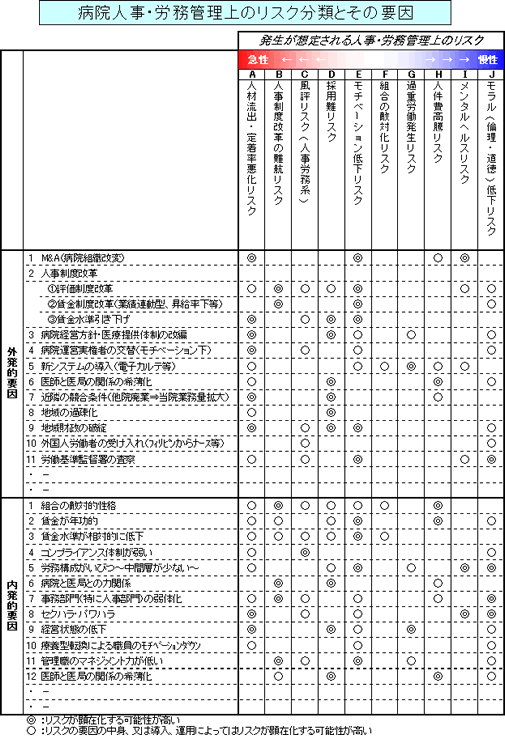
(2)病院人事リスク・ポートフォリオの作成
(1)で抽出した10項目のリスクの経営に対する影響度を「組織的リスク・個人的リスク」と「リスク顕在化速度」の2軸からなるマトリックスにプロットしました。
1)横軸 組織的リスクと個人的リスク
リスクの影響が組織全体に及ぶリスクを組織的リスク、個人のモチベーションや心身に影響を及ぼすリスクを個人的リスクとして区分します。これらは影響の及ぶ範囲が大きく異なるため、組織的リスクには組織的かつ制度改革的な対応、個人的リスクには職員個々人を見据えたきめ細かな観察とフォローが必要になります。
2)縦軸 リスク顕在化速度
(1)で説明した慢性的・急性的の区分を使用しています。
3)経営に対する影響度
リスクが顕在化した場合の経営に対する影響度を円の大きさで示しています。大きさはすべてのリスクを相対評価したものです。
下図における4つの象限は次のように整理することができます。
右上の第1象限 「組織的かつ急性的 いずれも大きな影響を及ぼしかねないリスク」
左上の第2象限 「個人的ではあるが急性的なリスクであり、影響度も少なくない」
左下の第3象限 「個人的かつ慢性的なリスクで、警戒を要する」
右下の第4象限 「組織的かつ慢性的なリスクで、影響は少なくない」
人事・労務管理上のリスク・ポートフォリオと医業経営に対する想定影響度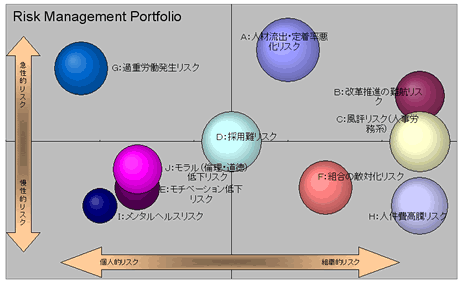
3.リスクの原因となるケース
2.で明らかにしたリスクを惹起するリスク行動をわかりやすく説明するために、それぞれのリスクについてショートケースにまとめて当ホームページ内クローズアップテーマ内「病院」カテゴリーの「調査・研究」コーナーに載せていますので詳細はそちらをご覧ください。
関連リンク
- クローズアップテーマ:「病院」『病院人事におけるリスク・ケース』

