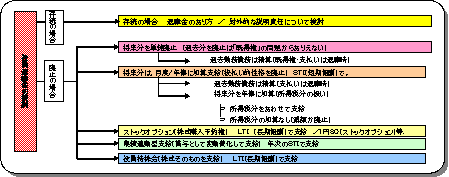コラム「研究員のココロ」
役員退職慰労金についての雑感<後編>
~あなたの会社では、まだ、役員退職慰労金を払い続けますか?~
2008年02月08日 三宅光頼
4. 役員報酬のあり方 - 報酬を決定するのは誰か
そもそも、代表取締役、取締役、従業員に関わらず、報酬は「何処から、そして、誰から」支払われるのでしょうか。
賃金労働対価理論、生産性原理など「賃金理論」は様々ありますが、確実に言えることは、報酬は(売上や利益や資産・資金から支払われるのではなく)その企業が産み出した『付加価値』から支払われているということです。利益を出したから報酬を受け取るのではなく、付加価値を産出したから報酬を受け取ることができるのです。もちろん、何もしなくても、同年程度の利益は産出できるでしょうから、単に産出するだけではなく、利益を増加させ、かつ継続維持させることに、本来の「役員としての存在意義に対する報酬の意味」があるのは当然のことといえるでしょう。
また、報酬は「誰から」受け取るのでしょうか。
現実的にいうならば、従業員は報酬を経営者から受け取り、経営者は取締役会から受け取ります。理念的には、(経営者が従業員に対して、顧客満足を徹底させることを目的として強調するために)自社の製品や商品を購入していただいた顧客から受け取るといった表現が妥当かもしれません。しかし、本質的には、報酬は「自ら貢献し産出した付加価値」から受け取るのであって、経営者から受け取ったり、顧客から受け取ったりするものでもありません。報酬は貢献の対価であり、自分自身の存在証明であり、株主のためのミッション遂行の結果なのです。その意味で報酬を決定するのは自分自身です。短期的に棚ボタやタダ働きがあったとしても、長期的には清算されます。自分で決定する以上、計算書は自分で作成し、明示する必要があります。お手盛りでない証明書を作成する必要があります。それがP/Lであり、B/S、C/Fであり、取締役会議事録となります。
5. 報酬機能の多様化と多機能化
ここで、近年急増している役員退職慰労金の廃止について、もう少し考えてみたいと思います。役員退職慰労金の廃止は、役員報酬のあるべき姿を再確認する作業でもあります。
実際に多くの企業は、単に退職慰労金を廃止し、既得権分を確定させた上で、将来分(期待権)を現行報酬に上乗せして支給している企業が多いようです。場合によっては、上乗せ分の増税分、さらに「退職税制により得るべきメリット分」まで、あわせて現行報酬に上乗せ加算している企業も見受けられます。これでは、いわゆる形だけの廃止で、実質、株主にとって本来的には何の改善にもなっていません。単純な役員退職慰労金の廃止と現給保証的な加算はむしろ問題が多いといえるでしょう。
過去においては、従業員の退職慰労金の過去勤務債務、簿外債務が問題になり、確定給付額の引き下げ、厚生年金基金の脱退や廃止を多くの企業が実施し、確定拠出への転換をしました。また、退職年金の将来の予定利率の引下げを行った企業もたくさん出ましたが、その際、補填をしていない企業が大半です。従業員には補填していないのに、役員だけ加算や補填をすればお手盛りになってしまいます。場合によっては、背任行為(会社に対して損失を与える行為)にもなりかねません。
現実的な改革の方法論として、役員退職慰労金の廃止には、役員退職慰労金を存続させる場合もいれて、下記の方法が検討されます。
役員退職慰労金を残す場合でも、報酬そのものをなんら変革しないということはありえません。存続させる場合も、株主に対して明確な説明が必要となります。
廃止の場合は、既得権(過去分)と期待権(将来分)についてそれぞれ別途検討する必要があります。手段についても、ストックオプション、役員持株会など、さまざまな方法も検討が必要です。
報酬とは、本来、長期(退職慰労金・年金)、中期(基本年俸・継続任用や重用)、短期(業績連動賞与)のバランスと、現金・株式・名誉・権限(肩書き)・環境(Perks:いわゆる役員特権、厚生)など、さまざまな方法と手段、支払いのタイミングによりバランスをとって、多様化、多機能化を図るものです。
会社法の改正により、役員賞与も役員報酬と同様の取り扱いができるようになり、経費処理することが可能となりました。実際に、賞与を損金処理するためには、下記の3つの要件をクリアしておくことが必要です。
1)当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書記載されるものに限る)を基礎とした客観的なもの
- 確定額を限度とし、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のもの
- 会計期間3月経過日までに報酬委員会が決定していることその他これに準じる適正な手続きを経ていること
- 内容が決定又は手続きの終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていること、その他の方法により開示されていること
2)利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること
3)損金経理をしていること
こうした処理を行うことによって、これまで利益処分だった賞与を経費処理することが可能となり、報酬の多様化、多機能化は一挙に進みました。これまでの「定時同額払い方式」だけでなく、「事前届出制」、「利益連動基準」による不確定報酬など、本来の成果主義に対応する方式を導入することが可能となります。
6. 株主総会における議決上の課題
役員退職慰労金の改革を行うにあたって、懸案と思われる点があります。
過去分の退職金は既得権になりますので、制度廃止の時に退職金額を確定させます。これを支給するのは実際の役員退任時になります。この役員退職慰労金の支払いには、「株主総会による議決」と「退職の事実」の2つの要件が必要です。株主総会は、退職金制度を廃止して、支給金額を確定させる廃止の決議の株主総会と、実際の退任時の株主総会の2回が必要だということです。
具体的な例でみてみましょう。たとえば、現在、下記のような役員履歴を持つ取締役がいたとします。
役員履歴の例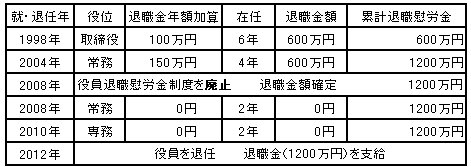
1998年役員に就任し、14年在任して、2012年に退任するとします。途中、2008年、常務取締役として在任している際に役員退職慰労金を廃止し、そのまま常務を2年、専務を2年務めて退任したと仮定します。この場合、2008年までの過去勤続分の退職金は既得権になりますので、1200万円が確定します。会計上、金額が確定した給与を何年も未払いで計上しておくのは好ましくないため、本来は退職時に確定させて一ヶ月以内に支給してしまうことが望ましいといえます。しかし、役員退職慰労金の支給は株主総会の議決事項のため、株主総会にかけない限り支給できないことになります。まして、退任していないのに支給することはできません。そのために2回株主総会の議決が必要になります。
ところが、実際に役員退職慰労金を廃止した企業の中には、退任時には改めて株主総会の議決をとる予定をしていない企業が多くあるようです。この場合、株主総会の議決なしで退職慰労金を支給することになり、退職慰労金の支給自体を否認されかねません。
当然、既に株主総会の議決を得ているので、再度は不要だという意見ももっともらしく思われます。事実、弁護士の一部には、2回目の株主総会への付議は不要だという人もいます。しかし、実際の退任が、退職慰労金の廃止から何年も後になって退任することも考えられるため、5年も10年も前の株主総会の決議で支給できるとしたならば、現在の株主の議決権を奪うことになってしまいます。議決後の経営責任を追及する必要がある場合も、効力を発揮できなくなります。役員退職慰労金を廃止された企業は、面倒でも実際の退任時に、再度退職慰労金支給決議をお勧めします。