プロフェッショナルの洞察
真の営業改革が進展するために 第2回 営業担当者が力を発揮できるために環境整備
2008年02月01日 木下輝彦
前回は営業改革の意義と必要性について事例を交えながらお話をうかがいました。営業改革の1つとして人材育成の観点があると思いますが、営業担当者が力を発揮するために企業はどのような環境を整備していくべきでしょうか?
 営業業務には定型業務が少なく、集合研修などのOff JT(Off the job Training)では営業マナーなど基本的なことしか学べないという理由で、営業担当者の能力開発はOJT(On the Job Training)が中心です。同じ製品でも、顧客の反応やニーズによって臨機応変に説明の仕方を変えなければならないことを学ぶ必要があるからです。ところが、その一番大事なOJTが無策に陥っているケースがあるのです。
営業業務には定型業務が少なく、集合研修などのOff JT(Off the job Training)では営業マナーなど基本的なことしか学べないという理由で、営業担当者の能力開発はOJT(On the Job Training)が中心です。同じ製品でも、顧客の反応やニーズによって臨機応変に説明の仕方を変えなければならないことを学ぶ必要があるからです。ところが、その一番大事なOJTが無策に陥っているケースがあるのです。上司やリーダーが営業担当者の営業活動に同行し、営業上の課題や方法論を指摘し改善させるのがOJTとして一般的な方法です。ただし、このやり方では、方法論や答えが一方的に与えられるだけで、顧客に対する対応方法を自ら考えるプロセスを経ていないため、営業担当者は局面ごとの対応を表面的に理解することはできても、今後、次々と現れる新しいニーズに応える力を醸成できません。新しいニーズに対応できるようになるためには、上司などによって教えられる過去のケースをそのまま当てはめるのではなく、営業担当者自らが自分の足りない点に気づき、解決方法を見つけ出すことが必要です。
OJTで営業活動の本質を営業担当者に考えさせるためには、上司などが手取り足取り 営業方法を教えるティーチング方式ではなく、営業活動上の課題を自ら発見し、改善策を検討する機会を提供するコーチング方式のOJTが最適です。
営業活動のOJTでは、トレーナーなどが営業活動に同行することがよくあります。そこで、たとえば営業担当者が顧客に不可解な説明をしたとき、ティーチング方式ではトレーナーは「あの顧客の困惑した顔は君の発言が原因だ」と指摘します。その一言で、営業担当者は自分が発した説明の拙さと本来すべきだった説明内容を理解することはできますが、臨機応変に対応できる力にはつながりません。
一方でコーチング方式では「今の顧客の表情の変化について君はどう思った?」と質問を投げかけるだけで、営業担当者自身で解答を考えさせます。このような機会を持つことで、自分が顧客に発した言葉がどのような意味合いを持つか、それによって顧客の置かれた状況や抱えている課題など営業活動の本質を把握することができ、今後の様々な機会に応用できるようになるのです。
 だからこのOJTで育成を担当するトレーナーには組織上の上長や上司という観点ではなく、顧客のことを良く理解できているという点で選ぶべきであり、営業活動で実際好業績をあげているトップセールスの人の方がふさわしいのです。 ある製薬メーカーでこのコーチング方式のOJTを取り入れたところ、コーチングを受けた営業担当者の中には、「私はこの会社に入って初めて育てられているという実感を持ちました」と感謝の意を述べる担当者が出てきたほどです。現在、この会社ではコーチング方式のOJTをますます強化しており、コーチングを担当するトレーナーの数も増えつつあります。
だからこのOJTで育成を担当するトレーナーには組織上の上長や上司という観点ではなく、顧客のことを良く理解できているという点で選ぶべきであり、営業活動で実際好業績をあげているトップセールスの人の方がふさわしいのです。 ある製薬メーカーでこのコーチング方式のOJTを取り入れたところ、コーチングを受けた営業担当者の中には、「私はこの会社に入って初めて育てられているという実感を持ちました」と感謝の意を述べる担当者が出てきたほどです。現在、この会社ではコーチング方式のOJTをますます強化しており、コーチングを担当するトレーナーの数も増えつつあります。このようなOJTは製薬業界において一時期ブームのように広まったのですが、営業担当者に考えさせる機会を与えず、トレーナーがいきなり正解を言ってしまうティーチング方式に陥ってしまっているケースが散見されます。というのも、営業担当者に正しいやり方を考えさせるプロセスに時間がかかる上、トレーナーの思った通りに相手の反応を引き出せないことが多いため、つい効率第一で進めているからです。結果として形だけ真似て、コーチングを行うトレーナーのスキルまで考えなかった他社のOJTは残念ながら短期間で終わってしまいました。つまりOJTが組織に定着するかどうかは、育成を担うトレーナーのコーチングスキル獲得が前提になってくるのです。
コーチングによって営業担当者自ら解を導く機会を作り出すことが、本質的な営業力を身につけることに繋がるのですね。
 そうです。ただし、そうは言っても営業部門のノウハウには言葉にしにくい暗黙知が多く、「この顧客の特徴は何ですか」、「この商品の売り方の極意は何ですか」、「なぜ売上を上げ続けることができたのですか」と聞かれても明確な言葉にできない難しい一面があるのも事実です。ある商品の販売で業績の良い営業担当者が、担当する商品を変更されると急に売ることができなくなってしまうケースがあります。そうしたケースは、新しく担当になった商品の知識が不足しているというよりも、営業活動の本質を根本的に理解していないためです。商品についての知識量だけではなく、顧客を本質的に理解する方法論や、暗黙知であるプロセスを形式知化するプロセスマネジメントの方法を自分の中にナレッジとして蓄積していかなければ、新しい商品の担当になっても従来と同じだけの成果をあげることができないのです。
そうです。ただし、そうは言っても営業部門のノウハウには言葉にしにくい暗黙知が多く、「この顧客の特徴は何ですか」、「この商品の売り方の極意は何ですか」、「なぜ売上を上げ続けることができたのですか」と聞かれても明確な言葉にできない難しい一面があるのも事実です。ある商品の販売で業績の良い営業担当者が、担当する商品を変更されると急に売ることができなくなってしまうケースがあります。そうしたケースは、新しく担当になった商品の知識が不足しているというよりも、営業活動の本質を根本的に理解していないためです。商品についての知識量だけではなく、顧客を本質的に理解する方法論や、暗黙知であるプロセスを形式知化するプロセスマネジメントの方法を自分の中にナレッジとして蓄積していかなければ、新しい商品の担当になっても従来と同じだけの成果をあげることができないのです。かつて私が実施したトップセールスマン研究で、トップセールスマンには二つのタイプが存在することがわかりました。ひとつは「ネットワーク形成型」で、顧客との人間関係を作ることを源泉に営業活動を行うタイプです。これはきわめて属人的な能力であり、その人のノウハウを他の営業担当者に移転することはとても困難です。
もうひとつのタイプは「プロセス形成型」のトップセールスで、最近若手営業担当者の中でよく見られるタイプです。この営業スタイルの人は、顧客先に頻繁に往訪することで顧客に関心をもってもらうというよりも、顧客をじっくり観察しながら顧客の心をつかむためのステップを、まるでゲームしているかのように考え出すことができるタイプです。
ある住宅メーカーでは、10年程前から「あなたは今までどのように業績を上げてきましたか」ということを尋ねたときに理路整然と説明できる人を管理職試験で登用してきました。なぜならばこのような管理職は、営業のノウハウを自分の中で形式知化できており、それを部下に教えることができる素地があるからです。
営業担当者の育成のためには、コーチング方式のOJTだけでなく、このように暗黙知であるノウハウや手法を組織の中でいかに形式知化し、共有していくかということも重要なテーマです。
能力開発以外で、営業担当者が直面している課題はあるのでしょうか。
営業担当者が顧客に単に商品説明をすればよかった時代に比べ、現在は顧客の商品知識が増え、ニーズも複雑化しており、販売方法などを含めた付加価値の高い商品情報を提供しなければモノが売れない時代になってきました。このような状況で一人の営業担当者に営業活動の計画から実施、アフターフォローまですべて任せてしまうことは無理があり、“会社(組織)対顧客”の組織的対応をどのように定着させるかが今、営業部門には問われています。この営業スタイルは、「ダイヤモンドモデル」と呼ばれるもので、営業・開発・物流などの各々の部門の担当者と顧客とが線あるいは面でつながり顧客に対応するスタイルです。
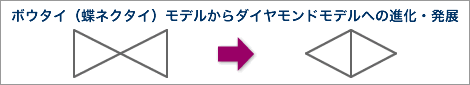
たとえば大手スーパーやコンビニのバイヤーは、納入メーカーの営業担当者に商品の開発コンセプトからターゲットごとの販売方法に至る知識や情報の提供を強く求めるようになっています。それはバイヤーが、物流担当者やマーチャンダイザー(商品計画担当者)など様々な部門の人々と連携をして商品の技術的な特徴や品質保証に対する細かな内容を知った上で購買先を選定しているからです。従来、営業担当者はバイヤー個人と数量調整や値引き交渉を担う役割でしたが、こうした情報を提供できないとバイヤーの選択眼に届かない状況を迎えているのです。
こうした動きは他の業界にも広がっています。複写機業界では顧客から日進月歩で進化する技術や費用対効果の詳細な情報の提供を要求されることが多くなっています。たとえば、ある複写機メーカーでは、さまざまな部品や技術について詳しい人がわかる社内のノウ・フー・データベースを持っています。この会社ではこのデータベースを活用して、営業担当者と部品や技術の専門家をマッチングさせ、専門家のノウハウを活用して共同で提案するという活動をしています。その結果、導入時のイニシャルコストやランニングコストを計算する財務担当者や、設置先の面積や温度を気にする総務担当者だけでなく、コピーを日常業務で使うユーザー部門の人たちの技術的ニーズにも対応できるようになりました。
この2つの事例からわかるように、営業担当者は専門性を持った人たちとチームを組むことで営業部門だけでは提供できない付加価値の高い情報を提供し、見事に受注を成功させているのです。
今後、営業担当者は社内の各部門の専門家との連携を増やしていくべきなのですね。
 そのとおりです。しかし社内の専門家といきなり連携するといっても各々自分の業務を持っており、最初から結束のある協力体制を敷くことは難しいものです。だからこそ段階を踏んで考えていくことが重要です。
そのとおりです。しかし社内の専門家といきなり連携するといっても各々自分の業務を持っており、最初から結束のある協力体制を敷くことは難しいものです。だからこそ段階を踏んで考えていくことが重要です。まず、第一のステップは商品開発など他部門の専門家を業種別にリストアップし、その専門家に同行してもらって営業活動を行うことです。これは顧客先に往訪する時だけの一時的な連携にしか過ぎません。
それがもう一歩進んで第二のステップになると、営業担当者と商品開発や物流担当者がタスクフォースを組み、営業先の選定など営業活動の計画段階から実施までを一貫して進めていくことになります。ただし営業部門以外の担当者は本来の業務があるので、未来永劫タスクフォースを続けていくことは無理です。
そこでこの活動の継続を目的とした第三ステップでは、商品開発や物流に熟知した営業担当者の育成がポイントになります。営業分野のみならず、商品開発や物流分野のことを理解している営業担当者がチームを組みながら顧客に対応します。
このような担当者を育成していくために、ある飲料メーカーでは営業担当者を研究開発部門に一定期間配置する思い切った施策を実施しました。この施策によって、営業担当者は商品開発段階における研究内容を知ることができ、営業活動に活かせるようになりました。また研究開発部門でも営業担当者を通じて知り得た顧客の生の声をうまく活用した商品開発がより多く行われるようになりました。
こうした人事の施策によって、さまざまな部門間の社内コミュニケーションを活性化させ、各々の部門の持つ情報やノウハウの共有を組織的に進めていくことも、結果として営業担当者の能力に大きく寄与していくのです。
関連リンク
01 営業改革が必要な会社
02 営業担当者が力を発揮できるための環境整備
03 営業改革を進めるときの注意点

